第七話
L'attente trop longue あなたを待ち焦がれて 《2》
ルームサービスのぬるいコーヒーを飲んでいるときに、電話が鳴った。
「岩城さん!」
「・・・ああ、おはよう、香藤」
香藤の声の明るさに、自然と微笑がこぼれた。
―――本当に単純だと、自分でも思うが。
俺の気分など、この男の声音ひとつでどうにでも変わってしまう。
「今、飛行機の中だよ!」
「えっ!?」
俺はあわてて時計を見た。
12月25日、午前8時半。
ちょっと待て。
ふと気づいて、俺は疑問を投げかけた。
「・・・なんでおまえ、電話できるんだ?」
「あはは、これは機内電話だよ。クレジットカードでかけるやつ」
「ああ、そうか」
そういえば最近のファーストクラスには、サテライト電話がついていることが多い。
「今ね、シベリア上空を飛んでるんだ。離陸したのが・・・えっと、4時間くらい前かな」
「・・・出発が決まったら、すぐに教えろって言っただろう」
不機嫌な声を出したつもりだったが、香藤はおかしそうに笑うだけだった。
「ごめんごめん。すねないで? さすがに岩城さん、寝てる時間だと思ったから。起こしたくなかったんだよ」
子供をあやすような口調。
昨日とは打って変わった上機嫌の香藤。
俺はつい、押し黙った。
―――まあ、いい。
文句は、こいつの顔を見てから言おう。
「メリー・クリスマス、岩城さん」
したたるような甘さで、香藤が言った。
それだけで、耳元がざわつく。
「―――岩城さんは、フランス語で言って?」
そうささやかれて、俺は吐息をついて応じた。
「・・・ Joyeux Noel 」
今日はクリスマス。
遠い昔、どこか遠い国で生まれた、神様の子供の降誕祭。
正直、俺にはどうでもいい話だ。
それでもその神様の前で、俺たちは結婚式を挙げた。
あいつへの生涯の愛を誓った、その気持ちは今も変わらない。
だから―――ああ、そうか。
香藤、おまえは正しいな。
やっぱり今日は、特別な日だ。
「―――岩城さん?」
いつだって俺は、気づくのが遅すぎる。
香藤は真実しか口にしないって、そろそろ覚えてもいい頃だ。
「・・・岩城さんってばあ・・・」
電話の向こうで、香藤が焦れた声を出す。
俺は、くすくすと笑っていたらしかった。
「何でもない・・・何でもないよ、香藤。俺は幸せだと、つくづく思っただけだ」
「・・・ええ!?」
香藤が素っ頓狂な声をあげた。
「待ってるから・・・いつまでも、待ってるから。だから早く、ここに来い」
キスをひとつ落として、俺は電話を切った。
頭の中で、フライト時間をざっと計算する。
あと7時間ほど。
夕方には、香藤はパリに着くはずだ。
俺はレイトチェックアウトを決め込んだ。
シャワーを浴びて、またベッドに寝転がる。
こんなに何もすることのない時間なんて、何年ぶりだろう。
本を読んでも頭に入らないので、目を閉じてじっと、香藤のことを考えた。
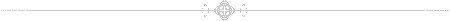
午後3時すぎ。
俺は再び、シャルル・ド・ゴール空港の到着ロビーに立った。
24時間遅れで香藤の乗った便が到着することは、すでに確認済みだ。
―――やっと、会える。
無事で着いてくれれば、後はもう、何もいらない。
俺はそれだけを心の中で繰り返した。
ざわめきが、ひときわ大きくなった。
クリスマスだというのに、到着ラウンジはごった返していた。
やっとの思いで到着したくたくたの乗客と、安堵の表情で出迎える家族。
再会する恋人たち。
お互いを見つけては歓声をあげる。
華やいだ笑い声。
幸せな抱擁と、キスの嵐。
どこかでフラッシュが焚かれていた。
うやうやしく花束を差し出す男性すらいる。
そうした小さなドラマを横目で眺め、スーツケースとカートの群れを避けながら、俺はゲートの手すりに近づいた。
どこにいてもひと目でわかる、長身の姿を探す。
香藤。
香藤。
香藤。
早く。
早く。
早く。
心臓が、早鐘を打っていた。
「岩城さん!」
俺の姿をみとめた途端、香藤が走り出した。
薄茶色の髪をなびかせて。
周囲の人間を蹴散らすように、まっすぐ俺だけを見て。
―――もう、空港の雑踏なんか、聞こえない。
「岩城さん!!」
俺が広げた両腕の中に、香藤は飛び込んで来た。
「おい、か・・・うわっ」
勢いよくすがりついてきた愛しい身体を受け止めかねて。
俺は香藤を抱きしめたまま、後ろにひっくり返った。
「え・・・!?」
あわてて香藤が身体を入れ替えようとしたが、間に合うはずもない。
そのままドサリと、俺は派手に尻餅をついた。
容赦なく、香藤の重みがのしかかる。
「痛・・・っ」
「・・・ごめん・・・!!」
―――この、バカ。
自分の体重を考えろ。
こんな、こんな人目のある場所で。
―――顔を見たら、文句を言うはずだったのに。
「岩城さん!」
香藤の顔を見た瞬間、何を言うつもりだったか忘れてしまった。
「岩城さん・・・!?」
代わりに、涙がこぼれた。
「ご、ごめんなさい、岩城さん!!」
飛びのいて、座り込んだままの俺の脇に膝をついて。
香藤がおろおろしながら、俺の背中をさする。
「・・・大丈夫!? 痛いの?」
泣きそうな瞳で、心配そうに覗き込む香藤。
「ばか・・・」
そうじゃない。
そうじゃないだろ。
何故、わからない。
俺は両腕を伸ばして、ぐっと香藤の首を引き寄せた。
―――もう誰が見ていても、構うもんか。
「・・・ス、くらい・・・っ」
「え?」
「・・・クリスマスが終わる前に、キスくらい、よこせ」
目の前でまたたく、明るい薄茶色のまなざし。
それを見つめたまま、俺は香藤にくちづけた。
甘い、熱い、久しぶりのキス。
香藤の太い腕が、俺の身体をぎゅうっと抱きしめた。
息もつけないほどのきつい抱擁。
そのぬくもりに安心して、俺は目を閉じた。
―――ああ、やっと。
俺のいるべき場所に戻ってきた。
待ち焦がれた抱擁の中で、全身の力が抜けていった。
耳元で、ためらいがちな声がした。
「あの、岩城さん?」
「ん・・・?」
「なんかすごい、注目を浴びてるんだけど―――」
俺はうっすらと目を開けた。
到着ロビーの利用客が遠巻きに、俺たちを見ていた。
チラチラと投げかけられる、好奇の視線。
俺は香藤の肩に額をつけて、嘆息した。
「・・・おまえが悪い」
空港の床に、いつまでも座っているわけにもいかない。
香藤の腕をつかんで引き上げながら、俺自身もゆっくり立ち上がった。
「いたた・・・」
「腰、大丈夫?」
俺のコートの埃をはたきながら、香藤が心配そうに言う。
「ああ・・・せいぜい、打ち身だろ」
笑って俺は、香藤の耳元にささやいた。
「痣になったら、責任取れよ」
俺の腰から尻の辺りをいたわるように撫でていた香藤の手が、はたと止まった。
「・・・もう、岩城さんてば・・・!」
香藤がさっと顔を赤くする。
ばか。
何を想像してるんだ。
―――まあ今さら、そんなことで照れるような関係でもないが。
そのとき。
「・・・ムッシュ・イワキ」
すぐ後ろで名前を呼ばれて、俺は飛び上がった。
「ジャン!?」
昨日、家に帰したはずの運転手が、大きな図体をすくめて立っていた。
「どうして・・・?」
ジャンが訥々と話しだす。
昨日の俺があまりに落胆していたので、心配だったのだと。
どうしても気になって、空港にフライト情報を問い合わせたのだという。
「・・・お疲れのマダムに、お車を、と―――」
ちらりと香藤を見て、気まずい笑みを漂わせる。
―――俺を気遣って、休日返上でわざわざ来てくれたのか。
たぶん、俺たちの再会の一部始終を見ていたのだろう。
「・・・ありがとう」
礼を言いながら、俺は顔が火照るのを感じた。
「岩城さん?」
事情がわからずにいる香藤に、俺は苦笑を返した。
「ジャンは俺の専属の運転手だよ。長旅で疲れてるだろう俺の女房を、迎えに来てくれたんだ」
「あは・・・そうなんだ」
香藤は明るい微笑をジャンに向けた。
「はじめまして。いつも岩城さんがお世話になってます」
「おい、日本語で言っても・・・」
ジャンがきょとんと俺たちを見つめる。
「残念ながら、俺は女じゃないけど。でも、マダム・イワキって呼んでくれてもいいよ?」
香藤の腕が、俺の腰にするりと回る。
「おい、香藤・・・っ」
「さあ、早く行こう?」
香藤の言ったことがわかったはずがないが。
ジャンは生真面目に頷くと、くるりと背を向けて歩き出した。
俺はほっとして、香藤を促して彼の後を追った。
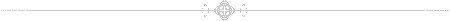
「本当にごめんね、岩城さん」
「香藤・・・」
「俺、岩城さんとの待ち合わせに遅れたことなんて、一度もないのに。本当に、ごめん」
「・・・もう、いいから」
「でも俺、イヴの夜に、岩城さんに淋しい思いをさせちゃったし・・・自分が許せないよ」
パリ市内に向かうリムジンの後部座席で、香藤はひたすら謝り続けた。
ぴったり寄り添って、香藤の肩に頭を預けて。
俺は目を閉じて、香藤の声を音楽のように聴いていた。
「本当に、ごめんなさい」
「もうよせ、香藤」
俺はそっと言った。
「・・・おまえが無事で、ここにいる。それだけで俺には、最高のプレゼントだよ」
運転席にいるジャンが気になったが、気を利かせてくれているのだろう。
さっきから、振り返るそぶりもない。
「岩城さん・・・って、あ、そうだ!」
香藤が突然、身体を起こしてかばんの中をゴソゴソかき回した。
取り出したのは、一枚の紙切れ。
「忘れるとこだったよ・・・はい。これ、俺からのプレゼント」
「なんだ・・・?」
押しつけられたそれに、俺は目をみはった。
オテル・ド・クリヨンの予約確認書。
コンコルド広場に面した、パリ屈指の超高級ホテルだ。
12月24日と25日の二泊。
―――マダム&ムッシュ・カトーとあるのには、気がつかないふりをした。
「香藤、これ・・・」
「うん」
香藤はうれしそうに頷いた。
「岩城さんが、クリスマスのパリはお店もレストランも閉まっちゃって、何もないって言うから。だったらホテルでのんびりっていうのも、いいかと思って」
「ば・・・」
口をついて出そうになった言葉を、俺は飲み込んだ。
―――こんな贅沢、分不相応だろう。
こんなこと、してくれなくていいのに。
おまえが来てくれただけで、俺はもう十分すぎるくらい幸せなのに。
「・・・ありがとう」
ようやく絞り出した声は、かすれていた。
ジャンに行き先の変更を告げると、あとはもうすることがなかった。
ステレオからは、サティの甘い旋律が流れていた。
ときどき降ってくるついばむようなキス。
腰を抱く香藤の力強い腕。
何もかもが心地よくて、そのぬくもりに浸った。
とろりと、このまままどろんでしまいそうだ。
「・・・岩城さん・・・」
香藤がゆっくりと、俺のセーターの中に手を忍ばせてきた。
「こら―――」
首を振った俺に、香藤がなだめるように言った。
「ごめん岩城さん・・・ちょっとだけ、触らせて・・・?」
切羽詰まった低いささやきに、俺は絡めとられる。
こんなところで。
なのに―――その手を振り払うことが、どうしてもできない。
「ん・・・」
声を出して、ジャンに気づかれるわけにはいかない。
俺はぎゅっと、唇を噛んだ。
大きな暖かい手が、懐かしむように素肌を探る。
久しぶりの、香藤の愛撫。
肌が、じんじんと熱を持って疼いた。
首筋にちろりと、香藤の舌が這う。
息が、乱れた。
胸をたどる指先が硬くとがった突起をくすぐった、その瞬間。
「・・・あぁんっ・・・」
俺は思わず、甘い声を上げていた。
香藤が驚いて手を止める。
目を開けた俺の視線は、バックミラー越しのジャンのそれにぶつかった。
驚愕と好奇の表情で、じっと俺を見ている。
おまえのほうが、女房だったのか。
そう言われているような気がして、俺は赤面した。
黙って、いたずらな香藤の手をセーターから引きずり出す。
「ごめんね・・・?」
香藤の声が笑っていた。
「・・・うるさい」
「岩城さん、敏感すぎ」
「うるさい」
俺はいたたまれずに、もう一度嘆息した。
夜のパリ。
リムジンが凱旋門に近づく。
イルミネーションで華やかに彩られた、シャンゼリゼ大通りの街路樹が見えた。
工夫を凝らした、華やかな街の灯り。
「うわあ・・・!」
香藤が子供のような声を上げる。
するりと俺の肩に回ってきた手をつかんで、俺は聞いた。
「ちょっと、歩くか」
「え・・・うん!」
ノエルの夜のパリのど真ん中。
ここからホテルまで、ゆっくり歩いても15分くらい。
香藤に、少しでもパリの街を見せてやりたかった。
明日の夜にはまた、こいつは日本に戻ってしまうのだから―――。
ジャンに礼を言って、俺たちはリムジンを降りた。
冷たい夜の風が、ほてった頬に気持ちいい。
「きれいだね・・・」
「ああ、そうだな」
俺たちは肩を並べて、ゆっくりシャンゼリゼを歩いた。
コンコルド広場のオベリスクが、遠くに見える。
「岩城さん・・・」
香藤がさりげなく、俺の手を取った。
俺は無言で、指を絡めた。
―――いつだって俺は、こいつに甘すぎるけれど。
何しろここは、聖夜のパリだ。
周囲には幸せそうなカップルしかいない。
恋人と手を繋いで道を歩くくらい、許されてもいいだろう。
―――最高のクリスマスだよ、香藤。
俺は、香藤の手のぬくもりをしっかりと握りしめた。
fin
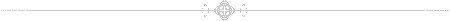
le 18 decembre 2005
藤乃めい
サイト引越に伴い2012年12月24日に再掲載。
これがシリーズ最終話です・・・それにしても、ベッタベタに甘いなあ(笑)。最後までおつきあい下さってありがとうございました。
初稿に若干の加筆・修正をしています。