第七話
L'attente trop longue あなたを待ち焦がれて 《1》
「ごめんね、岩城さん。本当に、ごめん・・・」
ふだん自分の強運を信じて疑わない、とにかく呆れるほどポジティヴな男なのだが。
今回ばかりは、さすがの香藤も相当参っているようだった。
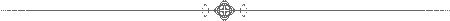
映画の撮影のために単身パリにやって来て、ほぼ二ヶ月。
香藤のいない日常生活にも慣れた。
―――寒くて、淋しくて、どうしようもない日もあるけれど。
認めたくはないが、慣れてしまった。
―――あいつの腕のぬくもりが恋しくて、眠れない夜もあるけれど。
話題のフランス映画に抜擢された驚きと喜び。
一流の共演者やスタッフに恵まれ、やりがいのある仕事をさせてもらっている。
役者として、充実しているのは確かだ。
紗のかかった、モノトーンの冬のパリ。
本当に美しい街だった。
―――これ以上は望めないくらい、幸運だと思いながら。
それでも俺は、東京の雑踏に戻ることばかり考えていた。
「今年のクリスマスは、一緒にパリで過ごそうね」
一日一回かかってくる、香藤からの電話。
香藤の声は、弾んでいた。
あれはいつのことだろう。
忙しい年末に、長い休暇なんて取れるのか。
あいつの仕事が気になってそう言った俺を、明るい笑い声がさえぎった。
「秋からこっち、俺もう、馬車馬みたいに働いてるもん! 社長がOK出したんだし・・・だいたい、長いって言ってもたった二泊四日だよ?」
「そうだな・・・」
照れくさくて、笑ってごまかしてしまったけれど。
―――嬉しかった。
そして心から、感謝した。
役者としての自分を優先させて、香藤をひとり日本に置いてきた。
そのことで俺が罪悪感を感じていることを、あいつは知っていた。
「岩城さんは、世界中どこでも、羽ばたいて行けばいいよ」
この映画の仕事が本決まりになったとき、香藤は言った。
俺の両手をとって、真摯な顔つきで。
「俺はどこまでも、追いかけて行くから。絶対に岩城さんを見失ったりしないから。だから岩城さんは、安心して好きなことをすればいい」
確信に満ちた力強いまなざしで、香藤はそう言い切った。
その言葉を信じたから、俺は今、パリにいる―――。
「岩城さぁん」
最初に電話がかかってきたのは、成田空港からだった。
パリ時間で12月24日、午前5時。
「・・・どうした」
日本とフランスの時差など、お互いとっくに頭に入っている。
こんな時間に電話してくるからには、緊急事態なのだろう。
「飛行機が、飛ばないんだよ」
「飛ばないって、どうして」
「荷物をチェックインしたのに、乗って来ないバカがいるんだ」
「・・・そうか」
搭乗ゲートに現れない乗客がいる。
おそらく免税品ショップで散財に夢中で、時を忘れているだけなのだろうが。
それでも航空会社は、爆弾テロの可能性を考える。
空港内アナウンスでその乗客を呼び出し、ゲートを閉めずに待つしかない。
それでも現れなければ、最終手段として、その乗客のスーツケースを積み荷から降ろす。
とっくに搭乗したほかの乗客は、その間ただ延々と待たされるのだ。
「―――あ、ちょっと待って」
香藤の声がふと遠くなった。
「ごめん岩城さん。今機内からなんだけど・・・電話、切れって言われて」
香藤が声をひそめた。
「・・・わかった。多少遅れようがちゃんと待っててやるから、心配するな」
「ごめんね、岩城さん」
俺は苦笑した。
「おまえのせいじゃないだろう」
「そうだけど」
「俺は大丈夫だから。ほら、早く切れ」
「うん・・・」
歯切れの悪い返事のあと、電話はぷっつり切れた。
俺は、ため息をついた。
次に電話が来たとき、俺はちょうどシャワーから出たところだった。
アンティークの姿見の前で、香藤を迎えに行くのに何を着ようかと思案していたとき。
「おまえ、今どこにいるんだ?」
「・・・まだ成田・・・」
俺は時計を見た。
午前10時すぎ。
「なんで、また―――」
さっきの電話から5時間が経っている。
さすがに驚きの声をあげた俺に、香藤はため息をついて説明した。
大遅刻の乗客はなんとか搭乗したのだが、今度は機材の故障が発見されたのだという。
「ジャンボ機後部の非常ドアが、ちゃんと閉まらないんだって」
香藤の声は、沈んでいた。
「それで今、機体の点検してるんだ。俺たちみんな、飛行機から降ろされちゃってさ。俺もう頭きて、別の航空会社のフライトに替えてくれるように頼んだんだけど―――」
深い嘆息。
それが言葉よりも雄弁に、香藤の落胆を物語っていた。
ただでさえ混み合っている年末年始シーズン。
おまけにヨーロッパ便はだいたい、出発時刻が正午あたりに集中している。
タイミングを逃すと、代替フライトもないのだ。
「・・・そうか」
俺はため息をかみ殺した。
辛いのは香藤のほうだ、と自分に言い聞かせる。
「ごめんね、岩城さん。本当にごめん」
「・・・さっき言っただろう。おまえは悪くないんだから、謝るな」
「うん・・・」
「いい方に考えよう。おまえの得意技じゃないか」
「得意技って―――」
「おまえの乗る飛行機に、何かあったら俺が困る。飛ぶ前に故障がわかって、本当によかった」
―――そうだ。
言いながら、俺は自分をも納得させようとしていた。
「うん」
「そう思えば、腹も立たない・・・だろ?」
「うん。そうだね」
香藤がくすりと笑った。
「ありがと、岩城さん。・・・大好きだよ」
「香藤・・・」
携帯電話越しに、キスが送られてきた。
香藤が空港のどこから電話をかけているのか、気にならないと言ったら嘘になるが。
俺はあえて、考えないことにした。
「・・・瞼?」
「はずれ。岩城さんのおいしそうな、鼻の先だよ」
「・・・ばか」
「じゃあ、これは・・・?」
今度は、もっと濡れたキスの音。
「・・・唇」
「あたり」
ちょっと笑って、香藤がささやいた。
「早くこの腕に、岩城さんを抱きたいよ」
「香藤・・・」
「早く、本物の岩城さんにキスしたい」
「・・・ああ」
想いは同じだ。
恋人の温かいぬくもりを待ちわびるせつなさ。
「もうすぐ、会えるさ」
それだけ言うのが、精一杯だった。
実は少し前に一度だけ、香藤がパリに来たことがある。
予告もなく忽然と俺のロケ先に現れ、その情熱で俺をさらって行った。
嵐のような、一昼夜。
俺は心身ともに翻弄され、ベッドからあいつを呆然と見送った。
―――今では、あれは夢だったのかもしれないとすら、思う。
それにしては夜が、あまりにも情熱的だったが。
午後3時。
空港までの送迎を頼んでいた運転手のジャンが、時間きっかりに現れた。
カタコトのフランス語で、日本からのフライトが遅れていることを知らせる。
ジャンはちょっと考えてから、とりあえず空港へ行ってみよう、と言った。
俺は黙って頷いた。
―――同じ待つなら、少しでも香藤に近いほうがいい。
「奥さまのいないノエルじゃあ、淋しいでしょうから」
早く到着するといいですね。
生真面目な顔でそう言われて、俺は苦笑を返すしかなかった。
もちろん、俺の左手の指輪を見ての言葉だろう。
待っているのは女房じゃない、と言おうかとも思ったが。
俺は躊躇して、結局なにも言わなかった。
隠すつもりはないが、あいつのことをどう説明すればいいのか、わからないからだ。
恋人・・・アマン?
シェリ。
アムール。
俺の知っているフランス語など、本当に限られている。
―――マリ。
思いついた単語の甘すぎる響きに、俺は赤面した。
いくら何でも、恥ずかしすぎる。
イレーヌには、それでさんざんからかわれた。
―――まあ、いい。
香藤を見れば、わかることだ。
俺はジャンを促して、パリ左岸のアパルトマンを出た。
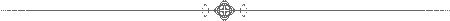
パリ郊外のシャルル・ド・ゴール空港。
到着ゲート近くのラウンジに、俺はどさりと腰を下ろした。
スチールの壁に、無表情な俺が映っていた。
白いセーターと、黒のハーフコート。
細身のヴィンテージジーンズに、皮のショートブーツ。
―――何の変哲もない格好だが、目立たなくていいだろう。
細い黒縁のメガネは、まあ、変装の小道具だ。
さすがに追いかけられたことはないが、パリにも日本人観光客は多いから。
俺はポケットから、単行本を取り出した。
そうやって、いっこうに姿を見せない香藤を待った。
待つ以外なかった。
時折、フライトの発着を知らせる電光掲示板を見上げた。
ふと周囲に視線を走らせては、脚を組み替えた。
ざわめきの中の、奇妙な孤独。
読みさしの本の内容が頭に少しも入らない。
気がつくと、胸ポケットの携帯電話をそっと指でなぞっていた―――。
午後6時。
フライト・インフォメーションのカウンターから戻ってきたジャンが、大げさに肩をすくめて見せた。
その仕草を見るのは、今日もう何度目だろう。
「今日はもう、飛ばないそうです」
それだけ聞き取って、俺はついと天を仰いだ。
―――ため息しか、出てこない。
はかったようなタイミングで、携帯電話が鳴り出した。
「香藤・・・」
「岩城さん・・・」
ほぼ同時に、深い吐息をついていた。
再び謝罪の言葉を口にしかけた香藤を、俺は制した。
「頼むからもう、謝るな。おまえのせいじゃないって言っただろう」
「・・・うん」
「こういうこともある。仕方ないさ」
「うん。これからどうするの、岩城さん?」
俺はちらりとジャンを見た。
明日はクリスマスだ。
いくらなんでも、もう彼を解放しないわけにはいかない。
「・・・近くのエアポート・ホテルを取るよ。明日、おまえが何時に到着するかわからないからな」
「そんな―――」
「アパルトマンに帰っても、どうせ何もない。ホテルのほうが気が楽だろう」
「岩城さん・・・」
香藤の吐息は悲鳴のように聞こえた。
「気にするな。もういいから、少し寝ろ。出発が決まったら、何時でもいいから電話してくれ。携帯はずっと、オンにしておくから。・・・な?」
少しでも、香藤が元気を出してくれるように。
俺はできるだけ、やさしく言った。
電話をくれと自分から言ったのは、パリに来て以来はじめてかもしれない。
「すぐに会える。焦るな」
香藤が、ひっそりと苦笑した。
「岩城さんがそんなふうに言ってくれるなんて、俺よっぽど、情けない声出してるんだ」
「・・・まあな」
共犯者のように、俺たちはひそかに笑った。
そうでないと、あまりにせつなかったから。
結局、空港から一番近いホテルに部屋を取った。
ジャンが手配してくれた、というべきか。
申し訳なさそうに去っていく彼を見送って、俺はむしろホッとしていた。
誰かを巻き添えにするより、独りで待っているほうがずっといい。
暖房のききすぎたダブルルームは、おそろしいほどに静かだった。
―――これでいい。
枕元に携帯電話を置いて、俺はベッドにごろりと寝転がった。
あいつと一緒になってから、クリスマスは毎年、大騒ぎだった。
仕事が入るときも、すれ違うときもあったけれど。
でもいつも、なんだかんだ言って、ふたりの時間を確保していた。
―――この日は、特別なんだよ。
クリスマスは、年に一度の恋人たちの祭典なんだからね。
そう断言する、イベント好きの香藤に引きずられて、毎年なにか『特別なこと』をしていたように思う。
どこかのイルミネーションを見に行ったり。
ティファニーやグッチでプレゼントを買ってみたり。
洒落たレストランでディナーを食べたりした。
それが出来ない年は、大きな薔薇の花束をもらったりもした。
―――そう、そして、いつの間にか。
俺はそういうことを、当然だと思うようになっていたのかもしれない。
クリスマスが楽しみなのではなく、香藤が何をするのかが、俺の毎年の楽しみになっていた。
香藤のいない、クリスマス・イヴ。
パリで、独りで迎えるクリスマス。
「・・・ばかやろう」
我ながら情けないが、最低の気分だった。
無意識のうちに、俺は携帯電話を握りしめていた。
香藤と俺をつなぐ、目に見えない電波。
そんなはかないものに頼るしかないのが、もどかしい。
睡魔が訪れるのを待ちながら、俺はそっと、ため息をついた。
きっと眠れないと思っていたのだが。
いつの間にか、うとうとしていたらしい。
かすかな雨の気配で、俺は目が覚めた。
カーテンを開けると、鬱々とした小雨。
あたり一面、けぶるような灰暗色の朝だった。
俺の気分は、さらに沈下した。
a suivre
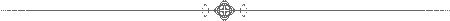
le 18 decembre 2005
藤乃めい
サイト引越に伴い2012年12月23日に再掲載(元は春抱き同盟への投稿作品ですが、ゆすらうめ異聞でも以前から展示していました)。
修正は最低限に留めました。