Of love, sex and ecstasy
Of love, sex and ecstasy
最初にそれを体験したのがいつだったか、覚えていない。
五年前か、十年前か。
いや、もっと昔のことかもしれない。
いずれにしても、かなり前の話だ。
香藤と初めて顔を合わせてから二十年と少し。
俺たちの転機となった映画『春を抱いていた。』のオーディションですら、
十七年ほど前になる。
思えば、本当に長いつきあいだ。
初めて会ったときの香藤は、大学一年生だったらしい。
まだ十代だった、ということになる。
当時は年齢など意識もしなかったし、正直なところ、あいつに興味もなかった。
生意気なガキだな、と。
ただそう感じたにすぎない。
今、あらためて振り返って思う。
あの時、香藤の運命は決まったのか。
そんな予兆すらなかったのに、人生はわからない。
まだ二十歳にもなっていない若者の人生を、結果的に俺が変えて
しまったのだ、と。
後悔も反省もないが、責任を感じないといったら嘘になる。
今でもふと、思う。
―――あのとき俺に会っていなければ・・・?
香藤の人生は、まったく違ったものになっていたかもしれない。
それがいいのか、悪いのか。
かつてはかなり考えた。
結局その答えは、香藤本人にしか出せない。
今はそう思っている。
俺たちは再会し、恋をした。
香藤は二十二歳。
俺はすでに二十七歳になっていた。
恋のきっかけが何だったのか、今でもわからない。
何かのはずみ、天のいたずら。
そんなものだったのかもしれない。
とはいえ、安易な結びつきではなかったと思う。
遊びで踏み出すには、むずかしすぎる恋愛だった。
本気でなければ続かなかった。
気づいたら、そこに香藤がいた。
いつもいつもそばにいて、俺を支えてくれた。
全身全霊で俺を愛してくれた。
今日ふたりでいられるのは、香藤のお陰だと思う。
五歳半の年齢差。
若いころはやけに気になった。
お互いに、そこはかなり意識していたと思う。
時間が経つにつれ、それは瑣末なことになった。
不思議なものだ。
今ではもう本当にどうでもいい。
ああ。
セックスの話だったか。
俺も香藤も男ははじめてだった。
性経験は豊富だったが、わからないことも多かった。
ただ夢中だった、としか言えない。
恋愛にのぼせ、抱き合うことに没頭した。
香藤に抱かれる、ということ。
それに関しては最初から違和感がなかった。
そこに理屈はない。
ごく自然に、あたりまえにそうなっていた―――としか言いようがない。
俺が逃げて、香藤が追いかける。
香藤が求めて、俺が応じる。
俺たちが当初、そういう形の恋愛をしていたからだろうと思う。
俺はもともと恋愛下手で、香藤のようにうまく気持ちを伝えることができない。
緩急も駆け引きもわからない野暮な男だ。
香藤は若いが、そのあたりは一枚も二枚も上手だった。
愛情表現が巧みで、ひとの気持ちを読むのがうまい。
情熱的かつ献身的、そのくせ男らしい。
俺とは比較にならないほど、あいつは “大人” だった。
知らず、俺はそれに甘えていた。
ずいぶん長い間、受け身でいるばかりだった。
それが、セックスにも現れていたんだと思う。
転機になったのは―――いや。
やっぱり思い出せない。
香藤と一緒に暮らすようになり、徐々に意識が変わって行った。
生涯を共に過ごすパートナー。
お互いにそういう覚悟が、はじめからあったのか。
今そう聞かれたら、正直わからない。
がむしゃらに突っ走って来た結果が、今の俺たちだから。
当時はまだ未熟で、「一生」の重みなど理解していなかったと思う。
感じる、ということ。
香藤とつきあうようになって初めて、俺はセックスの意義を知った。
抱き合う喜びや、繋がる幸せ。
際限のない欲望。
そういったすべてを、香藤に教えられた気がする。
自分で言うのも可笑しいが、俺たちの関係はとてもフィジカルだと思う。
セックスが根本にある、とでもいうのか。
時間の許す限りそばにいたい。
できることなら、いつでも抱き合っていたい。
どれだけ一緒にいても、セックスに飽きることはない。
―――いい歳の大人が、と笑われるかもしれない。
だが、それは今でも変わらない。
それはある日、いきなりやって来た。
特に前触れもなかった。
言葉でどう説明すればいいのか。
男が感じるセックスの快感。
それをはるかに凌ぐ、凄まじい衝撃だった。
月並みな表現をするなら、絶頂感、とでもいう他ない。
それが瞬間ではなく、長く引き続く。
後を引く。
何度もなんども襲ってくる。
―――終わらない悦楽。
俺が今まで、体験したことのない感覚だった。
痛みにも似た強い快感。
全身が痙攣するほどのショック。
身体の中心から脳天に駆け抜ける電流。
視界が真っ白に飛び、何も聞こえなくなる。
それから、恐怖を覚えるほどの墜落感。
俺は実際、意識を失ってしまった。
―――あれは何だったのか。
それを最初に味わったときの混乱は、今でも覚えている。
何が起きたのか。
俺はどうなってしまったのか。
なにもわからず、ただ香藤にしがみついていたように思う。
いっちゃったんだね、と。
香藤が嬉しそうに笑った。
それでようやく俺は気がついた。
女性がセックスで体験するという官能の頂点。
点ではなく、線のエクスタシー。
それによく似たものだ、ということに。
正直―――ああ、なるほどな、と思った。
これがそうなのか、と。
射精による快感とはまるで別次元の感覚。
男にも稀にそういうことが起こると、知識としては知っていたせいかもしれない。
驚きはしたが、意外だとは思わなかった。
それは、いつも起こるものじゃない。
いつ、どういう仕組みで起こるのか。
俺たちには今もわからない。
お互いのタイミングと、精神的な要素が大きいように思う。
せいぜい一年に何回か。
頻度でいえば、その程度だった。
本音を言えば、あれは刺激が強すぎる。
香藤はそれを “岩城さんのエクスタシー” というような呼び方をする。
その状態の俺をいつでも見たがる。
だがそれは凄まじく体力を消耗するものだし、何より気恥ずかしかった。
だから、ときどきでいい。
俺はそう思っていた。
それが変化したのは、最近のことだ。
きっかけは今度も曖昧だった。
俺の発病と入院。
手術後の経過観察と自宅療養。
それに香藤の京都ロケが重なり、俺たちはしばらく抱き合うどころか、
顔を見ることもままならなかった。
―――それが、どう作用したものか。
心細かったのか、飢えていたのか。
これまであまり考えずに来た将来の不測の事態について、まじめに
考えるようになったせいなのか。
その辺はよくわからない。
いずれにせよ、俺たちの関係はまた微妙に変わったのだと思う。
それ以降、セックスもまた変わった。
俺が極端に敏感になってしまったからだ。
―――どう説明すればいいのか。
俺は仕事をあらかたキャンセルし、ほとんど家にいる。
通院と、たまにオフィスに顔を出す以外することがなく、ずっと自宅で独りだ。
本を読み、掃除機をかけ、香藤の出るTV番組を見る。
静かな世界に、俺ひとりだけ。
そんな錯覚を起こしそうになる。
日に何度か、香藤から電話がかかってくる。
他愛のない会話を交わし、電話を切る。
またひとりになる。
ずっと、その繰り返しだ。
気づくと、香藤のことばかり考えていた。
女々しいと言われれば、そうかもしれない。
次はいつ声が聞けるのか。
次に東京に戻って来るのはいつなのか。
香藤がほしい。
香藤に会いたい。
そればかり考えるようになった。
決して口にはしないが、言わなくても香藤は察していただろう。
撮休日のたびに、香藤は帰って来た。
といっても日帰りのことも多く、一緒にいられるのが数時間しかないときもある。
俺たちはそのすべての時間、ひたすら抱き合った。
若い頃のように、お互いを貪りあった。
一分でも一秒でも離れたくなかった。
―――馬鹿みたいだと、自分でも思う。
ただ、恋しくて。
恋しくてたまらない。
香藤がほしくてたまらない。
これほどの飢餓感を覚えたことは、今までにない。
心境の変化。
言葉にすれば、それだけのことだろう。
それにあわせて俺の身体もまた、変わったのだと思う。
香藤が帰宅し、香藤に抱かれる。
時間制限つきのセックス。
ひどく切なく、むごく感じられた。
俺はそれを考えずにすむように、我を忘れて香藤に縋りつく。
飽くことなく、俺たちは抱き合った。
獣のようにお互いを食らい尽くす。
そのたびに深い快感に満たされ、それがつかの間であることがいっそう辛くなる。
―――離れたくない。
ずっと俺の中にいて欲しい。
心でそう繰り返す。
―――もっと、もっと。
もっと深く、もっときつく抱いてほしい。
気がついたら、俺は気の遠くなるような絶頂感にむせび泣くようになっていた。
終わらないエクスタシー。
全身がしびれるほどの衝撃。
かつては滅多に起きなかったことが、頻繁になっていった。
香藤に抱かれて、どうしようもなく感じてしまうこと。
女のように深いエクスタシーに翻弄され、乱れてしまうこと。
今はそれを気恥ずかしいとも思わなくなった。
香藤に愛され、香藤に望まれる悦び。
香藤を受け止め、香藤の快感を見届ける幸せ。
それのどこが悪いというのか。
ただ、怖くなることはある。
あの感覚はあまりにも強烈すぎる。
一度でも知ったら逃れられない、甘美な媚薬のようだ。
脳神経を焼き切るほどの絶頂感。
俺は声を嗄らし、のたうち回る。
ほとばしる情熱に引き摺られ、流される。
まるで宙に放り出されるような錯覚を味わう。
そして、墜落する。
―――それが怖い。
本能的な惧れ、とでもいうのか。
これほど強い感覚を知ってしまっていいのか。
いつか本当に戻れなくなるのではないか。
今までの生活に。
香藤の腕の中に。
バカバカしいようだが、そんな恐怖を感じてしまうのだ。
香藤にそれを言ったことはない。
説明したところで、理解されないだろうと思う。
―――いや。
もしかすると、とっくに知っているのかもしれない。
制御できない快感。
強すぎる刺激。
それを無理やり、俺は抑えようとする。
高みまで一気に駆け上がってしまいたいのに、一方でそうするのが怖いからだ。
俺のアンビバレンスに、香藤は気づいているのかもしれない。
香藤は俺の迷いを見逃さない。
惧れやためらいを吹き飛ばし、容赦なく俺を煽る。
あの果てしないエクスタシーへと、俺を導こうとする。
『いって、岩城さん!』
そう言われて俺は気づく。
香藤もまた、最高の快感を求めている。
それはふたり一緒でなければ、得られないのだと。
―――いったい俺は、何を怖がっているのだろう?
香藤がそこにいるのに。
香藤と、身体のいちばん深いところで繋がっているのに。
そして何より、香藤がそれを求めているのに。
後は、真っ白な閃光だ。
俺はなにもわからなくなる。
香藤の命と、俺の命。
他にはなにも要らない。
今年、香藤は四十歳になる。
香藤洋二はその人生の半分以上を、俺と過ごして来た。
俺は今さらながら、その事実に驚嘆する。
その間ずっと、香藤は俺にゆるぎない愛情を注いでくれた。
香藤がいなければ、今の俺はない。
かけがえのない恋人。
誰よりも愛しい。
―――言葉は陳腐だ。
とても香藤の存在感を満足に表せない。
俺の気持ちの半分も伝えられない。
もどかしいが、だからこそ俺たちは抱き合うのだろう。
言葉だけでなく、身体のすべてで。
ありとあらゆるかたちで、思いの丈を伝えるために。
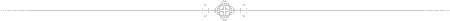
藤乃めい
12 January 2015
(edit 13 September 2015)
この散文詩(?)は、今年1月12日のブログに掲載した即興的作品を加筆・修正したものです。
『テンダー・グリーン』(雑誌掲載時)の岩城さんの「イキっぱなし」発言を自分に都合よくMAX拡大解釈し、妄想に願望をこってり盛ったらこうなりました。
後日コミックス収録の際の加筆・修正を見るに、この妄想もあながち的外れではなかったような・・・? というのは牽強付会にすぎるか。
それにしても、まあ。
なんというか、困りましたね・・・(笑)。
ご覧のとおり、セックスの快感に特化したネタ。
ゆえに、どうしても一人称になります。
岩城さんのひとり語り。
で、いったい誰に向かってしゃべっているのか???
それを考えると夜も眠れない。
・・・よね(笑)。
というか、相手が誰であっても、こんなことをベラベラ語るわけがない。
インタビューとか論外です。
あり得ない。
つまり、これはあくまで岩城さんの深層心理なのだ、と。
誰にも言わない、言うつもりも必要もない本音なのだと。
決して口にすることがないからこそ、饒舌でストレートなのだと。
・・・そう思ってやってください。
お願いします。
あぐぐ。
Uploaded 17 September 2015
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright (c) 2005-2016 May Fujino



