第一章
ゆれるベッドの上で、俺は覚醒した。
「・・・香藤・・・?」
手探りで気配を探したが、隣りにあるはずの温もりがない。
不審に思ってのそりと身体を起こし、何気なく周囲を見回した。
「!!」
俺はしばし、絶句した。
夢を見ているのか・・・?
唖然として―――それから俺は、ごしごしと目をこすった。
「・・・何だ!?」
・・・そこは、綺羅の空間だった。
きらめくクリスタルのシャンデリア。
しゃらりと天井から吊り下げられ、ゆらゆら揺れていた。
ルネッサンス絵画のような、あでやかな天井の宗教画。
金糸銀糸の刺繍をふんだんに使った、目がくらむほど豪奢なカーテンと絨毯。
優美な曲線を描く、クラシカルな家具の数々。
アラバスターの彫刻が、部屋のあちこちに配されている。
片隅には・・・あれはもしかすると、竪琴というやつだろうか。
真珠をはめ込んだ、とんでもなく凝った細工の楽器。
「うそ・・・だろ?」
俺はまだ、自分の目が信じられずにいた。
このうえなく贅沢な空間のど真ん中に、俺はいた。
正確には、このきらきらしく広い寝室の中心にどんと据えられた、天蓋つきの巨大なベッドの上だ。
「・・・ここは、どこだ!? ベルサイユ宮殿か・・・!?」
叫んだ途端に、わずかな衣擦れの音。
おそるおそる見ると、俺自身、ピラピラしたレースの服を着ていた。
象牙色の柔らかい生地のドレスに、ピンクのリボン。
・・・めまいが、した。
俺の叫び声を聞きつけたのかもしれない。
どっしりしたマホガニーの扉の向こうから、声がした。
「お姫さま? エレナ姫? どうかなさいましたか」
ノックと同時に、背の高い女が部屋に入って来た。
紫のロングスカートの裾を引き摺り、俺の前で優雅にお辞儀をする。
その顔は、どう見ても―――。
「佐和さん!?」
仰天した俺の呼びかけに、きょとんとした顔をする。
「・・・どうかなさったのですか、エレナ姫」
声は確かに、佐和さんのものだったが―――とても芝居とは思えない口調だった。
「何の冗談ですか、これは・・・」
言い募った俺を、女は訝しげに見返した。
その表情はまったく真剣で、困惑しているのは明らかだった。
「お姫さま・・・?」
「佐和さ・・・?」
俺は再び、絶句した。
佐和さんじゃない・・・のか?
女が当然のように、俺を「姫」呼ばわりするのが気になって。
俺はそっと、視線を自分の身体に落とした。
ひらひらした衣装の下に見え隠れするのは、どう見ても俺本来の―――普通の男の身体だ。
上腕をひねってみる。
それはやはり、女の細腕にはほど遠かった。
・・・わけが、わからん。
そう思ったとき、視界がぐらりと大きく揺れた。
「うわっ!?」
いや、この部屋自体が、不安定に左右に揺れているのだ。
まるでふわふわと空の上に浮かんでいるかのように。
「何が、どうなって・・・?」
頭を抱えた俺に、女が穏やかに語りかけた。
「お姫さま。ご気分がすぐれないのでしたら、今少し、横になられたほうがよろしいのではございませんか。シチリア島はまだ遠うございます。何より明日は、大切な日でございますから・・・」
女の言葉は温かい感情に満ちていて、本当に心配しているのが感じられた。
俺はため息をついて、女に問いかけた。
「ここは・・・どこだ?」
「まあ」
ころころと笑って、女が答えた。
そんな仕草も、佐和さんそのままだ。
「よもやお忘れではありますまい。我が公国の誇る、『フェラーラの薔薇』号の上でございますよ。お姫さまの別名をそのまま頂戴した、幸運なお船ではございませんか」
―――フェラーラの薔薇?
ちょっと待て。
―――俺が、薔薇!?
だいたいその、『お姫さま』ってのは何だ。
冗談なら笑えるが、あいにく女はまじめくさった顔をしていた。
船上と聞いて、部屋が揺れるのには納得がいったが。
「・・・おまえは?」
これには、女は相当びっくりしたようだった。
「・・・本当に、お忘れなのでございますか?」
窺うようにそう言われて、俺はぐっと言葉につまった。
おまえなんか知らない。
そう言えばいいのかもしれないが、女を傷つける趣味はない。
俺はあいまいに頷いた。
「お姫さまの侍女長の、アドリアーナでございますよ?」
「・・・ああ」
俺は目をつぶって、ちょっと考えるふりをした。
アドリアーナ。
フェラーラ。
シチリア。
ここはどうやら、イタリアらしい。
そうえいば俺は・・・さっき、エレナと呼ばれていた気がする。
衣装といい、「侍女長」がいることといい―――現代のこととは思えなかった。
まさか、時間を遡ったのか・・・?
「そんな、馬鹿げた・・・」
ふと思いついて、俺は自分の頬を強くつねった。
「痛・・・っ」
「お姫さま!?」
あわててアドリアーナが駆け寄る。
俺はそれを制して、苦笑した。
―――夢なら醒めると思ったのだが。
悪夢でもないとなると、もうさっぱり事態が把握できなかった。
まさかとは思うが・・・荒唐無稽すぎて笑えないが、これはタイムトリップというやつだろうか。
「冗談だろう・・・」
そう、つぶやいた瞬間。
俺は、いちばん大切なことを思い出した。
「香藤・・・香藤は!? どこにいるんだ?」
俺は勢い込んで、アドリアーナにつめよった。
「カト・・・?」
女が困ったように首をかしげる。
「香藤だよ。知らないのか?」
「・・・どなたで、ございますか・・・?」
「香藤は香藤だ。俺の・・・」
俺はそこで、はたと口をつぐんだ。
恋人なのだと。
伴侶だと言ってしまって、いいのだろうか。
何しろアドリアーナは、とうてい女性には見えないはずの俺をつかまえて、『エレナ姫』呼ばわりしているのだ。
どうやら相当身分が高いらしいこの深窓のご令嬢に、恋人がいていいものなのだろうか?
俺にはさっぱり分からなかった。
―――いや、俺はそれでどう言われても、一向に差し支えないが。
香藤がどこで何をしているのか見当もつかないのに、不用意なことは言いたくなかった。
「香藤・・・」
「お姫さま?」
「いや・・・いい」
俺は慌てて、言葉を濁した。
アドリアーナが不安そうに俺を見上げる。
俺は作り笑いを浮かべた。
「そういえば・・・」
「はい?」
「さっき、明日が大事だとか言ったな。俺はシチリア島に、何をしに行くんだ?」
俺の目をじっと見つめて。
アドリアーナは今度こそ、本当に心配そうにため息をついた。
「それも、お忘れでございますか・・・」
俺は反応のしようがなくて、曖昧に笑った。
彼女が本当に気づかっているのがわかるから、よけい居心地が悪い。
「・・・明日の夜には、シチリア公国に到着いたします。お姫さまはそこで、ご領主のコルラード伯爵さまに、お輿入れなさるのですよ・・・?」
「はあっ!?」
俺はベッドの上で腰を抜かしそうになった。
「お、お輿入れ・・・?」
アドリアーナが、神妙な面持ちで頷く。
お輿入れ。
―――冗談じゃない。
俺はとっくに既婚者だぞ。
思わず俺は左手に視線を走らせたが、そこに結婚指輪はなかった。
いつもしているわけではないから、仕方がないが。
それでも、薬指が妙に寒々しく感じられた。
香藤の存在を証明する唯一のものが、ない。
俺は深く嘆息した。
「コルラード・・・?」
「ええ、シチリアのご領主さまでございます。昨年フェラーラにお越しの折に、お姫さまをお見初めになったと。・・・お父上さまから、お聞きになりましたでしょう?」
アドリアーナは微笑した。
そんなことを言われても、俺には返事のしようがない。
「・・・嫁入りだって・・・?」
今度こそ本当に、俺は強いめまいに見舞われた。
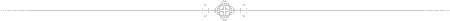
13 March 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
お待たせしました! いよいよエレナ姫シリーズ復活です(笑)。
はじまりが荒唐無稽のパラレルですので、ぬる〜い気分で読んでいただければと思います。(ちなみに、わたしに岩城さんを女装させる趣味はありません。・・・断じてない、はず。)
2012年12月26日、サイト引越により再掲載。