第二章
地中海は、凪いでいた。
海に沈むオレンジ色の夕陽を浴びながら―――。
俺はひとり、舳先に立っていた。
ヒラヒラした白いドレスの裾が、風をはらんで舞い上がる。
もちろん、俺に女装趣味はない。
こんな格好でいるところを、出来れば人に見られたくはない。
だが、なにしろ他に着るものを与えられないので、やむを得なかった。
甲板では、アドリアーナがうろうろと俺の様子を伺っていた。
『お輿入れ』にショックを受けた俺が、世を儚んで、身投げでもすると思っているらしい。
冗談じゃない。
心配してくれるのはありがたいが、それはまったくの杞憂だった。
どうすればいいのか、見当もつかないが。
それでもこのわけのわからない世界から、脱出しなくてはならない。
少なくとも香藤を見つけ出すまで、世を儚んでいる暇などなかった。
『フェラーラの薔薇』は、大型のガレー船だった。
名前の趣味はともかく、雄々しく、美しい船だと思った。
輝く大海原と潮風を眺めながら―――。
俺はふと、『冬の蝉』の船上ロケを思い出した。
香藤の演じる草加十馬の渡英シーンの撮影を、口実を作ってわざわざ見学に行った日のことだ。
大型帆船の船首で、俺たちは他愛ない冗談を交わしてじゃれ合った。
こうしているとそれが、大昔のことのように思える。
「香藤・・・」
思わずそう口に出した、そのとき。
俺は波の向こうに、キラリと光る何かを見つけた。
いつの間にか日は落ち、薄闇が辺りを覆っていた。
「なんだ・・・?」
ゆらゆらと揺れる、幻のようなあれは・・・松明か?
海の上を滑るように、ぐんぐん近づいて来る。
俺は目をこらして、光の方角を見つめた。
松明を落とした小ぶりの帆船。
闇に紛れて、『フェラーラの薔薇』の船腹に忍び寄る―――。
「海賊だ!!」
俺は叫んだ。
それはもう、直感としか言いようがない。
もちろん俺は海賊など見たことはないが、絶対にそうだという確信があった。
舳先から駆け下り、侍女長に急を告げる。
「佐・・・アドリアーナ! 右舷に海賊が近づいてる! 船長に知らせろ!!」
彼女は頷くと、すぐに近くにいた護衛の兵士たちに何か指示を与えた。
それから、俺の腕をぐいと掴んで船内に引きずり込む。
「な、なんだ・・・?」
もつれるドレスの裾に辟易しながら、俺はアドリアーナに聞いた。
「海賊の襲撃なら、俺も応戦するぞ?」
「ご冗談を!」
きっぱりそう言うと、アドリアーナは俺の、もといエレナ姫の居室に俺を押し込め、後ろ手で鍵をかけた。
螺鈿のチェストから素早く短剣を出して、胸に握りしめる。
「お姫さまは、私が命にかけてお守りいたします。『ソレントの堕天使』には、指一本触らせません!」
俺はあっけにとられて、アドリアーナの形相を見つめた。
彼女がそれを本気で言っているのは、明らかだった。
ほうっと深呼吸して。
俺はつとめて、落ち着いた声で聞いた。
「・・・海賊の正体を、知っているのか」
アドリアーナは、こくりと頷いた。
「この辺りの海域で、いやしくもフェラーラ公国の船に奇襲をかけるような大胆不敵な輩は、『ソレントの堕天使』より他に考えられません」
きっぱり、そう言い切る。
ソレントの・・・堕天使?
彼女の目がこれほど真剣でなければ。
俺はまたしても、そのネーミングのセンスに失笑していたかもしれない。
その口ぶりからして、『ソレントの堕天使』はかなり悪名高い海賊だということが察せられた。
―――堕天使、なあ。
「おそらく・・・」
言いにくそうに目を伏せて、アドリアーナが続けた。
「エレナ姫お輿入れの噂を、聞きつけたのだろうと・・・」
俺は眉をひそめた。
俺が、関係あるのか?
俺・・・いや、エレナ姫が、フェラーラの薔薇と讃えられるほどの美女らしいことは、もうわかった。
わざわざその嫁入りの旅を狙って、襲撃するとは―――まさか。
半信半疑。
できれば冗談であってほしい、という気分ではあったが。
「俺を・・・攫いに来たのか・・・」
俺は愕然とした。
アドリアーナが、痛ましそうな顔つきで俺を見上げる。
花嫁略奪。
どこかの芝居やオペラでなら、聞いたことがある。
無論、自分の身に降りかかる日が来るなど、想像したこともなかった。
「・・・冗談だろう・・・?」
俺はがっくりと、ソファに沈み込んだ。
しばらくすると、船が派手に左右に揺れ始めた。
ドーンと大きな音と、ズン、ズンという衝撃。
それから大勢の兵士たちの上げる気勢と、足音。
何が起きているのか分からないまま。
アドリアーナと俺は無言で、部屋の外の気配に神経を尖らせていた。
やがて。
バタバタと慌ただしい足音が、廊下から聞こえてきた。
剣のしのぎ合う嫌な音と、荒い吐息が、だんだん近づいて来る。
アドリアーナが、短剣を握る手にぎゅっと力を込めた。
俺は、アドリアーナにあてがわれたレースのヴェール越しに、彼女の震える拳を見つめた。
鬱陶しいヴェールは、顔を隠すためにと強引に着けさせられたものだ。
突然ガタンと、扉が揺れた。
俺が立ち上がろうとした、その瞬間。
重い扉を蹴破り、剣をかざした二人の男が飛び込んで来た。
「エレナ姫を頂戴する!」
そう叫んで俺を見つめるその顔には、見覚えがあった―――。
「え!?」
小野塚くんと、宮坂くん・・・!?
思わず立ちすくんだ俺を、アドリアーナが身を挺して庇う。
「返り討ちにしてくれる・・・!」
彼女は剣を構えると、男たちににじり寄った。
すぐに、凄まじい真剣勝負が始まった。
アドリアーナの剣さばきは見事だったが、何しろ相手は男二人だ。
すぐに劣勢に陥り、苦しそうに肩で息をし始めた。
「剣を貸せ、アドリアーナ」
とても見ていられずに、俺は背後から彼女に声をかけた。
ヴェールもドレスの裾も、かなり邪魔だったが。
女性を盾に、いつまでも隠れているわけにもいかない。
「なりません・・・お姫さま!」
「いいから剣を貸せ!」
俺は無理やり、彼女の短剣を奪い取った。
俺を攫いに来た輩なのだ。
もちろん、シチリア島に嫁に行きたいわけではないが。
海賊に捕まって、どこかに売られるのは真っ平だった。
嫌なら、自分で撃退するよりほかないだろう。
最後に自分を守れるのは自分だけだと―――いつか香藤も言っていたじゃないか。
俺は剣を斜に構えた。
男二人は戸惑ったように顔を見合わせると、ひそひそ話を始めた。
「姫を傷つけるわけには・・・」
「いや、しかし・・・」
その様子には、まったく危機感が感じられなかった。
俺・・・エレナ姫の剣の腕前など、鼻からバカにしているのだろう。
中世ヨーロッパのお姫さまは、剣の修業などしないのかもしれないが。
俺は高校まで、剣道部で竹刀を握っていた。
手にまめができるほど殺陣の稽古に打ち込んだのは、つい最近のことだ。
刃渡りと服装でハンデがあるので、相手が油断してくれるのはありがたかった。
「おやめください、エレナ姫!」
アドリアーナの悲鳴を無視して、俺は二人に切り込んだ。
「うわあ!?」
「おおっ!」
剣道の所作が珍しいのだろう、彼らは仰天して飛びのいた。
不意をつかれたせいか、太刀筋が読めないせいなのか。
彼らの剣は鈍く、防戦一方だった。
俺はずんずん彼らを壁に追いつめ、短剣をかざした。
「・・・剣を捨てろ。さもないと、一刺しにするぞ」
脅しをかけると、男二人は瞠目したまま、あっけなく降参した。
あまりに簡単なので罠かと疑ったくらいだが、どうやら本当に、震え上がってしまったらしかった。
―――あっけないな。
俺はアドリアーナに、二人を縛らせた。
アラバスターの土台に括りつけられ、猿轡をかまされた小野塚くんと宮坂くん・・・もとい、海賊の手下を見るのは忍びなかったが、仕方ない。
俺はほっと、安堵の吐息をついた。
と、そのとき。
バン、と派手な音をたてて。
すでに鍵の壊されたドアが、乱暴にスウィングした。
「おまえら、何をしている! 姫はまだか!?」
その声に、俺は驚愕して振り返った。
「え・・・!?」
すらりとした長身の男が、そこに立っていた。
―――香藤!!
心の叫びは、言葉にならなかった。
明るい茶色の髪を後ろでひとつに束ねた若い男。
懐かしい甘い茶色の瞳。
懐かしいしなやかな身のこなし。
俺は息をするのも忘れて、香藤の一挙手一投足を追った。
黒いマスクで顔は半分覆われ、怪しげなマントをひるがえしてはいたが。
俺が香藤を、見間違えるはずがない。
「・・・香藤!」
俺の声を聞いて、香藤がゆっくりと俺に視線を向けた。
会いたかった薄茶色の瞳。
舐めるような視線が、俺の全身を値踏みするように絡みついた。
そこには・・・何の感情もなかった。
何の暖かさも、なかった―――。
「香藤・・・?」
もう一度呼ぶと、香藤がニヤリと笑った。
見たこともない、冷たい顔つき。
なぜか、背筋に寒いものが走った。
「・・・エレナ姫、だな」
つかつかと俺に近づいて来る。
俺は、黙って頷いた。
だらりと下げた腕には、短剣を握ったまま。
―――俺が香藤に、刃を向けられるわけがない。
俺の心はもう、決まっていたから。
呆然とつっ立っている俺を見かねたのか、アドリアーナが走り寄った。
「お姫さま!」
香藤は、片手で簡単にアドリアーナを払い除けると、俺のまとっているヴェールに手をかけた。
ああ、そうか・・・俺はやっと、それに気づいた。
きっとこのヴェールのせいで、香藤は俺がわからないのだ。
「なりません!」
アドリアーナが悲鳴を上げる。
無造作にヴェールを引き破る香藤に、俺は抵抗しなかった。
素顔を晒した俺を、香藤がまじまじと見つめた。
「香藤・・・」
そっと、呼びかけたのだが。
探るようなまなざしは、しかし、冷たいままだった。
香藤の手が、俺の顎をくいと上げる。
「・・・噂には、聞いていたが」
至近距離で、香藤が・・・いや、香藤の姿をした俺の知らない男が、ニヤリと笑った。
―――海賊、なのか。
「たしかに美しい。オスマン・トルコの好色太守に、売り飛ばすつもりでいたが・・・惜しいな」
したたるように甘い声だった。
甘い、けれど残酷な声。
香藤はわずかな笑顔を見せながら、俺をしっかりと抱き寄せた。
抱擁・・・ではなかった。
俺の腕を背中に回し、一瞬の早業で手首を縛り上げる。
「お姫さま・・・!」
まったく無抵抗の俺に焦れて、アドリアーナが叫ぶ。
「すまん・・・」
俺は首を捻って、忠実な侍女長にそっと詫びた。
そう、俺の心はもう、香藤の姿をみとめた瞬間に決まっていた。
たとえ、地獄に連れて行かれるのだとしても。
たとえこの男が、俺を覚えていなくても。
どこまでも、俺は香藤について行くつもりだった。
どうしようもないだろう。
俺は、この男のものなのだから。
離れたくない。
・・・離れられるわけが、なかった―――。
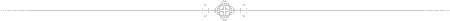
16 March 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2012年12月27日、サイト引越により再掲載。