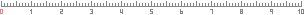Ma voix 2 ─ La lune descendante
この1週間で2度だが、近所の雑貨屋や食料品店に彼を伴って行ったことはあった。
今回はそれよりもほんの少し街の中心地に足を伸ばしていた。
「重い?」
マリの問い掛けには答えずに、風で乱れた前髪を掻き上げるように首を振った。
両手が、缶詰とバケットが入った紙袋で塞がっていたからだが。
荷物になるからと、買い求めたサンドベージュのトレンチコートを着ていた。
それに加えて出掛けにマリが彼に巻かせた渋いハリスツィードのマフラーが、
まるで彼のために誂えたように似合っていた。
持ち主の欲目もあるのかもしれないが。
それにしても、モード誌の表紙から抜け出たようだった。
「ちょっと奮発した甲斐があったかしらね」
ブティックの店員が、楽しそうに彼のために何枚もの服をあてがっていたのを思い出し、
マリは自然と笑みが零れた。
足元で乾いた音を立てる枯葉も、たった今風に飛ばされた枯れ葉さえも、
彼のために降らせたようだ。
数多の画家が描き止めたパリの風景画よりも鮮やかに、そして時間を止めたような
その情景に、マリは思わず足を止めた。
そのマリの行動に、青年が訝しむような視線を向けた。
「ちょっと休んでいかない?」
少し困ったように笑うマリをどう見たのか。
それでも数メートル先にある噴水を指差し、そこに腰を下ろすように動作で指図すると、
青年はその通りに噴水の縁に腰を下ろした。
そしてマリは彼の横に荷物を下ろすと、マロニエの木蔭に陣取る屋台に向かった。
亜麻色の髪を一纏めにしていたハンカチーフを解き、それに包み込める分だけ
焼き栗を買い求めた。
包んだハンカチの端を指先で摘むようにして小走りで噴水まで戻り、青年に笑いかける。
「食べたことあるのかしら?」
青年の横に置かれた紙袋を少しどけて、マリは縁にそのハンカチを置いて包みを開けた。
焼き栗の湯気が、一瞬で秋風に紛れていった。
「はい」
青年の口元に摘み上げた栗を差し出す。
青年は少し顎を引いたが、躊躇いながら口を開いた。
「うふふ、いい子ね」
栗を押し込んで、マリは満足気に微笑んだ。
その微笑に、マリ自身が驚いた。
自分は、そんなに面倒看がよい方ではない。
自分のことにすら横着に思うことが多いのに。
それなのに、何故かこの青年には手を掛けたくなってしまう。
自分に語り掛けてくれることはおろか、微笑みもしないのに。
まるで無償の愛のような・・・
母親が我が子にかけるような ───?
「馬鹿だわ、私ったら・・・」
マリが首を振った。
「こんな・・・ままごとみたいなこと・・・」
そう呟いた唇は震えていた。
こめかみに手をあて、暫し俯いた。
そのマリの肩に、青年が手を置こうとする仕草をした。
一度も彼のほうから差し出されたことのなかった手は、マリに触れる手前で止っていたが。
「優しいのね」
マリは続けた。
彼のほうは見ずに、マロニエの木々に視線をぼんやりと向けて。
「私のお腹にいたあの子も、生きていたらいつかこんな風になったのかしら」
子どもが生まれたら、庭の木にブランコを取りつけたいと笑っていたクロードの顔。
それを、生まれる前から物件を契約してきて、気が早いと笑っていた自分。
張るお腹を摩りながら、仕事を続けていた事。
いつもと違う痛みだと思いながら医者に行かなかった事。
これらは何年も過ぎて心の奥に仕舞っていた事で、決して忘れることの出来ない・・・
いや、忘れてはならないと思っていたことだった。
「男の子だったって・・・・・・。私、あの子に、子守唄を歌ってあげることはおろか、
名前も付けてやれなかった・・・」
マリは、自身の身体を掻き抱いた。
「抱くことも出来なくて・・・・・・」
小刻みに身体が震えていた。
が、今はもう涙も出なかった。
あの時泣きすぎて。
そして今はもう、泣く資格などないと思っていて。
あのときからずっと抱いてきた後悔と自責だった。
今でも時折真夜中に目覚めることがある。
そんな時は、ただただ窓から見える月を西の空に傾くのを願うしかなかった。
夫のクロードは、マリを責めなかった。
けれど、それを機に庭に手を入れ始めるようになった。
家の庭は、前の持ち主の頃からきれいに手入れをされてはいたようだったが。
元々彼の研究テーマであるアジア様式に急に様変わりするようになった。
まるで、マリとふたりで思い描いていた事柄に蓋をするかのように。
マリも、仕事に没頭するようになっていった。
夫婦の会話は次第に少なくなる。
別れ話が出るのは必然だった。
「仕事を続けるのに都合が良かったからじゃないわ。私はあそこに住まなくてはいけないのよ。
あの子に・・・謝り続けないと・・・」
彼にこんなことを言ってどうするというのだろう。
言葉が通じているのかどうかも分からない相手に。
でも、思い出すことも、今彼の前で話すことに、不思議と不快感はなかった。
切ない思いは、もちろんマリの心にあるけれど。
だからと言って、彼にそれを解かってもらおうとは思っていないのだけれど。
水が高いところから低いところに流れるように、ごく当たり前に自然に。
そして秋風に吹かれて何枚も舞い落ちる葉のように。
止めどなくマリの口からこれらが零れていった。
マリが語り終えると、辺りは静まり返っていた。
話しているときですら耳に入っていた枯れ葉の動く音も、高く公園の空を飛んでいる
鳥のさえずりも聞こえてこない。
が、何かが僅かに動いている気配がした。
恐る恐るマリは掌で覆っていた顔を上げ、気配の主を辿った。
横に座る青年の漆黒の瞳から一滴の涙が零れ落ち、頬を伝っていた。
肩を震わせているわけではない。
彼の身体で動いているのは、秋風に揺れる前髪とその涙だけだった。
*
家に戻ると、留守番電話のランプが点滅していた。
録音されたジャンの言伝を聞きながら送信されていたファックスを手に取ると、
マリはそのまま青年を連れて用紙に書かれていた病院に向かって行った。
タクシーの後部座席で横目で彼の表情を見たが、いつもと変わりがなかった。
あの時たった一筋流れた涙の跡は、すぐに秋風で乾いてしまった。
ルクサンブールの噴水の水滴が風に舞って彼の頬についたのかもしれないと思うほど、
彼の表情は変わっていなかった。
だが、彼の潤んだ瞳が、やはりあの時の涙が錯覚ではなかったことを表していた。
「マリ、と、えっとシャ・・・とにかくこっちだ」
病院の入り口に待機していたジャンがマリと青年を、病棟のとある一室に誘導した。
広い病室にはベッドが一床あるだけで、それを見て
「私はここで」
と言ってマリは足を止めた。
が、その時、ジャンに背を押されて病室に入る青年がふと振り返った。
それが、マリには一緒に来て欲しいと言っているように見えた。
食事の際にマリを待つなど、彼女を気遣いながらも彼自身は自分の感情を
表に出すことは殆どなかった。
その彼が、明らかに意思を持って瞳を一瞬だけ煌かせた。
マリが長い間抱えていた心の闇を彼に明らかにしたように。
彼もまたマリに抱えている何かを伝えようとしているのかもしれない。
部外者だからと一旦は病室に入ることを躊躇したのに、青年に付き添って
中に入ろうとすることを、少し意外そうに見つめるジャンの視線を感じたが、
マリはそのまま中に進んだ。
判っていることと言えば、彼はほんの少し前まである老人と一緒にいたということ。
それだって、本当のことかどうか。
偶然そこに居合わせたのかもしれないのだから。
もし一緒にいたことが事実だとしたら、その老人と彼がどのような関係なのか。
いつからどうしてそうしていたのか。何もかもが判っていない。
彼は、何も話してくれなかったから。
唯一理由を知っていると思われる老人も口が利ける状態ではなかった。
意識も、もうないようで。
それまでも、うわ言でさえ彼の名が出ることはなかったそうだから。
真っ白なベッドに横たわっていたのは、シーツのように白い髪と長い髭を蓄えた老人だった。
老人の傍らにあるのは、呼吸器だけ。
一輪の花すら生けられていなかった。
その老人に向かって青年はまっすぐに進んだ。
毎日ドアを開けて庭に出て行くときと同じ表情で。
そして、やはりいつもと同じように、まるで草花を弄るように、そして慈しむように
老人の髪を撫でた。
何かの映画や小説なら、ここで老人が目を覚ますのかもしれないが。
そこではなにも起こらなかった。
マリの傍らで、ジャンの肩が僅かに気落ちしたように下がった。
そしてマリも、自分の過去の経験から奇跡はそう簡単におこるわけはないと
解かっていながらも、やはり重い息を吐いた。
彼と老人は、実は何の面識もなかったのかもしれない。
そう思うことにしようと考え、身体の向きを変えたときだった。
ジャンが、息を呑んだ。
その気配に、マリが再び彼らに視線を向けた。
老人は僅かに反応したようだった。
呼吸器に覆われている唇が微かに動く。
声は聞こえてこない。
けれど、彼には老人の言わんとしていることが解かったようだった。
そして、彼の唇が動いた。
「Je vous remercie」
その声は、重苦しい空気の中に、まるで木の葉を一枚揺らすかのような
風が吹いたようだった。
*----------*----------*
「そうだったの・・・。その道に疎い私でも名前は聞いたことがあるわ」
彼が最期を看取った老人が、かつては国内外で活躍する庭の設計士だったとは。
電話の相手であるジャンは実感が湧かないといった風だった。
どういう経緯(いきさつ)でふたりが出会ったのかは結局分からないままだ。
とはいえ・・・
「あの彼が、20年近くも所在が掴めなかったエヴァン氏を捜し出すのに一役買ったって訳だ」
しかも自分たちが“Chat Noir”と呼んでいた青年が、ジャンのオフィスの向かい側にある
ビルに入っている日系企業の御曹司だったとは。
なるほど、あの少々堅苦しいお礼の言葉も納得できるわけだった。
ジャンはそれらを含めてかなり興奮して話しているが、彼女の心は電話の相手と違って、
とても穏かだった。
それに、マリには彼がエヴァン氏を探し当てたという風には思えなかった。
だからといってエヴァンと彼との出会いがあながち偶然とも思えないのだが。
敢えて言うならば―――
惹かれあったような気がするのだ。
彼とエヴァン氏が。
そして彼と自分が。
「して、その功労者のシャノワール君はどうしてる?」
「・・・・・・いないわ。此処にはね・・・・・・」
事態が飲み込めず、何度も
「何処に!?」
と繰り返す彼に、マリは
「さあねぇ」
と、とぼけた答えを返していた。
ジャンは一呼吸置くと、気を取り直した風で更に続けた。
「そうか。ま、いいさ。でもな、シャノワール君との出会いが、君にとって何かプラスに
なったんじゃないかと思うんだけれど、いかがなものかな?」
「え?」
「いつか君の小説に登場してくるんじゃないのか?」
向こうの受話器の先でニヤついているであろうジャンの顔は、容易に想像できた。
「まぁ、あなたにそんな策士なところがあったなんてね。でも、おあいにくさま。
彼のことは私、表に出す気は全くないのよ」
「そうなのかい?何で。もったいないと思うけどな、あんなエキゾチックな雰囲気・・・
実に君の創造的な部分を刺激するものだと思うんだけどね」
「確かにそうだとは思うけれど。じゃ、また面白そうな話があったらよろしくね。
あんまり煩わしいことはごめんだけれど。うふふ・・・」
含みのある笑いを返して、マリは受話器を置いた。
そして顔を上げると、彼のいなくなった庭を眺めてマリは呟いた。
「フランス人が作った煩雑な中国庭園が、彼のおかげですっきりとしたヨーロッパ庭園に
生まれ変わったわね」
彼が日本人だからそう見えたのかもしれないが、思い切りが悪そうな彼の所業が、
逆に何年も自分が引きずってきた思いを吹切ったのだ。
そのことに彼が気付いてもいないのだろうと思うと、笑可しい気がした。
それに・・・
先ほどジャンが言ったように、確かについ物書きの悪い癖で、彼を登場させた
小説でも書いてみようかと思ったことはあった。
だが、それは止めておこうと思った。
彼が自分に僅かに開いてくれた心の扉。
そこから垣間見えた一筋の光は、自分だけの宝物にしなければならないと思ったからだ。
そう。
たとえこの手に抱くことが出来なくとも、あの時一度自分の内に授かった命と同様に。
「久しぶりにクロードに連絡を取ってみようかしら?この庭を見たらなんて言うかしらね」
マリは何処までも続いていきそうな空を見上げた。
そこには、やはり何処までも続いていきそうな飛行機雲が伸びていた。
月は傾き、やがて西の空に沈み、そして夜は明けたのだ。
「Je vous remercie(=お礼申し上げます)」
彼がたったひと言発した言葉を、マリも空に向かって囁いた。
その言葉が、彼に、元夫に、友人に、そしてかつてお腹にいた我が子に届くといいと思った。
Fin..
'08.03.31.
みわ
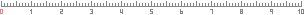
©
みわさま
みわさん、本当の本当にありがとうございました!
アップがもの凄く遅れてしまって、大変申し訳ありません。
満足できる壁紙が作れなくて、数ヶ月葛藤していました。
この素敵なお話に相応しいものをと、力みすぎて(汗)。
いつもありがとうございます。心から、感謝しています。
藤乃めい
2008年8月3日
2012年10月12日 サイト引越に伴い再掲載