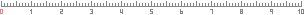Ma voix 1 ─ La lune descendante
今は昔ほどには辛いとは思わなくなってはいるが。
それでも時折、マリ=コレットは真夜中に目覚めることがあった。
そっと半身をベッドに起こしてカーテンを開ける。
と、冴えた月が高々と昇っていた。
だが、もう彼女は闇の中で月が傾くのをじっと待つ必要はなくなっていた。
*----------*----------*
室内にはエアコンはなかった。
「いやぁね、どうして今日はこうも暑いのかしら。街路樹の葉が色づき始めたっていうのに。
夏のようだわ」
窓を全開して窓枠に腰を掛けるように立ち、そして首筋にまとわりついた亜麻色の髪を
掻き上げると、マリ=コレットは抜けるような青空を恨めしそうに見上げながら続けた。
「大体、今年の夏は異常なほど暑くて・・・ようやく心地よい気候になったと思っていたのに」
パリのセーヌ側に面したこの一角は、官公庁が多く建ち並んでいる。
「確かに今年の夏は散々だったわ。それでも、この事務所はまだマシな方だったのよ。
知ってるでしょ?それより向かい側のビルなんて、こっちより30年は前の建物なんだから。
しかも両側には昨年建て替えられたアジア系商社のビル。窓を開けたらたちまち
熱風が来ていたそうよ」
マリのほぼ向かいにある机に向かう女性が、キーボードの手を休めることなく答えた。
「そう。ま、いいわ、向かいのことなんて。それでフラン(フランソワーズの愛称)、
今日私を呼んだのには何の理由があって?これでも結構忙しいのよ」
「マリったら相変わらずせっかちね。そんなだからそんな風に痩せているのよ。もう少し
のんびりなさいな。もうすぐ私もこれを打ち終わるから。そうしたら何か飲み物を出すわ」
「結構よ。だったらエスポワールにでも行ってるわ。ソルベでも頼んで、店の前にいた方が
気持ちよさそうだもの。どうせまだ終わらないんでしょ?」
そう言って腰を上げかけたときだった。フランソワーズの前の電話が鳴った。
受話器を取る前に、彼女が言った。
「待って。今すぐカフェに行くのは無理そうよ」
相手が誰か判っているようだった。
そしてその数分後。
事務所のドアが開き、ひとりの男が入ってきた。ジャンという男だ。
そもそもここは3年前までマリが勤務していた事務所で、彼は彼女の元同僚でもあった。
「久しぶりね、ジャン。フランから聞いたわ、先月ここの責任者になったんですって?
それでお腹周りもこの通りよく成長したのね?」
軽く抱き合い、頬にキスをしあったあと、彼の腹を撫でながら笑った。
「おお、久しぶりだね、マリ。相変わらずだね。元気そうだ」
彼も、マリの性格はよく解かっているようだった。
「えっと・・・ここじゃぁ何だな。エスポワールにでも行くか。そこでなにか冷たいものでも注文しよう」
マリが肩を竦めて脇を見ると、フランも同じようにして彼女たちを見ていた。
そしてふたりは事務所をあとにした。
「ちょっと待って、エスポワールとは逆の方向だわ。私をどこに連れて行くつもり?」
「君に頼むみたいことがある。お願いだから黙って来てくれ」
それだけ言って、ジャンは両手でマリの背を押しながら観光客で賑わうオルセー美術館の
前まで彼女を連れて行った。
そして今度は片手をマリの背を押し、片手でマリの手を握ったまま入り口をくぐると
美術館の中を進んでいった。
マリは奥にあるオルセー名物の大時計を横目で見ながら、厄介なことになりそうな予感がした。
*
「何ですって!この人を!?私に?どうしてそういうことになるのよ!?」
美術館の最上階のバルコニーには不似合いなふたりのやり取りを、黒髪の青年は
ただ黙ってみていた。
自分のことについて話されているのにも関らず、他人事のようで、困っている様子が
全くといっていい程なかった。
青年のその様子をマリは横目で見て、不思議な感覚を覚えた。
普段の自分ならば、こんな他人事のような態度を見たら、不快に思うだろう。
けれど、何故か腹を立てるどころか、むしろ彼のその様子が彼にとって自然な気がしたし、
どこかで見たような気さえしていた。
まるで階下にある印象派の絵を見るときのような気分だった。
「仕方ないんだ。うちにはカミさんもいるし、年頃の娘もいる。僕の知っている人間で
彼を任せられるのは君しかいないんだよ。頼む」
「年頃・・・って・・・まだ8つでしょうに・・・まったく、今からそんなじゃ将来子離れが出来そうにないわね」
溜息をつきながら言うマリに向かって、ジャンがそれこそ神に祈りを捧げるように胸の前で手を組んだ。
ふたりのやりとりを、まるで他人事のように見ていた青年だったが、さすがにジャンの
頼み込む様子を見て何かを感じたのか、ぺこりと僅かに頭を下げた。
「あら、彼・・・le Japonais なのね?」
青年の肩が一瞬ピクリと震えたように見えた。
「え?そうなのかい?てっきりこの長身、Chinoisかと思ったよ」
「私だって断言は出来ないけれど・・・」
横目で見た青年は、まだ俯いたままだった。
「そう、だから私のところに来たって訳なのね?生憎だわ」
ジャンが何故この青年を自分のところに連れて来ようとしたのか、マリには合点がいった。
「大体、それは私の趣味じゃないわよ」
別れた夫の趣味だった。
ジャンが溜息をついた。
「済まない。アジア趣味はクロードのものだとは知っているんだ。だが、君だって
造詣がないわけじゃないだろ。現に・・・」
コレットも溜息をついた。ジャンよりもっと深いものだった。
「少し・・・そう、1週間でいいんだ。いや、もっと短くなるかもしれないし」
マリはチラリと青年を見た。
「そうねぇ。身元さえ判れば大使館なりそれなりのところが保護してくれるでしょうし。
大体お役人なんてそういうところは融通が利かないものね。さっきも私たちに彼を預けた途端、
さっさと行ってしまったもの」
マリが溜息をつくと同時に、バルコニーに秋風が吹き付けていった。
「身元が判る物は何も無し。事情を知っていそうなその老人とやらも、今は病院の
ベッドの上で意識が戻らない、ってことなんですものね。仕方ないわ」
彼は、自分のことを話題にされているのにもかかわらず、ぼんやりとテーブルの上に
置かれた飲み物を見ているだけだった。
落ち着いた感じではあるが、額にかかる前髪と、心もとない気持ちを表している瞳が
その年齢を判らなくさせていた。
こと東洋人の年齢は分かりづらいが。
「彼を診察した医師の見解では、目撃した事故のショックで一時的に声が出ないんだろう
ということなんだ。言葉は多分理解できているんじゃないかということだし、それに、
雰囲気からいって・・・ねぇ?」
確かに育ちはそれなりに良いと思われた。
それに、悪いことは到底出来そうもない。そんな瞳だった。
「他ならぬジャンの頼みだし。その代わりいい待遇を期待しないでちょうだいよ?」
テーブルに肘をつけて右手を差し出した。
「ほら、握手よ。よろしくね、Chat noir(シャノワール=黒猫)君」
「はっ!それはいい。印象的な髪と瞳だからね」
*
「驚いた?」
ふたりが歩く度に、庭の落ち葉や枯れ枝が音をたてていた。
大きく見開いた黒い瞳に、鬱葱とした庭の木々が映っている。
マリーが薄く苦笑いを浮かべて、青年の表情を窺った。
が、彼は問い掛けに答えるどころか、マリの方を見てさえもいなかった。
しかも彼の唇は、息を飲んだときの形のまま身塵も動いていなかった。
それを見て、マリーが小さく溜息をついた。
「まぁ、そんなに都合よくこの庭を見て何か声が出るとは思っていなかったけど」
庭に目を奪われたままの彼には、彼女の呟きは聞こえていないようだった。
それでもマリは続けた。
「これ、ね。別れた夫の趣味なの。そういうのに私が無頓着な所為でこの有様なのよ。
今年の夏はおかげで虫に酷く刺されてね。秋になってホッとしていたのよ」
マリーの言葉にも、彼は振り向かなかった。
「ああ、気にしないで頂戴。だいぶ前の話だし。ひとりでせいせいしているから」
聞いているのか、聞こえていないのか、解っているのかも分からない。
けれど、話しておこう・・・何故かそんな気にマリをさせる雰囲気が彼にはあった。
無造作に伸びた木々や芝が生い茂る庭に、彼は何の違和感もなく立っている。
少し神秘的な雰囲気を漂わせながら。
Beaute asiatique (=Asian beauty)。
よくここに立って嬉しそうにそう言っていた男の言葉を、ふと思い出した。
マリはこの庭に植えられている植物のことは全くと言っていいほど知らなかったし、
興味もなかった。
別れて10年近く経つ元夫が、呆れるほどアジア、こと中国文化にかぶれていたのだ。
“(桃)”だとか“(松)”だとか言っていた記憶はあるけれど、どれがどれなのかマリは
覚えてもいなかった。
だからと言ってそれが不自由だとも感じていなかった。
苦い思い出があるこの家に彼女がそのまま住み続けるのは、単に仕事を続けるに
都合が良かったからだ。
まさかそれが、このような出会いに通じるとは考えてもいなかった。
「おかげで貴方みたいなお客さまを迎えられるしね」
ようやく振り返った青年は、目を伏せ気味にしていた。
*
「適当に食べていて、って言ったでしょ?私を待っていなくていいのよ?」
噛んで含めるように言って聞かせた。
この日の昼食前にも、昨日も一昨日も自分が席に着くより前に言っていたことだった。
青年は俯いていた。
「別に怒っているわけじゃないのよ」
マリが言っても、ほぼ無反応と言ってもよかった。
そういえば、初めて彼と会ったときにも、ジャンの問い掛けなどに無反応だった。
ただ一度、マリが発した“Japon”以外には。
身元が判るのを恐れているのかもしれないし、自分の殻に閉じこもっているのかもしれない。
マリはそう解釈していた。
様子を気にしてジャンが2日に一度は顔を出すが、その度に挨拶に出るわけでもなかった。
鼻梁から華奢な銀縁眼鏡のフレームがずれたのをのそのそと直して、そのまま
スプーンも持たずに座っている。
マリが諦めたように自分の席に着きフォークを持って食事をし始めると、
ようやく彼は自分もフォークを持った。
それを見て、マリは呟いた。
「その眼鏡・・・修理したけれど、やっぱりどこか合っていないのかしらね?」
どうせ返事などは来ないと思ってはいても、口に出さずにはいられなかった。
事故現場にあった眼鏡は彼の持ち物らしいのだが、どうも彼の輪郭に合っていないようだった。
しかも今朝になってようやく判ったことだが、度も入っていない。
所謂伊達か、変装用か・・・
が、それも彼が話してくれなければ分からないことだった。
バケットにクリームチーズを塗り、それを齧る度に滑り落ちていく眼鏡を見ながら
マリは野菜ジュースを飲んだ。
遅れた昼食だった。
「今日の風は心地いいわね」
自分が仕事場に篭って書き物をしている間に彼が開けたのだろう。
「でも、さすがにもう全開では肌寒いわ」
マリが立ち上がって窓を閉めた。
*
結局、青年の名前はそのまま定着していた。
宝石のような光沢を放つ黒い瞳は、その名に抵抗を示していないと感じたからだった。
受け入れてもいないようではあったけれども。
「シャノワール?」
マリが原稿を仕上げてからありあわせの材料で夕食を作り終えると、庭に向かって呼びかけた。
しばらくすると、薄暗くなり始めている庭の隅から青年が姿を現した。
今日も彼は1日中庭にいた。
まるでもう何年も前から、そうしてそこにいるように。
ごく自然なその風景に、僅かな時間でマリは見慣れてしまった。
見慣れる、というより彼が庭にいるのが似合っているような気がしていた。
会った当初抱いていた、どこか育ちのいいお坊ちゃんのような雰囲気とは逆の印象だった。
確かに、家事などは何も出来ないみたいだが。だがそれは男としてそんなに珍しいことではない。
以前マリが一番プライヴェートの時間を共有していた男性と似たようなものだ。
しかも、その男とこれまた同じように庭にいる時間が長い。
マリにとってやや不快な共通の事実の筈なのだが。
けれど、その青年が笑顔は見せないまでも、庭にいるときにだけ見せるひたむきな表情を
部屋の中からこっそりと見るのが、彼女の密かな楽しみにもなっていた。
マリにとっても、これは少し不思議な気分だった。
「もう・・・、枯葉がこんなところにも付いているじゃないの。折角の黒くて艶のある
きれいな髪が台無しよ。夕食の前にシャワーを浴びる?」
マリが背伸びをして頭に付いた小枝や葉を取ろうとすると、青年は腰を曲げて屈んだ。
「うふふ、大きな子どものようね」
乱れた前髪の間から、上目遣いの瞳がマリを見つめた。
珍しく、ふたりの視線が合った。
「いやだ。私にあなたみたいな年頃の子どもがいるわけないじゃないの」
払い落とすように枯葉を取り除いたあと、
「別に、そんなに精を出して庭仕事をしなくていいのよ?ま、きれいになるのは嬉しいけれど」
と、マリは、ぶっきらぼうに言った。
「ねぇ、寒くない?」
ふと思いついたように、マリが訊いた。
マリを見つめたまま、青年が小首を傾げる。
長く庭にいた所為か、いつも彼が纏っている緊張感が少し和らいでいるようだった。
「その服装で、ってことよ?」
当初見積もっていた1週間はとうに過ぎていた。その間にパリの秋は駆け足で深まっていた。
「明日、原稿料が入るのよ。ちょっと買い物に行かない?庭をきれいにしてくれたお礼をしたいの」
彼は、ほんの何日か前までは、たとえすれ違っていたとしても声すら掛けなかったであろう
見ず知らずの人間だ。
確かに時間と空間を共有している事実に戸惑いを感じないわけではないが、不思議と
一緒にいて窮屈さは感じなかった。
何かしてあげたい ───
不意にそんな感情がマリに芽生えた。
出掛ける前。
やはり青年はマリの支度が出来るまでの間も玄関先の草を抜いていた。
そこにマリが腕に幅広の渋いハリスツィードのマフラーを掛けて出てきた。
「お待たせ・・・でも、あなたの庭仕事にはきりがないみたいだけどね」
自分の言った言葉に吹き出し笑いをしながら、マリは腕に掛けていたマフラーを
無造作に半分に折ると、背伸びをして彼の首に巻いた。
そして一歩下がり、彼を見て
「東洋人は若く見えるし。これならリセの学生でも通りそうね」
と言ってもう一度笑った。
「まぁ、若くてスタイルのいいあなたは何を着ても似合うのでしょうけれど。それにしたって
生成りのセーターとストレートのジーンズはねぇ・・・ジャンったらもう少しセンスを磨いて
欲しいものだわ」
マリのところに来る前に、ジャンが何枚かの衣類を用意して持たせてきたものと、
昨日着替えだといって持ってきたもの。
どれも似たり寄ったりな服だった。
つづく
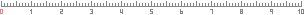
©
みわさま
みわさん、本当の本当にありがとうございます♪
こんな素敵なお話を頂けるなんて、本当に光栄です。
謎めいた岩城さんを想像するだけで、わくわくしますね(笑)。
まさに、フランス映画のアンニュイな雰囲気そのまま・・・!
ありがとうございました♪
※壁紙は手作りです。パリ6区の写真ですけど(苦笑)。
藤乃めい
2008年4月30日
2012年10月12日 サイト引越に伴い再掲載