春隣 Spring steps
春隣(はるどなり)――― Spring steps ――― 1
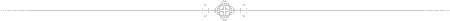
岩城さんが、小さなため息をついた。
夜遅く帰宅して、ぱさりとコートをダイニングの椅子にひっかけて。
「どしたの?」
俺はソファから立ち上がって、横抱きに岩城さんを包み込んだ。
「何でもない」
照れたように笑って、きれいな指先でそっと俺の筋肉をなぞる。
俺の腕の中で、安心したみたいに弛緩する、愛しい身体。
それはもう、今朝と変わらない暖かさで。
―――別に何か、辛いことがあったわけじゃないみたいだね。
なら、いいんだ。
言いたくなったら、言ってくれれば。
俺はゆっくり、岩城さんを解放した。
「ご飯、食べた?」
「・・・いや」
「うーん、遅い時間だけど。リゾットくらいなら、いいかな」
俺はそう言って、キッチンに立った。
お風呂あがりの岩城さんが、パジャマにセーターをはおってテーブルについた。
ほかほかのリゾットには、冬野菜とベーコン。
これくらいなら、胃にもそんなに負担にならないよね。
「うまそうだな」
岩城さんはうれしそうに笑って、礼を言った。
無造作に乱れた、湿った髪のせいかもしれない。
それとも、スプーンで一口すくっては、フーフーしてるせいなのかな。
とにかく、おいしそうに食事をする岩城さんが、とても可愛く思えて。
俺は、その腕を捕らえてキスしたい衝動に襲われた。
―――いや、別にキスしたって、岩城さんは嫌がらないだろうけど。
俺だってもう、いい歳の大人なんだから。
恋人が夜食を食べる間くらい、待てる余裕が欲しいよね。
「岩城さん、明日は何着ていくの?」
明日は、映画『冬の蝉』の封切だ。
ハリウッドでのワールド・プレミア上映も大好評のうちに終了し、満を持しての日本全国一斉ロードショー。
俺たちは有楽町と日比谷の映画館で、監督や他の出演者と一緒に、初日の舞台挨拶に出ることになっていた。
いよいよ、映画の真価が問われる。
緊張しないといったら嘘になるけど、俺は案外、落ち着いていた。
俺たちが、最高のものを作るためにスタッフと力を合わせ、渾身の情熱を注いできた映画だ。
きっと、成功する。
そう確信できるだけの、手応えはあった。
「特に考えてはいないが・・・まあ無難にスーツだろう。おまえは?」
「・・・俺も、スーツにしようかな」
映画も俺の役もシリアスだから、ちょっとまじめな格好でもいいかもしれない。
岩城さんと並んで恥ずかしくない、そんな役者を目指してるんだから。
「・・・そうだな。ネクタイを貸してやるよ」
「うん」
俺はほうじ茶を淹れて、岩城さんに湯呑みを渡した。
芳ばしい香りが、鼻をつく。
「・・・香藤」
「ん?」
「明日・・・お義父さんたちも、来るのか?」
「ああ、有楽町プレミア? うん。金子さんに頼んで、実家に招待券を送ってもらったから。確認はしてないけど、来ると思うよ。何しろ俺が仕事してるとこ見るの、久しぶりだからね」
岩城さんは、うっすら笑った。
でもなんだか、ちょっと屈託がある感じで。
「・・・岩城さんの実家は?」
誰も来ないのかもしれない。
遠距離だし、まだしこりが残ってないわけじゃないから。
―――いや、招待だって、したかどうか。
「ああ、そうじゃない」
岩城さんが、俺の顔色を読んで首を振った。
「俺は本当に、気が利かなくて・・・。でも、清水さんが招待券を手配してくれてたんだ。兄貴が親父を連れて上京するって、昼間、電話があった」
照れたように笑う岩城さん。
俺も思わず、うれしくなる。
「よかったね。会うの、久しぶりでしょう」
「ああ・・・」
「・・・どうしたの?」
言いにくそうに、口ごもる。
もしかして・・・さっきのため息の原因か、これ。
「会いたくないわけじゃ、ないよね・・・?」
「・・・ちがうよ」
頬を染めて、岩城さんはちょっと決まり悪そうに笑った。
「・・・はじめて、だろ」
「え?」
「だから・・・おまえの家族と、うちの親父。顔を合わせるの」
「ああ、そういうこと!」
俺はやっと岩城さんの悩みの原因に思い当たって、破顔した。
岩城さんは、すねたように上目遣いで俺をにらむ。
「・・・何がおかしい」
「ごめん」
そういうことで、悩んじゃうんだ。
かわいいね、岩城さん。
俺は伸び上がって、岩城さんの鼻先にキスをした。
食事を終えた岩城さんの腕を引いて、俺はリビングに移動した。
「おい、香藤・・・」
ちょと眉を寄せて、俺を見つめて。
それでも岩城さんは、促されるままにソファに座った。
俺はどさりと床に腰を下ろし、岩城さんの両膝の間から恋人を見上げる。
くすりと笑って、岩城さんはそっと俺の髪をすいた。
なんだかペットを撫でてるみたいだよ、岩城さん。
気持ちいいから、いいけどね。
「今まで、さ」
「ん?」
「一度もきちんと、挨拶したことなかったよね。俺たちの家族ってさ」
「ああ・・・」
「だからさ、いい機会なんだよ、きっと。映画を口実に会うなら、どっちの家族にとっても、ちょっとは気が楽だろうしね。みんな大人なんだから、大丈夫だよ。・・・うちの親父たちは少なくても、岩城さんのお父さんに会えたら、うれしいと思うよ」
「そうだな・・・」
岩城さんは、困ったような笑顔を見せる。
「俺は・・・おまえのご両親には、本当によくしてもらってるから。感謝してるんだ。いやな顔ひとつせず、いつも本当の家族みたいに扱ってくれて―――」
「何、言ってるの!」
俺は岩城さんをさえぎった。
「今さらだよ。岩城さんは、うちの家族なの。もう何年もずっと、親父もお袋も、そう思ってるよ。俺の・・・」
俺は岩城さんを見上げて、にんまり笑った。
「・・・奥さんなのか、旦那さまなのか、未だに決めかねてるみたいだけどね」
岩城さんが、さっと顔を赤くした。
「そんなこと・・・」
頬を撫でるきれいな指先を、俺はそっと手のひらで捉えた。
「考えるなってほうが、無理みたいだね。・・・でもさすがに、聞けないでしょ。だからこっそり、岩城さんは嫁なのか婿なのか、悩んでるんだよ」
俺が冗談めかして言うと、岩城さんは、赤い顔のまま苦笑した。
「・・・心配、かけてるな」
「心配するのは親の仕事だって、思ってるよ」
「そうだな・・・。だからこそ、うちの親父に、おまえのご両親に礼のひとつでも言ってほしいんだが・・・」
岩城さんは俺の頭を引き寄せて、膝で挟み込んだ。
信じらんないけど―――無自覚でやってるんだよね、こういう仕草。
心臓に悪いよ、ほんと。
「・・・うちの兄貴なんかは、そこまで、割り切れないと思う。お礼どころか、お義父さんたちに失礼なこと、言うかもしれない」
「大丈夫でしょ」
俺は岩城さんの膝に、頬をこすりつけた。
ほんのりした肌の熱が、パジャマ越しに伝わってくる。
「・・・お義兄さん、世間体を気にするタイプだから」
こっそり言ったら、頭を小突かれた。
「痛いよ」
「ばか」
「心配しないで。大丈夫だよ、きっと」
「ああ・・・」
甘いテノールが、ちょっとかすれた。
「ねえ、岩城さん。ホントに夫婦って感じだよね、こういうの。・・・親戚づきあいの気苦労?」
「・・・ばか」
それは恥ずかしいけどうれしい、って意味の「ばか」だね。
俺は岩城さんの内腿に、そろりと指を這わせた。
悩むのはもうおしまい、って合図。
弾力のあるきれいな筋が、きゅっと緊張する。
ゆっくりゆっくり、シルクのパジャマの上から愛撫した。
もどかしいと、思って欲しくて。
「・・・香藤」
俺の髪にからんだ指に、力が入った。
「・・・二階、行こう・・・?」
ささやいたら、ちょっと笑われた。
「わかりやすいな、おまえは」
「だって岩城さん、いい匂いがするから」
俺は立ち上がって、岩城さんの腕を取った。
「・・・加減しろよ。明日は朝から、仕事だぞ」
岩城さんはそう言うと、先に立ってベッドルームに向かった。
「んん・・・」
深いキス。
岩城さんの息が鼻に抜けて、色っぽい。
ほのかなランプの灯火に浮かび上がる、しなやかな全裸。
潤いを帯びた、なめらかな素肌。
―――ほんとにいつも、思うけど。
どこをどう見ても、見事に男性の身体、なんだ。
きれいについた筋肉も、骨格も。
すらりと伸びた硬質の肢体も。
性器だって、立派だよね。
あんまり体毛の濃いほうじゃないけど。
でも。
どうしようもなく、そそられる。
この綺麗な人を、俺だけが自由にできる。
この綺麗な人が、俺だけにすべてを許して脚を開く。
そう考えるだけで、くらくらするんだ。
「あぁ・・・ふっ・・・ん・・・」
あえぎ声に、心臓がバクバクする。
岩城さんの両腕が俺の首にからみついた。
俺はぎゅっと、愛しくてたまらない恋人を抱きしめた。
「はぁ、ん・・・か・・・とぉ・・・」
夢見るようにうっとりと名前を呼ばれて、全身がしびれた。
「・・・い、わき・・・さんっ」
煽られて、俺はいっそう激しく腰をグラインドさせた。
岩城さんの最高にいいところ。
肛穴の奥の奥の、俺しか知らない聖地。
俺を求めてうねる、熱い肉壁。
そこを苛むようにペニスを叩きつけ、刺激を与えた。
何度も、何度も、いたぶるみたいに。
「ああぁ・・・あん・・・はうっ・・・!」
我を忘れたような、嬌声。
涙をこぼしながら、岩城さんが上半身をよじった。
荒い息をつきながら、夢中で、俺に腰を擦りつける。
快感にしびれながら、俺は岩城さんの痴態を見下ろした。
なんて、扇情的な人なんだろう。
岩城さんは俺にとってはもう、麻薬みたいなもので。
全身どこを見ても、触っても、俺は興奮する。
いつもいつも、抱いていたい。
この熱い肌を、キスの痕で埋め尽くしたい。
どれほど貪り尽くしても、まだ足りない。
そんな独占欲丸出しの願望で、頭がおかしくなりそうだった。
「んん・・・ねえ、いい? い・・・岩城さ・・・んっ」
細い腰を抱え直して、俺は聞いた。
岩城さんの身体を二つ折りにするみたいな、無理な姿勢のまま。
それでも岩城さんは、瞳を閉じたまま、頷いた。
眉を寄せて、俺にしがみついて。
俺は首を伸ばして、岩城さんの乳首に噛みついた。
「ああっ・・・!」
途端に、甘い悲鳴が上がった。
感じるんだよね、ここ。
下手すると乳首だけで達けるんじゃないかってくらい、敏感なんだ。
歯形がつくくらい、執拗に、俺はそこを責めた。
こらえきれずに、岩城さんのペニスが弾けた。
俺のペニスをぎゅうぎゅう締めつける内壁が、条件反射のように熱く震えた。
どうしようもない、酩酊感。
俺は仰け反る岩城さんの身体を支えながら、ラストスパートをかけた。
「やっ・・・あぁぁん・・・はぁ・・・んはっ」
半開きの唇からは唾液が伝い落ち、もう、かすれたような吐息まじりのあえぎ声しか、聞こえてこない。
桜色に染まって、痙攣する身体。
両脚が、するりと俺の腰にからみつく。
貪欲に俺を求め、誘い、翻弄する。
「いわ・・・きっ・・・さんっ!」
根こそぎ持っていかれそうな快感に、とうとう降参して。
俺は腰を叩きつけて、岩城さんの最奥で果てた。
「んあ・・・あ、あ、はぅ・・・っ」
中ではじける熱いしぶきに、岩城さんがのたうち回った。
俺はほてった愛しい身体を腕に抱いて、なだめるようにキスをした。
汗のしたたるうなじに。
まだ弛緩できずにいる肩に。
鎖骨の下の、消えかかったキスマークに。
好きだよ。
好きだよ。
好きだよ。
呪文のように、そう繰り返しながら。
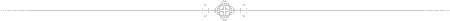
ましゅまろんどん
11 December 2005
2012年10月26日、サイト引越にともない再掲載。サブタイトル改題。また、若干ですがテキストを修正しました。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
