春隣 Spring steps
春隣(はるどなり)――― Spring steps ――― 2
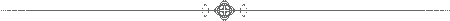
荒い息が少しずつ静まる。
鼓動が、緩やかになっていく。
「・・・か、とう・・・」
かすれ声が、充足を伝える。
うれしくて、俺は岩城さんの額にキスした。
ぺったり濡れた黒髪が一筋、唇に張りつく。
セックスの後の、正気に戻る時間―――っていうのかな。
俺は、この瞬間が案外、気恥ずかしい。
バカなことを言って岩城さんを怒らせるのは、こういうときが一番多い。
―――それがわかってるから。
なるべく余計なことは、言わないようにしてる。
つもり。
ぐったりして、岩城さんは眠そうに目を閉じた。
時計を見ると、午前二時ちょっとすぎ。
「・・・大丈夫?」
わずかに頷く。
「しんどそうだね、岩城さん。寝てていいよ。俺が、きれいにしてあげるから」
うっすらと、瞼が開いた。
どうしようか、迷ってる感じのまなざし。
それから観念したみたいに、ふるえる睫毛で頷いた。
余力のあるときなら、俺を振りほどいて、さっさとひとりでバスルームに行っちゃうんだけどね。
今晩の岩城さんは、疲労困憊、って風情だった。
―――無理させて、ごめん。
心の中で謝って、俺はバスルームから持ってきたタオルで、岩城さんの身体を丁寧に拭いた。
濡れたタオルで、汗をぬぐって。
ふかふかのタオルで、もう一度、全身をきれいにする。
ときどきくすぐったそうに、ちょっと身をよじるけど。
岩城さんは安心しきって、俺に全身を任せてくれてた。
気持ちよさそうで、すごく可愛い。
―――こういうとき、ね。
本当に、惚れてるよなあ、って思う。
惚れられてる、とも。
ただの恋人じゃなくて、夫婦なんだって実感する。
こうやって奉仕するのが、うれしい。
こうやって甘えてもらえるのが、うれしい。
俺はそっと、岩城さんの太腿に手をかけた。
なめらかな筋肉が、ピクリとわずかに緊張する。
岩城さんが頬を染めて、顔を背けた。
抵抗がないのを確認してから、俺はそろそろと、指を岩城さんの肛穴に這わせた。
「・・・ん・・・」
かすかに、色っぽい声がもれた。
それだけで、俺は理性を失いそうになる。
聞こえないふりをして、俺はそこに指を差し込んだ。
なるべく刺激を与えないように。
―――ってのは、まあ、不可能なんだけど。
愛撫をしたいわけじゃないから、今は。
ぽってりとピンク色に腫れた蕾は濡れていて、ヤバイくらいだけど。
俺は慎重に、少しずつ、そこから自分の精液を掻き出した。
とろりとした粘液があふれ、俺の指を伝わる。
エロすぎる、眺め。
「んっ・・・あん・・・」
目を閉じて、下半身を俺に預けたまま、岩城さんがそっとあえぎをかみ殺す。
いや、かみ殺せてないから、問題なんだけど。
でも、俺がセックス目的でやってるんじゃないって、信用してもらっちゃってるから。
俺はなけなしの平常心にしがみつきながら、劣情と戦った。
半ば目を逸らして、丁寧にそこを清める。
そう・・・俺にとっても、岩城さんにとっても、大事なところだからね。
きれいにしたい。
してあげたい。
「はい・・・おしまい」
小さくそう言って、俺はため息をついた。
上半身を起こしかけた岩城さんを制して、俺は肘をついて、キスをねだった。
自制心を保てたご褒美、ちょうだい。
くすりと笑って。
岩城さんは片腕で俺の首を抱きこむように、キスしてくれた。
「・・・パジャマ」
そう言われて、俺は床に散らばっていたパジャマとセクシーな下着を拾い上げた。
「着せてあげようか?」
からかい半分でそう聞くと、岩城さんが目を細めてにらんだ。
「・・・それくらい、自分でできる」
低い声でそう言って。
片腕を無造作に、俺に突き出した。
起こしてくれって、無言のご下命。
ほんと、女王様なんだから。
でも、これって・・・甘えて、くれてるんだよね。
それが、うれしくって。
俺はうやうやしくその手にくちづけて、岩城さんを助け起こした。
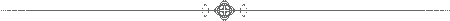
「岩城さぁん」
ドア全開の、岩城さんの部屋。
俺はまっすぐにクローゼットを目指した。
ひょいと覗き込むと、奥のほうでかさかさと物音がする。
「ねえ、ネクタイ―――」
岩城さんは、弾かれたように振り返った。
「どしたの?」
言いかけて、俺は岩城さんが触れていたものに気づいた。
ウォークイン・クローゼットの一番奥。
防虫カバーのかけられた、白いタキシード。
「あは・・・!」
顔を緩めた俺を見て、岩城さんが眉をしかめた。
顔が、ちょっとだけ赤い。
「うるさい」
「・・・何も言ってないよ?」
「・・・うるさい」
まったく、もう。
俺は狭いクローゼットの中で、岩城さんを抱き寄せた。
鼻をこすりつけて、至近距離で見つめ合う。
「花嫁衣裳、もう一回着たい?」
「・・・誰が花嫁だ」
「自分で白、選んだくせに」
くすくす笑う俺を、岩城さんは不機嫌そうに見返した。
「白タキシードはお嫁さんだよって、俺あのとき、言ったでしょ?」
「・・・おまえが・・・」
「ん?」
「・・・おまえが、白を着た俺を見たいって、言ったからだろう」
憮然とした低い声。
照れ隠し、なんだよね。
「そうだけど。でも・・・残念だけど、岩城さん」
「・・・?」
「もうあのタキシードは、二度と着れないよ。俺と結婚、したからね」
絶対に離婚なんて、ありえないからさ。
そう言ったら、岩城さんは諦めたみたいに笑った。
「そんなこと、わかってる。・・・まあ、昔のことはいい」
「昔のことって」
俺は苦笑して、岩城さんのおでこにキスをした。
「あれ見て何を、考えてたの?」
「・・・忘れた」
岩城さんは、するりと俺の腕の中から抜け出した。
「んもう」
「・・・貸せ」
ぶっきらぼうに、俺が手にしていたネクタイを奪う。
「俺を嫁扱いするのは、ネクタイのひとつもまともに結べるようになってからにしろ」
ふてくされたようにそう呟いて、岩城さんは無造作に細長いシルクを俺の首に巻きつけた。
無言で、向かい合って。
岩城さんは慣れた手つきで、俺のネクタイをしめてくれた。
朝日のあたる明るい部屋で、俺は改めて、岩城さんを見つめた。
光沢のある渋いグレイのダブルのスーツ。
―――やせて一回り細くなって、昔のスーツが着られなくなった岩城さんが新調したばかり。
流れるようなきれいなテイラードのラインが、岩城さんの身体を優雅に包み込んでる。
胸元には、ワインレッドのタイ―――エルメス、だよね。
それはもう、水も滴るいい男ぶりだった。
「ほら、できたぞ」
ポンと俺の胸をたたいて、岩城さんがちょっと眩しげに目を細めた。
俺が着てるのは、岩城さんが見立ててくれたモカ色のシングルスーツ。
四つ釦で細身のシルエット。
ポケットが縦にふたつ並んでる、ちょっと遊びのあるデザインだ。
くすんだオレンジ色のゼニアのタイは、岩城さんから借りた。
「・・・俺、いい男?」
岩城さんがうっとり見てるもんで、俺は思わずそう聞いた。
「ばーか」
軽くいなして、岩城さんは時計を見た。
「行くぞ。そろそろ、迎えが来るだろう」
「うん」
岩城さんの後を追って、俺は階段を駆け下りた。
―――実を言うと岩城さん、ちょっと腰、辛そう。
昨夜は遅かったのに、強引に相手させちゃったから。
いま謝るとよけい怒られるから、黙ってるけど。
靴箱の前にしゃがみこんで、岩城さんは靴を探してた。
「おまえは、これだな」
ほとんど黒みたいなダークブラウンのウィングチップ。
そうか。
俺、このスーツに合う靴持ってないから、貸してくれるんだ。
―――興味なさそうなくせに、俺の靴や服のレパートリー、本当によく知ってるよね。
そのまま磨こうとする岩城さんから、あわてて靴を奪い取った。
「自分でやるよ、それくらい!」
岩城さんは自分の靴を履いて、ドアの前に立った。
俺の格好を、頭の先からチェックするみたいな視線。
「・・・うん」
「どうしたの?」
「いい男、だな」
「え!?」
虚をつかれて、俺は岩城さんをマジマジと見つめた。
「これなら、ご両親にもきっと・・・」
満足そうに頷く岩城さんを、俺は問答無用で抱きしめた。
「・・・おい、香藤っ」
起きたときから、ずいぶんかいがいしく面倒を見てくれると思ったら。
岩城さん、俺の家族の目を意識してたんだ。
―――ほんとに、もう。
「可愛いすぎだよ、岩城さん。・・・キスして?」
耳元で、ささやいた。
「・・・朝っぱらから」
苦笑した柔らかい唇が、そのままそっと重なる。
暖かい舌が俺の下唇をそろりと舐めて、あっという間に離れていった。
「・・・おしまい?」
「・・・もう清水さんが、来るだろう」
ドアを指差した岩城さんの左手に、光るものを見つけた。
仕事のときはしないって、なんとなく暗黙の了解になってる、結婚指輪。
「いいの、岩城さん?」
俺の視線を追った岩城さんが、ふっと笑った。
マリアさまみたいな、やさしい笑顔。
最近の岩城さんは、よくこういう顔をする。
「いいだろ、今さら」
ひょっとしてこれも、俺の家族と会うから、なのかな。
船橋に行くときは、意識して、リングしてるよね。
岩城さんは、俺たちが夫婦だってことに、とてもこだわりがあるから。
それはもう、ときどき俺がびっくりするくらい。
―――俺だってもちろん、結婚を軽く考えてるつもりは、ないんだけど。
なんて言うのかな。
古い日本の、伝統的な「夫婦」のありかたを、一生懸命なぞろうとしてる感じ?
夫唱婦随って言ったら、おかしいかな。
実家のご両親の結婚のかたちを、たぶん無意識に、真似てるんじゃないかと思う。
―――って、これは俺の勝手な想像。
プラチナの指輪をそっとなぞって、岩城さんが低く聞いた。
「嫌か?」
「まさか。俺もしたほうがいいかな、と思っただけだよ」
ちょっと首をかしげて、岩城さんは笑った。
「おまえはいいんだ。どっちでも、好きにすればいい」
ちょうどそのとき、清水さんのヒールの音が玄関の外で聞こえた。
「おはようございまーす!」
俺は先に立って、玄関を開けた。
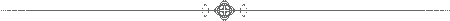
ましゅまろんどん
11 December 2005
2012年10月29日、サイト引越にともない再掲載。若干ですがテキストを修正しました。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
