水の都にて
水の都にて 4
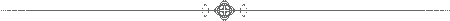
映画祭の最後の夜を飾るパーティーは、なかなか盛大だった。
壮麗な貴族の館のバンケティング・ホール。
見渡す限り、華やかな映画スターたちで賑わっていた。
一応同業者ではあっても、今までスクリーンの上でしか見たことのない、どこか自分とは世界が違うと思っていた俳優さんや監督たちが、俺と岩城さんに気がつくと笑顔で声をかけてくる。
いい映画だったよ、とか。
ハリウッドに来たら声をかけてくれ、とか。
国際的な映画スターのオーラに、さすがの俺もちょっと押され気味。
俺はため息をついて、岩城さんを見つめた。
岩城さん、それはもう凛とした、水も滴るいい男っぷりなんだもん。
―――艶姿、なんて言ったら、すごく怒られるだろうけど。
めったに着ないタキシード。
岩城さんも俺も、お揃いのデザイン。
俺の胸には、赤い大輪の薔薇と濃いオレンジ色のスプレー薔薇が飾られていた。
岩城さんの胸には、白い百合と紫色のかすみ草。
シャープな仕立てのラインと漆黒に輝くシルク地のせいで、岩城さんのすらりとした肢体と白皙の美貌が引き立つ。
背筋をピンと伸ばしたその長身の立ち姿は、いやでも人の目をひいた。
実際、セクシーなカクテルドレスをまとった美女たちが、岩城さんを囲んでちやほやしていた。
それも気になるけど。
ゲイだと噂のあるあの役者、この監督が、にこやかに岩城さんに話しかけ、それこそ舐めるように値踏みしているのに、本当に冷や冷やさせられた。
―――当の岩城さんはそういう秋波に疎いから、それが救いではあるけど。
テーマが「仮面舞踏会」だというので、俺たちは一応、いかにもヴェネツィアらしい金の縁取りのついた半面マスクをホテルで借りてきていた。
だけど実際には、マスクをしてる人はほとんどいなくて。
正装すらしてない参加者もいるくらいで、正直、少々気が抜けた。
凝った細工のマスクを片手でもてあそびながら、俺は岩城さんを振り返った。
「こんなんだったら、俺たちももうちょっとカジュアルでもよかったかもね」
「そうだな」
眩しそうに俺を見つめる岩城さんの姿に、俺の顔がどうしてもゆるむ。
周囲の視線がちらちらと岩城さんに向けられるのを感じながら、俺はまたしても、おなじみの葛藤に陥っていた。
―――美しい恋人を、世界中に自慢したい。
反面、美しすぎる恋人を、誰の目にも触れさせたくない。
ああ、永遠のジレンマ。
―――俺はよっぽど間抜けな惚け顔で、岩城さんを眺めていたんだろう。
「香藤・・・?」
「ごめん。俺、岩城さんにみとれてた」
「・・・ばか」
岩城さんの左手をとり、指輪のあたりにキス。
そのまま引き寄せて、細い腰に腕を回す。
手のひらでそっと、腰から下へ撫で下ろした。
岩城さんは、俺の腕からつるりと逃げ出した。
「・・・岩城さんが、きれいすぎるからいけないんだ。老若男女関係なく、誰でも流し目ひとつで殺しちゃうんだもん」
「何を言ってるんだか」
岩城さんは、ちょっと俺をにらむように見つめた。
「俺のことばっかり言うな。おまえこそ、自分がどれだけ注目されてるか、気づいてないじゃないか」
俺だってやきもちくらい焼くぞ、と恨めしそうにささやかれて。
―――だめだ。
岩城さん、かわいすぎ!
「岩城さんしか見えてないよ。知ってるくせに。・・・ねえ」
首をかしげて俺を見る岩城さんに、いたずらっぽく囁いた。
「昨夜はすごい盛りあがっちゃったよね。―――腰、大丈夫?」
とたんに、白い頬に朱が散った。
「・・・わかってるなら、無茶するな・・・!」
「あは、ごめん。でもさ、ほら、ここ」
白い項を指でそっとなで上げた。
「キスマーク、ぎりぎり隠れてよかったよね」
「・・・!」
低く唸って、さっさと俺から遠ざかる後姿。
追いかけようとしたら、脇から声をかけられた。
「香藤くん」
知り合いの映画評論家だった。
日本から来てるジャーナリストや映画関係者の数の多さには驚きっぱなしだけど、これはどうやら、何かと話題の『冬の蝉』効果らしい。
彼らに愛想をふりまくのも、俺たちの仕事のうちだ。
「『冬の蝉』成功、おめでとう。コンペ出品作品じゃないのに、すごい話題になってるね」
「ありがとうございます」
「これで君も、完全復帰だねえ」
映画のプロモーションの予定。
次のドラマの撮影。
CMとポスター撮り。
こういう話をするのも、俺の仕事なんだけど。
この評論家は辛辣だけど根はいい人で、だからこそちゃんと相手をしないと失礼なんだけど。
―――俺の視線は、どうしても、岩城さんを探してしまっていた。
広い会場の真ん中あたりで、海外ジャーナリストに囲まれてる岩城さんの黒髪が見えた。
くすくす笑われて、我に返った。
「あ・・・すみません!」
「相変わらずだねえ、香藤くん」
「へ?」
「岩城くんのことさ。愛妻家っていうのか、恐妻家っていうのか。彼のことになると、盲目だよねえ」
「・・・お恥ずかしいです」
「ま、いつまでもお熱くて結構だけど。ほんとにね、君たちを見てると、あんまり開けっぴろげなんで、特殊な関係だってことを忘れそうになるから困るよ」
「特殊って・・・」
俺は顔をしかめた。
「だってそうでしょ? ゲイだってだけで幾らでもバッシングにあったり、干されたりしかねないはずなのに。なんでかそれが、人気の理由になってるんだからねえ」
こういうとき俺は、黙って笑うことにしてる。
俺自身は、自分のことをゲイだと思ったことはない。
岩城さんもそうだけど、お互いと恋愛関係になるまで、同性に興味を持ったことがまったくないからだ。
ないけど、実際、男性である岩城さんを生涯の伴侶と呼び、心も身体も許しあっている以上、あんまりしつこく「俺はゲイじゃない!」と言い続けるのもどうかと、最近、思うようになった。
ほんと言うと、どうでもいいじゃん、って感じ。
「・・・ほら、奥方様のお呼びだよ。それじゃ、またね、香藤くん」
指差された方向を見ると、岩城さんが大きなフレンチ・ウィンドウの脇にひとり佇んでいた。
ようやく人の輪から解放されたらしい。
ワイングラスを片手に、俺のほうに、ちらりと物言いたげな視線を走らせる。
俺はそのすらりとした美貌の人に向かって、まっすぐ歩き出した。
「インタビューは終わったの?」
「ああ。インタビューって言うより、仕事の打診・・・かな。『冬の蝉』を気に入ってくれたフランスやイタリアのプロデューサーが、俺の来年のスケジュールとか聞いて来るんだ。どこまで本気なのか知らないが」
「すごいね、岩城さん。おもしろそうな話だといいね」
「うん・・・まあ。うれしいけど言葉の壁があるから、あまり現実的じゃないだろうな」
「そう? その気もないのにそんな話、持ちかけないと思うけど」
「―――そういえば、昨日の記者に謝罪されたぞ」
くすくす笑いながら、岩城さんが言った。
「ああ、あの意地悪な質問したやつ。何だって?」
「アメリカでは、メインストリームの俳優が好んでゲイの役をやるなんてありえないから、俺みたいのはどうしても色眼鏡で見てしまう、らしい」
「ふーん」
思ったほど気に病んでないみたいで、俺はほっとする。
「そういえば俺もね、さっきそんなこと聞いたよ。『冬の蝉』はヨーロッパでは、主人公の性別なんか超越した悲恋だって受け入れられるだろうけど、アメリカでは違うだろうって」
「どう違うんだ?」
「アメリカでは、どうしても政治的プロテストに思われちゃうって。男同士でも真剣な恋愛は成り立つ、悪いか、って言ってるって解釈されるって。・・・なんか意外だよね」
「そうだな」
岩城さんが俺を見つめる。
「どしたの?」
「・・・さっき。おまえのことも、ずいぶん聞かれたぞ」
「ほんと? どんなこと?」
「仕事のこともだけど・・・そっちは、所属プロダクションが違うから答えられないって言ったんだ。でも、プライベートな話のほうが多かった」
「昨日の記者会見で、私生活はオフリミットって言ったからでしょ」
「だろうな。よっぽど、俺たちのことに興味があるらしい」
岩城さんが苦笑した。
「―――そんなに、珍しいかな」
「岩城さん?」
「芸能界なんてところにいても、誰にだって家庭がある。俺たちだって同じだろ。どっちも役者なんてやってるから、露出度が多いのはしかたない。でも、昨日や今日一緒になったわけでもないのに、なんでみんな、俺たちのこと知りたがるかな・・・」
困ったように笑う岩城さんを、俺は抱きしめたくなった。
「しょうがないよ、岩城さん。有名税ってやつでしょ、それ」
「うん・・・」
「ここにいる人たちは日本での俺たちを知らないから、余計に知りたがるんだよ」
「・・・そうだな」
「うざいこともあるけど、それも含めて、俺たちの生きてく世界だもんね」
「ああ」
「・・・俺が守るよ、岩城さん。岩城さんにいやな思いは絶対にさせたくない。辛いことがあったら言ってね。俺、岩城さんが笑っててくれるなら、何でもするから」
「ああ・・・」
そうだったな、と頷いて、岩城さんはやさしい笑顔を見せてくれた。
―――この人を守りたい。
この人がいつも安心できる場所でありたい。
俺はあらためてそう思った。
ふいに、優雅な音楽がバンケティング・ホールに響き渡った。
室内オーケストラが軽快なワルツを演奏し始め、客がパートナーの手をとってリズムに合わせて踊りだした。
ざわめく会場のライトが落とされ、ヴェネツィアン・ガラスのシャンデリアが、いっそうきらびやかに輝きだす。
ゆらゆら揺れる蝋燭の光。
窓の外には、水の都。
なんていうのか―――ヴィスコンティ映画の世界に紛れ込んでしまったような錯覚を起こす。
俺は、岩城さんの耳に唇を寄せた。
「岩城さん、踊ろう!」
「えっ?」
本気でびっくりしてる黒曜石の瞳が、くっきりと俺を映した。
「冗談だろう」
「いいじゃない、俺たち映画祭参加者のための舞踏会なんだから」
腕を取られて、わずかに抵抗する。
「俺はワルツなんて踊れないぞ」
「大丈夫だって。俺だってステップなんて知らないけど、ほら見てよ。みんな、音楽に合わせて適当にスウィングしてるだけだよ」
「男同士で、踊るつもりか・・・?」
「うん。俺のパートナーは岩城さんだけだから、そうなるね」
「・・・本気なのか」
いやだというより、本当に困惑した表情で、岩城さんは俺を見つめた。
「写真取られて、帰国したら、またさんざんマスコミに騒がれるぞ・・・?」
「うん、そうだろうね。でもそれも、映画のいい宣伝になるんじゃない?」
あんまり説得力があるようには思えなかったけど、このパーティーに出るのも仕事のうちだってことを、岩城さんは思い出したみたいだった。
「・・・おまえには、羞恥心ってものがないのか・・・」
ため息まじりに岩城さんが言った。
その身体から少し力が抜けたのを感じて、俺は、強引に岩城さんの手を取り、ダンスフロアに引っ張って行った。
会場から、どよめきが起こる。
「お手をどうぞ」
俺はうやうやしく一礼した。
「・・・ばか」
周囲の視線を一身に浴びた岩城さんが、顔を真っ赤にして文句を言った。
「悪目立ちしすぎだろう、これ」
「いいから。ほら、気にしないの」
俺は岩城さんの抗議をいなして、その細い腰に腕を回した。
岩城さんの手を取って、俺の肩に置かせる。
ちろりと、岩城さんが不本意そうな視線を投げかけた。
―――ごめんね。
女性扱い、してるわけじゃないけど。
でもこの状況じゃあ、俺がリード役に回るしかないでしょう?
音楽が再び始まる。
どこかで聞いたことのある、きれいなワルツのメロディー。
踊ってみると案外リズムが早くて、ついていくのが大変だった。
ぎこちない岩城さんをあやすように胸に包み込んで、俺は音楽に合わせてスウィングした。
タキシード姿の長身の男が身を寄せ合って踊る様子に、会場が騒然としてる。
無数のフラッシュが焚かれ、目がくらみそうだ。
俺たち、ワルツの腕前はあやしいけど。
頬を染めて俺に身を預ける岩城さんの立ち上るような色気に、周囲が圧倒されてるのがわかった。
「信じられない―――」
すっきりした眦をピンクに染めて、岩城さんがつぶやく。
「んん?」
俺のわがままに甘すぎる自分が悔しくてしかたない、という表情。
おまえはだいたい非常識すぎる、って小声で文句を言いながら。
岩城さんはそれでも、おとなしく俺の腕の中で音楽に身を任せていた。
「・・・岩城さん。ヴェネツィアの別名、知ってる?」
「別名?」
「うん。アドリア海の真珠、って言うんだって」
「・・・きれいな名前だな」
「うん。―――俺ね、岩城さんのことみたいだな、って思ったんだ」
「ばっ・・・」
ワルツに少し息を乱しながら、岩城さんが俺を睨んだ。
頬を染めてそんな顔したら、俺を喜ばせるだけだって、気づいてないんだよね。
―――ほんとに、もう。
「好きだよ、岩城さん」
「・・・香藤」
つややかな黒髪が俺の頬をくすぐる。
「キス、してもいい?」
「!」
岩城さんが俺の腕をすり抜けるより早く。
俺は、その魅惑的な唇を盗んでいた。
この誰よりもきれいで、かわいくて、色っぽい恋人が、俺だけを愛してくれているって。
岩城さんは、俺のものだって。
そして俺も、岩城さんだけのものだって。
世界中の人に、知ってもらいたかった。
ヴェネツィア最後の夜。
俺は夢心地で、しっかりと岩城さんを抱きしめた。
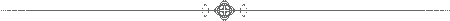
ましゅまろんどん
26 September 2005
最後までおつきあいくださり、ありがとうございました。
長年文章を書いて生活してますが、これが『春抱き』二次創作としては最初の長編。
砂を吐きそうな甘さばかり目立ちますが、ゆるく楽しんでいただければ幸甚です。
2012年10月22日、サイト引越にともない再掲載。若干手直ししてあります。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
