春隣 Spring steps
春隣(はるどなり)――― Spring steps ――― 3
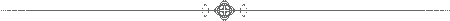
『冬の蝉』の有楽町プレミア。
何しろヴェネツィア映画祭で派手に話題をさらい、ハリウッドでも大好評の映画だ。
久々に世界が注目する邦画ってことで、配給側も制作会社も、かなり気合が入ってるらしい。
「岩城さん!」
「香藤くーん!」
「サインお願いしまーす」
「こっち向いて!」
映画館ビル前に車でつけると、待ち構えていたファンの大歓声が上がった。
報道カメラマンの焚くストロボライト。
携帯電話のカメラのフラッシュ。
差し出される花束やカード。
ロープを張ったその向こうの、何重もの人だかり。
差し出される、手、手、手。
―――びっくりするほどの喧騒だった。
「大丈夫か?」
ぶつけられた花束を無造作につかんだ岩城さんが、俺を振り返って苦笑した。
その笑顔を狙って、一斉にシャッター音が響く。
「ほんとに久しぶりだよ、こういうの!」
大声を出さないと、聞こえないくらいの騒ぎ。
「お兄ちゃーん・・・!」
その中で、か細い声が聞こえたのは、本当に偶然だ。
黄色い声を張り上げる女の子たちの波に揉みくちゃにされ、飲み込まれそうな俺の妹の姿。
「洋子!?」
俺は呆れて、大股で近づいた。
本来なら招待客は、とっくに館内に案内されてるはずだ。
「何してるんだ、おまえ!?」
「だって・・・遅刻しちゃって。どこから入っていいのか、わからないんだもん」
俺に向かって悲鳴を上げるファンたちに囲まれて、洋子は途方に暮れた顔をした。
「バッカ・・・トロすぎだろ、おまえ。親父たちは?」
「もう、中だと思う」
離れた場所にいた岩城さんが、こちらを向く。
俺たちのいる一角に、大勢の女の子たちがざざっと押し寄せた。
「洋子さん?」
妹の姿を見とめて、岩城さんが周囲に視線を走らせた。
「香藤、このままじゃ洋子さん、押しつぶされるぞ」
「うん」
俺は警備の職員に事情を説明して、洋子をロープの向こうから救出した。
女の子たちの嬌声が、ヒステリックなものに変わる。
洋子が首をすくめた。
「ごめんね! 家族なんだ!」
俺は苦笑して、気色ばんだ彼女たちに肩をすくめてみせた。
「俺たちはもうしばらくここにいるから、早く、清水さんと―――」
洋子にそれだけ言って、岩城さんはさっさと別の方向に歩いていった。
カメラに向かって笑顔を見せ、何枚かの色紙にペンを走らせる。
俺もそれにならって、ファンサービスに徹した。
目の端に、清水さんが洋子をかばうように会場に入って行くのが見えた。
プレミアっていうのは、俺たちにとっては仕事の場だ。
スポンサーや配給会社のお偉いさん。
DVDやサントラの制作会社の人たち。
海外マーケティング担当のエージェントさんたち。
マスコミや映画評論家。
滝沢監督やスタッフの面々。
原作の伊坂先生。
もちろん、共演者たち。
全員にきちんと挨拶し、お礼を言うのは、単なるマナーってだけじゃない。
今後の仕事につながる、大切なネットワーキングの機会でもある。
「ふえー・・・」
一応ひととおり義務を果たした頃には、もうくたくただった。
プレミア独特の熱気に、あてられた気分。
どさりとパイプ椅子に倒れこんだ俺を、岩城さんが立ったまま笑って見下ろした。
岩城さんの控え室。
「フルで芸能界復帰したら、こんなものじゃないぞ」
俺の髪を撫でながら、静かに言う。
「わかってるよー」
目の前の細い腰を抱きしめて、俺はグレイのスーツに額を擦りつけた。
「こら」
そろりと腰から下へ這いだした俺の右手を、岩城さんが捕まえた。
「この辺、辛そうだから」
頭の上で、苦笑混じりのため息。
「・・・そういうのは、気づかないでいいんだ」
それから、もう一度ため息。
今度は、俺が理由じゃないね?
「・・・どしたの?」
「すっかり忘れてたんだが―――」
岩城さんが、困ったみたいに笑った。
「何を?」
「あるだろ・・・ラブシーン」
あは、顔が赤い。
「あれを家族に見られると、思うとな」
そうか。
―――確かに俺、映画の中で、岩城さんを抱いてるよね。
『冬の蝉』は文学作品だから、そんなにあからさまな性表現があるわけじゃないけど。
それでも岩城さんは二度ほど、全裸で俺に組み敷かれてる。
いやもちろん、本当に全裸だったわけじゃないけど。
俺は、川原で裸に剥いた岩城さんの身体を思い出した。
輝くような白い肌。
あれ、日本中の人が、見るんだ・・・?
「うわ・・・やば」
「は?」
「あんなシーン、撮らせるんじゃなかったぁ」
頭を抱えた俺が何を考えてるか、岩城さんにはわかったらしい。
「また、そんなこと」
苦笑して、俺の髪をくしゃくしゃかき回した。
「話をそらすな」
「・・・そらしてなんか、ないけどさ」
ふと、記憶がよみがえった。
『身体の奥に、火をつけてくれ―――』
岩城さんの、熱いささやき。
草加とのただ一度かもしれない逢瀬にすべてを捧げる秋月の、痛々しいほどせつない心情。
―――もちろん俺だって、わかってる。
あれは裸だ、エッチだって、茶化せるようなシーンじゃない。
逃げ場のない、息が苦しくなるほどの想い。
ハッピーエンドなんてあり得なかった時代の、あだ花みたいな悲恋。
あまりにも純粋で、それゆえに哀しくて。
―――俺も、岩城さんも、それを演じるのに夢中だった。
「大丈夫だよ、岩城さん」
「・・・香藤」
「そりゃあ岩城さんは、恥ずかしいだろうけど。俺だって、きっと映画見るたびに、なんで岩城さんの肌見せちゃったんだろうって、後悔すると思うけど。・・・でも大丈夫。絶対大丈夫だよ」
岩城さんがひっそり笑った。
「おまえの大丈夫には、何の根拠もないんだがな・・・」
だけど、安心するんだよ、って言うみたいに。
岩城さんは、俺の肩にしっかりと手を回した。
「岩城さんのお父さんも、うちの家族も、あの映画を見たらわかるよ。あそこにいるのは、秋月と草加だって。それを役者の俺たちが演じてるんだって、わかってくれるよ」
「・・・ああ」
岩城さんが、ゆっくり腰をかがめた。
降りてくるキスを、俺は首を伸ばして受け止めた。
「ん・・・」
確かめるような、穏やかなキス。
岩城さんの片手が、やさしく頬を撫でる。
―――俺さ、岩城さんの手、すごい好きなんだ。
いつだってすごく雄弁に、岩城さんの思いを伝えてくれるから。
『冬の蝉』の封切上映は、大成功だった。
結局、俺たちはずっと、岩城さんの控え室にいたんだけど。
スタッフたちはモニター室から客席のようすを覗いていて、かなりの手応えを感じたって興奮してた。
最初の回は、抽選で選ばれた一般招待客200人を除けば、みんな業界関係者やマスコミばっかり。
それでもあふれる熱気で、拍手が止まらなかったらしい。
そんな話を内線電話で聞いて、舞台挨拶にそろそろ出ようかってとき。
ノックの音がした。
「失礼します。岩城さん・・・と、ああ、香藤さんもご一緒ですか」
映画館のスタッフが、顔を覗かせた。
「ご家族の方、お通ししてもよろしいですか」
「俺の・・・ですか?」
「そうです。お忙しければ、お断りしますが?」
ちらりと俺に視線を走らせてから、岩城さんが頷いた。
「いえ、構いません。お願いします」
入れ替わりに、岩城さんのお父さんとお兄さんが入ってきた。
俺は思わず、姿勢を正した。
「親父・・・兄さん。遠いところを来てくれて、ありがとう」
そう言ったきり、岩城さんはどう続けていいのか、わからないみたいだった。
「どうぞ」
俺は立ち上がって、お義父さんに席を勧めた。
俺に軽く会釈しながら椅子に座り、お義父さんが口を開いた。
「元気でやってるようだな」
今まで聞いたことがないくらい、柔らかな口調。
それだけで、岩城さんの緊張が解けるのがわかった。
「いい映画だった」
渋い低音で、一言。
その後ろでお義兄さんが、同意して頷く。
岩城さんが、小さな笑顔を見せた。
「・・・ありがとう」
顎をしゃくって、お義父さんが俺に視線を向けた。
「香藤さん」
「はいっ」
実を言うと、俺は未だにこの人が苦手で。
まともに視線を合わせると、情けないことに少々ビビッてしまう。
「ああいうことなのかと、思いましたよ」
「・・・え?」
虚をつかれて、俺はお義父さんをマジマジと見つめた。
「君と京介も、あの主人公の二人のようなものなのかもしれない」
淡々とした口調だった。
「・・・そう考えれば、京介のことはあきらめがつく。そう思うことに、しました」
お義父さんなりに、俺たちを理解しようとしてくれてるって、ことか。
ありがたくて―――俺は黙ったまま、頭を下げた。
「・・・あきらめって、親父」
岩城さんが苦笑した。
「俺たちは・・・『冬の蝉』のふたりとは、ちがうよ」
ちょっと首をかしげて考えてから。
岩城さんはすっと左手を差し出して、指輪をかざして見せた。
「・・・これを、香藤がくれたときは」
お義兄さんが、眉をひそめた。
「俺自身、香藤がいつまで俺と一緒にいてくれるのかって、思ってた」
「岩城さん!」
俺は抗議の声をあげた。
「ちょっと待って。それは聞き捨てできないよ!」
「いいから、香藤」
黙って最後まで、聞いていてくれ。
そう訴える視線に、俺はしぶしぶ口をつぐんだ。
「・・・でも、親父。今は言えるよ。香藤は俺を捨てない。一生、捨てない。俺は、こいつがいなければ生きていけないけど、香藤も・・・俺がいなくちゃ生きていけないんだ」
ちょっと言葉を切って、岩城さんは照れたように笑った。
迷いのない、きれいな笑顔。
「確かに、秋月と草加に似てるかもしれないけど。でも、違うんだ。・・・俺は、香藤のために死なない。命を投げ出してもいいなんて、絶対に思わない。死ぬのは簡単だけど、そんなことをしたら」
岩城さんが、ちらりと俺を振り向いて微笑した。
「こいつも、生きてはいないから。俺は、何があっても、香藤と一緒に生きていたいんだ」
澄んだ黒い瞳がきらめいた。
「親父、兄さん・・・俺たちの関係を受け入れてくれとは、言わない。こうやって許してもらえて、それだけで十分、感謝してる。・・・だから、見ていてほしい。わかってもらえるように努力するから。お互いを伴侶に選んだのは間違ってなかったって、一生かけて、証明するから。最期まで添い遂げる覚悟だから。そのときに、俺たちを認めてくれれば―――」
そう言って岩城さんは、お義父さんとお義兄さんに深々と頭を下げた。
俺も一緒に、頭を下げた。
しばしの沈黙。
ゴホンと、お義兄さんが咳払いをした。
「京介、いい加減にしろ」
「え・・・」
「そういうのは、のろけって言うんだ。親父の前で、恥ずかしげもなく・・・」
顔を真っ赤にして、あさっての方角を見ながら、早口に言う。
つられて岩城さんも、ぽっと頬を染めた。
―――ほんと、兄弟だよねえ。
お義父さんが、くすりと笑った。
「雅彦。京介から、まさか夫婦の心構えの説教を聞かされるとは、思わなかったな」
心外な顔をするお義兄さんを無視して、お義父さんが続けた。
「京介。おまえの言いたいことはわかった。だが、ひとつだけ間違っておる」
岩城さんが、目をみはる。
―――こういう仕草、ほんと意外と幼くて、かわいいよね。
「儂を、幾つだと思っている。おまえたちの一生なんぞ、見届けられるわけがない。どうしても証明したいなら、儂の生きてるうちに済ませなさい」
お義父さんは、ゆらりと立ち上がった。
「そろそろ、舞台挨拶の時間だろう」
もう一度俺に会釈して、お義父さんはドアを開けた。
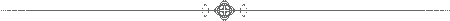
ましゅまろんどん
11 December 2005
2012年10月30日、サイト引越にともない再掲載。若干ですがテキストを修正しました。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
