第五話
Je te veux 2 あなたが欲しい 《1》
《la France》
冷たい雨がしとしと降っていた。
俺はふと、思い出す。
こういうのを氷雨と呼ぶんだと、以前、香藤と話したことがあった。
冬のパリ左岸、広大なリュクサンブール公園。
足元から凍てつくような寒さだった。
出演者用のテントの中で暖をとりながら、イレーヌが眉をしかめて俺に言った。
「まったくもう・・・これで今日も流れたら、私、しばらくアメリカよ。せめてここのシーンだけでも、今日中に撮っておきたかったのに」
「ええ」
「・・・大丈夫、キョースケ? 寒くない?」
小柄で、折れそうなほど細身の彼女が、身長180センチを越す大男の体調を心配する。
それがまるで母親か姉のように自然だから、おかしかった。
「大丈夫ですよ」
俺はそっと微笑を返した。
しばらくして気がつくと、雨はほとんどやんでいた。
セガン監督が、俺たちのテントに顔を出す。
「そろそろ、準備してくれるかな」
イレーヌの被っていた毛布を受け取り、俺はかわりに、彼女に衣装用の分厚いコートを着せかけた。
俺も、サンドベージュのトレンチコートに袖を通し、渋いハリスツィードのマフラーを首に巻きつけた。
細い銀縁のめがねをかけて、俺の準備は完了する。
イレーヌとふたり、円形の噴水に近づいた。
彼女の扮するマリ=コレットが、言葉を話さない、名前すら知らない異邦人の青年にはじめて、失った息子のことを打ち明けるシーンだった。
フランス語が通じるのかどうかもわからない相手に、とつとつと、子供を失った空虚感を語る母親。
それをじっと聞いていた青年が、黙ってひとしずく、涙をこぼす。
心を閉ざしていた彼が、彼女の哀しみに共鳴する―――。
この静謐な美しい映画の、中心となるはずの情景だった。
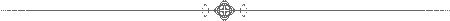
それは、しいて言えば、空気のゆらめきのようなものだった。
何かが聞こえたわけではない。
ただ、何かを感じて、俺はふと振り返った。
「え・・・」
幻影を見ているのだと思った。
冬枯れのマロニエの木立を駆け抜ける、長身の人影。
ダークブラウンのロングコートの裾をひるがえして、まっすぐ近づいてくる。
一直線に、俺に向かって。
思わず息を呑んだ。
「キョースケ?」
イレーヌが、俺の腕に手をかけたのがわかった。
その手を、やんわりと振りほどいた。
「ちょっと・・・失礼します」
そう言ったつもりだが、ひょっとしたら日本語だったかもしれない。
吸い寄せられるように、俺は立ち枯れの並木に向かって歩き出した。
ぬかるみを器用に飛び越えて、香藤が足を止めた。
「・・・どうして・・・」
「岩城さん!!」
信じられない。
目の前に香藤がいる。
―――なぜ、どうして?
そう思った瞬間、香藤が勢いよく俺に飛びついてきた。
「岩城さん!」
「かと・・・おいっ」
がっしりした体躯を受けとめて、俺は思わずよろめいた。
「ちょ・・・っ!」
そのまま身体が傾いで後ろに倒れそうになったのを、香藤が俺の背中にあったマロニエの大木に手をついて支えた。
ざあっと雨だれが降りこぼれてきて、俺たちはあっという間に冷たい雨に濡れそぼった。
「岩城さん・・・!」
荒い吐息。
かすかに潤んだ眼差し。
俺はそのまま、香藤の腕に抱き込まれた。
骨がきしむほどの、きつい抱擁。
「あ・・・っ」
思わずもがいた俺の顎を、香藤は片手でついと持ち上げた。
「ああ、岩城さんだ・・・会いたかった・・・!」
輝くような笑顔。
俺がそれに答える間もなく、キスが落ちてきた。
熱い唇、飢えた唇。
そのくちづけの激しさに、目眩がしそうだった。
すがるように、俺は香藤の首に両腕を回していた。
「・・・んんっ・・・」
ただ、夢中だった。
香藤の舌が俺の唇をこじ開け、侵入し、俺の舌に絡まった。
なつかしい、濡れた感覚が俺を誘う。
流れ込む香藤の唾液を、俺は喉を鳴らして吸い取った。
やわらかい咥内を蹂躙され、気が遠くなる。
マロニエの大樹に力任せに背中を押しつけられ、俺は身動きもできなかった。
「く・・・ん・・・んぁ」
息を奪われて、呼吸できない。
キスで俺を縫いとめたまま、香藤が膝で俺の両脚をこじ開けた。
強引なしぐさで、俺の股間を刺激する。
―――こんな、こんなところで!
甘い疼きが、全身を支配した。
「・・・よせ・・・っ」
ようやく香藤の唇から逃れて、俺は荒い息をついた。
濡れた唇が、名残惜しげに俺の頬に触れる。
腰を抱き寄せられたまま、俺は肩で息をした。
「か、とう・・・」
それでも、目が離せない。
信じられない。
俺の香藤が、俺の腕の中にいた。
「来ちゃったよ、俺」
香藤はいたずらっこのような顔で笑い、俺に鼻をこすりつけた。
俺はその、雨でしっとり濡れた薄茶色の髪をかきあげてやった。
「香藤・・・」
言葉が出てこない。
代わりに、香藤の額にそっとキスをした。
気持ちよさそうに、香藤が目を閉じた。
「もっとキスして、岩城さん。生き返る気がするから」
「ばか・・・」
香藤がうれしそうに笑った。
とろけそうに甘い囁き。
「岩城さんにばかって言われるのも、久しぶりだ」
「・・・ばか」
俺も笑った。
「濡れちゃったね」
香藤が俺の髪をそっと指ですいた。
「ああ―――」
「キョースケ」
いきなり名前を呼ばれて、俺は弾かれたように振り返った。
イレーヌが両腕を組んで、そこに立っていた。
俺はあわてて、香藤の腕から抜け出した。
「イレーヌ!」
香藤が、ひゅうと口笛を吹いた。
「野暮はしたくないんだけど・・・」
彼女は、呆れたように肩をすくめてみせた。
「いつまでもラブシーンやってそうだから、忘れてるといけないと思って。一応まだ、仕事中よ?」
それから一歩近づいて、大輪の花のような笑顔を香藤に向けた。
「はじめまして」
英語だった。
「はじめまして、マダム・デュトワ」
返事も英語だ。
香藤が、にっこり笑って右手を差し出した。
イレーヌが首を振り、伸び上がって香藤の両頬にキスをした。
「女性に握手は失礼よ」
「あ、すみません」
「キョースケ。ちゃんと紹介、してくれないの?」
促されて、俺は苦笑した。
イレーヌにはさんざん香藤の話をしているが、一度も名前すら出したことがない。
そもそも、香藤を誰かにまともに紹介するなんて、ここ数年はしてないだろう。
「・・・イレーヌ、これが、ヨージです。俺の―――」
どう言ったらいいのだろう。
俺は、口ごもった。
俺のフランス語のボキャブラリーなど、たかが知れている。
―――ほかに思いつかなくて、俺はとうとう、その言葉を口にした。
《Et...il est mon mari》
イレーヌがさすがに、目を丸くする。
顔がほてるのが自分でわかった。
「どうしたの、岩城さん?」
不思議そうに首をかしげる香藤を、まともに見られなかった。
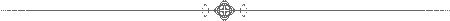
ややあって、ざわめきが耳に戻ってきた。
おそるおそる振り向くと、案の定、撮影スタッフが遠巻きに俺たちを見ていた。
真冬の、それも雨の日のリュクサンブール公園。
普通なら、誰もいないのだろうが―――。
公衆の面前であれだけの愁嘆場を演じておいて、今さらかもしれないが。
俺はようやく、自分の置かれている状況を把握した。
羞恥心に目眩がする。
できるものなら逃げ出してしまいたかったが、あいにく仕事中だ。
イレーヌの後について、俺はすごすごと噴水の前に戻った。
香藤は上機嫌だ。
俺は、そっとため息をついた。
「お待たせして、すみません」
深く頭を下げた俺に、セガン監督がニヤリと笑った。
「いやあ、驚いたよ。クールなキョースケに、あんな情熱的な部分があるなんてね」
恥ずかしくて、顔を上げられない。
「恋人との久々の再会じゃ、しかたないでしょ」
イレーヌが横から口をはさんだ。
「勘弁してください・・・」
「かなりのハンサムだよね。紹介してよ」
俺はちらりと、すぐ後ろにいる香藤を振り返った。
「なあに?」
「・・・紹介しろって、監督が」
香藤が笑顔で頷き、セガン監督に向き直った。
ゆったりした英語で、自己紹介をする。
―――なかなか堂に入ったものだ。
こいつは前の映画のために特訓を受けて以来、英語に自信を持っているから。
「なるほど、そうか。いや、キョースケの恋人は年下の男の子だって、聞いてたからねえ。どんなかわいいトイボーイかと思っていたら―――」
まさか、君みたいなナイトが現れるとはね。
監督はそう言って、声を上げて笑った。
「トイボーイって・・・!」
顔から火が出そうだった。
困り果てた俺を、香藤が後ろから抱きしめた。
「はは・・・まあ、岩城さんのトイボーイなら、喜んでなるけどね」
耳元にささやいて、キス。
「おいこら、いい加減にしろ」
俺はあわてて、香藤を引き剥がした。
香藤は俺の肩に顎を乗せて、拗ねた顔をする。
「あはは!」
笑ったのは、やはりイレーヌだった。
「アンドレアス」
歌うように監督の名前を呼ぶ。
「もう、今日はあがりましょうよ。暗くなってきたし、また雨が降りそうよ。だいいち―――」
ちらりと、彼女は俺を振り返った。
「キョースケのあの顔じゃ、とても沈痛な面持ちの青年なんて演じてもらえそうにないわ。どうせ今日も流れちゃう計算でスケジュールの調整、してますから。だから、」
イレーヌは俺たちに向かって、派手なウィンクを飛ばした。
「今日はもう、このどうしようもない恋人たちを解放してあげましょうよ」
フランスきっての人気女優にそう言われて、セガン監督は苦笑する。
「そうだね」
俺たちと腕時計を、交互に見て。
「じゃあ今日は、おしまいにしようか」
それを合図に、スタッフが機材を片づけ始めた。
「じゃあキョースケ。明日は11時に、サン・ジェルマン・デ・プレ教会だ。詳細は、エージェントに伝えておくけど」
「はい」
俺はほっとして頭を下げた。
―――役者失格かもしれないが、とても今から仕事のできる心理状態ではなかったから。
「香藤」
「うん?」
「・・・帰るぞ」
俺はそう言って、くるりと背を向けた。
香藤がすぐに追いついて、俺の手を取った。
凍てつく冬のパリ。
つないだ手から、香藤のぬくもりが伝わってくる。
俺は絡めた指先に力を込めた。
a suivre
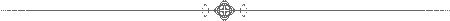
le 8 novembre 2005
藤乃めい
サイト引越に伴い2012年11月5日に再掲載。
修正は最低限に留めました。
蛇足ですが、セガン監督の「ナイト」発言に関しては・・・「シュヴァリエ」(フランス語)にしとけばよかったかなあ(笑)。