第五話
Je te veux 2 あなたが欲しい 《3》
翌朝。
シーツにくるまった香藤をたたき起こしたときにはじめて、こいつが何も荷物を持って来ていないことに気がついた。
持っているのは、普段から持ち歩いている小さなショルダーバッグひとつ。
「だって、1泊3日だよ? 何もいらないよ」
眠そうな声で、香藤がそう説明した。
伸びてきた腕から逃れて、俺はため息をついた。
それでも洗面道具とか、下着とか、必要だろう。
そう言おうとして、俺は苦笑した。
「・・・そうだな」
そんなこと、どうでもいいな。
コーヒーを淹れていると、香藤がシャワーから出てきた。
真冬だというのに、腰にタオルを巻いただけの姿。
「こっちのシャワー、使いにくいね」
「まあ、慣れたよ」
裸足でペタペタ、部屋中を歩き回る。
「いいところだね」
「ああ」
そのまま窓から外を覗いて、声をあげた。
「うわあ。ほんとにパリの街並だ―――」
無邪気に感嘆する香藤に、俺は微笑した。
―――昨夜、さんざん俺を啼かせたくせに。
こういうところは、子供のようだ。
「何か着ろ。風邪をひくぞ」
「うん。岩城さん、何か貸して?」
「ベッドルームにクローゼットがある。適当に探せ」
「うん」
しばらくして戻ってきた香藤と、朝食を摂った。
「よく、俺の居場所がわかったな」
「・・・ああ、それは」
香藤がおかしそうに笑った。
「わかんなかったよ。岩城さんには連絡つかなかったし、清水さんは、リュクサンブール公園だってことしか知らなかったし。まあ、行けば何とかなるだろうと思ったんだけど」
笑いながら、クロワッサンをかじる。
冬のパリの朝。
ここに、香藤がいる。
―――奇跡のようだ。
「俺、あんなに広い公園だって知らなくって。タクシーで降ろされて、あわてたよー。夕方で、雨が降ってたし、もう、どうしようかと思ったんだけど・・・」
香藤が、俺をじっと見つめた。
「うん?」
「・・・直感っていうか、嗅覚っていうか。どっかで、岩城さんの匂いがしたんだ」
「匂いって・・・」
頷いて、香藤が笑顔を見せる。
「もう、おかしいよね。あ、この匂い岩城さんだって、ピンと来た。後はもう、こうダーッと突進して・・・ビンゴだったねえ」
香藤は俺の腕を引き寄せ、唇をペロリと舐めた。
「おい・・・」
じゃれつく香藤が、あまりに幸せそうだったので。
俺はそのまま、香藤の腕の中でじっとしていた。
「・・・愛してるよ、岩城さん」
ささやかれて、俺の身体が熱くなる。
「香藤―――」
「俺には、岩城さんだけだよ・・・」
うっとりとそう告げられて。
俺は目を閉じて、降ってくるキスを待った。
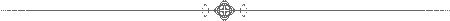
同伴していいものかと、少しは迷ったのだが。
家にひとりにするわけにもいかなくて、結局、俺は香藤を連れてサン・ジェルマン・デ・プレ教会に出向いた。
からりと晴れ上がった冬の空。
徒歩で15分ほどの距離を、香藤と並んで歩いた。
すれ違う日本人の観光客はともかく。
道を行く地元の人間からも、ずいぶん視線を浴びた。
「ねえ岩城さん。なんか、すごい注目されてるんだけど―――」
香藤が首をかしげて聞いた。
「俺たちが背が高いからだろう」
実際フランス人は、本当に背が低い。
だから、長身の東洋人が珍しいんだろう、と思っていた。
「いや・・・まあ、岩城さんが目を引くのはわかるけど」
ぶつぶつ言う香藤に、俺は呆れた。
香藤はいつも、俺が自分の容姿に無頓着だと言うが。
この男のほうこそ、自分の魅力を知らなすぎる。
「ねえ、岩城さん」
香藤が急に声をひそめた。
「なんだ?」
「この下着さあ・・・こんなのいつも穿いてて、よく腰、冷えないね」
「ばっ・・・」
「こういうの初めて着たけど、なんかスースーして」
「・・・」
俺は絶句した。
どんなに美しい街にいても、香藤は香藤のままだった。
まあ、あたりまえか。
「・・・いやなら、着るな・・・!」
香藤を見捨てて、俺はさっさと道を急いだ。
サン・ジェルマン・デ・プレ教会前に、イレーヌが立っていた。
シルヴァーフォックスのコートにジーンズ、カラフルなスカーフでまとめた髪。
これ以上ない粋な姿だった。
彼女がスタッフに囲まれているのを、観光客が遠巻きに見守っている。
ロケ撮影前のざわめき。
二ヶ月のパリ滞在で、今やお馴染みの光景だった。
「おはよう、キョースケ」
「イレーヌ。今日からハリウッドじゃあ・・・?」
挨拶のキス4回にじたばたしている香藤を無視して、俺は尋ねた。
「夜のフライトに変えてもらったわ。こんな気持ちのいい日のロケを逃したくはないから」
笑って、香藤に流し目をくれた。
「ボンジュール、ヨージ」
香藤が腰をかがめて、彼女の頬にキスをした。
「覚えが早いわ。いい子は好きよ」
小さく笑って、イレーヌは俺たちを見上げた。
「・・・パリのクラブでもときどきそう思うけど。どうしていい男同士、くっついちゃうのかしらねえ。本当に、もったいないわ」
大げさにため息をついてみせる。
俺は苦笑した。
「監督は?」
「まだ撮影チームと打ち合わせよ」
スタッフがまだ、準備を始めていないのを確かめて。
彼女はふいに、嫣然と微笑んだ。
「幸せそうな顔、してるわ。昨日までと全然ちがう」
「え・・・」
「満たされて、寝不足・・・かな」
覗き込むようにそう言われて、俺は赤面した。
「ヨージ!」
イレーヌはくるりと香藤に向き直った。
「はい?」
「いいこと、教えてあげるわ」
相変わらず、香藤と話すときは英語だ。
「昨日あなたを紹介するとき。キョースケが何て言ったか、知りたくない?」
「それは、もちろん」
香藤がうれしそうに頷いた。
「イレーヌ・・・!」
俺はあわてて、彼女を止めようとしたのだが。
イレーヌは片手で簡単に俺を制して、ゆっくり言った。
「うまい表現が、見つからなかったんでしょうけど・・・」
彼女の瞳がおかしそうに揺れていた。
「・・・il est mon mari って言ったのよ。私の夫です、っていう意味。本当にかわいい奥さんね、ヨージ」
「!!」
今度は香藤が絶句した。
俺はため息をついて、天を仰いだ。
「岩城さん・・・!」
背中から飛びついてきた香藤に、俺は抱きすくめられた。
「やめろ、香藤」
「岩城さん、顔が真っ赤だよ?」
「・・・人前で」
「・・・今さら?」
首筋にキスを落とされ、俺は身をよじった。
「うれしいよ、岩城さん!」
「あ・・・あれは・・・っ」
俺は香藤の腕から逃げ出した。
「夫婦だって・・・言いたかったんだ」
「・・・岩城さん・・・」
「でも、そんな言葉知らなくて―――」
香藤が、くしゃりと笑った。
俺は、深い息をついた。
―――友だち、では白々しすぎる。
他に、言いようがないじゃないか。
「・・・おまえを妻だとは、言えないだろ・・・」
恥ずかしさで、顔から火を噴きそうだった。
「岩城さん・・・!!」
俺はもう一度、香藤に抱きつかれた。
「この人たちは、もう・・・!」
イレーヌが声を上げて笑った。
冬晴れのパリ。
クリスマスはもうそこまで迫っていた。
fin
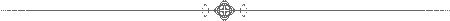
le 13 novembre 2005
藤乃めい
サイト引越に伴い2012年11月15日に再掲載。
修正は最低限に留めました。