水の都にて
水の都にて 1
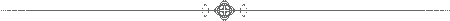
「ヴェネツィア!?」
驚きのあまり、俺の声は裏返っていたかもしれない。
「ヴェネツィアってベニスだよね、イタリアの。あの、ゴンドラのとこだよね?」
「あたりまえだ。他にどんなヴェネツィアがあるっていうんだ」
「行くの、俺たち? 岩城さんと一緒にイタリア行けるの!?」
「そうだ。仕事だけどな」
「わお!」
俺はソファから手を伸ばして、目の前に立っている岩城さんの腰を抱きしめた。
「・・・まったく、おまえは・・・」
眉をしかめてるけど、岩城さんもうれしそうだよ?
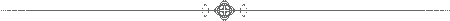
岩城さんと俺の主演する映画、『冬の蝉』のクランクアップからまもなく。
俺は、『冬の蝉』がこの秋のヴェネツィア国際映画祭に、特別招待作品として出品されることになったと聞かされた。
映画の世界に詳しくない俺でも、それがどれほど名誉なことか想像はつく。
「ほんとに凄いよね! ハリウッドでのワールド・プレミアが決まってるだけでも、信じられないくらい幸運なのに。なんか、夢みたい」
俺はほうっと息をついた。
あぐらをかいた膝に、愛しい身体の重み。
「ずいぶんかわいいことを言うんだな」
岩城さんは身をよじると、耳にかすめるようなキスをくれた。
お返しのキスをつややかな黒髪に落とす。
「まあ、何だか話が大きくなりすぎて、俺なんかには分不相応な気もするけどな・・・」
「何言ってんの、岩城さん!」
俺は抱きしめる腕に力を込めた。
「そりゃあね、こんなに綺麗で魅力的な岩城さんを、これ以上他人に見せたくないって思うけど。いつだってそう思ってるけど・・・」
「―――香藤」
「でも、ね? 秋月を演じる岩城さんは、本当に凄かったもん。俳優・岩城京介が世界で評価されるのは、当然だと思う」
「・・・なに言ってるんだ」
あれはおまえの映画でもあるんだぞ、とつぶやいて、岩城さんは照れて顔をそむけた。
相変わらず、ストレートに誉められるのに弱い。
赤らんだその頬に、俺はそろりと舌を這わせた。
顎からうなじへ。
多忙な一日を終えた岩城さんの汗の匂いを嗅ぎとって、俺の息が乱れた。
「こら、ちょっと待て」
つるんと魚が逃げるように、岩城さんは俺の腕からすり抜けた。
「あん・・・もう」
―――くやしいけど。
こういう時は、年季を感じちゃうね。
ほんと、俺の気配を読むのがうまくなった。
自分が乗り気じゃないときに俺がしかけると、こうやって上手に逃げ出してしまう。
一緒に暮らし始めて、8年目。
岩城さんとの生活はいつだって喜びと発見に満ちていて、毎日が幸せで幸せで。
昨日も今日も明日も、岩城さんがあたりまえのように俺の側にいてくれるのがうれしくて、本当にあっという間に何年も経ったって感じなんだけど。
口を尖らせてじっと見つめる俺の頭をぽんと軽くたたいて、岩城さんが苦笑した。
「俺がおまえのそういう顔に弱いの知ってて、わざとやってるだろう」
ずるいぞ、と唇が動いた。
音にはならなかったけど。
ふわりと笑って、そのままリビングを出て行こうとする。
俺の視線がその背中を追っているのがちゃんとわかってる、って歩き方。
ドアのところでスローモーションみたいに振り返り、もう一度笑った。
俺の下半身を直撃する、扇情的な微笑。
―――意識してやってるなら犯罪だよ、それ。
「・・・風呂が先だ」
揺れる黒曜石の瞳が誘っていたから。
俺はむくりとソファから立ち上がった。
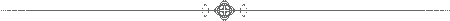
マルコ・ポーロ空港から小型モーターボートに乗って、俺たちはホテルに向かった。
運河の向こうに、アドリア海の夕暮れ。
うっすらと空を覆う薄紫色の雲が、夕日に染まって半分オレンジ色に輝いてる。
遠くに見える鐘楼が、黄金色に染まっていた。
言葉もなくて―――。
俺は前を見つめたまま、片手を伸ばして岩城さんの左手を取った。
手の甲にそっと指をすべらせ、結婚指輪の感触を確かめてから、手のひらを重ねる。
俺の右肩のすぐそばで、岩城さんが小さく笑った。
だって、ボートは俺たちの貸切だし。
つまらなそうに舵取りをするイタリア人のおじさんは、振り向く気配もないもん。
「―――岩城さん」
「ん?」
「綺麗だね・・・」
オレンジからピンクへと、鮮やかなグラデーションを見せるヴェネツィアの空。
運河の波間に見える瀟洒な建物。
ボートを避けるようにゆらゆらと揺れるゴンドラ。
これ以上ないロマンティックな風景に酔って、俺は岩城さんの腰に腕をまわした。
「・・・香藤」
岩城さんの低い声。
あは、これは調子に乗りすぎらしい。
払いのけられる前に、俺は腕をはずした。
それを見計らったようなタイミングで、おじさんが振り返ってニッコリ笑った。
指差す向こうには、貴族のお屋敷みたいな豪奢なホテルのエントランス。
「チプリアーニ」
それが、俺たちが滞在するホテルの名だった。
ハリウッドのスーパースターが定宿にする超高級ホテル。
成田を出発するときに、金子さんからそう聞いてはいたけど。
そこは完全に別世界だった。
―――俺だって芸能人だから、高級ホテルを知らないわけじゃないけど。
ホテル・チプリアーニの桁外れの豪華さに、俺は感動を通りこして、目眩がしそうだった。
七色の大理石。
そこかしこの金箔。
きらびやかなヴェネツィアン・ガラスのシャンデリア。
ロビーからして、どっかの宮殿に迷い込んだみたい。
金に糸目をつけないって、こういうことを言うのかって感じ。
キンキラで派手な彩色なんだけど、悪趣味に見えないのが凄い。
「・・・こんなすごいとこ、よく事務所が取ってくれたよねー」
思わず貧乏くさい感想をもらすと、岩城さんがくすりと笑った。
窓ごしの夕陽を受けて、その白皙の頬が淡い朱色に染まっていた。
深い深い水のような瞳と、陰をおとす長い睫毛。
長旅で疲れたんだろう、瞼がちょっと重たそうで、それがまた色っぽい。
ふっくらした紅い唇。
意外と肉感的で、いつもそそられる。
―――岩城さん、きれいすぎ。
すぐに押し倒したい衝動にかられて、俺がさっさとレセプションに向かおうとしたとき。
「ミスター・イワキとミスター・カトーですよね?」
思いがけず、日本語が聞こえてきた。
ガイジン発音の、でもきれいな日本語。
驚いて俺たちが振り返ると、栗色の髪の青年が頭を下げた。
握手ではなくて、あくまで日本流のペコリ。
一枚の紙切れを手に持っている。
「僕はファビオ・ロッシといいます。インタープロのシミズさんから、ファックスで仕事の依頼を頂きました。お二人の滞在中、お世話します」
岩城さんがファックスを受け取った。
「現地で通訳を手配すると聞いてはいたが、なるほど。―――岩城です、よろしく」
「香藤です。よろしくお願いします。日本語、お上手ですね」
ファビオはほめられて嬉しそうに笑った。
純情な好青年って感じ。
チェックインのために、俺たちからパスポートを預かった手際はテキパキしてて手馴れた印象だけど、もしかしたら案外若いのかもしれない。
ほどなく、彼が戻ってきた。
なぜか顔が赤い。
「どうしたの?」
「あの、ホテル側の手違いだと、思うんですけど・・・」
ファビオが口ごもった。
「おふたり同室で、予約が入ってるって言うんです。それが、スイートだって言われて・・・」
岩城さんの頬がさっと赤くなった。
今回、ホテルの手配をしたのは岩城さんの事務所だ。
スイートはともかく、俺と同室っていうのは、今さらリクエストするまでもない当然のこと。
日本では俺たちの関係を誰でも知ってるから、それに疑問を抱く人間もいないけど、確かにここでは事情がちがう。
「―――日本の有名な映画スターで、わざわざ映画祭に来てるのに、同室なんて失礼だって言ったんですけど。ほかに空室はないって・・・」
ファビオが肩を落として報告する。
俺は、岩城さんにちらりと視線を走らせた。
恥ずかしいのもあるだろうけど、それよりも、彼に余計な気を遣わせてしまって申し訳ないって顔をしてる。
「・・・あのね、ファビオくん」
俺は、にっこり笑った。
「それでいいんだよ」
「・・・え?」
「予約は間違いじゃないから、気にしないで。俺たち男同士だけど、夫婦なんだ」
「・・・えぇ?」
ほら、と俺は、結婚指輪をかざしてみせた。
ファビオの視線が泳ぎ、おそるおそるといった感じで岩城さんの左手を確認する。
「だから、同室でいいんだよ。っていうか、岩城さんと別室なんて考えられないから」
「・・・」
驚きのあまり声も出ない彼に、岩城さんが言った。
「・・・ファビオくん。びっくりさせてごめん。そういうのが嫌なら、この仕事、無理しなくていいから・・・」
その言葉に、弾かれたようにファビオが反応した。
「そんなことないです! ただ、驚いてしまって・・・ごめんなさい」
小さな声で謝罪されて、岩城さんが苦笑した。
気まずい沈黙。
「ねえ、早くチェックインしよう?」
俺が言うと、二人ともほっとしたように頷いた。
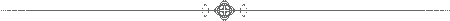
翌日。
『冬の蝉』は、大成功を収めた。
クレジットロールが流れる間ずっと、スタンディング・オベーション。
拍手と「ブラボー」の声が、会場いっぱいに響き渡った。
―――実を言うと。
編集が終わって音響もすべて入った、つまり完成されたフィルムを大きなスクリーンで見るのは、俺たちも初めてだった。
岩城さん演じる秋月が、死を決意してからラストまでの息の詰まるようなシーン。
不覚にも、涙がこぼれそうになった。
他人から見たら、自分が主演してる映画で何を泣いてるんだ、って呆れられると思うけど、もちろん俺がぐっときたのは、岩城さんの名演技のせいだけじゃない。
これを撮影したとき、宮坂の脅迫に精神的にぎりぎりまで追い詰められていた岩城さん。
俺のために、俺を守るために、自分を犠牲にすることも考えたというほど、葛藤していた。
撮影中の、あの鬼気迫るような演技を思い出す。
草加のために命を投げ出す秋月に、自らを重ねて、身を削るような思いでいたんだろう。
―――どんなに、辛かっただろう。
ひとりで悩んで苦しんで、それをいっさい俺に気づかせなかった―――。
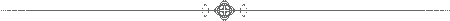
ましゅまろんどん
26 September 2005
『春抱き同盟』様に投稿したわたしの記念すべき?処女長編です。(Treasures掲載のマミ様のエッセイに、この作品に関する裏話あり。合わせてお読み下さると・・・笑えるかも?)
2012年10月16日、サイト引越にともない再掲載。初期作品で手直ししたい箇所は山ほどあるのですが、最小限の修正にとどめました。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
