水の都にて
水の都にて 2
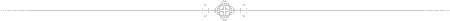
「・・・おい、香藤?」
岩城さんに呼ばれて、俺は我に返った。
拍手の嵐の中、観衆の視線が特別席にいた俺たちに向けられてるのに気がついて、俺はあわてて立ち上がって会釈した。
―――いけない。
仕事で来てるんだから、俺たち。
「ブラボー」の声に応えて、にっこり笑って手を振った。
隣で岩城さんは、頬を少し上気させながら、ゆとりのある笑顔を見せていた。
納得いく仕事に手ごたえを感じてる、したたかなプロの役者の顔。
ほれぼれするほど男らしい、憎らしいくらいカッコいい、俺の岩城さん。
俺もそういう顔をしてるといいな、と思った。
上映後の舞台挨拶というか、記者会見には、滝沢監督が合流した。
この映画制作の過程について、熱弁をふるう監督を横目に見ながら、俺は正直ほっとしてた。
もちろん俺たちだって、『冬の蝉』には相当の思い入れがあるけど、こういう席で多くを語るのは得意じゃないから。
俺たちの思いは、力の及ぶ限り、演技にすべてぶつけたのだから、それでわかってもらえると信じたかった。
向けられた無数のカメラにニコニコと笑顔で応える岩城さんも、同じ思いだったろう。
「ミスター・イワキに質問です」
通訳の声に、岩城さんが顔を向けた。
「数年前の『春を抱いていた』に続き、今回も同性愛映画ですが、ゲイ俳優というイメージが固着することに抵抗はないですか」
虚を突かれて、岩城さんは目をみはった。
質問に悪意を感じたのは俺だけじゃないらしく、監督が眉をひそめた。
通訳の隣にいる金髪のジャーナリストが、にやけた顔つきで俺たちを見上げてる。
―――まるっきり、忘れてたけど。
そういえば、岩城さんと佐和さんが共演した映画『春を抱いていた』は、海外ではアートハウス系映画として、けっこう評価が高かったって言ってたっけ。
二本の主演映画で、同性愛者の役を演じた岩城さん。
海外のマスコミは、それしか知らないわけだ。
もちろん、私生活での俺との関係を知った上での質問なんだろう。
「・・・確かに、『春を抱いていた』も『冬の蝉』も、たまたまそういう役柄ですが」
岩城さんのテノールは、硬い響きだった。
「オファーをいただいた仕事をお受けするかどうかは、脚本の良し悪しで決めています。それ以外に条件はありません」
静かな口調だったけど、岩城さんのほの白い怒りの炎が見えるような気がした。
「―――『冬の蝉』は、生涯ただ一人の、運命の相手にめぐり合ってしまった恋人同士の悲劇を描いたものです。秋月も草加も、お互いにめぐり合わなければ、おそらくそれぞれ決められた女性と結婚し、家を継ぎ、子供を育てて、穏やかな、それなりに満ち足りた人生を送ったでしょう。動乱の時期ではありましたが、少なくても、ああいう形で早死にすることはなかった」
岩城さんの言葉に、会場がしんと静まり返った。
「・・・でも、二人は出会ってしまった。運命とは、そういうものです。自分ではどうにもならない何かに操られ、人生を狂わされる」
―――そう、俺たちも運命の出会いをしたんだよね。
だけど、そのせいで、岩城さんの人生は狂ったんだろうか・・・?
思いがけず、俺の心にさざ波が立つ。
岩城さんは凛とした眼差しで、会場を見渡した。
「過酷な、残酷な運命だったと思います。でも、彼らは短い人生を必死に生き、愛し、お互いだけを見つめて死んでいった。今の俺たちから見れば悲恋ですが、命をかけて守りたいと思うほどの相手にめぐり会えて、幸せでなかったはずがない。―――出会わなければよかったとは、最期まで決して思わなかったでしょう」
自信に溢れた言葉。
きっぱり言い切る岩城さんの言葉に、俺の心は凪いでいった。
ちらりと、ほんの一瞬だけ、岩城さんの視線が俺をとらえた。
―――俺が、岩城さんの言葉にどう反応したかなんて、お見通しなんだろうな。
「・・・そういう人生のドラマに惹かれて、俺は『冬の蝉』を演りたいと思いました。俺にとってこの作品は、普遍の愛の物語です。男同士だろうと、共演者が誰であろうと関係ない。この役を誰にも渡す気はありませんでした」
深い湖のような光をたたえる瞳が、強い信念に輝いていた。
息を呑むほどきれいな岩城さんの横顔に、俺は呆けたように見惚れる。
「この映画をご覧になって、ただ同性愛映画という感想しか持っていただけないとしたら、とても残念なことです。・・・俺たち役者の力不足、ということなのかもしれません」
―――岩城さんは最後の一言を、下世話な質問をしたジャーナリストをちろりと見下ろしながら、ゆっくり微笑んで言ったんだ。
もちろん、『冬の蝉』がスタンディング・オベーションを受けるほど好評だったからこその台詞。
―――岩城さん、かっこよすぎだよ。
会場につめた記者たちが、いっせいに感嘆のため息をついた、気がした。
「では、このあたりで―――」
滝沢監督が、質疑応答を切り上げるように腰を上げた。
それを合図に、俺も勢いよく立ち上がった。
岩城さんの腰に手を添えてエスコートするように、その場を退出する。
くすぐったそうに岩城さんは少し身体をよじらせたけど、俺の腕を振り払おうとはしなかった。
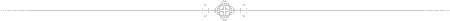
「本気か?」
岩城さんは顔をしかめた。
「もちろん! ここはヴェネツィアだよ。ゴンドラに乗らないでどうするの!?」
チプリアーニの、それはそれは豪華なスイートに戻ってきたのは、その日の夕方だった。
もともと3泊5日の強行スケジュール。
明日はインタビューや映画のプロモーションの仕事が入ってるし、夜は映画祭関係者のパーティーだから、ふたりで自由になる時間は今しかない。
岩城さんは、今いち乗り気になれないみたいだった。
理由はわかってる。
モーターボートとちがってゴンドラはのろいし、屋根がついてるわけでもないから、運河沿いを歩く人々から丸見え。
ファンやジャーナリストがカメラを向けても、逃げる場所なんかない。
岩城さんにしてみれば、気が重いんだろう。
俺はとびきりのおねだり目線で、駄々をこねてみた。
「ねえ岩城さん、一生のお願い! ヴェネツィアなんて、もう二度と来れないかもしれないじゃん」
香藤―――と、甘い困惑顔でささやいて。
岩城さんは俺の耳をぎゅっとひねりあげた。
「いてて!」
大げさに騒ぐ俺と、ため息をつく岩城さん。
じゃれあっている俺たちを、ファビオが楽しそうに眺めていた。
「本当に、仲がいいんですね」
「そう思う?」
俺はちょっとうれしくなって聞き返した。
俺とファビオは案外気があって、今日一日ですっかり打ち解けていた。
「はい。昨日夫婦だって言われたときは、信じられないっていうか、どうしたらいいかわからなかったんですけど。朝からご一緒して、僕は納得しました」
「納得って?」
「おふたりが、お互いをとても大事にしていらっしゃるのがわかりました。愛し合っていて、それが自然に見えます。特にミスター・イワキは、ミスター・カトーを見るときの目が、とても優しいです」
視線を向けると、岩城さんが頬を染めていた。
―――長年連れ添ってても、こういう顔、できちゃうんだよね。
初々しいっていうか、本当にもう、食べちゃいたいくらいかわいい。
さっきの記者会見みたいな、凛とした男前な岩城さんも好きだけど、俺だけにしか見せない恥らう素顔は、俺をどこまでもメロメロにする。
「あは、鋭い。岩城さん、俺には甘いからねー」
「・・・調子に乗るな」
小声でつぶやいて、岩城さんがソファから立ち上がった。
俺の視線を無視して、さっさとベッドルームに消える。
「あれえ、岩城さん?」
少し開いたドアの死角で、バタンバタンとクローゼットを開閉する音が聞こえた。
かすかに衣ずれの音―――あれ、着替えしてる?
ファビオと俺が顔を見合わせてると、じきにカジュアルな服装の岩城さんが出てきた。
細身のヴィンテージジーンズに、白いタンクトップ。
その上にはおってるのは、俺のポール・スミスのシャツだ。
暖色系のマルチカラーストライプがとにかくきれいで、最近すごく気に入ってるやつ。
財布を後ろのポケットにねじり込みながら、岩城さんが俺のキャップを目深にかぶるのを見て、俺はうれしくて立ち上がった。
―――岩城さんが俺の服を着ることなんてめったにないから、こういうの、ぐっと来るね。
「ありがと、岩城さん!」
「さっさと仕度しろ」
言葉はほとんど同時だった。
岩城さんの頬に派手な音をたててキスして、俺はベッドルームへ飛び込んだ。
背後から、ゴンドラの手配をしますね、というファビオの声が聞こえた。
暮れなずむ水の都。
ゴンドラがゆっくりと方向を変え、カナル・グランデから細い運河へ入った。
クラシックな街灯の光が、水面に映ってゆらゆら揺れる。
とろんと青みがかった闇が落ちていた。
街中たくさんの人で溢れかえっているんだろうけど、姿が見えないだけで、ざわめきもそれほど気にならない。
朽ちかけた石橋の下を次々とくぐりながら、ゴンドラは静かに水上をすべっていた。
「こういうの見てると、マドンナごっこ、したくなるねー」
「はあ?」
「岩城さん知らない? 『ライク・ア・ヴァージン』のプロモーションビデオ」
「―――おまえは」
いつの話をしてるんだ、と岩城さんが呆れたように言った。
―――運河を漂い、橋の下をくぐるゴンドラで立ち上がって、十字架のネックレスをじゃらじゃらさせて、思いっきり挑発的に歌うマドンナ。
俺の子供時代の強烈な記憶なんだけど。
「あの歌が流行った時って、俺だってせいぜい中学生くらいじゃないか?」
おまえはいったい幾つだったんだ、と岩城さんが続けた。
「うん・・・8、9歳くらい? 偶然つけたテレビで見て、すごい興奮したんだ」
「とんだマセガキだな」
「そだねー」
俺は笑って、岩城さんの肩をぎゅっと抱き寄せた。
愛しい身体がちょっと抵抗する。
すぐ後ろ、船尾に立つゴンドリエのおじさんから丸見えなのを気にしてるんだとわかってはいたけど、俺はかまわず腕に力を込めた。
「おい、香藤・・・」
たしなめる声はたしかに困惑気味だけど、心なしか甘い。
俺の心臓が、とくんと鳴った。
ほとんど耳を舐めるように唇を寄せて、俺は囁いた。
岩城さんの官能が、俺と同じくらいに煽られることを祈りながら。
「もう暗いし、見えないよ」
「・・・そんなことないだろ・・・」
「水の上は冷えるから、あっため合ってるだけだって思ってるかも」
「ばか言え」
「大丈夫だよ。映画祭で、世界中から客が来てるんだもん。男同士のカップルがいたって、不思議じゃないって」
「まったく、おまえは―――」
うつむいて苦笑する岩城さんの顔は、キャップのつばでよく見えない。
「なにしろ、マセガキだからね?」
俺はちょっと笑って、腕の中でおとなしくしている最愛の恋人にささやく。
「小学生でマドンナに興奮して夢精して、14歳で初体験。15で六本木デビューしてさ」
「・・・」
「夜遊びしたくて、18歳の誕生日をジリジリ待って。今から考えると、何をそんなに急いでんのかって感じだよね」
「・・・」
「でさ、22歳ですっとーんと恋に落ちて、強引に同棲に持ち込んで。24歳で家建てて、26歳で挙式だよ。早熟人生、まっしぐらって感じ?」
「香藤―――」
「・・・俺さ、岩城さんに出会って、わかったんだ。何かに追い立てられるみたいに、早く大人になりたくて、人生ずっと駆け足だったのは、先を歩いてる岩城さんに追いつくためだったんだなあって」
「香藤・・・」
「ずっと走って、走り続けて、やっと岩城さんを捕まえた。俺はまだまだガキで・・・追いついたとは言えないかもしれないけど。本当の意味で、岩城さんに追いつく日なんて来ないのかもしれないけど。でも、岩城さんはこんな俺の腕の中にいてくれる。やっとつかまえたんだ・・・何があっても、もう絶対、離さないからね」
「・・・ばかやろう」
甘いテノールの声がふるえて、かすれた。
岩城さんは俯いたまま、俺の腕をつかんでぎゅっと引き寄せた。
俺はその手に手のひらを重ねて、そっと指を絡めた。
背中をこすりつけるように、岩城さんが全身を預けてきた。
―――口下手で恥ずかしがりで、いまだに甘えるのが苦手な恋人の、精一杯の愛情表現。
ちゃぷんと、舳先に小波がぶつかる。
ゆらゆら揺れるゴンドラに身をゆだね、俺たちは無言で、夜のヴェネツィアをただよっていた。
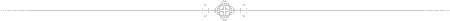
「・・・あぁあっ・・・んんっ!」
岩城さんの弛緩した身体が、ぐったりとベッドに沈み込んだ。
荒い息を吐いて、額にぺったり張りついた髪をかきあげながら、ゆっくり俺を見上げる。
官能に濡れた、漆黒の瞳。
「香藤・・・」
かすれた低い声で俺を呼んだ。
「岩城さん・・・」
誘うようにうっすら開かれた唇に、俺はキスを落とした。
舌を絡め、頬の内側をねぶるようになぞり、まだ息も整わない岩城さんの咥内を存分に味わう。
「ん・・・っ」
ぞくりとするような甘い吐息がもれて、俺の身体を再び熱くした。
俺のペニスが、岩城さんの中でずくりと力を持つ。
「ちょっと待て―――」
岩城さんは俺の背中に回っていた腕を解いて、なだめるように俺の髪を指ですいた。
「・・・なあに?」
俺の声もかすれていた。
情欲にまみれた、すっごいいやらしい声。
きっと俺、とんでもなく飢えた、卑猥な顔をしているんだと思う。
岩城さんが、そんな俺を見上げて苦笑した。
「まだできるのか・・・元気なやつだな」
「・・・誰のせいだと思ってんの。岩城さんが煽ってるんだよ」
何を言ってるんだ、と岩城さんは笑うけど。
実際、ゴンドラを降りてホテルに戻ってきたときの岩城さんは、壮絶なまでに色っぽかった。
腰を抱かれて、黙って俺に寄り添っていた岩城さん。
ロビーを横切るほんのわずかな時間。
さざめく周囲の視線を釘づけにするほど、強烈な色香をまき散らしていた。
全身で、俺を欲しがっていた。
スイッチが入った状態の岩城さんのフェロモンは、ちょっと測定不能なまでの破壊力を持っているからね。
―――外でそうなっちゃうのは、本当に珍しいけど。
ああいうの見せつけられて、どこかで理性のぶち切れる馬鹿な男がいるんじゃないかと思うと、本当に気が気じゃない。
夜のゴンドラ・デートの間中、時間をかけて丁寧に口説いて、岩城さんの身体の奥に火をつけたのは俺だから・・・まあ、いわば自業自得なんだけど。
「香藤」
「うん?」
「ちょっと、休憩させろ。喉がカラカラだ」
そういえば、俺も喉が渇いた。
ゆっくりと岩城さんの中から俺を引き抜き、俺はペタペタと裸足のまま寝室を抜け出した。
豪勢な大理石のバーカウンターの冷蔵庫から、よく冷えたボトルを抜き出した。
シャンパングラスをひとつだけ持って、ベッドに戻る。
「・・・シャンパンか・・・?」
気だるそうに、岩城さんが上半身を起こした。
「うん。この地方の発泡酒、プロセッコって言うんだって。ファビオが教えてくれたんだ」
岩城さんの眉が、ほんの少しだけ寄せられた。
「何・・・アルコールはいや?」
「そうじゃない―――」
ベッドに腰かけた俺に、岩城さんが顔を寄せてくる。
「うん?」
「・・・ずいぶん仲がいいんだな・・・?」
至近距離でようやく聞き取れるほどの小さな声。
俺は、思わず顔が緩むのを抑えられなかった。
「岩城さん・・・!」
岩城さんがやきもちを焼いてくれるのはうれしい。
そのやきもちを素直に俺にさらけ出してくれるのが、さらにうれしくって。
グラスにきらめく液体を注いで、そっと手渡した。
「俺には、岩城さんだけだよ」
知ってるくせに。
―――そうささやきながら。
赤い顔をして、岩城さんはグラスを一気に空けると、俺の顔をぐいと引き寄せた。
照れ隠しのような、乱暴なキス。
炭酸を含んだ甘い冷たい酒が、俺の喉にゆっくり流れ落ちてきた。
「んんっ・・・」
もっともっと、その甘さを味わいたくて。
俺はボトルから直接プロセッコをあおると、岩城さんの唇を貪った。
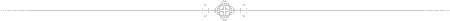
ましゅまろんどん
26 September 2005
「Like a virgin」のPV・・・古すぎるという自覚はあります(汗)。
2012年10月17日、サイト引越にともない再掲載。オリジナル原稿をいくらか修正してあります。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino
