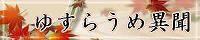ゆらめく情動
ゆらめく情動 2
翌日、俺は都内の小さなスタジオにいた。
生放送のラジオ番組にゲスト出演するためだ。
トーク番組やバラエティは苦手なのだが、最近どうもこの手の仕事が多い。
まだ俳優としては駆け出しなので、気が進まないという理由でこういうオファーを断ることはしないが、正直、億劫に感じていた。
誰も彼も俺を捕まえては、香藤とのことを聞きたがる。
芸能界にいる以上、マスコミに注目されるのがいやだとは言わない。
たとえそれがプライベートがらみでも、自己プロモーションに利用すればいいというのは、したたかな香藤が教えてくれた。
玄関先でのキスも、同居騒動も。
俺が蒔いた種ではないが、スキャンダルを提供しているのは俺たちだ。
それで記者に追い回されても文句は言えない。
―――だが。
俺たちの関係に微妙な変化が起き始めている、今。
いや、俺の心に、というべきか。
ゆらめく情動に俺自身、どうしていいのかわからない。
そんなときに香藤とのことを語れと言われるのは、少しつらい。
「それでは、今日のミステリーゲストをご紹介します。まずは、これをお聞きください」
パーソナリティーを務める織田みちるが、マイクに向かって言った。
もう熟女といってもいい年頃のはずだが、才能がある上に美人。日本中で知らない人はいないくらいのシンガーソングライターだ。
日曜日の午後に放送されるこの番組も、何年も高視聴率を維持しているという。
俺はヘッドフォンをつけて、オンの合図を待った。
用意されていたテープが回り始める。
ほんのわずかな、布がこすれるような音。
何かがきしむ、小さな音。
俺はあわてて、向かいの織田さんを見た。
―――自慢じゃないが。
長い間その業界にいたので、それが何の音なのか、瞬時にわかってしまう。
人間の肌が、糊のききすぎたシーツの上をすべる音。
スプリングの堅い、おそらく真新しいマットレスが人の重みで沈む音。
冷や汗が流れた。
このラジオ番組には、ゲストを紹介する前に、そのゲストの出演したドラマの一部などをリスナーに聞かせるという趣向がある。
―――まさか、とは思うが。
今さら、あの当時の俺の声を聞かされるなんて、冗談じゃない。
最近ようやく、「AV上がりの岩城京介」というレッテルを貼られなくなってきたのに。
事務所は、このことを知っていてオファーを受けたんだろうか。
いっそ席を蹴って立ち去ろうか、とまで考えたその時。
耳慣れた熱い吐息が、耳に飛び込んできた。
「好きだ・・・彰二。今まで抱いてきた女たちとおまえは、全然違う・・・」
香藤の熱っぽい声。
「・・・俺も愛してる。悦司・・・」
甘い、甘すぎるかすれ声。
俺の声ににじむ、思いがけない艶。
―――俺はこんな声で、あいつを呼んでいたのか。
顔がカッと火照った。
テレビ版『春を抱いていた』の撮影が終わって、もうじき一年になる。
テレビのスクリーンで香藤と抱き合ったことなど、忘れかけていたのに―――。
「・・・というわけで、皆さんもうおわかりですよね。去年話題になったこの衝撃のシーン。今日のゲストは、俳優の岩城京介さんです!」
ランプが点灯して、俺ははっとした。
「こんにちは、岩城です。よろしくお願いします」
「うっわー、いい声!お忙しいところ、ようこそ。岩城さん、今すっごいブレイクしてますよねえ・・・」
軽快なおしゃべりにつきあって、放送が進んだ。
デビューのきっかけ。
今主演してるドラマ。
今後の予定―――。
「ところで、岩城さん。私生活のほうでも、相変わらずニュースになってますけど。香藤洋二さんとの甘い新婚生活はどうですか?」
「・・・勘弁してください。俺たちは、そんなんじゃないですよ」
「また、そんなこと。私は前からお二人の味方ですから、遠慮なさらないで。大恋愛の末に電撃ゴールインなさって、そろそろ同棲一周年って聞いてるんですけど?」
ほがらかにそう言われて、俺は言葉につまった。
「ちが・・・いや、あの。同棲とか言われると・・・」
「あらだって、一緒に暮らしてらっしゃるんでしょ?」
「・・・まあ・・・」
「まさかお友達が居候してるだけ、なんて言わないですよねえ?」
「それは・・・」
「最近の香藤さん、夜遊びもパッタリおやめになって、毎日すっ飛んでお家に帰るんですってね。どこのスタジオでも、岩城さんのこと盛大にのろけてるって、業界じゃ有名ですよ」
お熱いですよねえ、と真顔で言われて、俺は困惑するしかない。
「あらら、お顔が真っ赤。照れてらっしゃるの、リスナーの皆さんにお見せできないのが残念!」
さらりと受け流すことができない自分がもどかしい。
「岩城さん。あんまり否定してると、他の誰かに香藤さん取られちゃいますよ? 彼、今めちゃくちゃ売れてるでしょう。あんなに可愛くて、かっこよくて、おまけに女性にモテモテの男の子が岩城さんに夢中なんだから、もっと自慢していいと思うんだけどなあー」
織田さんが、本当にうらやましそうに言う。
「・・・男の子って・・・」
「あら、ごめんなさい。悪気はないんですよ。香藤くんみたいな若いタレントさんはね、私みたいなおばちゃんから見れば、十分男の子なんです。ジゴロの香水のCMでは、すいぶん大人の色気を振りまいていらっしゃったけど。岩城さんも、かわいくてしかたないんじゃないですか? 年下の彼氏ですよね?」
「・・・五歳半、離れてますが・・・」
たしかに、ずいぶん歳が離れている。
その年下の男にさんざん翻弄されていることに、俺は苦笑した。
「素顔の香藤さんってどうですか? 一緒に暮らして、気づいたこととかあります?」
「素顔ですか・・・?」
俺はちょっと考えた。
「裏表のない性格なんで、ファンの皆さんの知ってる香藤とあまり変わらないと思います。しいて言うなら・・・意外とわがまま、かな」
「それ、ほめてないですよ?」
「・・・わがままで強引なのに、憎めないというか。明るくて誰にでも好かれるし、要領がいいので、許されるんだと思います。・・・すごく得な性格ですね」
「ああ、そういうタイプ、いますよねえ。ほかには?」
「そうですね・・・意外なくらい、マメですね」
「マメというと?」
「ロケでどこに行っても、しつこく電話かけてきます。遠くに行くと絵はがきを寄こすし、本当に、どこにそんな時間があるのか、まったく呆れますね」
織田さんが、目をみはった。
「・・・よく、男が釣った魚に餌をやらないとか言うけど、あいつはその逆じゃないかな。だから女たらしなんてやれてたのか、と妙に感心して・・・」
俺はそこまで言って、はたと口をつぐんだ。
織田さんのニヤニヤ顔に、自分の言ったことを反芻する。
―――顔がほてるのがわかった。
「うっわ、ごちそうさまー! 岩城さん、自覚なさってないみたいだったけど、それ、すごいのろけですよ?」
「・・・そんなつもりじゃ・・・」
「香藤くんから毎日ラブコール、来るんでしょ?」
―――電話が来るたびに、邪険な応対しかできないが。
最近の俺は、香藤の電話を待つようになってはいなかったか。
ふと、俺は自問した。
あいつがそうやって、眼に見える形で愛情表現をすることに、安心感を覚えてはいなかったか。
「岩城さんは、香藤くんのそういうところに惹かれたのね?」
黙ってしまった俺に、織田さんが笑って言った。
「そういえば私、友人からすっごい特ダネ、聞いてきたんですけど」
「何ですか?」
「先日、極秘で香藤くんとハワイ旅行したんですって?」
「えっ・・・」
俺はふたたび絶句した。
そうだ、あのハワイ旅行に出かけるとき。
俺たちのせいでマスコミに騒がれて、洋子さんの結婚式が台無しにならないように、ずいぶん気をつかったつもりだった。
しぶる香藤を説き伏せ、現地に着くまで、ほとんど別行動だった。
あいつと一緒にいるだけで悪目立ちする、という自覚はあったから。
「・・・」
「ごめんなさい。そんなにショック受けるとは思わなかった。もしかして、ほんとに秘密だったんだ? 誰にも気づかれないと思ってた?」
―――いや。
日本人だらけのハワイでは、限界があると思ってはいたが。
「その友人がね、びっくりしてたんですよ。香藤くんの熱愛ぶりに比べて、ふだんそっけない岩城さんが、とってもやさしい顔をしてたって。おふたりと同じホテルに泊まってたらしくてね。二晩続けて、仲むつまじくレストランにいるのを見たって、興奮してましたよー」
うれしそうにそう言われ、俺はため息をついた。
人目があるからいやだと言った俺を引きずって、衆人環視のメイン・ダイニングでディナーを食べることにこだわったのは香藤だ。
キャンドルライトの下で黙々と飯を食う俺を、とろけそうな目で見ていたのを思い出す。
―――あれを仲むつまじいと言えるかどうか、疑問だが。
「プールサイドでも、ずっと一緒だったんですって? おふたりがあんまり堂々としてらっしゃるんで、周囲のほうが目のやり場に困ったって聞いてますよ」
「いや・・・」
あのとき。
俺はプールサイドで本でも読んでるから、おまえは波乗りでもして来い。
そう言った俺に、香藤は不本意そうに顔をしかめた。
得意だというサーフィンの腕前を俺に見せられないのが、不満だったのか。
それとも、あいつを追い払ってひとりになろうとした俺に腹を立てたのか。
―――結局あいつは、意地を張ったように一日中、俺のそばを離れなかった。
「ね、教えて? 新婚旅行だったの?」
織田さんにいたずらっぽく聞かれて、俺は正直、迷った。
否定するのは簡単だ。
あれはすべて、香藤のわがままだと。
香藤の妹の結婚式がなければ、一緒に旅行することなんてありえなかったのだと。
そう言いたいが、どう言い訳しても、白々しく聞こえるだけだろう。
―――俺は、否定したくない、のか・・・?
そうかもしれないと思った。
降参、の気分。
「・・・そんな、たいしたものじゃないです。香藤がひとりで全部手配したんで、俺はついて行っただけで」
「また、そんな言い方して。岩城さんたちみたいな売れっ子のタレントさんが合わせてオフ取るのがどれだけ大変か、私だって知ってますよ? 何ヶ月も前から計画しないと、海外旅行なんてできないでしょう」
―――鋭い指摘だ。
「ご想像にお任せします」
「あら、いいの? ほんとに勝手に想像しますよー」
「はは・・・」
「ふたりっきりのハワイ、楽しかったですか?」
楽しかったかどうかなんて、考えたこともなかったが。
ふいに、香藤の言葉がよみがえってきた。
―――俺の家族になると、香藤は言った。
俺の寂しさも幸せも、背負っていく覚悟がある、と。
そう言い切ったあいつの目に、迷いはなかった。
苦労を知らない若い男のたわ言かもしれない。
いつか裏切られて、傷つくかもしれない。
それでも俺は、あのとき、香藤の真摯な瞳を信じたのだ。
信じていたい、と思った。
「・・・そうですね。楽しいっていうか、うれしかった、かな。ちょっと一生忘れられそうにない言葉を、もらいました」
「ちょっとちょっと、岩城さん!」
彼女が顔を赤くした。
「いきなりそういう爆弾、落とさないでくださいよー。リスナーの皆さん! 岩城さんね、今のセリフ、フェロモン全開の微笑つきで言ったんですよー! ああ、なんて目に毒・・・」
何を言われたのか教えろ、と懇願されて、俺は笑った。
「俺たちにも、たまには秘密があってもいいでしょう?」
放送終了。
ランプが消え、俺はほっと息をついた。
ましゅまろんどん
22 October 2005
2012年10月11日、サイト引越にともない再掲載。文章に最低限の改訂を施しています。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino