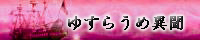Clair de lune ― 月の光 ―
Clair de lune ― 月の光 ― 2
☆ ☆ ☆
その日は、眩しいほどの秋晴れだった。
「もうずいぶん、空が高いな―――」
昼下がりの寝室。
ベランダから戻ってきた岩城は、颯爽と部屋に入ってきた香藤を見止めて、顔をほころばせた。
「どう?」
渋い色合いのかっちりしたスーツに、明るいストライプ柄のシャツ。
合わせた海老茶色のタイは、岩城のクローゼットから失敬したものだ。
「ずいぶんまた、地味なのを選んだな」
歩み寄り、ネクタイの結び目を整えてやりながら、岩城が言った。
「目立たないように、気を遣ったつもりだけど」
くすり、と岩城が笑った。
「無理だろ」
「また、そんなこと言う」
「何を着てようが、おまえは人目を惹くからな」
ふっと顔を上げて、岩城はほのかに笑った。
「せいぜい大人しくして、新郎新婦に花を持たせてやれよ?」
「岩城さん」
こつん、と額をつけて、香藤が秘めやかな微笑をもらした。
「もっと素直に、言ってくれない?」
「うん?」
かすめるようなキスを盗んで、ささやく。
「それって、俺が誰よりもいい男だっていう意味でしょ」
「・・・ばか」
眉をしかめて、岩城はついと身体を離した。
くるりと向こうを向いたその細身を、香藤が背後から抱き寄せる。
「ねえ、岩城さん」
「ん?」
香藤の肩に後頭部を預けるようにして、岩城が聞き返した。
「・・・好きだよ」
こぼれ落ちる愛の言葉にかぶせて、香藤は岩城の額にキスを落とした。
「大好きだよ」
封印のように、重ねられる誓い。
岩城はくすぐったそうに笑って、わずかに頷いた。
「わかってる」
自分を捉える太い腕に、そっと手のひらを添えながら。
「―――そろそろ時間だぞ」
ゆっくりと抱擁を振りほどき、岩城は時計を指差した。
「うん・・・」
なお名残惜しげな香藤の、背中をポンと叩いて。
「ほら、行って来い」
岩城は振り返って、にっこり笑った。
「あ、これ」
立ち去ろうとした香藤が、思い出したように。
ポケットの中から、小さな紙切れを取り出した。
「なんだ?」
「読んどいてよ。読んだら、捨てていいから」
ウィンクを残して、香藤はするりと姿を消した。
岩城は手元に残された紙片を、しげしげと眺めた。
くしゃくしゃのメモを開くと、女性の字で短い手紙があった。
「あ・・・」
今日、晴れの日を迎える花嫁の、香藤へのメッセージ。
たった一度のデートが、当時の彼女にとってどれほど特別なものだったか。
叶わぬ夢だと思っていたウェディングドレスを着ることへの、手放しの喜び。
かわいそうな病弱の少女ではなく、幸せな花嫁姿を見て欲しい、と。
香藤先輩のように、幸せな家庭を築きたい、と―――。
「・・・かなわないな」
幸せが弾けそうなメッセージを読みながら、岩城は苦笑した。
会ったこともない、おそらく一生会うこともないだろう女性。
・・・顔も声も、知らない相手ではあるが。
幸せになって欲しい。
岩城は心底から、そう思った。
☆ ☆ ☆
その日、岩城が帰宅したのは、夜も9時を回った頃だった。
雑誌の取材が一本あっただけの、中途半端な仕事の終わり。
「・・・香藤?」
リビングに恋人の気配がないことに、ふと、眉を寄せてから。
「二次会にでも、行ったかな」
居心地が悪くて、早々に退席するよりはいいだろう。
「洋子ちゃんも、いるだろうしな―――」
そう思いを巡らせながら、岩城はキッチンに向かった。
マグカップになみなみと、紅茶を淹れて。
岩城はリビングのソファに、のそりと腰を下ろした。
香藤の過去の女性遍歴が話題に上ることは、これまでにも何度かあった。
それを微笑ましいと思ったことも、傷つけられたこともある。
すべてを知っているとは思わないし、すべてを知りたいとも思わない。
―――まったく何も感じないと言えば、嘘になる。
だが、恋人の歩んできた華やかな人生を考えれば、あたりまえのことだ。
そう、思ってきた。
「・・・お互いさまだしな」
そう嘆息して、岩城は苦笑した。
「いや、そうでもないか―――」
自分だって、叩けば多少の埃くらい出るだろうが。
香藤のように、後々まで他人(ひと)の心に印象を刻むような、そういう恋愛をした記憶はない。
年齢ばかり重ねたけれど、だから人生経験が豊かだということにはならない。
それは日々、香藤に身をもって教えられている。
「子供だったのは、俺だな・・・」
希薄な人間関係しか、知らなかった。
―――香藤が強引に、岩城の人生に踏み込んで来るまでは。
太陽のような恋人に愛され、導かれ、燃えるような恋を知った。
「・・・とんでもないのに、捕まったもんだな」
岩城はそっと、唇をほころばせた。
ガラリと窓を開放して、庭を眺めた。
蒼い闇に、煌々と街を照らす丸い月。
「十六夜の月、だな・・・」
さわさわと秋風が吹き、リビングの空気がひそりと揺れた。
都心とは思えない静けさの中。
岩城はじっと、立待月を見つめた。
「・・・これからも、こういうことはあるんだろうな」
声に出して、その心もとなさに岩城は苦笑した。
今回はただ、高校時代の淡い青春のひとコマ。
若かった自分の驕りに気づいた香藤が、ほんの少し罪悪感を感じただけだ。
・・・だから心がざわめくような、そういう事態ではないけれど。
いつかまた、思いがけず傷つくこともあるかもしれない。
「ま、いいさ」
ソファに立ち戻って、岩城はごろりと身体を横たえた。
不安があるわけじゃない。
信じていれば、それでいいから。
―――香藤が俺のところに帰って来る限り、他に何もいらない。
何があっても揺るがない、絶対の愛情を注いでくれるのは香藤だ。
それに、全身全霊で応えたい。
祈るような気持ちで、岩城はそう思った。
―――こうして、年月を重ねて。
「いつか・・・」
香藤が岩城と共に歩んだ時間が、何よりも誰よりも、いちばん長くなる。
早くそうなるといい。
「・・・それで、充分だな」
過去も未来も、現在もすべて。
香藤は岩城に、捧げているのだから。
岩城が香藤に、捧げているように。
☆ ☆ ☆
ガタリ、と玄関で音がした。
いつの間にかうたた寝をしていた岩城は、はっと目を醒ました。
壁の時計は、11時を回っていた。
見れば、窓は開け放ったまま。
「無用心だって、叱られるな」
苦笑して、岩城はそっと身体を起こした。
「ただいま」
軽快な足音が響いて、香藤がリビングの扉を開けた。
とろけるような満面の笑みで、まっすぐソファに近づく。
「ああ、おかえり」
つられて甘い笑顔を見せて、岩城は香藤を見上げた。
「どうだった?」
「うん、いい式だったよ」
―――吹っ切れたような会心の笑み。
ネクタイを緩めながら、膝でソファに乗り上げ、上から包み込むように岩城を抱き寄せた。
「ん・・・」
そのまま、天から降ってくるようなキス。
首筋を伸ばし、うっとり目を閉じて、岩城はそれを受け止めた。
「・・・んふっ・・・」
深いくちづけに、岩城は喉を鳴らして応えた。
ふわりと腕が上がり、香藤の腰に絡みつく。
「・・・んっ」
執拗なキスから逃れるように、岩城は小さく首を振った。
肩で息をしながら、潤んだ瞳で睨むように香藤を見上げる。
「・・・酒くさいぞ」
顔をしかめて見せると、香藤がひょいと眉を上げた。
「ごめん」
「・・・なに、にやけてるんだ・・・」
相好を崩したままの香藤に、岩城は憮然とした視線を投げかけた。
「いや、ね」
ドサリ、とソファに沈み込んで。
香藤は甘えるように、岩城の肩に凭れかかった。
「今日さ。俺は幸せだなあ、ってしみじみ思ったんだ」
「・・・はあ?」
「だって、さ。家に帰って来ると、岩城さんがいるんだよ」
「そりゃ・・・」
「岩城さんにおかえりって言ってもらえるのは、世界中で、俺だけだって―――」
香藤がほうっと、熱い息を吐いた。
あまりにも嬉しそうに、うっとりそう囁くので。
「・・・酔っ払い」
岩城は照れて、ついと顔を背けた。
香藤の重みを、しっかりと受け止めたまま。
穏やかな、しばしの沈黙を破って。
くすくすと、香藤が声を立てずに笑った。
「―――きれいな花嫁さんだったけど」
のんびりそう言いながら、香藤は岩城の手を取った。
指を絡めて、ぎゅっと握りしめる。
「ん?」
「世界でいちばんきれいな花嫁は、うちにいるからね」
ずるずると上肢をずらして、香藤は岩城の膝枕に納まった。
とろけそうな眼差しで、まっすぐ岩城を見上げる。
「・・・誰が花嫁だ」
岩城は苦笑して、香藤の頬をぱちりと叩いた。
「痛いってば」
低く笑いながら、香藤は緩慢に身を捩った。
岩城の手はしっかり握ったまま、ゆっくり、半ば瞼を閉じかける。
「あふ・・・」
あくびをかみ殺す香藤に気づいて、岩城は微笑した。
「寝ようか」
薄茶色の髪をそっとすきながら、静かに言う。
「うん・・・」
―――もうちょっと、このまま。
独り言のように、小さくそう呟いて。
子供のような満ち足りた顔で、香藤はくったりと身体の力を抜いた。
ましゅまろんどん
30 October 2006
2013年2月3日、サイト引越にともない再掲載。初稿を若干修正しています。タイトルはドビュッシーの「月の光」から―――あのピアノの旋律をBGMだと思っていただければ。
なお、背景に使用した画像(まんまお月様!)は1ページ目が満月、このページは十六夜(いざよい、立待月)です。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino