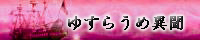日傘
日傘
居間の電話が鳴った。
洋子は反射的に席を立ち、受話器を手に取る。
「はい、香藤です」
「ご無沙汰してます。岩城ですが・・・」
澄んだバリトンの声が響いて、洋子はすぐに顔をほころばせた。
「あっ! お久しぶりです、岩城さん。私です、洋子です」
「あれ・・・」
小さく息を呑んでから、岩城の声が柔らかく笑った。
「洋子ちゃん、本当にしばらくだね。声、お義母さんとそっくりだ。ちょっとわからなくて、びっくりしたよ」
「やだ、岩城さん」
ころころと笑いながら、洋子が明るくまぜっ返した。
「それ、誉め言葉かどうか、微妙ですよ? お母さんが聞いたら、若々しい娘みたいな声だって言われたって、すっごい喜ぶと思うけど」
「あっ、ごめん。そんな意味で言ったわけじゃ・・・」
慌てて、申し訳なさそうに謝る岩城に、洋子は受話器のこっち側で大げさに手を振った。
「冗談ですってば、岩城さん。全然、気にしてないですからー」
けろりと笑って、洋子は続けた。
「今日は、お休みなんですか?」
しばしの雑談を決め込んだ洋子が、楽しそうに尋ねた。
「うん、そう。久しぶりに、ひとりで家にいるんでね。・・・って、あれ。洋子ちゃんもそういえば、船橋に戻ってるんだね」
急いでいる風もなく、ゆったりと岩城が応じる。
「そうなんです。啓太さんが出張でしばらく青森に行ってるんで、親孝行がてら里帰り。・・・って言うのは、口実。ホントは、甘やかされに来てるんですよー」
「あはは、なるほど。ご両親にとっては、いつまでたっても可愛い一人娘だからね。久しぶりで、喜んでるんじゃない?」
「一応、叱られましたけどね。うちを放り出して怠けに帰って来る主婦なんて、って。でも二人とも、洋介にはメロメロだから。ディズニー・シーだ、海浜公園だって、ここ数日もう大騒ぎですよ」
「そうだろうね」
「ええ。おかげで私は、楽させてもらってますけど」
洋介の名前を聞いて、岩城の声がワントーン低くなった。
「洋介くんか。もう、ずいぶん会ってないな・・・」
ほとんど甘いと言ってもいいような声音で、懐かしむように。
岩城はささやくように、そう言った。
「もう5歳、だよね? 可愛い盛りだね。まだ俺のこと、覚えていてくれてるといいけど・・・」
それを聞いて、洋子がくつくつと笑った。
「その心配は、ないと思いますよ。何しろ、お兄ちゃんがさんざん躾けてますからねー。うちでもね、テレビで岩城さんを見つけるたびに、『あ、岩城しゃんだー』って、凄くはしゃいでますよ?」
「・・・俺の出てるドラマ、見せてるの?」
岩城が、小さく笑った。
「言いたくはないけど、教育上よさそうなドラマって少ないよね。子供向けの番組には、まったく縁がないからな―――」
「あは、ご心配なく! ドラマは確かに、まだ無理ですけど。でも岩城さん、いっぱいコマーシャルに出てらっしゃるから。子供は目ざといから、ちーゃんと岩城さんを見つけますよ?」
「あ、そうか」
思い出したように答える岩城に、洋子は呆れた声を出した。
「そうかって、岩城さんたら。・・・ホント、自覚がないんだからー」
「え?」
「ご自分が売れっ子の役者さんだって、忘れてるみたい。・・・そういうとこは、お兄ちゃんも同じですけどね」
「・・・ああ。香藤は本当に、そうだな」
ふと、岩城の声音が変わる。
とろけるように、柔らかにほころんだ響き。
甘さを秘めたそのやさしいトーンに、洋子はくすぐったそうに肩をすくめた。
「岩城さんって、ホント・・・」
「なに?」
「プロの俳優さんなのに。どうしてそういうときは、ご自分の感情を隠せないのかしら? っていうか、気づいてないのかな」
くすくす笑いながら、洋子が言った。
「え・・・?」
岩城が、戸惑いの声を漏らす。
「今のたったひと言、香藤って。ホントに嬉しそうで、何ていうか・・・岩城さんがお兄ちゃんの話をするのって、聞いてて、こっちが照れちゃう感じ?」
「・・・そんな」
返答に困ったのか、岩城は小さく苦笑した。
「話ってほどの話は、してないと思うけど・・・」
「でも、わかるもん。お兄ちゃん、本当に愛されてるなあって思います」
きっぱりそう断言されて、岩城はきまり悪げに咳払いした。
「・・・ごめん」
「あん、謝らなくても!」
洋子は驚いて、甲高い声を出した。
「えっと、あの、岩城さん。さっきから暇な私のおしゃべりに、つき合わせちゃってますけど。うちの両親に、何かご用があるんですよね?」
「ああ、うん」
ほっとしたように、岩城が言葉を続けた。
「楽しくて、こっちもすっかり忘れていたよ。あのね、今朝、お義母さん宛てに小包を送ったから。それを、伝えておこうと思って」
「小包?」
「ああ、そうなんだ・・・」
ふと、思い出したように。
岩城は言葉を切って、ゆったりした声で笑った。
「香藤が、お義母さんにって日傘を買ったんだよ」
「・・・日傘、ですか?」
意外なその言葉に当惑して、洋子はオウム返しに岩城に聞き返した。
「なんでまた・・・今さら、日傘? もう秋だと思うけど」
「うん、そうなんだけどね」
岩城の声がわずかに弾んだ。
「この間・・・お盆の前に一日だけオフが取れたときに、そちらに寄らせてもらったんだけど」
「ええ、それは、母から聞いてます」
「そのときちょうど、お義母さんが、お気に入りだった晴雨兼用の日傘が壊れたって嘆いてらして。それで香藤が、じゃあ新しいのを買ってあげるよって、請け負ったんだよ」
「ああ、なるほど・・・」
ようやく事情が飲み込めた、という風に。
洋子は受話器を握りしめたまま、小さく頷いた。
「今までそれを忘れてたのね、お兄ちゃんったら」
「忘れてたわけじゃ、ないんだけど」
軽く笑って、岩城は話を続けた。
「忙しさにかまけて・・・かな。とにかく気づいたら、もうとっくに日傘のシーズなんて終わっててね。でもあいつ、約束したからには、どうしても最高の日傘を見つけてお義母さんに贈るって、聞かなくて」
洋子は思わず笑みをもらした。
「あはは、もう! 無駄な意地張って、お兄ちゃんらしいや」
「うん、それでね。もうどこを探しても、なかなか売ってなかったんだ。直接デパートに電話かけたり、インターネットで探したり、気に入ったのを見つけるのに、けっこう苦労したんだ」
「・・・お兄ちゃん、バカすぎ・・・!」
爆笑した洋子に、岩城は楽しそうに言葉を返した。
「まあ、子供みたいなところはあるよね。ムキになると特に」
でも、と岩城は続けた。
「母親思いの、いい息子だと思う。だから俺もずいぶん、一緒に探したんだけど」
「岩城さんも?」
「ああ」
あっさりと肯定する岩城の明るい口調に、洋子は微苦笑した。
「・・・どっちもどっちね・・・」
「え?」
「ううん、こっちの話!」
ひと息ついてから、岩城は説明を続けた。
洋子にはそれはもう、惚気にしか聞こえなかったけれど。
「そういうわけで、ようやく俺たちの気に入った日傘を見つけたんだ。今さら時期はずれだとは思うけど、今朝、宅急便で送ったから。お義母さんに、そう伝えておいてもらえるかな」
「うん、岩城さん。伝えておきます」
「あ、今の裏話はオフレコのほうがいいな」
「はい、もちろん!」
「ありがとう、洋子ちゃん。それじゃ俺は、そろそろ・・・」
屈託のない岩城の声。
それを聞きながら、洋子はふと、思った。
ときに無防備なほど純粋な、兄の恋人。
親戚―――家族としての彼は、テレビや映画で見かける俳優『岩城京介』とはまったくの別人だ。
ひたむきで献身的で、そしてどこか脆い。
自分よりはるかに年上のはずなのだが、守ってあげたくなるような危うさを持っている。
兄が脂下がって、ことあるごとに岩城を「可愛い」と惚気るのが、今ならよくわかる。
たしか、兄とそういう関係になって、もう10年近いはずだ。
それなのに、いまだに初々しさの抜けないのはなぜだろう。
香藤しか見えていないからか。
それが、打算のない愛だからか。
全身全霊で恋をしているのが、傍から見ていてもわかるからかもしれない。
それが当然であるかのように、ごく自然に。
岩城は、香藤洋二のために生きている。
もちろんキャリアへのこだわりもプライドも、人一倍あるのだろうけれど。
それとは比較にならない深いレベルで、生涯のすべてを、香藤との恋愛に捧げている。
せつないほどの純愛。
それがわかるから、洋子の家族も岩城を受け入れたのだろう。
受け入れることが、できたのだろう・・・。
「―――そういう盲目的な愛って、女には無理って気がするな・・・」
「・・・え?」
洋子のつぶやきにを聞き取れずに、岩城が問い返した。
「ううん、なんでもないの」
「ごめん、俺、ぼうっとしてたかな?」
「そんなことないよ、岩城さん」
洋子は穏やかに笑って、首を振った。
「じゃあ、俺はこれで。洋介くんと、ご両親によろしくお伝えください」
「はい、伝えます。岩城さんも、いつもお忙しいみたいだから、無理しないでくださいね?」
「うん、ありがとう。香藤にもそう、伝えておくよ」
最後にもう一度、最愛の恋人の名前を口にして。
岩城はそっと、電話を切った。
ましゅまろんどん
10 October 2006
サイト開設1周年記念のつもりで書いたお話です。
香藤家の一人娘と兄嫁の、のん気な昼下がりの会話(笑)。
でも今思うと・・・岩城さん、しゃべりすぎよね(汗)。
2013年2月11日、サイト引越にともない再掲載。初稿を若干修正しています。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino