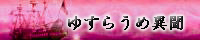The Pretender
The Pretender: the show must go on
「そう、いいね、岩城くん!」
しんと静まり返ったスタジオに、持宗の声がびんびん響いた。
「オッケー!」
持宗が、横柄に顎をしゃくる。
「これで行こう」
「はい」
脇に立つアシスタント・ディレクターが頷く。
「じゃあ今のシーン、本番行きまーす!」
それを合図に、カメラを抱えた男が二人、セットの端ににじり寄った。
風が凪ぐようにざわめきが止み、多数の視線がセットの中に凝縮される。
「あのー、監督。岩城さんの衣装替えは―――」
忍び足のスタッフが、肩越しに持宗に声をかけた。
「黙って」
「すみませんっ! でも、あの、予定では・・・」
しどろもどろになりながら、なお食い下がる若い男を、持宗はちろりと見下ろした。
蔑むような冷たい視線。
「うるさいよ、黙って」
「・・・」
男は声もなく、うな垂れた。
本番の声がかかり、スタジオが一気に緊迫する。
最後列で撮影を見守っていた別のスタッフが、そっとため息をついた。
「なんだか、なあ・・・」
「どうしたの?」
隣りに立つ女が、声をひそめて尋ねた。
「いや、岩城さんさ。・・・すっげえよな」
「ああ」
話が見えたと言わんばかりに、女は頷いた。
「何があったのか知らないけど、ここ数日、とにかく震え上がるほどの演技をしてるよな」
「そうね。いきなり突き抜けた・・・っていうか。正直、怖いくらいよ―――」
周囲を見回してから、女は小声で続けた。
「監督が求めてたのは、この岩城京介だったってわけね」
「・・・らしいな。持宗さん、ここんとこ凄まじくノってるから。イメージ通りの『周防崇』に夢中っつうか」
「そうね」
「岩城さんとあれだけやりあったことすら、忘れてんだろうなー」
女は、小さく笑った。
「岩城さんの、あの顔。―――サロメよね」
「・・・はあ!?」
思いもかけない喩えに、男が素っ頓狂な声を出した。
途端にスタジオのあちこちで、叱責代わりの咳払いが起こる。
「す、すみません・・・!」
男は低くそう言って、持宗の後姿に頭を下げた。
本番の撮影は、まもなく始まろうとしていた。
「あんたが、変なこと言うから―――」
俯き加減のまま、男は隣りの女に恨めしげな視線を向けた。
「あら、サロメのどこが変なの?」
平然と返された言葉に、しばし絶句する。
「あんた、ねえ。どこがって・・・サロメって女だろ? それも、聖職者に恋した挙句、なびかない相手の首を斬らせた頭オカシイ女・・・だよな」
「そうよ」
「それのどこが、岩城さんの『周防崇』なんだよ?」
その反論に、今度は女が小さくため息をついた。
「・・・見えてないの? 岩城さんが演じてるあれは、通常の意味での『男性』じゃ、ないじゃない」
「なんだそりゃ?」
「なんていうか、恋にすべてを賭けて、すべてを失った・・・そんな感じに見える。常軌を逸した女の、鬼気迫る狂気を感じない?」
「鬼気迫るって、そりゃ・・・」
男はチラリと、セットの中でスポットライトを浴びる岩城に目をやった。
何も映さない、昏い瞳。
まったく人間らしさの感じられない、無機質なまなざし。
ほの暗い冷酷な微笑は、見る者を恐怖に陥れる―――。
暖かい血が通っているとはとうてい思えない、禍々しい存在感。
―――そこには、修羅を演じる岩城京介が、いた。
「なるほど・・・」
ゆっくりと、男が頷いた。
「何もかも失って、人間性を切り捨てた夜叉―――って、ことか」
「そうね」
「殺人鬼『周防崇』もかつては普通の人間だったってのが、岩城さんの解釈なわけだ」
「そんな風に見えるよね」
「おもしろいな。この勝負・・・」
男がニヤリと、笑った。
「化けてみせた岩城京介と、それを引き出した持宗さん。どっちの勝ちなんだろうな」
「―――これだから、男って」
女が軽口で応じた。
「どうしてこう、勝ち負けにこだわるのかしら。きっと凄い映画ができる。それだけでいいじゃない?」
「それも、そうだな」
二人は、顔を見合わせて微笑した。
☆ ☆ ☆
「じゃあ今日は、ここまで!」
「お疲れさまでーす」
「お疲れー」
撮影終了と同時に、持宗は黙って席を立つ。
「ありがとうございました」
セットに背を向けかけた若き監督に、岩城が挨拶をした。
毎日必ず、繰り返されるジェスチャー。
深々と頭を下げて礼を尽くす主演男優を、持宗は振り返った。
「いいから、それ」
「え?」
「嫌味に見えるから、さ」
眉をしかめて、持宗は言った。
「やめてくれって、この間もマネさんに伝えたと思うけど」
「ええ、ですが」
「僕より岩城くんのほうがギャラもずっと高いし、よっぽど有名人でしょ。そんな風に頭を下げられても、慇懃無礼な感じがするし―――」
途中まで言いかけて、あとはまるで飽きたかのように。
持宗はその続きを呑み込んで、小さなため息をつく。
「もう、いいから」
そのまま軽く手を振り、すたすたと立ち去った。
「―――」
呆然と見送る岩城に、清水がそっと声をかけた。
「岩城さん、あの・・・」
「ん?」
「車、回してきます」
「ああ、はい。お願いします」
それから彼女は、半ば独りごとのように呟いた。
「あれ・・・監督なりのお気遣い、なんでしょうか・・・?」
「気遣いって」
岩城がくしゃりと笑った。
「もういちいち、腹も立たないけど。相変わらず失礼なこと、言われただけじゃ・・・」
「―――そうかも、しれませんが」
持宗の後ろ姿を、見るともなく見送りながら。
岩城を見上げて、清水は言葉を続けた。
「・・・最近の岩城さんのお仕事ぶりを認められて、それで。頭は下げなくていいって、仰ったおつもりかもしれませんね」
「どうだか、ね」
小首をかしげて、岩城は微笑した。
「本当に、癖のある方らしくて・・・」
「まあ、いいさ。あの人の理不尽な物言いには、もう慣れたよ」
鷹揚に笑って、岩城は歩き出した。
「ずいぶん寛容に、おなりですね」
一歩先を歩きながら、清水がくすりと笑った。
「ああ、それはね」
肩越しに清水を見返して、岩城が答える。
「・・・あきらめ、とはちょっと違うけど。達観したのかな。いちいち怒ってたら、俺の身がもたないから」
そう言って肩をすくめた岩城の笑顔は、晴れやかだった。
「そうですか」
清水はそっと、控えめに頷いた。
☆ ☆ ☆
「あ・・・―――」
清水に先導されるように撮影所を出た岩城は、正面玄関の向こう側に停まっているベンツに気づいて、目を瞠った。
「あら、あれ・・・」
一瞬遅れて、清水も小さな声をもらす。
長身のシルエットが、ゆったりと車から降り立った。
「岩城さん」
そのまま二歩、三歩。
穏やかな笑みを浮かべた香藤洋二が、指先で小さくキスを飛ばした。
「香藤―――」
俳優・岩城京介の仮面が、ゆっくり、剥がれ落ちた。
ふうわりと花咲き、こぼれ落ちるような微笑。
緊張していた四肢が、まろやかな薫風に融けるように、ゆっくりと弛緩していく。
「来てたのか」
つややかなバリトンが、甘く掠れた。
岩城が恋人にしか絶対に見せないその表情に、清水は目を細めた。
香藤が、のんびりと近づく。
「五日ぶりだね、岩城さん。迎えに来たよ」
さらりとそう言って、香藤は清水に、軽く頭を下げた。
「すみません。岩城さんは、攫って行きます」
「まあ、いいえ」
清水は手を口にあてて、笑いかけた。
「香藤さんも、復帰のお仕事でお忙しいでしょうに。私の仕事を代わってくださって、ありがとうございます」
「ありがとう、清水さん」
屈託なく笑って、香藤は岩城に視線を戻した。
「うちに、帰ろう」
「ああ」
岩城が手にしていた衣装入りのバッグを、香藤は当然のように取り上げた。
「じゃあ清水さん、また明日」
「ええ、明日の撮影は―――」
ちょうど、そのとき。
正面玄関のドアが無造作に開けられ、ふらりと持宗が姿を現した。
「監督―――」
くぐもった声で何か言いかけようとした岩城に、気づいて。
持宗は、面倒くさそうに振り返った。
「まだ何かあるの、岩城くん」
その不躾な物言いに、香藤が眉をしかめた。
「おや・・・」
岩城のバッグを提げてすらりと立つ香藤に、持宗が目を向けた。
細身の秋色のシャツに、色あせたジーンズ。
サンダルをつっかけただけの普段着の香藤を、値踏みするように見つめる。
「・・・香藤洋二くんか、なるほどね。岩城くん、旦那さまのお迎えかい」
いいご身分だね、と持宗は続けた。
「おっと。プライベートに口出ししちゃ、いけないんだったっけ」
撮影中は別居する、という条件が守られていないことを揶揄する言葉だった。
挑発するような言い草に、香藤がますます眉をひそめる。
それに気づいて、岩城がそっと、香藤の肘に手をかけた。
「香藤」
「岩城さん」
小さく振り返った香藤に、岩城は黙って、首を横に振った。
「・・・そう」
香藤は少し天を仰いで、ふうっと深呼吸した。
鋼のような筋肉に覆われた体躯が、ゆるやかに弛緩する。
岩城が隣りでそれを察して、胸を撫で下ろした。
その一部始終を観察していた持宗が、笑った。
「なるほど、ねえ・・・」
「持宗監督、はじめまして。香藤洋二です」
姿勢を正して、香藤はすっと頭を下げた。
「うん、はじめまして。お噂はかねがね聞いてるよ」
「そうですか」
眼下の持宗をじろりと見下ろして、香藤が口を開いた。
―――笑顔だが、眼差しは厳しく、辺りを睥睨したまま。
「いつもうちの岩城が、お世話になっています」
低い声でそう言って、香藤はにっこり笑った。
「これからもどうぞ、よろしくお願いします」
自信に満ちあふれた、太陽のような存在感。
「・・・それは、どうもご丁寧に」
芸能界から忘れかけられていた男とは思えない、その眩しい笑みに、持宗は目を眇めた。
その脇で、岩城がくすりと笑った。
持宗が目にしたこともない、甘やかな表情で。
「―――じゃ、監督。俺たちはこれで」
捨て台詞のように言うと、香藤はすっと隣りに腕を伸ばした。
差し出された手のひらに、迷わず岩城の手が重なる。
「失礼します」
岩城はそう付け足して、くるりと背を向けた。
毅然とした背中。
「いい歳して、あれかい―――」
持宗はぼやきながら、長身の二人の後ろ姿を眺めた。
持宗の探るような視線を、意識しているのかいないのか。
香藤の腕が、ごく自然に岩城の腰に回った。
それを感じて、岩城が一瞬、甘えるように身体を香藤にすり寄せた。
視線が絡み、吐息が重なり、二人の身体が密着する。
キス直前のあやうさ。
ほんのわずかな時間に漂う、エロティックな交歓。
それから、するりと戒めから抜け出すように。
岩城は身体を離し、すたすたと車に戻っていった。
すぐに追いついた香藤が、岩城のために助手席の扉を開ける。
ちらりと視線で会話を交わして、岩城が車に乗り込んだ。
ドアに手をかけたまま、助手席を覗き込むように、香藤が腰を屈める。
二人のシルエットがぴたりと重なった。
・・・ややあって、香藤が運転席に滑り込んだ。
―――その間ずっと、途切れることなく。
岩城の顔には、ほころんだほのかな微笑が浮かんでいた。
甘いと言っていいほどの、香藤だけを映すまなざし。
キスを誘う紅い唇。
触れた肌からとろけ出しそうな、あやうい渇望。
しなやかな身体が、溢れるほどの愛情を訴えていた。
全身全霊で、香藤のぬくもりを喜んでいるのがわかる。
あまりに無防備な、恋する素顔。
―――その、すべて。
持宗が一度たりとも、目にしたことのないものだった。
「なるほど、ねえ」
彼は嘆息した。
岩城が醸していた、したたるような色気。
香藤にだけ向けられる、婀娜めいた微笑。
「・・・香藤洋二、か」
岩城を支える男の存在の大きさを、持宗が実感した瞬間だった。
「役者のプライベートに、興味はないけどね」
眩しいほどに鮮やかな、岩城京介。
まるでフィルムに焼き付けることのできない、夢のような。
「僕は、岩城京介の何を、知っていたって言うんだろう・・・」
見たばかりの幻影に苛まれて、持宗はガシガシと頭を掻いた。
☆ ☆ ☆
「香藤―――」
甘い吐息で、岩城が呼びかけた。
「んん?」
その言葉の続きをキスで封じながら、香藤は岩城のシャツのボタンに手をかけた。
ひとつ、ふたつ。
ボタンがはずされ、香藤の指が首筋をなぞる。
「・・・ふぅん・・・」
せつなげに鼻から抜ける息が、恋人をいっそう煽り立てた。
「おい・・・」
長いキスから逃れて、岩城が小さく制止した。
濡れた唇が、駐車場のぼんやりとした照明を受けて、ざくろ色に光る。
はだけられたシャツからは、ほの白い肌が覗いていた。
「久しぶりだね・・・」
香藤はそこに、ゆっくりと手のひらを這わせる。
「ばか・・・」
つんと尖った乳首が、香藤の愛撫を待っていた。
器用な指先がそこを軽く弾き、揉み込み、引っ張りながら肌をまさぐる。
「はうっ・・・んん」
凝った乳首を弄るように愛されて、岩城の全身が震えた。
「吸って欲しい・・・?」
「・・・いぁ・・・」
「嫌なの?」
熱い息が、車内に満ちる。
軽く仰け反って、シートに深く沈みこみながら。
岩城は左手で、香藤の悪戯な手を掴まえた。
「何も、こんなところで」
息を弾ませて、岩城は香藤を睨みつけた。
くすり、と香藤が微笑を返す。
「嫌がってない、みたいだけど」
耳元でそう囁いて。
香藤は、岩城をすっぽりと抱き寄せた。
岩城の肌が、ゾクリと粟立った。
狭い車中で、可能な限り、身体と身体を密着させる。
露わになった項に、香藤は舌を這わせた。
「ふっ・・・」
じっくりと、肌の甘さを味わうように。
香藤はゆるゆると、岩城の首筋を舐めあげた。
「か、と・・・」
濡れた舌の軌跡に息を吹きかけられて、岩城は身体を震わせた。
そろそろと香藤の手が岩城の背筋を伝い、尻にたどり着いた。
「ぁん・・・」
みっしりと硬い感触を確かめるように、香藤の両手がそこを這い回る。
岩城は顔を香藤の肩に埋めて、かすかに呻いた。
「・・・ぅん・・・」
布越しの、やわやわとした愛撫。
緩急をつけて執拗に尻を揉みしだかれ、岩城の息が乱れた。
時折、まるで揶うように、香藤の指が双丘の間に触れる。
そのたびに、岩城は小さく息を呑んだ。
神秘の入口を求めて、香藤の指があやしげに蠢く。
岩城の腰が、ねだるように揺れる。
「・・・んくっ・・・あぁ・・・」
岩城が息を詰めると、何もなかったかのように、また指はそこを離れていった―――。
「欲しい?」
「んあ・・・っ」
「それとも、欲しくない?」
「ばっ・・・」
官能を追い立てるのではなく、やんわりと思い出させるようなその感触。
もどかしさに、岩城は頬を染めて香藤にしがみついた。
「岩城さん・・・」
ため息混じりに、香藤が恋人を呼んだ。
「・・・ん?」
「顔、見せて―――」
耳を噛まれて、岩城はぶるりと身体を震わせた。
ゆるゆると顔をあげて、香藤を見つめる。
「好きだよ、岩城さん」
「香藤・・・」
甘い声。
それよりもっと甘い、濡れたまなざし。
すっかり紅潮した頬を恥じるように、俯きがちに岩城は言った。
「帰ろう・・・」
「うん」
小さく頷きながら、香藤は片手で、岩城の顎を持ち上げた。
「綺麗だよ」
「かと・・・」
「本当に、綺麗だ―――」
ため息と共にそう言って、香藤は岩城にくちづけた。
「・・・んん―――」
深い、深いキス。
岩城の両腕が、しっかりと香藤の首に廻された。
それに応えるように、香藤も岩城をぎゅっと抱き寄せる。
「・・・んふっ」
「岩城さん・・・」
皮のシートが、きしりと乾いた音を立てた。
黄昏の薄闇の中。
恋人たちは固く抱き合ったまま、しばらくぬくもりを分け合った。
ましゅまろんどん
5 September 2006
これは、小説ではなくてSSですね(苦笑)。 小さなシーンを切り取っただけで、起承転結は二の次(爆)。 『フライト・コントロール』後を妄想してたら、こうなりました。
2013年2月9日、サイト引越にともない再掲載。初稿を若干修正しています。
No reproduction, copying, publishing, translation or any other form of use or exploitation allowed without authorisation. All copyright and other intellectual property rights reserved and protected under Japanese and UK statute and all relevant international treaties.
Copyright(c) 2005-2012 May Fujino