Prelude 01
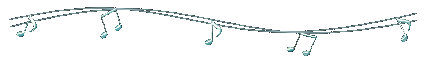
小さなぬくもりがするりと離れていった。
「おい、こら待て、洋介!」
一瞬の隙だった。
俺があわてて声を上げるのと。
パタパタと、幼い後ろ姿が廊下を走っていくのと。
無機質な白いドアが音も立てずに開くのは、ほぼ同時だった。
「危ない・・・っ!!」
ドアから、背の高い人影が現れた。
「洋介!!」
「あ・・・っ」
勢い余って、洋介がその男の膝あたりにドンッとぶつかる。
「・・・え?」
はずみ、というのはおそろしい。
思いがけず足をなぎ払われた格好のその男は、ふらりとバランスを崩した。
ゆらりと傾(かし)ぎ、そのまま廊下に倒れる。
高いところから、すとんと落ちるみたいに。
「あ・・・!」
思わず、俺は息を呑んだ。
あたふたと駆け寄り、ぺこりと半身を折る。
「す、すみません!!」
洋介は、きょとんとしている。
その頭を軽く小突いてから、俺はその男に手を差し伸ばした。
「こいつがとんだことを・・・あの、お怪我は?」
その男がゆっくりと、こちらを振り向いた。
―――俺は、言葉を失った。
「え・・・」
深い湖水のような光をたたえた切れ長の瞳。
真珠のような、艶めいた輝きの白い肌。
秀でた額にはらりとかかる黒髪。
意外なほど肉感的な赤い唇が、うっすらと開かれている。
「あ・・・の、大丈夫ですか」
俺はガラにもなくうろたえた。
息を呑むほどの、美貌だった。
―――美貌、としか呼びようがなかった。
どう見ても、俺と同じ男だというのに。
精巧につくられた繊細な工芸品のような美しさ。
―――なんだ、これ!?
なんなんだ、これは。
こんな男、見たことない。
動揺を悟られないように、俺はもう一度声をかける。
「あの、怪我はありませんか」
倒れたときに打ったのか、男は腰のあたりにそっと手をやった。
その仕草が妙に官能的だった。
・・・馬鹿じゃないのか、俺は。
―――そりゃ、きれいな顔をしてはいるが。
目の前の彼は、れっきとした成人男性だ。
服装にも態度にも、女性めいた部分など、どこにもないというのに。
「いえ・・・」
つややかな甘いテノールだった。
「どうも。大丈夫だと、思います」
苦笑しながら、彼は俺を見上げた。
―――の、だが。
差し出されたままの俺の腕。
その目と鼻の先にいながら、まったく反応がない。
こちらを見ている、その視線が俺に届かない。
どこか、方向がずれている―――そんな奇妙な感覚。
目が合わない。
何かがおかしい。
俺はかすかな違和感を感じた。
「あの・・・」
言葉がぽつんと宙に浮く。
廊下に散乱している大判の紙切れに、ふと目が行った。
楽譜、だった。
気づかなかったが、彼が転倒したときに落としたのだろう。
それを何気なく見て、俺ははっとした。
楽譜一面をおおう、無色の小さな凹凸の羅列。
これは―――。
俺はようやく、事情を理解した。
「あの・・・ほ、本当にすみません」
俺はもう一度、深々と頭を下げた。
男はまだ、立ち上がらない。
「うちのバカ息子が突然走り出して、ぶつかったんです。・・・あの、手を貸しましょうか」
そこまで言って、彼の顔をもう一度見つめた。
きらめく黒曜石の瞳。
俺と、交わろうとしないその視線。
こんなに綺麗なのに、何も映さないのだろうか・・・?
「ありがとう」
ほとんど囁きのような声。
男は逡巡しながら、その白い手を差し出した。
その腕を慎重に掴み、俺はゆっくりと男を立ち上がらせた。
「どうも・・・」
すらりとした肢体。
背格好は、俺とたいして変わらないだろう。
彼はそろりと左右の手首に触れ、確かめるように小さく回した。
それから、俺のほうに向き直る。
「息子さんに、怪我はありませんか」
声が少し、やわらかくなったような気がする。
「はい、それは・・・」
俺は振り返り、つくねんと立ち尽くす洋介を手招きした。
「洋介、このお兄さんに謝りなさい」
洋介はもぞもぞと俺の脚の間にもぐりこんだ。
「こら、叱られたいのか?」
俺の低い声に、洋介は泣きそうな顔をする。
「・・・なさい」
「聞こえないぞ」
「・・・ごめんなさい」
消え入りそうな声。
よくできた、とほめる代わりに、俺は洋介の髪をくしゃりと撫でた。
子供の声のする方向に、彼が微笑んだ。
「俺は大丈夫だよ。僕は、いくつ?」
「よっつ」
「そうか。ちゃんとごめんなさいが言えて、えらいね」
やさしい顔で笑う。
何か言おうと口を開いた俺は、その男の微笑にみとれた。
―――綺麗だ、と思った。
そのとき、足音がした。
振り返ると、長い廊下の向こうから黒いスーツ姿の女性が近づいて来る。
黒髪のボブに、銀縁の眼鏡。
いかにも有能な秘書といった雰囲気の、几帳面そうな人。
男は小さく、ため息をつく。
「すみません、清水さん。待たせてしまって」
いきなり名前が出て、俺は面食らった。
見えない・・・はずではないのか?
それから、パンプスの音でわかったのかもしれない、と思い直した。
ろくに彼女の方向を見もせずに、彼が静かに言った。
「もう時間ですか」
「いいえ、それはまだ・・・」
清水と呼ばれた女性は、ふいに立ち止まった。
驚いた表情で、そこに立ち尽くす俺たちを見つめる。
―――ああ、そうか。
廊下に散乱した楽譜に気づいたのだろう。
すっと屈んで手早く拾いながら、心配げに聞いた。
「岩城さん。何か・・・?」
俺たち父子に、ちらりと視線を投げかける。
感情のない、硬い口調だった。
洋介は再び、俺の脚の間に隠れてしまった。
「何でもありませんよ」
岩城と呼ばれた男は、穏やかな声で言った。
それから俺のほうをじっと見つめた。
さまよう視線。
―――見えるわけじゃないのだろうが。
それでもその瞳は、今度は真っ直ぐに俺の顔に探し当てたようだった。
どうしてわかるのだろう。
どこまで、わかるのだろう。
動揺する心の中まで、見透かされそうだ。
「残念ですが、リハーサルがありますので。これで失礼します」
ちょっと口ごもる。
―――リハーサル・・・?
何の、と聞こうとした矢先だった。
「・・・あの」
「え?」
「・・・いや、何でもない。それでは」
そう言って会釈し、彼は唐突に話を打ち切ってしまった。
「え・・・」
そのまま、廊下をすたすた歩いて行く。
よっぽど歩き慣れているのだろう、清水さんも手を貸そうとしない。
とても目が見えないとは思えない、堂々とした歩き方だった。
―――見えない・・・んだよな?
それとも、そう思ったのは俺の錯覚だったのか?
「パパ・・・」
「うん?」
無意識に洋介の頭をなでながら、俺は思わずつぶやいていた。
「岩城さんって言ってたっけ。誰なんだろう・・・」
++++++++++
「岩城京介に会ったあ!?」
俺の疑問は、翌朝あっさりと氷解した。
俺の勤める公立小学校の教員室。
音楽教諭の同僚、芦田ゆかりに聞いたのは正解だった。
たぶん目の見えない、ハンサムな男性。
会ったのは、市民文化センターの廊下。
楽譜を持っていたから、音楽家だろう。
点字つきの楽譜などというものは初めて見た。
秘書らしき人がいるくらいだから、プロかもしれない。
・・・俺の手がかりは、その程度だったのだが。
「信じらんない。超有名人だよ!?」
盲目のハンサムと聞いただけで、ゆかりは大声を張り上げた。
「今じゃ海外でもけっこう知られた、クラシック音楽界のスーパースターだよ。ハリウッド映画の音楽なんかもやってるし。香藤先生、本当に知らないの?」
驚くというよりは、呆れたという口ぶりだった。
随分ニュースになっているのに、ということらしい。
「そんなこと言われても・・・」
知らなかったのだから、しかたない。
クラシック音楽とは無縁の人生を過ごしてきた。
音楽といえば、子供の好きなアニメの主題歌くらいしか聞かない。
「一般常識の範囲だと思うけどなあ」
ブツブツ言いながらも、ゆかりは彼について教えてくれた。
岩城京介、34歳。
国際的に名の知られたピアニスト。
どうやら、中学だか高校だかのときに事故で失明したらしい。
弱冠18歳で、チャイコフスキー・コンクール入賞。
―――と言われても。
チャイコフスキー・コンクールがどのくらいすごいのか、すごくないのか、俺にはわからない。
ただ、凄いんだろうな、と思うほかない。
「今週は、市民文化センターでコンサートがあるのよ」
その情報を知らないほうがおかしい、と言わんばかりの彼女に、俺はもう頷くしかなかった。
つまり、そのための準備であそこにいたというわけだ。
リハーサルがあると、実際そう言っていた。
「なるほどね・・・」
リサイタルで全国を飛び回るピアニスト、か。
それなら、コンサート会場の廊下を迷わずに歩けても不思議はない。
―――大したもんだな。
俺は妙に感心した。
「それにしても」
「ん?」
「香藤先生こそ、どうして文化センターなんかにいたの?」
「ああ、息子のね」
俺は苦笑した。
「あそこ、市営のキッズセンターがあるんだよ」
「それって」
「うん、保育園」
「・・・そっか。洋介くん、預かってもらってるんだ」
「うん」
「そっかあ」
そこでふと、会話が途切れる。
俺はもう一度、頭をかいた。
正直、職場で子供の話をするのはあまり好きじゃない。
―――したくない、というわけじゃなくて。
周囲に余計な気を遣わせてしまうから。
思い出すのが、辛いから。
―――もう、三年も前のことなんだけどな。
ふと、記憶が再生する。
病気がちだった妻の智美が早世してから、そろそろ三年。
生まれて間もないひとり息子を残して、彼女は逝ってしまった。
洋介はだから、母親を知らない。
―――忘れたいわけでも、忘れられるはずもない。
彼女を失って、俺の半身は死んだ。
死んだも同然だと思っていた。
―――だが俺には、洋介がいるから。
死ぬわけにはいかなかった。
生きるしかなかった。
それから三年。
同僚に関して言えば、そろそろ痛ましげに俺を見るのはやめてほしいというのが、正直な気持ちだった。
さんざん心配してもらって、図々しい願いかもしれない。
同僚たちの親身な気遣いに、今まで支えられて来たのも事実だ。
それでも、いつまでも腫れ物のように扱われるのは、少々しんどい。
どんなに辛くても、生き残ったほうは働いて、食べていかなくちゃいけない。
洋介がいるから、洋介のためにも。
―――俺たち、頑張ってきたよな。
たしかに、洋介は不憫な子供かもしれない。
でも実際、母親がいなくてもたくましく育ってる息子を見ていると、責任を感じる反面、生きることの楽しさを思い出す。
命の温かさを思い出す。
明日を夢見てもいいのだ、と感じる。
それでいいんだ、と思う。
くよくよ悩んでも、失った過去は取り戻せないから。
―――始業のチャイムがなった。
「さ、お仕事ですよ」
俺は笑って立ち上がった。
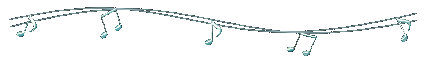
藤乃めい
23 October 2005
原稿が古すぎて、どこをどう修正すればいいのか・・・(汗)。
2013年09月07日、サイト引越により新URLに再掲載。