Prelude 02
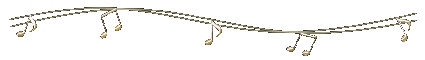
++++++++++
その次の週。
俺は一大決心をして、市民文化センターに出かけた。
実家の両親が洋介を預かってくれたので、今日はひとりだ。
シングルファーザーになって、そろそろ三年。
仕事がらみ以外で夜、子供を置いて外出するのはこれが初めてのことだ。
『ゆっくり息抜きしてらっしゃい』
お袋は何も聞かず、笑顔で俺を送り出してくれた。
―――やけに嬉しそうだったな。
思い出して、俺は苦笑した。
どこか浮足立っている俺に、勘づいていたのかもしれない。
美貌の、盲目のピアニスト。
彼のことを知ってからしばらく、夜になるとインターネット検索に勤しんだ。
岩城京介という人について。
経歴や、評判や、ディスコグラフィー。
インタビューや、雑誌の記事。
彼に関することなら、何でもむさぼるように読んだ。
ファッション誌のグラビアにすら、ときおり登場していた。
―――凄い。
相当な有名人だというのは、疑いようがなかった。
熱狂的なファンが世界中にいることもわかった。
―――なんで今まで、知らなかったんだろう。
自分の無知を恥じるしかない。
それから、岩城さんのコンサートの日程を調べた。
チケットは全日程がすでに完売。
まずはそのことに驚いた。
いったんは諦めた俺だが、当日券があると知った。
出勤のない土曜日だったのも幸いした。
『ともかく、行ってみよう』
教え子の父兄に遭遇しないことを祈りながら、俺は早くから行列に並び、なんとか席を確保した。
クラシックコンサートのチケットを買うのも、生まれて初めての経験だ。
―――どんな格好をしていけばいいんだ?
前夜になると、別の悩みが生まれた。
少し考えて、めったに触れないクローゼットの一番端の扉を開けた。
独身時代に奮発したブランドもののスーツ。
洋介が生まれてからは、たぶん一度も着ていない。
智美にもらったイタリア製のネクタイ。
めかしこんでいる自分に気づいて、俺はちょっと笑った。
―――俺、何やってんだろ。
まるでデートするみたいに浮かれてる自分に驚く。
この三年間で、初めてのことだ。
だいたい、相手は男性だ。
それも雲の上の人。
俺は聴衆のひとりとして、観客席から見上げるだけだ。
会えるわけじゃない。
かりに会えたとしても、俺のことなんて、覚えているかどうかもあやしい。
俺と洋介は、ちょっと接触した通行人にすぎないのだから。
―――だいたい、会ったとして何を言うんだ?
なにを期待しているんだろう。
なぜ、こんなに気になるんだろう。
相手は世界を飛び回るピアニストだ。
れっきとした男性で、五歳も年上だ。
俺はしがないやもめの公務員。
釣り合うわけがない。
いや、待て。
・・・おかしいんじゃないのか。
―――釣り合うとか、釣り合わないとか。
それ以前の問題じゃないか。
『バカだろ、俺・・・!』
暴走する妄想が止まらない。
どうしてももう一度。
もう一度だけ、岩城さんに会いたかった。
遠目でいいから、あの微笑を見たい。
俺は、そう思わずにはいられなかった。
++++++++++
ざわめくコンサート会場。
開演まで、まだ三十分ある。
手持ちぶさただった俺は、壁にかかるポスターをぼんやりと眺めていた。
深紅の背景に、ブラックタイ姿の岩城さん。
ピアノに手を添えて微笑んでいた。
優雅な、悠然たる美貌。
男らしいのに、どこか艶がある。
ヴィスコンティ映画の世界から抜け出して来たようだ。
この間はふつうのシャツとジーンズだったけれど、こういう華やかな服装がよく似合う。
―――別世界だよなあ。
きれいな漆黒の瞳に、俺はみとれた。
障害という言葉が、これほど似合わないひともいない。
若い女性が数名、しゃらしゃらと近づいてくる。
結婚披露宴帰りかと思うような、目いっぱいの盛装姿。
彼女たちの高揚ぶりは、その表情からわかった。
揃ってハンドバッグから携帯電話を取り出して、揃ってポスターの前でそれを構える。
―――ああ、そうか。
俺はあわてて、最前列を譲った。
フラッシュが光り、何度も電子音がする。
素敵、カッコいい・・・という囁きが聞こえた。
―――なるほど。
ファンの憧憬を一身に受けるピアニスト。
音楽の才能に加えて、あの美貌だ。
女性にもてないはずがない。
ぼんやりと、そんなことを考えた。
「あの・・・」
ふいに声をかけられて、俺は驚いて振り返った。
きっちり硬めのスーツ姿の女性だった。
一瞬、考えてから。
先日あの廊下で見かけた女性だ、と思い出した。
たしか、清水さんって―――。
「探しておりました」
「へ?」
俺は面食らった。
―――なんだって・・・?
彼女は丁寧に頭を下げる。
「いらしてくださって、本当によかった。お待ちしておりました」
「え・・・?」
「岩城のマネージャーの清水と申します。先日はどうも、ご挨拶もせず失礼いたしました」
慇懃な口調。
声を落としているのは、周囲の耳を憚ってのことか。
「あの、清水さん・・・?」
「開演前の短い時間では、探せないのではと危惧しておりました。お会いできてよかった」
彼女は明らかに、安堵の表情を浮かべている。
何が起きているのかわからない。
探していた・・・?
待っていたって、どういうことだ。
「あの・・・?」
「不躾は承知で、声をおかけしました」
混乱した俺を見て、彼女が静かに言った。
「岩城から、コンサートの後で楽屋にご案内するようにことづかっております。恐縮ですが、少しお時間をいただけますでしょうか」
「ええっ」
大声を出しかけた俺を、清水さんは制した。
「声が」
「す、すみません!」
「・・・他のお客さまに聞こえると大変ですから」
俺は、無言で彼女を見つめた。
冗談を言ってるようには見えない。
―――でも、なんで。
俺が今日ここに来ることを、彼が知っていたわけがない。
自分でも、やっと決心して足を運んだのだから。
俺の困惑を読み取って、清水さんが笑顔を見せた。
そうすると彼女の印象がずいぶん柔らかくなって、俺はほっとした。
「岩城が、こう申しておりました」
「え・・・」
「・・・名前は知らない。どこで何をしている人かもわからない。自分を知らないようだったから、クラシック音楽もたぶん聴かない」
「はあ・・・」
「でも、もしかしたら、今日のコンサートに来てくれるかもしれない、って」
雲をつかむような話ですよね、と彼女は笑った。
子供のわがままに苦笑する母親のように見えた。
俺はただ、息を呑んだ。
―――信じられない。
こんなことがあるんだろうか。
岩城さんが、俺を覚えていた。
なぜか、俺に会いたがってくれている。
といってもお互い名乗ってもいないし、連絡手段もない。
それで唯一、俺の顔を見覚えているマネージャーに、観客席を探させたのか。
「まさか・・・」
俺があの日以来ずっと、岩城さんの面影に囚われていたように。
彼もまた、俺を思い返していたというのか。
ほんの数分の遭遇。
そこから何か、感じるものがあったというのか。
―――俺と、同じように・・・?
何をどう言っていいのかわからず、俺はただ突っ立っていた。
彼女の顔を、凝視しながら。
「正直、私も心もとなかったのですが、お会いしてすぐにわかりました」
見つけられてよかった、と清水さんが再度言う。
俺は彼女の記憶力に、驚嘆するしかなかった。
同時に、心から感謝した。
「それで、あの、如何でしょうか」
「あ、すみません!」
俺はペコリと頭を下げた。
「ぜひ、ご一緒させてください」
「こちらこそ、ありがとうございます」
それで―――と。
なにか問いたげに、彼女は上目づかいに俺を見た。
「宜しければ・・・」
「あ、そうか! 失礼しました」
俺は苦笑した。
「俺、香藤洋二って言います。小学校の教師をやってます」
「香藤さん、ですか」
「はい」
少し考えてから、俺はつけ加えた。
「・・・岩城さんにお伝えください。今日のコンサート、楽しみにしていますって」
「ええ、それはもう」
もう一度深くお辞儀をして、清水さんは去っていった。
++++++++++
煌々と灯りのついた長い廊下。
装飾ひとつない、寒々しい空間。
まるで人の気配がないのに、ざわついた雰囲気。
「どうぞ、こちらへ」
清水さんの後について歩きながら、俺はまだ衝撃にしびれたままだった。
初めて体験した、岩城京介。
正装で舞台に立つ彼の端正な美貌にため息をついた。
しなやかに鍵盤の上をすべる指にみとれた。
目が、離せなかった。
そして何より。
彼の奏でる音楽の美しさに、俺は魂を奪われた。
とうてい言葉にできないインパクト。
―――知っている曲は正直、ひとつもなかった。
だけどもの悲しいメロディも、軽快なリズムも、すべて俺の心に染み入った。
心の中の何かを、激しくかきたてた。
時が過ぎるのも忘れて、俺は陶然と、岩城さんの音楽に酔った。
「失礼します」
楽屋のドアを開けた、その途端。
むせ返る花の香りに俺はたじろいだ。
所狭しと並べられた豪華な胡蝶蘭の鉢植えや、カサブランカの花束。
ファンからのプレゼントだろう、テーブルに積み上げられたギフトボックス。
―――しまった!
手ぶらで来た自分に、今さらながらうろたえた。
俺も花くらい、買ってくるべきだったのか?
・・・でも男が男に、花束なんて・・・?
そう思ったとき。
長身のスワロウ・テイルが優雅に振り返った。
―――ああ、本物だ。
岩城さんが、そこにいた。
「あの・・・」
言葉はそこで途切れた。
本物の岩城京介。
ふわりと、軽やかな身のこなし。
さっき舞台でアンコールの拍手を浴びていたときと、まったく変わらない姿だった。
・・・ボウタイをほどいて、白い喉もとをさらしているのを除けば、
「ああ」
白皙に、かすかな微笑が浮かぶ。
「あの・・・」
どう話し始めていいのかわからず、俺は口ごもった。
「香藤さん」
つやめいたテノールが、俺の名前を奏でた。
「・・・っておっしゃるんですね」
「は、はい」
「本当に来てくださるとは思わなかった。ありがとうございます」
軽く会釈して、岩城さんが笑った。
コンサートの余韻をひきずっているのか、頬が紅潮している。
おそろしく魅力的な笑顔だった。
「いえ、あの・・・」
情けないことに、俺は完全にあがっていた。
何を言えばいいのかわからない。
「香藤さん」
後ろに控えていた清水さんが、中へどうぞ、と促す。
俺はぎくしゃくと、部屋の中に足を踏み入れた。
―――岩城さんの楽屋。
足が、震えた。
勧められて、俺はパイプ椅子に腰を下ろした。
岩城さんは立ったままだ。
「・・・コンサート、すごくよかったです。あの―――」
月並みな言葉しか出てこないのがもどかしい。
俺はそれでも、一気に続けた。
「凄かった。どの曲も凄くきれいで・・・俺、クラシックなんて全然知らないんですけど、ものすごく感動しました」
「ありがとうございます」
「本当に・・・!」
誉め言葉が、宙に浮いた。
ぎこちない沈黙。
岩城さんはじっと俺の顔を見ている。
―――見えない瞳で、じっと。
助け舟を出してくれたのは、やっぱり清水さんだった。
「岩城さん。この後どうなさいますか?」
「うん、そうだね・・・」
「ご自宅へお戻りでしたら楽屋口に車を回しておきますが、香藤さんは・・・?」
「そうだな」
岩城さんはちょっと考えて、それから俺のほうを向いた。
「香藤さん」
「は、はい!」
「差し支えなければ・・・」
ほのかな微笑が彼の頬に浮かんだ。
「ちょっと遅いけど、ご一緒に・・・夕食につきあっていただけますか」
「ええ・・・!?」
俺は椅子から、飛び上がりそうになった。
「・・・ああ、でも、息子さんが待っているのかな」
申し訳なさそうに彼が笑う。
その顔が寂しげで、俺の心臓がバクバクした。
「いえ、いや!」
俺はあわてて首を振った。
「俺・・・俺なんかでよければ」
声がみっともなくひっくり返る。
「ぜひ、ご一緒させてください。息子は一晩、実家に預けてきてるんで!」
・・・信じられない。
俺は呆然と、岩城さんを見上げていた。
まさかこの人に食事に誘われるなんて、考えもしなかった。
こうしてわざわざ会ってくれただけで、俺は充分に驚いていたのに。
―――夢じゃないのか、これ。
俺はきっと、百面相みたいな顔をしてただろう。
岩城さんにそれを見られなくてよかった。
彼はじっと俺に、俺の声のする方向に、視線を向けていたけど。
「・・・清水さん」
「はい」
「それじゃあ、今日はこれで。俺はあとで適当にタクシーを拾うから」
帰っていいよ、と彼女にねぎらいの言葉をかける。
清水さん相手だと、言葉づかいがずっとカジュアルになるらしい。
「・・・着替えてきます」
岩城さんはさらりと、俺に向けて言った。
「すぐ済みますから、申し訳ないけどここで待っていてください」
そう言って彼は微笑した。
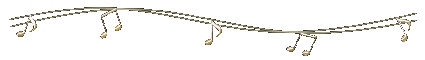
藤乃めい
23 October 2005
加筆部分、多すぎかも。
2013年09月27日、サイト引越により新URLに再掲載。