Prelude 03
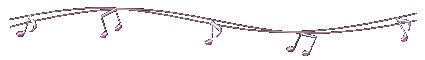
「あれ・・・」
文化センターの楽屋口。
外に出ようとして、俺は雨が降っているのに気がついた。
「さて、どうしよう」
腕組みして、俺は思わず呟いた。
『土地勘がないから、適当なレストランをみつくろってほしい』
そう、岩城さんに頼まれたのはいいが。
「困ったぞ・・・」
彼のリクエストは難題だった。
―――どこでもいい、って言われても。
それを真に受けるほど、俺もバカじゃない。
何しろ相手は超売れっ子のピアニストだ。
そうでなくとも水もしたたる美形で、とにかく目立つ。
―――どこでもいいわけ、ないじゃないか。
「うーん」
おまけに、あいにくの雨と来ている。
目の見えない岩城さんに、知らない街をあてもなくうろうろ歩かせたくはない。
この街は俺の地元だけど、最近あんまり飲み歩いていない。
ふだん教師仲間と行くチェーンの居酒屋、ってわけにもいかないだろう。
「独身の頃なら・・・」
ちょっとこじゃれた店にも、詳しかったんだけど。
岩城さんにふさわしい場所。
さあ、どうする?
俺は脳みそをフル回転させた。
どこか、女を初めてデートに誘うときの感覚と似ていた。
高揚感と、かすかな緊張感。
どんな店に連れて行くかで、今後が決まる。
―――無難なところ、となると。
湾岸沿いの高級ホテルぐらいしか思いつかなかった。
ちょっと洒落たリゾートホテル群。
そういえば、あの辺はずいぶん行ってない。
亡き妻にプロポーズしたとき以来、足は遠ざかっている。
だけどホテルのレストランなら、大きく外れることもないだろう。
「・・・香藤さん?」
後ろから岩城さんの声がした。
ひと足先に出口に向かったはずの俺がまだそこにいたので、意外に思ったのだろう。
「すみません、岩城さん」
俺は振り返って頭を下げた。
「どこに行こうか、ちょっと迷っていて―――」
「雨ですね」
スチール扉の外を見上げるように、岩城さんが呟いた。
ぱたぱたと、雨だれの音がする。
「あの、岩城さん。ここで待っててください」
「え・・・」
「俺、駐車場のけっこう奥のほうに停めちゃったんです。ここまで車、回して来ますから」
岩城さんは、首を振った。
「俺も行きますよ」
「でも」
「たいした雨じゃない。大丈夫ですから」
ちょっとためらってから、俺は頷いた。
「・・・えと、じゃあ・・・」
失礼します、と断ってから。
俺はそっと、岩城さんの肘あたりを引き寄せた。
雨の中、俺たちはゆっくり歩いた。
つかんだ肘にかけた指の力加減で、歩く方向を知らせる。
岩城さんが、くすりと笑った。
「上手ですね」
誘導するのが、という意味だろう。
俺はあいまいに頷くのが精一杯だった。
「・・・ここです」
俺の中古シルビア。
思い入れのある愛車だけど、お世辞にも見栄えはよくない。
―――こんなポンコツにこの人、乗せていいんだろうか。
今さら、そう思っても遅い。
不謹慎にも、俺は岩城さんの目が見えなくてよかった、と思ってしまった。
「片づいてないけど、どうぞ」
「ありがとう」
助手席のリクライニングを調整して、俺はそこに彼を座らせた。
「あ、頭!」
ぶつけないように、慌てて彼の頭頂部に手を添える。
「ありがとう」
小さな微笑。
長身を屈める姿すら、どこか優雅に見えた。
「ここ・・・」
シートベルトの位置を、岩城さんの手を誘導して知らせる。
―――絶対に、絶対にわざとじゃないんだけど。
ボディタッチが多くて変に思われないだろうか、と少し気になった。
目の見えない人をエスコートするとなると、慣れていないせいか、言葉よりも先に身体が動く。
「あ、そうだ」
それから俺は、後部座席のドアを開けた。
無造作にタオルを引っ張り出し、岩城さんの濡れた髪と肩をざっと拭く。
「濡れちゃいましたね」
「ああ、いえ」
後は自分でやる、という意思表示なのだろう。
岩城さんがタオルを掴んだので、俺は運転席にまわった。
「・・・用意がいいですね」
「ああ、それは」
俺は苦笑した。
「小さな子供がいますから。タオルやティッシュ、薬箱やごみ袋・・・いろいろ積んでるんですよ」
ちらりと俺に視線を向けて、岩城さんが頷く。
それを合図に、ゆっくりと車のエンジンをかけた。
―――何気ないふりをしたけど。
かすかに指先が痺れていた。
岩城さんの身体に、髪に触れた手。
緊張で、俺は少し強張っていた。
狭い車内。
岩城さんから香るほのかな匂い。
その甘さに、うろたえてもいた。
・・・おかしいだろう、これ。
トワレとか、整髪料とか、そんなものだろうけど。
さっきまで気づかなかった。
彼の存在。
彼の体温。
あの岩城京介が、俺の車の中にいる。
彼の吐息がすぐ隣に聞こえる。
俺はこっそり、深呼吸した。
++++++++++
結局、俺たちは、贅沢なつくりのバー・ラウンジに落ち着いた。
外資系リゾートホテルの高層階。
大きな窓の外には、きらめく東京湾の夜景。
―――さすが、というべきか。
岩城さんをひと目見るなり、スタッフの目つきが変わった。
どこからともなく蝶ネクタイをした年配の男が現れ、うやうやしく挨拶をする。
「目立たない席、ありますか」
そう尋ねた俺に、ちらりと目配せをする。
―――うん?
思わせぶりな視線を、どう受け止めればいいのかわからない。
地に足がついてない感覚。
「どうぞ」
男は笑顔で、奥まったアルコーヴ席に案内してくれた。
半個室、とでもいうのか。
アンティーク調の衝立と背の高い観葉植物の鉢が、フロアの客の視線を遮るようにさりげなく配置されている。
これがVIP待遇、ってやつか。
わずかに聞こえる物憂い音楽。
親密な雰囲気を醸し出すほの暗い照明。
ほかのテーブルのざわめきが、遠く感じられる。
夜景が見えないことに、俺はむしろほっとした。
「メニューをどうぞ」
岩城さんの前にもメニューは置かれたが、彼はそれに触れようとしなかった。
俺が読みあげたほうがいいんだろうか・・・?
それとも、好みを聞くべきか。
迷っていると、岩城さんが小さく笑った。
「何でもいいです。軽いものを、適当に」
何もかも、お見通しなのか。
俺は苦笑して、ウェイターに注文を告げた。
「お飲み物は、どうなさいますか」
ワインリストは、俺の手の中。
―――どうしよう。
ワインのことなんか、何も知らない。
戸惑っていると、再び岩城さんが助け舟を出してくれた。
ソムリエを呼び、何か小声で相談している。
「じゃあ、それを」
「承知しました」
短い会話が交わされるのを、俺はぼうっと見ていた。
―――主に、岩城さんの紅い唇を。
どうしてそれを、エロティックだと思うんだろう。
俺はどうかしている。
「香藤さん」
ふいに名前を呼ばれて、俺はぎくりとした。
目の前には、紅い酒の入った丸いグラス。
向かいに座った岩城さんが、ワイングラスを掲げている。
「乾杯を」
心なしか、嬉しそうだ。
・・・目の前にこの人がいるのが、いまだに信じられない。
「乾杯」
俺もならって、小さくグラスを傾けた。
「あ・・・」
名前も知らないフランスの酒。
口に含むと、馥郁とした香りがした。
思ったよりも軽い、爽やかな飲み心地。
「お口に合いますか」
グラスのステムをきれいな指で掲げながら、岩城さんが聞く。
「はい、美味しいです」
「よかった」
ふわりと笑う。
そうすると、目尻にわずかに皺が寄った。
どういう理屈なのか、それに気づいてまたどきどきする。
この人は本当に心臓に悪い。
「フレッシュな味でしょう。まだ若いけど、とても美味しい」
そう言って、岩城さんはグラスに口をつけた。
―――白い、喉元。
半ば瞳を閉じた、うっとりした表情。
目が離せない。
意識がどうしても、引き寄せられる。
今や彼の仕草すべてに、俺は色香を感じてしまっていた。
―――まずいだろ、本格的に。
俺は無理やり、意識を自分の手元に戻した。
「岩城さん・・・あの」
「なんです?」
「お願いがあります」
さっきから思っていたこと。
だしぬけに、俺はそれを口に出していた。
「教師やってて恥ずかしいけど、俺、敬語っていうか・・・真面目な言葉づかい、苦手なんです」
岩城さんが、目をぱちくりと見開く。
いきなり俺が何を言い出すのか、想像もつかないって顔。
「はい・・・」
「もともと堅苦しいのがダメで、香藤さんなんて呼ばれるガラじゃないし、俺のほうが岩城さんより年下ですし。だから、あの―――」
「・・・」
「その・・・できたらこの先、敬語はなしにしてもらえませんか」
思い切って、頼んだつもりだった。
とろりとした美酒に酔っていたせいかもしれない。
岩城さんは眼を丸くして、俺を見返している。
俺の顔をじっと探っている、ように見えた。
―――早まったかな。
途端に俺は、居心地の悪さに襲われた。
唐突すぎて、失礼だったか・・・?
いくらなんでも、気が急きすぎたかもしれない。
心配になったとき、ふと。
「・・・おもしろいな、おまえ」
岩城さんが、おかしそうに笑い出した。
―――え・・・!?
「あの・・・」
俺は、自分の言ったことを反芻する。
そして、その意味に気づいて慌てた。
・・・何を言ってるんだ、俺!
岩城さんは、くつくつとまだ笑っている。
「す、すみません!!」
一気に頭に血が上る。
なんて考えなしなんだろう、俺。
言っちゃってから、気づくなんて。
―――岩城さんと俺、丸っきり他人じゃないか。
お互いのことなんか、何も知らない。
芸能人とファン、ですらない。
―――それなのに、俺は・・・!?
敬語はやめてほしいって、何様なんだよ?
まるで今後も、この人とのつきあいが続くみたいに。
まるで・・・そう、対等の友達づきあいみたいに。
「それは―――」
甘いテノールの響き。
岩城さんも、同じことを考えたんだろう。
にやり、と。
不敵に笑ったように見えたのは、気のせいだろうか。
「・・・また食事につきあってくれる、という意味か?」
いたずらっ子のような目をして、そう言った。
黒い瞳が妖しくきらめいている。
さっきまでと違う低い声―――。
これは、テノールじゃない。
もっともっと挑発的な、バリトンに近い美声だ。
「あ、あの・・・!」
俺はおもむろにうろたえた。
そこにいるのは、先ほどまでとは別人に見えた。
鮮やかに変貌した岩城京介。
目に見えない毒を含んだ、つやめく夜の華。
俺は、息を呑んだ。
「岩城さん・・・」
「・・・年下だと言ったな」
ぞくり、とした。
「はい」
「香藤はいくつなんだ」
いきなりの呼び捨て。
心臓を鷲づかみにされたようで、鼓動が跳ねた。
―――こんなの反則だよ!
口調を変えた岩城さんは、今までよりもずっとセクシーだった。
なんというか、男の色気、というやつだ。
俺は思わず身震いした。
「に、29です」
「おまえは敬語のままなのか」
悠然と、また笑う。
「苦手なんだろう?」
ワイン片手に、じっと俺に視線を向けながら。
実際、岩城さんはよく笑った。
―――ぜんぜん、違うじゃないか!
話が違う、と俺は脳内でぐるぐる考えた。
こんなはずじゃなかった。
インターネットで調べた、岩城京介というピアニスト。
そこには常に、『薄幸の貴公子』のイメージがつきまとっていた。
失明したことから来る、当然の連想。
あるいは、そういう売り方をされている、ということなのかもしれない。
―――冗談じゃない・・・!
俺はそっと、首を振った。
こんなはずじゃなかった。
こんなに魅力的な笑みを零す人だなんて、想像もしなかった。
悲運の天才とか何とか、俺は知らない。
ただ、俺の目の前で笑い、飲み、食べている岩城さんは、マスコミの吹聴するイメージとは丸っきり異なっていた。
まったくの別人だと言っていい。
今、そこにいる生身の岩城京介。
リアルの彼は、もっともっと、ずっと彩り豊かで逞しい。
ずっと艶めかしくて、熱い。
盲目だからと憐れむなんて、とんでもない侮辱だ。
彼に同情すべき点なんか、どこにも見当たらない。
「どうした?」
プロの音楽家としての自負。
大人の男としての自信。
そういうものを十分に覗かせた、成熟したひとりの男に見えた。
―――そう、非常に魅力的な。
しかも彼は、それを自分自身よくわかっている。
「香藤?」
「岩城さん・・・」
俺の動揺を探りあてる眼差し。
見えないはずなのに、誰よりも鋭い。
かなわない、と俺は思った。
そこには幾ばくか、悔しさも混じっていた。
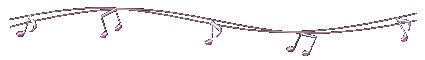
藤乃めい
23 October 2005
2013年10月11日、サイト引越により新URLに再掲載。初稿にかなり加筆・修正を加えていますので、リニューアルに近いかも。
なお、『ゆすらうめ異聞』は今日、まさかの(笑)開設8周年を迎えました。いろいろありましたが、ここまで続いたのはひとえに応援してくださる『春抱き』ファンの皆様のお陰です。本当にありがとうございます。