Prelude 04
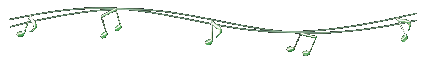
あっという間の、二時間あまり。
俺は夢中で、岩城さんの一挙手一投足を追っていた。
料理もうまい、酒もうまい。
そのどれよりも、岩城さんは鮮烈だった。
彼というとびっきりの美酒に酔っていた―――というところか。
俺はふわふわとした、非現実的な世界にいた。
食後のドルチェの代わりに、とろりと甘い食後酒。
名前はもう、思い出せない。
最後にエスプレッソ・マキアートを頼んだところで、俺はついと口を開いた。
「ねえ、岩城さん」
「ん?」
「どうして俺を、探してくれたの?」
「さあ」
黒曜石の瞳が、鈍く光って俺をみつめた。
「・・・どうして、かな」
ほろよい加減の岩城さん。
白い項がほのかに朱に染まっていた。
蠱惑的。
そんな形容詞が、脳裏をかすめた。
「なんで俺のこと、覚えてたのかなって・・・」
「さあな」
さらさらと黒髪が揺れた。
到底、まじめに答える気はなさそうだった。
「香藤はどうして、コンサートに来る気になったんだ?」
逆に、気まぐれみたいに俺に聞いてくる。
「まさか本当に見つかるとは、俺も思っていなかった」
「う・・・ん」
それは、核心をついた問いだった。
どうしよう。
言わないほうがいいのかもしれない。
少しワインを飲みすぎたせいかもしれない。
―――でも、俺は。
誤魔化したくはなかった。
いや、ちょっと違うかもしれない。
話してしまいたかった。
岩城さんに本当のことを知ってもらいたい、という誘惑に勝てなかった。
「・・・会いたかったんだよ・・・」
こぼれ落ちた言葉。
言っちゃだめだ、と理性が危険信号を発していたけど。
聞いて欲しい言葉があふれて、とまらなかった。
―――俺はどれだけ、飢えていたんだろう。
大人同士の駆け引きめいた会話に。
子供のことをいっさい聞かれない開放感に。
独り言みたいに、俺は呟いた。
「なんでかな。自分でもよくわからない」
視界がくらり、と揺れた。
ああ、俺はずいぶん酔ってる。
「でも、あの時からずっと、もう一度会いたかった」
「香藤・・・」
「・・・会って、ゆっくり話をしたいと思ってたんだ・・・」
「・・・」
俺はじっと、岩城さんを見つめた。
彼のきれいな瞳以外、何も見ていたくなかった。
熱い吐息が、俺のすぐ近くで聞こえたような気がした。
「え・・・」
近すぎる、ような気がした。
どうしてだろう。
彼の鼓動が聞こえるような気すらした。
「・・・!」
岩城さんが素早く、俺の手を引き寄せる。
何が起きているのか、理解するひまもなかった。
ひんやりと冷たい指先。
岩城さんの指先が、俺の手に絡まった。
電流みたいな刺激が体内を走る。
「俺に―――会いたかったのか」
彼がまるで厳かな呪文のように囁いた。
「岩城さん・・・」
頷いた俺の声は、みっともなく掠れていた。
―――ああ、絡めとられる。
なぜかそう思った。
実際、俺は少し震えていたと思う。
「俺もだ」
たったひと言。
微笑を浮かべてさらりと、岩城さんが言った。
「え―――」
岩城さんの紅い唇。
それがやけに間近に感じられた。
―――なにが起きているんだ・・・?
夢魔に魅入られたような恍惚感。
岩城さんがすっと、ほんのわずか上半身を屈める。
彼の唇が、引き寄せた俺の手の甲に触れた。
ほんの一瞬、かすめるようなキス。
俺の身体に再び、電流が走った。
「え・・・!?」
視線がかちり、と交錯した気がする。
「・・・あ・・・」
ろくに瞬きする間もなく、彼の手が離れていく。
そのまま岩城さんは、すらりと立ち上がった。
すぐに駆け寄ってきたフロアマネージャーに、ひと言ふた言。
俺は呆然としたまま、動けなかった。
―――なんだ、今の。
今、岩城さんは何をした・・・!?
「行こう」
何かを受け取った岩城さんが、俺の肩をつついた。
「・・・香藤?」
「あ、うん」
どこへ、と聞いてはいけない気がした。
++++++++++
鼓動が、やけにうるさい。
ピクチャーウィンドウの向こうには、見渡す限りの湾岸の夜景。
―――これは、夢だよな。
豪奢なインテリア。
あいまいな闇をつくる灯り。
ふかふかのソファ。
そこに身体を沈めて、俺はほうっと息をついた。
頭がガンガンする。
ワインを飲みすぎたせいだろうか。
―――どうして、こんなことになったのか。
ぼんやりと、あたりを見渡した。
俺は、さっきまでいたバー・ラウンジのすぐ下のフロアにいた。
客室階の最上階らしい。
広々としたスイート。
・・・何が起きているんだろう・・・?
わかっている。
でも、わからない。
わかってしまうのが怖い。
部屋をとった、と岩城さんは言った。
飲みすぎたようだから、酔いを醒ましてから帰ればいい、とも。
いかにも物慣れた、さりげない誘い方だった。
―――それって、つまり。
そういうこと、なんだろうか。
俺は自問自答する。
そういうことだと思っていいんだろうか。
男女の間であれば、それが意味するところは明らかだ。
だけど俺も岩城さんも、男じゃないか。
「男・・・だけど・・・」
俺は、広い応接エリアの向こうのドアを見つめた。
あの向こうは、寝室だ。
・・・寝室って・・・!
やっぱり、そういうことなんだろうか。
俺はそれと知って、ここにいるのか。
ゆらりと、自意識がぐらついた。
―――馬鹿、何考えてるんだ。
きっと酔っ払って、おかしくなってるんだ。
そう思ったとき。
寝室のドアが開いて、岩城さんが現れた。
携帯電話をカチリと閉じて、俺のいるほうに戻ってくる。
危なげのない歩き方。
俺はひそかに舌を巻いた。
見えないはずなのに、という気持ちと。
あんなに飲んだのに、という思いがせめぎ合う。
―――敵わない。
悔しいけど、俺はこの人に翻弄されっぱなしだ。
「待たせたな」
そう言って、どさりと俺の向かいに腰を下ろした。
「岩城さん・・・」
「そんな情けない声を出すな」
岩城さんが苦笑した。
「取って食いはしないから、安心しろ」
冗談とも本気ともつかない台詞。
俺の表情をうかがうように、黒い瞳が俺を見つめる。
―――俺は信じない。
唐突にそう思った。
この目が、まったく俺を映さないなんて信じない。
俺はぼんやりと、岩城さんを見返した。
彼のきれいな顔を。
うまく、言葉が出てこない。
「・・・俺が悪かった」
しばらくして、岩城さんが肩をすくめた。
その声はとても楽しそうで、謝ってるようには聞こえないけど。
「え・・・?」
「悪ふざけがすぎたようだな」
「悪ふざけ・・・?」
「頼むから、そんなに緊張しないでくれ」
「そんなにって・・・」
そのまま沈黙が落ちる。
お互いの視線が絡まる・・・気がした。
彼は大げさにため息をつき、再び立ち上がる。
すたすたと、岩城さんは壁際のグランドピアノに近づいた。
―――そう、グランドピアノ。
あまりにも非現実的すぎる、それの存在。
俺はあらためて、室内を見回した。
俺の30年近い人生で、グランドピアノの置いてあるホテルの部屋なんて、初めて見た。
もしかして岩城さんは、この部屋を知ってたのか。
ふと思う。
ここに泊まったことがあるんだろうか。
―――誰と・・・?
思わぬ問いが浮かび、俺はあわてて首を振った。
バカじゃないのか。
俺はいったい何を想像してるんだ・・・?
「岩城さん・・・」
俺はぼうっと、岩城さんの後ろ姿を追った。
―――月夜とピアノと、岩城さん。
窓から見える夜景に照らし出されたシルエット。
夢みたいに非現実的だった。
彼は優美な手つきでピアノの鍵盤蓋を開ける。
鍵盤をそっとなぞってから、小さく頷く。
手探りで椅子を引き出し、手品のようにその高さを調整する。
そしてピンと背を伸ばして、そこに座る。
ふ、と空気が張りつめた。
―――よどみのない、慣れた仕草。
その一連の所作を、きれいだ、と思った。
岩城さんは、生きる芸術品のようだ。
彼の生み出す音楽だけじゃない。
その姿も動作も、何もかもが感動的に美しい。
「岩城さん、きれいだ・・・」
思わず、そう呟いていた。
それが聞こえたのか、聞こえなかったのか。
するりと俺を振り返って、彼は静かに微笑んだ。
「車だってわかってるのに、ずいぶん飲ませてしまったな」
やさしい声で、小さくそう言った。
もしかして、謝ってるつもり・・・なのか。
「飲んだのは、俺だよ・・・」
うっとりと、俺はそう返していた。
誰に飲まされたわけでもない。
岩城さんに酔って、タガが外れた。
いつもなら、こんな簡単に酔わないのに。
「あの・・・」
「なんだ?」
「それ、開けないの・・・?」
ぼんやりと、俺は腕を伸ばして聞いた。
なんでそんなことが気になったのか、自分でもわからない。
「・・・なんだ?」
岩城さんは首をちょっと傾げて問い返した。
「その、ピアノのさ、おっきな蓋」
撥ね上げると優美な曲線を見せる、漆黒の翼のような。
「コンサートのときは、開いてるでしょ・・・?」
「ああ」
岩城さんがやさしく微笑んだ。
譜面台の向こうを指さしながら、低く笑う。
「これか。これは、屋根と言うんだ」
「屋根・・・?」
「ああ。どのくらい開けるかで、音量を調節する」
「へえ・・・」
「ただでさえ、グランドピアノは音が大きい。真夜中、屋根を開けて弾いたら苦情が来るだろうな」
さらりとそう言って、俺を見つめた。
そういうものなのか。
俺は感心して、何度も頷いた。
「凄いなあ、岩城さん」
「・・・まあ、いい」
子供をなだめるように、岩城さんが微笑した。
「俺が子守唄を弾いてやるから、しばらくそこで寝てろ」
「うん・・・?」
「―――酔いがさめたら、勝手に帰ってくれていい」
それだけ言うと、彼はピアノを弾き始めた。
夢みたいに甘い旋律。
ほろほろとこぼれ落ちる音が美しい、ゆったりしたメロディー。
ああ、何だっけ。
どこかで聞いたことがある、と思った。
子供のころ・・・?
俺はぼんやりと、追憶を辿った。
甘いなつかしい音が部屋に満ちる。
岩城さんの奏でるやさしい福音。
・・・この人の澄んだ音は、俺の心を揺さぶる。
「きれいな曲だね・・・」
ため息がこぼれる。
俺はしばらくじっと、目を閉じて聞き惚れた。
それが何曲目だったのか、わからない。
睡魔に襲われて、俺は少し寝ていたかもしれない。
多分、ほんの一瞬のことだけど。
やがて再び、俺は意識を取り戻した。
身体がぼんやりと熱い。
酔いのまわった―――酔いが抜ける直前の―――感覚。
ピアノの旋律はまだ聞こえている。
「本当に、ホントなんだ・・・」
岩城さんがそこにいる。
夢かもしれない。
夢にしては、都合がよすぎるくらい。
あの岩城京介が、俺だけのためにピアノを弾いてくれてる。
そんな夢みたいな現実に、俺は酔っていた。
それでうたた寝なんて、贅沢すぎると思う。
「・・・信じらんない」
それから、ふと。
俺は鍵盤の上に踊る岩城さんの指を、見たくなった。
―――あの指。
さっき俺に触れた、あの冷たい指。
夢・・・じゃないはずだ。
そろそろと、俺はグランドピアノに近づいた。
「あ・・・」
俺の気配に気づいたのだろう。
岩城さんの背中が、わずかに強張るのがわかった。
・・・そうか。
大胆に振舞っているけど、この人も緊張しているんだ。
―――そうだよなあ。
見知らぬ男と、ホテルの部屋で二人きり。
緊張しないほうがおかしいくらいだ。
そう思ったとたん、肩の力が抜けた。
「・・・それ、何ていう曲?」
驚かせないように、そっと。
俺は後ろから声をかけた。
音符がきらめくような、はかない、美しい音楽。
「・・・ノクターン。夜の想い、って意味だ」
指を止めずに、岩城さんが小さく答えた。
「きれいだね」
ノクターン。
夜想曲、だったっけ。
俺の視線は、岩城さんの首筋に吸い寄せられた。
―――こんなところまで綺麗だ。
繊細な磁器のようななめらかな肌。
無防備な白いうなじが、俺を誘っている。
そう思った。
そう思ったことに、俺はあらためて衝撃を受けた。
・・・これは、そういう感情なのか?
俺は、そういう衝動を持っていたのか。
―――そんな、馬鹿な。
できるものなら否定したい。
でも俺は、岩城さんの真珠の肌から目が離せなかった。
いや、今だけじゃない。
この数時間ずっと、いや、もっと前から。
俺は彼にどうしようもなく惹かれているじゃないか。
ノクターンはまだ続いていた。
やさしい、切ないメロディ。
―――駄目だ・・・!
誘惑に勝てず、俺はふるえる指を伸ばした。
岩城さんのうなじに、そっと触れる。
「あ・・・っ」
息を呑んで、岩城さんは全身をこわばらせた。
音がひとつ、ぴょんと跳ねた。
不協和音。
リズムが乱れる。
それでも彼は、ピアノを弾く手を休めなかった。
―――逃げない、のか。
俺はごくりと、喉を鳴らした。
「いいの・・・?」
止めろと、岩城さんは言わなかった。
制止されないのを知って、俺はそこに手のひらを這わせた。
心臓がばくばくする。
じわりと、掌に汗がにじんだ。
吸いつくような淡い肌に、俺の下半身が熱くなった。
「・・・んっ・・・」
あえかな吐息。
それを俺は、どうしようもなく色っぽいと思った。
そそる、なんてもんじゃない。
・・・男に性欲を感じるなんて、信じられない。
目眩がしそうだった。
―――ちょっと待て、香藤洋二。
俺は必死で、呼吸を整えた。
いいか、この人は年上の男だ。
だいたい俺は、この人のことを何も知らないじゃないか。
どうしてここに一緒にいるのかも、わかってないだろう?
―――だけど、だけど!!
そう・・・俺はわかっていた。
本当は、分かっていたんだ。
あの日からずっと、もやもやした想いを抱えていた。
最初にこの人を見たときから、その美貌に心を奪われた。
水が高いところから低いところに流れるように。
当然のように、まるで最初からそうなる運命だったように。
気づいたら、俺はこの人に魅かれていた。
今ならわかる。
俺は、この人に抗えない。
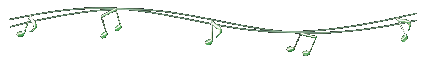
藤乃めい
23 October 2005
2013年10月17日、サイト引越により新URLに再掲載。初稿にかなり加筆・修正を加えていますので、リニューアルに近いかも。