第三章 (1)
・・・のどかな情景だった。
おとぎ話のような、テラコッタ色の煉瓦の古城。
尖塔の天辺だけが、鈍い鉄色に光っている。
はめ殺しの窓からは、ぐるりと四方を取り囲む湖が見えた。
紺碧、いやターコイズの水が深そうだ。
はるか彼方に、ちいさな釣り船がさざ波にゆらゆら揺れている。
白鳥がたわむれ、ときおり魚が跳ねた。
その向こうには、しんと静まり返る緑の森。
鳥の鳴き声と空を渡る風のざわめき以外、何も聞こえない―――。
「静かだな・・・」
俺はいつの間にか、独り言を口にしていたらしかった。
「何を、悠長に仰ってるんですか」
アドリアーナが、俺の背中に声をかけた。
「こんな状況なのに。お姫さまは冷静すぎますよ」
「慌てたところで、何が変わるだけでもないだろう?」
呆れた口調の侍女長に、俺は苦笑で応えた。
俺たちのガレー船『フェラーラの薔薇』を襲撃したのは、やはり『ソレントの堕天使』だった。
地中海を荒らしまわる、泣く子も黙る海賊だという。
数年前に忽然と現れた謎の武装集団で、誰も正体を突き止められないのだ、と。
思ったとおり、というべきか。
香藤―――香藤の姿をしたあの若い男が、その首領だった。
手下のひとりが、あいつをクラウディオさまと呼んでいた。
「クラウディオねえ・・・柄じゃないな」
俺はその耳慣れない名前を、そっと舌先で転がしてみた。
イタリア語の、甘い響き。
「悪くは、ないが・・・」
背後で、アドリアーナが深いため息をついた。
船上で捕らえられた俺は、アドリアーナと共に海賊の根城に連れて来られた。
あてがわれた部屋は立派だったが、高くそびえる塔の上。
もちろん、外から施錠されていて、自由に動き回ることなど許されていない。
幽閉されたも同然だった。
香藤は・・・俺がここに来た日以来、一度も姿を見せていなかった。
―――自由を奪われたことよりも。
そうやって俺を拘束した香藤が、それっきり俺を放っていることが、信じられなかった。
幸い、どこぞのハーレムに売り飛ばされる気配こそなかったが。
香藤が俺に興味を示さないという事実が、俺を打ちのめしていた。
どんなことがあっても、お互いの手を離すことなどないと思っていた。
たとえ記憶を失っても、あるいは命が果ててすら。
それでも生まれ変わって添い遂げると、誓ったのに。
「香藤・・・」
おまえは本当に、俺を忘れてしまったのだろうか・・・?
その日は朝から、城内が騒がしかった。
尖塔の最上階に閉じ込められていても、慌ただしい気配は感じられた。
「何か、大きな行事でもあるのでしょうか・・・」
窓の下の豆粒のような人の往来を見ながら、アドリアーナが首を傾げる。
「さあな」
俺は曖昧に返事をした。
―――俺には関係のないことだ。
逃げ出す算段をしてもよかったのだが、何しろ、香藤の姿が見えない。
あいつを置いて、この場を離れるわけにもいかなないだろう。
唐突に、俺の部屋のドアが開いた。
細身の男が、膝をついて丁寧に会釈した。
これは・・・金子さんだ。
「失礼いたします。クラウディオさまがお呼びです、エレナ姫」
俺は黙って、目を瞠った。
香藤が―――俺を呼んでいるのなら。
金子さんは、それ以上何も説明せず、くるりと踵を返した。
ついて来い、ということだろう。
俺が腰を上げると、アドリアーナが腕を引いた。
「いけません、お姫さま」
戸惑った目で、俺を見上げる。
もちろん、囚われの身の俺に自由はない。
この城の主が来いというのなら、それに従うしかないのだが。
アドリアーナはとうに、俺が香藤に執着しているのに気づいているのだろう。
大きな瞳が、不安に揺れていた。
俺はその手をそっと退けた。
「心配しなくていい」
彼女をねぎらうように微笑して、俺は部屋を出た。
案内された部屋は、贅沢なつくりだが殺風景だった。
ふだん、あまり使われてないのかもしれない。
「こちらへ」
俺の背後で、重いマホガニーのドアが閉められた。
「ようこそ、エレナ姫」
部屋の真ん中の大きなベッドに、香藤が―――いや、海賊の首領クラウディオが腰かけていた。
アラブの民族衣装のような服装に、ずっしり重たげなアクセサリー。
派手で奇抜なデザインが似合ってしまうあたりがいかにも香藤らしくて、俺はくすりと笑った。
男の眉間に、不審げなしわが寄る。
「・・・なんだ?」
手招きされて、俺は黙って香藤に近づいた。
きれいな薄茶色の瞳を、俺は食い入るように見つめた。
俺がわからない香藤。
俺を求めない香藤。
いっそ、人違いであってくれれば―――。
そう願ってはみたものの、俺にはわかっていた。
これは、まちがいなく、香藤だ。
俺の目が、心が、肌が、これは香藤だと告げていた。
「待たせたな・・・今日久しぶりに、城に戻ってきたところだ」
ささやいた香藤が、俺の腕をぐいと引いて、ベッドに横倒しにした。
香藤ではない香藤が、俺にのしかかる。
「そんな目をするな。・・・それとも、誘っているのか」
性急な展開に俺は瞠目したが、抵抗はしなかった。
「かと・・・」
俺の声に、香藤が低く笑った。
ひんやりとした指が、俺の頬を撫でる。
「誰の名前を呼んでいるかは知らないが・・・気の毒だったな。助けは来ないぞ」
ぞっとするような甘い声だった。
香藤の指が俺の首筋をたどり、ドレスのリボンにかかる。
俺が抵抗しないのが意外なのか―――ひょいと片眉をあげて、香藤は俺の顔を覗き込んだ。
絶望的な気分で、俺は香藤を見上げた。
香藤ではないが、香藤なのだ。
俺の肌が、香藤の指に無条件に反応していた。
「ん・・・」
香藤の吐息が、首筋にかかった。
キスを求めて、俺は思わず視線を下へやった。
コルセットの紐を、香藤は器用に解いていく。
その手馴れた仕草に、俺の心がツキンと痛んだ。
パサリと、胸がはだけられた。
同時に、香藤の手がスカートの下から忍び込み、俺の股間にたどり着く。
俺は思わず、目を閉じた。
「!!」
その瞬間、香藤の指が弾かれたように突然、硬直した。
「・・・?」
「は・・・っ!!」
香藤はいきなり俺を突き放し、ベッドから二、三歩飛びのいた。
その瞳が、驚愕に見開かれていた。
「かと・・・?」
何が起きたのかわからず、俺は半裸のまま、呆然と香藤を見上げた。
香藤の表情が、やがて嘲笑を帯びたものに変化する。
「まさか・・・世に名高い『フェラーラの薔薇』が、男だったとはな・・・!」
乾いた声だった。
「よくも今まで隠し通せたものだ・・・! 女のなりをするのが、よほどお得意と見える」
俺は、耳を塞ぎたくなった。
「シチリア公は、このことを知っているのか」
香藤が俺を蔑む言葉など、一生聞くことはないと思っていたのに。
「いや・・・シチリア公には、こういう倒錯趣味があったのか・・・?」
容赦ない言葉が、俺の心に突き刺さる。
「・・・ちがう!」
俺は思わず、そう叫んでいた。
「違う、ちがう!」
香藤が片眉をひょいと跳ね上げる。
「何が、どう、違うんだ?」
からかうような低い声。
光る薄茶色の瞳を見ながら、俺は絶句した。
―――俺に女装趣味など断じてないが。
自分をゲイだと思ったこともないが。
そもそも何故ここにいるのかすら、わからないのだが。
それでも、おまえと俺は、夫婦なのだと。
身も心もすべてを与え合い、許しあい、生涯をともに過ごすと誓った仲なのだと。
どうして、この目の前の男に言えるだろう?
どう言ったら、わかってもらえるのだろう。
「香藤・・・」
ため息とともに、思わず俺はそう呟いていた。
それ以外の言葉を、俺は持ち合わせていなかったから。
「・・・なるほど」
香藤―――いや、クラウディオはそう言って、片頬で微笑した。
「それがおまえの情夫の名前、というわけか」
―――おまえの名前だ、馬鹿野郎。
俺は覚えず、心のうちで悪態をついた。
そうでもしなければ、やりきれなかった。
クラウディオは、俺から何歩か離れた位置のまま、ドアの方角に顎をしゃくった。
「行け」
女ではないエレナ姫に、用はないということか。
屈辱を感じる心をねじ伏せて、俺はのろのろとベッドから起き上がった。
香藤の拒絶。
絶望感が、ひしひしとこみ上げる。
それを受け止めるには、しばらく一人きりの時間が必要だった。
―――少なくても、こいつに涙を見せてやる義理はない。
俺は適当に身づくろいを済ませ、無言で部屋を横切ろうとした。
「エレナ姫」
まだ、言うことがあるのか。
俺は緩慢に、男を振り返った。
―――香藤であって、香藤でない男。
いっそのこと、こいつを嫌って忘れられればいいのに。
「・・・!」
見返った俺を見つめるクラウディオの目が、ふと、すがめられた。
「・・・?」
俺たちの視線が、一瞬からみ合う。
男の目が、思いがけない迷いを見せた。
「何か・・・?」
「いや・・・」
クラウディオは、するりと俺に背を向けた。
「行っていい」
彼はもう、振り返らなかった。
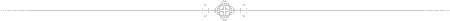
14 April 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2012年12月30日、サイト引越により再掲載。