第三章 (2)
☆ ☆ ☆
翌日。
朝からうっとおしい雨が降っていた。
窓の外がけぶり、森が霧を刷いたようにぼんやりと見える。
俺は起き上がる気力もなく、ぐったりとベッドに寝そべっていた。
「お姫さま、これを・・・」
アドリアーナが、絞ったやわらかい布を差し出した。
「・・・うん?」
ベッド脇の小さな木椅子に腰かけた彼女が、心配そうに俺を見おろす。
「・・・お顔を、お拭きになったほうが」
静かな言葉。
いっそ痛ましい、と思っているような声だった。
そんなわけは、ないのだが。
―――ひょっとして、涙の跡でもあるのだろうか・・・?
漠然と、そう思った。
泣いた記憶はないが、瞼がとても重たい。
俺は嘆息して目を閉じた。
昨夜、クラウディオに呼び出された俺に何があったのか、アドリアーナは聞かなかった。
俺の戻りが、あまりにも早かったのと。
俺の着衣がごまかしようのないほど乱れていたのと。
俺が言葉もないほど憔悴し、そのまま寝台に身体を投げ出したこと。
―――それをアドリアーナが、どう解釈したのかはわからないが。
何も聞かない彼女の気遣いが、ありがたかった。
尋ねられても、俺自身、どう説明すればいいのかわからなかったから。
昨夜は、一睡もできなかった。
香藤が俺を拒否した。
俺が、香藤と同じ男であることを。
それが普通の男の反応なのだ、と思えば思うほど、心が軋んだ。
香藤は特別なのだ。
―――香藤と俺は、そんなものを超越したところで繋がっているはずだ。
そう考えるたびに、昨夜の香藤の嘲笑が耳によみがえった。
・・・俺は、驕っていたのかもしれない。
そう思った。
香藤の愛情をあたりまえだと思ったことはない、と言いながら。
あいつの心が離れていくことを、かつてあれほど恐れていたくせに。
長年一緒に暮らすうちに、いつの間にか―――。
あいつの存在を、あって当然のものだと思うようになっていたのかもしれない。
香藤が俺の側にいてくれることへの感謝の気持ちを、どこかで忘れていたのかもしれない。
いつも香藤が先回りして俺の気持ちを察してくれることに、甘えていた―――。
だから、昨夜の拒絶を受け止められないのだ。
そう思うと、後悔の念が湧いた。
もっと素直に、俺の想いを伝えればよかった。
言葉を惜しむことなく、あいつが俺にとってどれほどかけがえのない存在か、教えてやればよかった。
・・・胸が、キリキリと痛んだ。
忸怩たる思いに苛まれながら。
俺は、自分の中にある香藤への果てしない執着を自覚した。
あいつがありのままの俺を愛してくれるから、今まで考えたこともなかったが、なれるものなら、女になってもいい。
―――香藤が、それを望むなら。
ごく自然にそう考えた俺は、自分でその発想に驚いた。
・・・驚きは、したが。
それがあいつを繋ぎとめる代償ならば、あまりにも瑣末なことに思えた。
香藤との幸福に満ちた生活を取り戻せるなら、俺は何でもできるだろう。
香藤なしには、生きられない。
香藤のいない人生など、俺には無意味なのだから―――。
ノックの音がした。
ぼうっとしたままの俺に代わって、アドリアーナが立ち上がった。
「失礼いたします」
入ってきたのは、金子さん―――もとい、海賊の首領の側近だった。
「ルジェーロと申します。昨夜は名乗りもせず、ご無礼をいたしました。以後、お見知りおきを」
そう言って、俺たちに向かって丁寧に頭を下げた。
俺はひそかに目を丸くした。
慇懃な態度が身についていて、とても海賊の一味とは思えない。
「クラウディオさまから、これをお渡しするようにと」
ルジェーロはひと抱えもあるような大きな箱を、アドリアーナに手渡した。
「これは・・・?」
首を傾げるアドリアーナに、ルジェーロは説明した。
「エレナ姫にはそれをお召しになって、ご朝食にご同席いただくようにと、申しつかっております」
もう一度会釈して、彼は早々に退出した。
「お姫さま」
アドリアーナに手渡された箱は、見た目よりずっと軽かった。
「何を、考えて・・・」
昨日の今日だ。
香藤、いや、クラウディオが何を企んでいるのか、想像もつかなかった。
俺はそっとその箱を開けた。
「まあ、これは・・・!」
アドリアーナが絶句した。
彼女が手に取ったそれは―――丁寧に折りたたまれた白と黒の布地だった。
黒曜石のようにつややかな光沢の絹のズボン。
ゆったりした白いドレスシャツも絹のようだった。
その襟元や袖口には、真珠と水晶がちりばめられていた。
それから、細い金のチェーン。
その先に、凝った金細工の懐中時計があった。
「・・・男性の衣装ではありませんか」
俺は、言葉もなく頷いた。
なぜ、こんなものを・・・?
化けの皮が剥がれた以上、偽の姫君の格好はするな、ということか。
いや、嫌味や冗談にしては、このプレゼントは高級にすぎるだろう。
どうして―――。
「・・・着替える」
俺はすっと立ち上がった。
あの男の意図がなんであれ。
もう一度会えるというなら、それは僥倖だった。
ひらひらしたドレスを着ないですむのなら、それに越したことはない。
「お姫さま・・・」
「断るわけには、いかないだろう?」
―――アドリアーナにはまだ、俺がエレナ姫に見えているのかもしれないが。
少なくともあの男は、俺自身を見ているわけだ。
そう考えると、少しは救われた気分だった。
☆ ☆ ☆
案内されたのは、ダイニングというより書斎といった趣きの部屋だった。
品のいい調度品と、優雅な彫り細工の円形テーブル。
豪奢ではないが、落ち着いたいい部屋だった。
「・・・遅かったな」
男装―――この表現はおかしいが―――で現れた俺に、クラウディオはちらりと視線を走らせた。
顎をしゃくって、向かいの席を示す。
俺は黙って席に着いた。
「エレナ姫・・・いや」
クラウディオは俺をじっと見つめた。
探るような、強いまなざし。
「・・・何か?」
低く問うと、彼は小さく笑った。
―――ああ、こういう表情は、まさに香藤そのものだ。
「そういう格好のほうが、ずっと似合う」
満足そうな声だった。
値踏みするような視線が妙に気恥ずかしくて、俺は目を逸らせた。
「・・・名前は?」
「え?」
「エレナというのは、本当の名前ではないだろう?」
思わず振り返ると、きらめく薄茶色の瞳がまっすぐに俺を射抜いた。
「・・・好きなように、呼べばいい」
しばらく考えてから、俺はそう答えた。
香藤が香藤でないなら、岩城京介が岩城京介である必要性はない。
そう思った。
男の眉間に、すっとしわが寄った。
「おまえには名前がないのか?」
俺はため息をついた。
「・・・京介」
「キョウスケ?」
「そうだ」
クラウディオが、片眉をすっと跳ね上げた。
「おかしな名前だが・・・まあいい。キョウスケ、食事が済んだら外出する。供をしろ」
俺は驚いて、まじまじと目の前の男を見つめた。
「馬には、乗れるな?」
「乗れるが・・・」
躊躇した俺の先を、男は指だけで促した。
「・・・なぜだ?」
囚われの姫君扱いも不本意だったが。
唐突に外に連れ出すと言われても、おいそれと乗れるものではない。
アドリアーナだって、心配するだろう。
「本当に、不遜な口をきく」
くつくつ笑って、クラウディオは俺の瞳を覗き込んだ。
「時計を渡したろう。あれは俺の従者の証だ。時読みには俺の側にいてもらわないと困る」
そう言って、彼は立ち上がった。
「あと30分で支度しろ」
言い捨てて、クラウディオは部屋を出て行った。
☆ ☆ ☆
その日を境に、海賊の首領クラウディオは、根城に戻ってくるたびに俺を呼びつけるようになった。
従者だと、言われてはいたが。
実際のところ、俺は従者らしいことは何ひとつしていなかった。
クラウディオが城に戻っているときは、たいてい側にいる。
ただ、それだけ。
誘い出されて鷹狩りにつきあったり、食事に同席したりした。
書物を読む彼の脇で、ただ座っているだけの夜もあった。
一緒にいるからと言って、話が弾むわけでもない。
気まぐれな王子様の従順な遊び相手を演じている、そんな感覚だった。
体のいいペットのようなものかもしれない。
―――それでも。
俺はいつの間にか、彼の帰城を待ちわびるようになった。
彼が不在のときは、相変わらず尖塔の最上階の部屋に閉じ込められた。
すでにそれを、不遇とも感じなくなっていたが。
高窓から下界を眺め、見るともなく香藤―――クラウディオの姿を探すのが日課になった。
あの男が、颯爽と馬を走らせて、城門をくぐるのを。
そんな俺を、アドリアーナは嘆息して見守っている、そんな感じだった。
俺が部屋にいると、それでも彼女は嬉しそうだったが。
―――心配してくれているんだろうな。
実は彼女には、何も事情を話していない。
気の毒だったが、何をどう説明していいのか、俺にはわからなかったから。
何週間かが、そうやって過ぎた。
帰城するたびに、クラウディオは俺に新しい衣服や装飾品を寄越した。
色鮮やかな東洋の更紗。
流れるようなラインが美しい、異国の民族衣装。
血潮色の珊瑚のベルト飾り。
俺の部屋にひとつしかない衣装箱は、いつの間にか高価な贈り物で溢れかえっていた。
何もいらないと、繰り返し告げても―――。
「いいから、黙ってもらっておけ」
そう言って、クラウディオはいっこうに取り合わなかった。
困惑しながらも、俺はひそかに思いをはせていた。
香藤が、俺に次々と何かを買ってきた日々が戻ってきたようだったから。
・・・それは、幸せな錯覚だった。
クラウディオが俺に対して、甘い表情を見せることはなかったが。
それでも最近は、穏やかな目をするようになっていた。
それが嬉しくないといえば、嘘になる。
☆ ☆ ☆
落雷の轟音が、すぐ近くに聞こえた。
「どう、どう・・・っ!」
たたらを踏む馬を必死でなだめて、俺は後ろを振り返った。
クラウディオが、俺の視線に気づいて首を横に振った。
彼の馬も、動転してまともに言うことを聞いてくれないらしい。
ザアザアと五月蝿いほどの音をたてて、雨が降っていた。
深い森の中。
引き返そうにも、視界はどしゃ降りの雨に遮られている。
ぬかるみの坂道を、恐怖にいななく馬に乗って下るのは危険すぎた。
途方に暮れて、俺は天を仰いだ。
久しぶりに戻って来たクラウディオに言われるまま、遠乗りに出た。
朝からしとしとと雨の降る晩秋の日。
霧が深いからと、ルジェーロは俺たちを引き止めたのだが。
クラウディオは耳を貸さず、笑って側近の懸念を一蹴した。
―――いつもの森で馬を駆るだけだ、心配には及ばない。
そう言った彼の表情は、明るかったのだが。
「見えるか、あそこだ・・・!」
豪雨に全身を打たれながら。
クラウディオの声を頼りに、俺は何とか馬を進めた。
木立の向こうには、森番の見張り小屋。
それを見て、俺はほっと息をついた。
あれならひとまず、雨はしのげるだろう。
「ほら、手を貸せ!」
手がかじかんでまともに手綱を引けない俺に焦れて、クラウディオが大股で近づいて来た。
彼の馬は、もう樹木に結びつけられていた。
クラウディオが鐙(あぶみ)を軽く叩いて、俺に飛び降りるように促す。
ごく自然に両腕を広げ、まっすぐに俺を見上げていた。
俺は深呼吸をして、その胸に飛び込んだ。
「・・・ん!」
俺の体重を受け止めて、クラウディオが一歩よろめいた。
凍えるほどの雨の中。
彼の胸の中の確かな熱に、俺は目眩を起こしそうだった。
「・・・おい、大丈夫か?」
なつかしい薄茶色の瞳が、至近距離で俺を覗き込む。
首筋にかかる、熱い吐息。
―――香藤。
この腕に抱かれたのは、いったい何ヶ月ぶりなのだろう?
そう思った途端。
クラウディオがついと、俺の身体を引き離した。
「・・・風邪をひくぞ。早く、中へ」
そう言って踵を返す男の後姿を、俺はため息をついて見つめた。
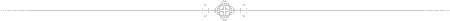
18 April 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2012年12月31日、サイト引越により再掲載。若干の加筆修正をしています。