第三章 (3)
のろのろと小屋に入ると、クラウディオがすでに暖炉に火を起こしていた。
パチパチと音を立てて燃え上がる、炎のゆらめき。
濃いオレンジ色の輝きが、香藤の―――クラウディオの横顔を照らしていた。
その端正なシルエットに、俺は見惚れた。
どこから探して来たのか。
彼は古ぼけた毛布を引っ張り出して、暖炉の前に置いた。
「キョウスケ。何を突っ立ってるんだ」
俺を振り返り、首を傾げる。
「ほら、ここに座れ」
無造作に指し示すそこに、俺は黙って腰を下ろした。
クラウディオはずぶ濡れの俺の身体を毛布で乱暴に包み込み、背中をポンと叩いた。
「震えている・・・」
かすれた声。
―――甘い響きだと思ったのは、俺の錯覚だろうか。
毛布の上からでもわかる、大きな手の感触。
それが彷徨うように、俺の背筋をゆっくりとすべり下りた。
背中に感じる、クラウディオの気配。
それだけで、俺の肌が粟立った。
―――俺の身体は、香藤の存在に無条件に反応する。
それを改めて、思い知らされた気分だった。
今さっきの一瞬の抱擁で、身体が覚醒したのかもしれない。
震えが、止まらなかった―――氷雨のせいではなく。
激しい雨音にかき消されて、心臓の音が聞こえないといい。
俺はそう願って、俯いた。
「当分、やみそうにないな・・・」
窓を叩く大粒の雨を見ながら、クラウディオがため息をついた。
外はすでに、墨を刷いたような夜闇だった。
彼は、膝を抱えて座っていた。
俺の隣り、ちょうど人ひとり分空けた距離。
たった一枚しかない毛布を俺に使わせているので、雨に濡れた衣服のままだ。
俺はその、しなやかな筋肉の乗った鋼のような身体を眺めた。
暖炉の炎がゆらゆらと、彼の顔に陰影を刻む。
「なんだ?」
俺の視線に気づいて、クラウディオが振り向いた。
「・・・寒くないのか」
俺の言葉に、ゆっくり微笑する。
「それほどやわにはできてない」
屈託のない笑顔だった。
イタリア全土を恐怖のどん底に陥れている海賊の首領だとは、とうてい思えない。
俺の沈黙を、どう解釈したのか。
彼は気障に肩をすくめた。
「気にするな。ルジェーロの忠告を聞かなかった俺が悪い」
そう言って、軽く顎をしゃくった。
「おまえのほうが、寒そうだからな」
照れたように笑う。
穏やかな声―――懐かしい、優しい目。
・・・香藤。
おまえはいつだって、そうやって―――。
たまらなかった。
俺は、自身の飢えを自覚した。
香藤のぬくもりが欲しくて、気が遠くなりそうだった。
身体よりも先に、心が悲鳴を上げていた。
香藤を愛したい。
思う存分、愛されたい。
ずっと封印をしてきた感情があふれて、奔流となって逆巻いていた。
目の前の男は、香藤ではないが。
でもやはり、俺の香藤でもあるのだから。
「・・・クラウディオ」
「ん?」
顔を上げた男を、俺は凝視した。
もう一度拒絶されたら―――それこそ、俺は壊れてしまうかもしれない。
だが、このままの状態には、もう耐えられなかった。
「・・・来いよ。寒いだろう?」
俺は毛布の端をめくり上げて、静かに言った。
目を逸らさずに。
「キョウスケ?」
いぶかしげな彼の視線を受け止めながら、俺はシャツ襟の細紐に手をかけた。
結び目をそっと解く。
指先がどうしようもなく、震えていた。
「暖めて、やるから・・・」
俺はゆっくりと、濡れて身体にまとわりつくシルクをはだけた。
「・・・キョウスケ」
低い声で、クラウディオは俺を見返した。
驚愕と、当惑。
俺の真意を探ろうとするような、まっすぐな視線。
―――だがその瞳に、嫌悪の情は見えなかった。
ちらりと欲情めいたものまで、見え隠れする。
思わず、俺は全身を震わせた。
「来いよ―――」
窓の外で、稲妻が光った。
すさまじい光が、ちっぽけな小屋の中を一瞬照らす。
雨音がいっそう激しくなった。
耳をつんざく落雷が響き、俺たちの沈黙を切り裂いた。
嵐の夜―――。
ほんの数秒が、永遠に感じられた。
ゴクリ、と喉を鳴らして。
クラウディオがのそりと立ち上がった。
一歩、二歩。
視線を合わせたまま、俺のすぐ脇に膝をつき、俺の顎に手をかけた。
ぐいと顔を上げさせて、俺の瞳を覗き込む。
吐息が、荒くなった。
「そんな目をするな・・・」
冷たい指先。
俺はそれに、ゆっくりと自分の手のひらを重ねた。
その瞬間。
「・・・!」
俺は太い腕に、羽交い締めのようにきつく抱かれていた。
「後悔、するなよ・・・!」
熱いささやきが耳朶にかかる。
香藤のにおいがした。
たくましい抱擁に絡めとられて、俺は目を閉じて頷いた。
―――香藤!
愛おしさに、気が狂いそうだった。
☆ ☆ ☆
すえた臭いのする毛布に、俺は力任せに押しつけられた。
「ああっ」
容赦なく体重をかけて、香藤―――クラウディオが俺に馬乗りになった。
真上から俺を見る視線が、火を噴くように熱い。
俺は荒い息をついて、胸を喘がせた。
香藤の手が、脱ぎかけた濡れた絹のシャツの上をすべる。
官能を期待して固く勃ち上がった乳首を、その指がかすめた。
「ん・・・っ」
そのわずかな刺激に、俺は思わず背中を仰け反らせた。
「ここが、いいのか・・・?」
いったい何週間ぶり、いや何ヶ月ぶりのセックスなのか、自分でもわからなかったが。
身体の飢えはどうしようもなかった。
クラウディオは、俺のシャツをそれ以上脱がせようとはしなかった。
代わりに布越しに乳首を掴み、乱暴にひねり上げた。
「はあっ・・・!」
疼痛に、俺は首を振った。
・・・だめだ、感じすぎる・・・!
「男でも、ここで感じるのか―――」
感心したようなクラウディオのかすれ声に、俺は赤面した。
とんでもない淫乱だと、指摘されたようで。
―――馬鹿野郎、おまえが俺をこんな身体にしたんじゃないか!
新しい発見を喜ぶ子供のように。
クラウディオは執拗に、俺の乳首を弄んだ。
「・・・っ!」
俺は歯を食いしばって、声を堪えた。
感じすぎて、どんな情けない嬌声をこぼしてしまうか、わからなかったから。
「そんなに、いいのか」
クラウディオは身体をずらすと、無造作に俺のズボンを引き下げた。
冷たい空気にさらされた下半身。
俺は思わず、肌を震わせた。
「・・・白い肌だな・・・」
独り言のように呟いて、クラウディオが俺の太腿に手をかけた。
ぐいと、まるで容赦なく、俺の股間を押し広げて覗き込む。
「・・・きれいな、ものだ・・・」
―――クラウディオが、そこを見ている。
その大きな手が、俺の内腿を確かめるように行き来した。
香藤なのだけれど、香藤ではない男。
その男に、こんな破廉恥な行為を許す自分。
「ああ・・・っ」
惑乱のあまり、目眩がしそうだった。
「興奮、しているのか」
低く笑って、クラウディオが俺のペニスを掴んだ。
「はうっ」
「男にこうされて、興奮するのか・・・」
隠しようもない。
俺のそこは既に勃ち上がり、手淫を喜んでドクリと脈打った。
浅ましい、どうしようもなく浅ましい身体―――。
クラウディオが俺を扱く。
そのリズムに合わせて、俺の腰が揺れた。
「いいか?」
上半身を倒して、俺の耳元で彼がささやいた。
俺は目を閉じたまま、首を左右に振った。
熱い吐息が項にかかる―――それだけで、肌がそそけ立った。
「いいんだろう?」
「ああ・・・っ」
俺の理性を吹き飛ばす、甘い声。
「言わないのなら、やめるぞ」
クラウディオのたくましい胸の厚みが、俺の乳首を押しつぶす。
甘い疼痛に、俺は呻いた。
ペニスへの愛撫は、そのままに。
「・・・いい・・・っ!」
ぎゅっと目を閉じたまま、俺は叫んだ。
―――たまらなかった。
あまりのことに、全身が羞恥で朱に染まるような気がした。
「そうだ・・・」
満足そうな、男の声。
「そうやって、素直になったほうがいい」
俺は堪えきれず、歓喜の涙をこぼした。
荒い吐息。
クラウディオは俺の脚を放り出すと、自分のズボンの前をくつろげた。
苦笑する気配。
俺は、緩慢に視線をめぐらせた。
「・・・男の股ぐらを見て、こうなるとは思わなかったな」
香藤のペニス。
見慣れたそれが、俺を欲して怒張していた。
俺の鼓動が、一気に跳ね上がる。
「かと・・・」
そう声をかけそうになって、俺は慌てて言葉を引っ込めた。
香藤が―――クラウディオが、俺の腰を乱暴に引き寄せた。
ヌルリとした感触。
先端の濡れそぼった大きなペニスが、俺の肛門に押し当てられる。
「・・・!!」
そこに圧力を感じて、俺は思わず飛び起きた。
「キョウスケ?」
肩で息をしながら、俺は身体をよじらせた。
「待て・・・っ」
瞠目して、クラウディオは俺を見つめた。
「いやなのか?」
―――誘ったのはおまえだぞ、と言わんばかりの声。
俺はゆっくり首を振った。
「いやじゃ、ないが・・・」
・・・香藤だけど、香藤ではない男。
こんなことを口にする日が来るとは、思わなかった。
「いきなりは、無理だ・・・!」
俺の言葉の意味が、わからなかったのかもしれない。
クラウディオは、きょとんとした顔で俺を見つめた。
その表情の意外な幼さに、俺は、彼がまだ若いことを思い出す。
・・・愛おしさを、感じないわけにはいかなかった。
―――記憶こそないけれど、これは俺の香藤なのだ。
この男と、ひとつになりたい。
この男の灼熱を、身体の内に受け入れたい。
それはもう、どうしようもない情動だった。
俺は深く息を吐いて、羞恥心をねじ伏せた。
―――愛おしさに、後押しされて。
クラウディオの手を取り、ゆっくりと俺の肛門に導いた。
香藤と繋がるための場所。
クラウディオの指先がそこに触れた瞬間、俺は覚えず戦慄した。
香藤しか、知らない場所。
「・・・女とは、違う。ここは、このままじゃ濡れないんだ・・・」
クラウディオは、呆然と俺を見ていた。
俺はひそかに苦笑した。
男同士のセックスの知識など、普通はなくてあたりまえだ。
「こうして、やるから・・・」
俺はクラウディオの指を引き上げ、口に含んだ。
愛情のありったけを込めて、彼の指をできるだけ丁寧に舐めねぶった。
「・・・んっ」
クラウディオの視線を痛いほど感じながら。
俺は彼の指に、たっぷりと唾液を絡ませた。
ほうっと、彼が息をついた。
俺はそっと、彼の手から顔を離した。
「気持ち悪く、なければ・・・」
俺は彼の瞳を見つめた。
「その指で、馴らしてくれ」
クラウディオが、少し驚いた表情をする。
―――お互いが快感を得るためには、必要なことなのだけれど。
香藤にセックスを教えるなんて、想像したこともなかった。
「・・・抵抗があるなら」
俺は目を伏せて、続けた。
いくら何でも、こればかりは照れるなというほうが無理だったから。
「あっちを向いていてくれ。・・・俺が、自分でやる」
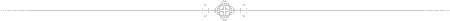
21 April 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月4日、サイト引越により再掲載。若干の加筆・修正ありです。