第四章 (1)
翌朝、俺は熱を出した。
雨あがりの森を抜けて、なんとか城に戻ったまではよかったのだが。
城門をくぐって安堵した途端、ふっと意識が遠くなった。
足手まといになりたくない。
その一心で堪えていた身体の痛みが、急激に俺の神経を襲った。
出血が酷く、全身が嫌な感じに冷えてゆく。
足がふらつき、視界がぼやけた。
「―――っ」
助けを求めようとしたが、声が出ない。
「キョ・・・スケ!?」
クラウディオが振り返って、大声で俺を呼んだ。
引いていた栗毛の馬が、気遣わしげに脚を止めるのと。
俺の体重を支えきれなくなった膝が、崩れ落ちるのと。
彼の逞しい胸に抱きとめられるのと、ほぼ同時だった。
「おい、キョウスケ!」
最後の記憶は、クラウディオの青ざめた顔。
後は何も、覚えていない―――。
☆ ☆ ☆
ピチャリ、という小さな水音。
額に触れるひんやりとした感覚に、俺はうっすらと目を開けた。
「ルジェーロ・・・?」
最初に目に飛び込んで来た顔に、呼びかけて。
・・・かすれた声のひどさに、驚いた。
頭痛がひどく、めまいがする。
「お目覚めですか、エレナ姫」
俺は緩慢に、周囲を見渡した。
そっけないほど広々とした部屋―――。
豪奢だが寒々しい印象には、見覚えがあった。
ここは、この城の主の寝室だ。
「クラウ・・・?」
俺の問いかけに、ルジェーロが頷いた。
「王子・・・いえ、クラウディオさまは外出中です。まもなくお戻りでしょう」
安心させるような口調は、今までとはずいぶん違って親身に聞こえた。
「姫は丸二日間、眠っておられたのですよ」
身内を労わるような、穏やかな声。
ふと。
彼は知っているのかもしれない、と思った。
あの、森での出来事を。
クラウディオと俺の関係が、変わってしまったことを。
―――でなければ、俺がクラウディオの寝台にいる説明がつかないだろう。
羞恥で、顔に血が上るのがわかった。
どう確かめたものか迷っている俺に、気づいたのかどうか。
「何も、ご懸念なさることはありません」
ルジェーロは小さく微笑した。
「すべて、クラウディオさまがよきように差配なさっていますから」
そう言うと、すっと一歩下がった。
「何か、お飲み物をお持ちします」
会釈して、彼は寝室から出て行った。
誰もいない、がらんとした寝室。
俺はそっと嘆息した。
・・・貪るように、クラウディオと抱き合った。
嵐の夜の狂気と、言えないこともないだろう。
―――自分でも、信じられないが。
俺は自らの意思で、あの男に抱かれたくて、誘いをかけた。
激しいセックスに溺れ、涙を流してクラウディオにすがりついたのも、俺のほうだ。
その抱きかたも、俺を呼ぶ声も、香藤とは違うというのに。
・・・それでも俺は、あの男を欲した。
彼が応えてくれたのは、いいが。
それが香藤を裏切ったことになるのか、ならないのか、自分でもわからない。
香藤なのに、香藤の記憶を持たない男。
俺のもののはずなのに、俺の腕の中に納まってくれない男。
―――本当に、信じられないが。
俺は自分が、どうしようもなくクラウディオに惹かれているのを、否定できなかった。
身体がだるく重かった。
熱のせいか、視界がぼんやりと霞む。
どうしても違和感が気になって、俺は痛む肛門にそっと手を伸ばした。
ぽってりと腫れたそこは、じんじんと熱をもって疼いていた。
痛い―――怖い。
指をほんのわずか、差し入れてみる。
「ん・・・」
ピリリと引き攣るような痛みと、ぬるりとした感触。
軟膏でも塗り込められているらしかった。
俺が気を失っている間に、誰かがそこを清め、手当てをしたのだろう。
―――クラウディオなのか?
そのさまを想像して、俺は赤面した。
おかしなことだが―――香藤だと思えば、耐えられるのだが。
クラウディオがそれをする、と考えるだけでのぼせそうだった。
とはいえ。
彼がルジェーロやアドリアーナに任せたのだったら、それはきっと、もっと耐え難いだろう。
・・・そう思った途端。
別のことに思い当たって、俺はシーツの中を覗き込んだ。
男ものらしきシャツと、下半身にはズボン下のようなもの。
見慣れない衣服なので、ひょっとしたらクラウディオのものかもしれない。
俺は恐る恐る、シャツの前立を飾る紐をほどいた。
「酷いな・・・」
肌に点々と散った、赤い痕。
キスマークというより、強く噛まれた痣と呼んだほうがいいものも。
乳首の片方には、歯型がくっきり残っていた。
すべて、香藤の愛した痕跡とはまったく違っていた。
―――まるで、陵辱されたかのような身体。
ため息が、出た。
これほど手酷い扱いを受けたというのに。
それでも、クラウディオと肌を合わせたことを後悔する気にはなれなかった。
「・・・業が、深いな・・・」
俺はひっそりと苦笑した。
『いい、俺がやる』
『ですが・・・』
ドアの外で、くぐもった会話が聞こえた。
俺がそちらに顔を向けるのと、ほぼ同時に。
「キョウスケ!」
黒檀の扉が勢いよく開き、クラウディオが大股で近づいてきた。
「目が醒めたのか・・・!」
乱れた髪を無造作にかきあげて、ベッドに横たわる俺を見下ろす。
ジャラリと、重たげな装飾品が音を立てた。
―――彼の衣装からは、はるかな海の匂いがした。
「キョウスケ・・・」
浅い息をつきながら。
クラウディオは俺の手を取り、片眼を瞑って手の甲にキスを落とした。
「おい・・・」
姫君に忠誠を誓う騎士の儀礼。
その気障なしぐさに、俺は赤面した。
彼の後ろに控えるルジェーロが、そっと目を伏せる。
俺の視線に気づいたクラウディオが鷹揚に頷き、ルジェーロを振り返った。
「もう、いい」
それだけ言って、さっさと側近を追い払うと―――。
クラウディオは、ベッドにのそりと腰を下ろした。
香藤の汗の匂い。
華やかな美貌が、俺をじっと見つめる。
それだけで、鼓動が早くなる気がした。
「クラウディオ・・・」
「ん?」
呼んでは、みたものの。
何も言うべき言葉が見つからず、俺は困って彼を見上げた。
視線が、どうにも面映ゆい。
「まだ熱は、あるのか」
「・・・ああ」
「そうか」
クラウディオは笑って、そっと俺の髪を撫でた。
「・・・あまり心配を、かけるな」
やさしい低い声。
俺は黙って、頷いた。
「もっとも」
「?」
「今回のことは、すべて俺のせいだ。・・・悪かった」
照れ混じりの謝罪。
同時にクラウディオの手が、すっと俺から離れていった。
思いがけず、俺の心にさざなみが立つ。
―――俺が寝込んでいる責任が、自分にあると言っているだけならいいが。
『今回のこと』には、あの夜の情交も含まれているのだろうか?
奔流に逆らえず、飢えた野獣のように求めあった。
あれは過ちだったと、言っているのか・・・?
謝罪の意味を計りかねて、俺は眉を寄せた。
「また、そんな顔をする」
クラウディオが俺の表情を読んで、小さく笑った。
・・・こんなふうに優しく笑うなんて、少し前までは考えられなかったことだ。
「その顔はダメだ。・・・誘っているようにしか、見えない」
したたるような甘い声で囁いて。
クラウディオは、すっと立ち上がった。
「水と・・・何か食べるものを、持って来よう」
すたすたと遠ざかる彼を、俺はじっと見送った。
もどかしい思いだけが、空回りしている気がした。
☆ ☆ ☆
「ほら、もっと脚を開け・・・」
やさしい夜の帳(とばり)が下りていた。
足元から聞こえる声に、俺はぎゅっと目を閉じた。
「何を、恥ずかしがっているんだ」
―――クラウディオの手の温もりを、直に感じて。
裸に剥かれた下半身が、ともすると熱を持ちそうになる。
それはもう、条件反射のようなものだった。
柔らかい布地に肌を拭われる、濡れた感触。
「クラウディオ・・・んっ・・・」
俺は声をあげまいと、必死で歯を食いしばった。
身体を拭いてやる、と言い出したのはクラウディオだった。
俺が腰を痛めて思うように歩けず、湯浴みもままならないからだ。
「・・・そのくらい、自分でできる」
「何を言ってる。まともに起き上がれもしないくせに」
同じ会話を、何度繰り返したことか。
これが香藤なら、誰のせいだ、と睨んでもやれるが。
クラウディオ相手に、それは無理な話だった。
困惑して押し黙った俺に、彼はさらりと言った。
「・・・昨日もおとといも、俺がやった。今さら、照れても遅い」
押し問答は終わりだ、と言わんばかりに。
クラウディオは慣れたしぐさで、俺の服に手をかけた。
「おい・・・」
シルクの生地を絞り、慎重に俺を清めていく。
・・・大切なものを扱うかのような手つき。
その真摯な目に、俺のほうが気恥ずかしくなるくらいだった。
「もう、いいから・・・」
そう言っても、彼は頑として聞かなかった。
「ここの、手当てを―――」
クラウディオの指が、ためらいがちに俺の肛門に触れた。
「あ・・・っ」
反射的に、俺は全身を強張らせた。
思わず感じた恐怖。
それを敏感に察して、彼が苦笑した。
「そんなに、怖がるな」
なだめるように、彼の手が俺の太腿をさする。
官能をかき立てるのではなく、労わるための穏やかな愛撫。
「薬を塗布するだけだ。少し、我慢してくれ」
「クラウディオ・・・」
彷徨うように差し伸べた俺の手を、彼はしっかりと握りしめた。
「何もしない。しないから・・・」
「ああ・・・」
俺は目を閉じて、深呼吸した。
身体を弛緩させようと、ゆっくり、大きく息を吐く。
―――傷を負ったのは、俺だが。
俺を傷つけたことでショックを受けているのは、クラウディオのほうだ。
彼にこれ以上、罪悪感めいたものを抱いてほしくはなかった。
「んん・・・っ」
そっと俺の中に入ってくる、一本の指。
それがそろりと、周囲の柔襞に触れる。
「あう・・・っ」
薬が沁みる感覚に、俺は思わず声をあげていた。
クラウディオの指が、驚いたように去っていく。
俺の右手を握りしめたままの温かい手が、あやすように指を絡めてきた。
「キョウスケ・・・」
叱られた子供のような、小さな声で俺を呼ぶ。
それは―――俺の可愛い香藤そのものだった。
「大丈夫だ・・・すまん」
愛おしさに、胸がはりさけそうだった。
「謝るな。・・・そんなに、辛いか?」
静かに聞かれ、俺は首を振った。
股間に座り込んでいる大きな男に、ありったけの思いを込めて微笑んだ。
愛してる。
おまえだけを、愛してる―――。
「もう、平気だ。・・・続けてくれ」
この男が、こうやって必死で俺を癒そうとするように。
俺も、この男の心の棘を抜いてやりたい。
そのためなら、何でもできる気がした。
☆ ☆ ☆
それから数日の間、俺はクラウディオの寝室で過ごした。
うつらうつらと浅い夢を見ては目覚める、そんな日が続いた。
おそらく、精神的に疲弊していたのだと思う。
熱が引いたり、ぶり返したりを繰り返した。
そんな不甲斐ない俺を、クラウディオは黙々と介抱してくれた。
粗野な印象の男が見せる、思いがけない細やかな気遣い。
―――愛されているのだと、錯覚するほどに。
日中、それでも彼は不在のことが多かったが。
そんなときはアドリアーナやルジェーロが呼ばれ、俺の身の回りの世話を焼いてくれた。
彼らは誠意をもって、面倒を見てはくれたが―――。
何しろ、できることは限られていた。
・・・俺の身体に指一本でも触れてはならない、というクラウディオの厳命を受けていたので。
当然、というべきか。
アドリアーナは猛然と抗議したのだが、クラウディオはまるで取り合わなかった。
「姫の身体に触れるのは許さん。おまえだけフェラーラ公国に突き返すぞ」
海賊の首領にそう、脅されて。
彼女は渋々、彼の出した条件を呑んだ。
「私を何だと、思っているのでしょうか」
仮にも、お姫さまの侍女長でございますよ―――。
憤慨するアドリアーナに、俺は内心で詫びた。
彼女には、心配をかけてばかりだったが。
この痣だらけの身体を彼女に見せるわけにはいかないので、俺は沈黙を貫き通した。
もっとも―――俺の裸など、検分しなくても。
アドリアーナはとうに、あの嵐の夜に何が起きたのか、察していただろう。
あの日を境に。
俺は一度も、尖塔の部屋に帰っていない。
何しろ囚われの身のはずが、城主の寝室に居座っているのだ。
・・・怪我をして寝たきりでは、まあ、どうしようもないが。
忙しいはずのクラウディオが、手ずから俺の面倒を見ていることも。
彼が俺に執着し、私室から出さないことも。
すでに城内では、周知の事実らしかった。
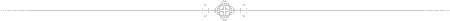
30 April 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月8日、サイト引越により再掲載。当時の原稿を若干加筆・修正しています。