第四章 (3)
「キョウスケ」
「・・・ん?」
ぴったりと抱き合ったまま―――。
俺は両腕をクラウディオの身体に廻して、重なるふたつの鼓動を聞いていた。
月の光が寝台を照らす、美しい夜。
「・・・よかったか?」
囁きとともに、小さなキスが額に落ちた。
「クラウディオ・・・」
「もっと、してやろうか」
からかうような、楽しそうな声で。
返事に困って顔を背けると、くつくつ笑いが聞こえた。
「恥ずかしいのか」
「・・・悪いか」
俺はそっぽを向いたまま、憮然として答えた。
「恥ずかしがることはない。快感に身悶えるおまえは、可愛かった」
さらりと言われて、俺は目を瞠った。
―――その言葉を聞くのは、いったい何時ぶりだろう。
「男なのに・・・どうしてだろうな。おまえが乱れて、俺の手で達くのを見ると、もっともっと可愛がってやりたくなる」
真顔でそう呟かれて、俺は赤面した。
「ほら、照れるな」
クラウディオの唇が、なだめるように俺の頬をなぞった。
柔らかいキスが、眉に、睫に、瞼に繰り返される。
降り注ぐ愛情。
それはあまりにも、香藤のしぐさを髣髴とさせて―――。
「かと・・・」
心地よさに、俺は陶然と身を委ねた。
・・・本当に無意識に、こぼれ落ちた言葉だったので。
しまった、と思ったときはもう遅かった。
俺に覆いかぶさっていたクラウディオの肢体が、ビクリと揺れた。
「キョウスケ」
俺を咎める、硬い声。
全身から汗がすうっと引いていくようだった。
「クラウディオ・・・」
張りのある背中を撫でながら、俺はそっと男の表情を窺った。
下弦の月はいつの間にか、雲間に隠れていて。
ゆらゆらと揺れる蝋燭の火が、ほんのりと寝台を照らしていた。
「あ・・・」
愛してやまない薄茶色の瞳が、じっと俺を見下ろしていた。
怒りではなく、ただの妬みでもなく、何ともやりきれない切なさを湛えたまなざしで。
俺の胸がツキンと痛んだ。
「クラウディオ・・・」
―――何も、言うべき言葉がなかった。
たとえ俺が謝罪しても、彼のプライドが傷つくだけだろう。
第一、俺は―――バカバカしいこだわりだが―――俺にとって唯一の男の名前を呼んだことを、謝る気にはなれなかった。
しばらくの間、ぎこちない沈黙が落ちた。
・・・俺の髪をすく手を止めて。
「おまえの、ここには・・・」
クラウディオは、指先をそっと俺の裸の胸にすべらせた。
心臓の上を、トントンと叩く。
「よほど特別な男が、棲んでいるらしいな」
「・・・」
「その男に、惚れているのか」
「・・・」
「それほど好きなら、なぜ別れた? ・・・いや」
クラウディオは、深いため息をついた。
「別れていないのか」
疲れたような、表情で。
「・・・ならばどうして、俺に肌を許す? 誰でもいいのか・・・それとも」
俺の心を見透かすような、まっすぐな視線。
「俺を、好きなのか」
俺はもどかしさに唇を噛んだ。
「なぜそんな顔で、俺を見る・・・?」
「・・・それは・・・」
言いかけて、結局、俺は口を噤んだ。
―――ひとつとして、まともに答えられない質問ばかりだった。
おまえしか、いない。
俺の心の中には、おまえしかいないのに。
・・・そのことが、おまえを傷つけているなんて。
やるせなくて、俺はただクラウディオを見つめ返した。
「・・・言いたくなければ、いい」
ふと諦めたように、クラウディオは表情を崩した。
香藤が一度も見せたことのない、淋しい笑いだった。
―――その顔を見た、瞬間。
何かが、俺の中で砕け散った。
「・・・昔の、ことだ・・・」
俺はようやく、それだけ言葉を絞り出した。
香藤との関係は、俺にとって決して過去などではない。
だが、そのことに拘っていたら、目の前の―――香藤としての記憶こそ持たないが―――本物の香藤を失ってしまうかもしれない。
それに思い当たって、俺は戦慄した。
―――それだけは、絶対にあってはならない・・・!
「・・・キョウスケ?」
俺を見下ろす、愛しい男。
その暖かな力強い腕に抱かれて―――これ以上の幸せが、あるだろうか?
「クラウディオ」
俺は片手を伸ばして、降りこぼれる薄茶色の髪の毛をかきあげた。
「俺の恋人は、おまえだけだ。おまえしか、いらないんだ」
結局、ありきたりの表現しかできないけれど。
―――それだけは信じてほしい。
「俺は、おまえだけを・・・」
必死で言葉を探す俺を、クラウディオはぐっと抱え直した。
「もう、いい」
それだけ囁くと、あとはキスで俺の唇を封じた。
「んん・・・っ」
深いくちづけに、すぐに息が上がった。
俺は両腕を彼の首に廻して、夢中でそれに応えた。
・・・俺の真実を、くちづけで伝えられるものならば。
濡れたキスの合い間に、クラウディオの声が聞こえた。
「誰の名前でも、呼べばいい。いつか―――おまえの身も心もすべて、俺だけのものだと言わせてみせる」
耳朶に直接注ぎ込まれる、官能的な低い声。
「あふ・・・っ」
「忘れさせてやるさ。昔のことなど・・・」
クラウディオの自信に溢れた囁きに、心が震えた。
愛おしくて。
たまらなく愛おしくて。
涙が零れそうで、俺はそっと目を閉じた。
☆ ☆ ☆
俺がようやく回復し、ほぼ日常生活に戻って数日後の朝。
いや、もう陽は高かったかもしれない。
前夜もへとへとになるまでクラウディオと愛し合い、泥のような眠りについた、その後朝(きぬぎぬ)。
俺は、高窓から降り注ぐ光の眩しさに、うっすらと目を開けた。
「目が、覚めたか」
ざらついた起き抜けの声。
「クラウディオ・・・」
俺を後ろからすっぽりと抱き込んでいる男の名前を、俺はうっとりと呼んだ。
ここ数日、こんな目覚めばかりだ。
顎に指がかかり、俺は強引に後ろを向かされた。
「ん・・・」
首をひねった姿勢で、俺は若い恋人のキスを受けた。
ねっとりと深いくちづけに、昨夜の快感の余韻が熾火(おきび)のようにくすぶった。
クラウディオの指が、探り当てた俺の乳首をくすぐる。
「・・・こら・・・」
俺は身をよじって、目覚めには濃厚すぎるキスから逃れた。
クラウディオがくすくす笑いながら、ペニスを俺のむき出しの尻に擦りつけた。
―――それはもう、堅くなり始めていて。
「昨夜も、あれだけ・・・」
言いかけて、俺は口を噤んだ。
香藤相手ならともかく、クラウディオをそうやって叱りつけることに、ひそかな戸惑いを覚えて。
代わりに、彼のいたずらな指をぎゅっと握って心臓に抱いた。
「こっちを向け、キョウスケ」
項にかかる吐息にゾクリと身体を震わせながら。
俺は素直に反転して、クラウディオの顔を見つめた。
「・・・ボンジョルノ」
甘い囁きに照れて、俺は俯いた。
―――10年近くも連れ添った男のはずなのに。
初めてふたりで迎える朝のように、気恥ずかしかった。
「ほら、俺を見ろ」
しっかりと抱擁されて、もちろん逃げようもないのだが。
促されて、俺はそろそろと顔を上げた。
眩しいほどの、香藤の―――クラウディオの笑顔。
とろけるような優しいまなざし。
香藤はクラウディオだが、クラウディオは香藤ではなくて。
・・・混乱しないと言ったら、嘘になるが。
俺はもう、悩まないことに決めていた。
目の前にいるこの美しい男が、俺の恋人―――それだけで、いい。
「おはよう・・・と言うには、遅すぎる時間だな」
俺はそっと手を伸ばして、わずかな髭にざらつく頬に触れた。
「きっとまた、ルジェーロに小言を言われるぞ」
クラウディオの唇に、触れるだけのキスをする。
「もう、言われた」
「・・・は?」
「一時間も前に、俺たちの様子を窺いに来たからな」
「・・・ええ!?」
あっさりと言われて、俺は絶句した。
「この寝室に・・・入ってきたのか?」
「俺の腹心だ。当然だろう?」
クラウディオは不思議そうに俺を見返した。
俺は天を仰いで嘆息した。
―――中世イタリアのプライバシーの概念が、俺と違うのは仕方ないのかもしれないが。
クラウディオに抱かれて全裸で眠っているところを見られたのかと思うと、眩暈がしそうだった。
今さら、かもしれないが。
「キョウスケ」
その声音には、耳覚えがあった。
とっておきのニュースがあるときの、喜びを隠せない香藤の口調。
「何だ?」
俺は目を細めて、先を促した。
クラウディオは俺の左手を取ると、甲にキスを落とした。
彼がよくやる、貴公子のようなしぐさ―――照れくさくて、これにはどうしても慣れない。
彼はチェストの上の小箱から、ゴソゴソと何か取り出した。
「・・・これを」
差し出された手のひらにあったのは、アンティークな金の指輪だった。
ぼってりした造りの大ぶりなデザイン。
真ん中には、深海の翠の結晶のようなエメラルド。
いったい何カラットあるのか見当もつかないような、大粒の。
唖然としている俺の指に、クラウディオはゆっくりとそれを嵌めた。
左手の中指に―――薬指には、大きすぎたので。
「おまえ、これ・・・」
驚く俺の頬にそっと手を触れて、クラウディオは満足げに微笑した。
「思った通りだ。よく、似合う」
「・・・クラウディオ」
「キョウスケ」
真剣なまなざしだった。
「これは、我が家に伝わる・・・」
言いかけてふと、クラウディオは苦笑して首を振った。
「そんなことは、どうでもいい。・・・これは、俺の誓いだ。受け取ってほしい」
「誓いって・・・」
「おまえを、俺の都合で気まぐれに抱く女のように扱いたくはない。いつまでもこの城に閉じ込めて、日陰の存在のように隠しておくのも嫌だ。今はまだ、時期尚早だが―――いつか必ず、陽の当たる場所に連れて行く。それまで、待っていて欲しい」
「クラウディオ・・・」
俺は瞠目して、目の前の男を見つめた。
・・・この男は、何を言おうとしている・・・?
「こんな気持ちになったのは、生まれて初めてだ。知り合ってまだ日は浅い。おまえのことも、何も知らないが・・・俺には、わかる。おまえは俺のものだ。俺だけのものだ。何があっても、手放すつもりはない」
意志の強い薄茶色の瞳が、俺をまっすぐに見据えていた。
「わかるか、キョウスケ。俺は今、おまえに求婚してるんだ。―――生涯、俺の側にいてくれ」
息を呑んで、俺はその言葉を聞いた。
「幸せにしてやりたい。・・・おまえに忘れられない恋があるなら、それでもいい。その記憶ごと、俺はおまえを愛するから」
「・・・!」
―――もしも、香藤が。
呆然とクラウディオを見つめ返しながら、俺は考えた。
俺たちの家を建てるとき、瓢箪から駒のような『プロポーズ』をしたのは俺のほうだった。
今はもう、遠い記憶だ。
・・・でも、そうでなかったら?
香藤はこんなふうに、いつか俺に結婚を申し込んだのだろうか。
―――生まれ変わっても、たとえ記憶をなくしても。
香藤も俺も、それでもお互いを生涯の伴侶に選ぶだろうと信じていた。
今、クラウディオが、それを証明している―――。
そう思った途端、涙があふれた。
「キョウスケ?」
「・・・っ・・・」
全身がガタガタ震えて、どうしようもなかった。
裸でベッドにペタリと座り込んだまま、俺は俯いてただ、泣いた。
泣くよりほか、できなかった。
「おい!?」
驚愕したクラウディオが俺の身体を抱き寄せ、あやすように背中をさすった。
情けないことに―――滂沱の涙が、とまらなかった。
「どうした、どこか痛いのか・・・?」
慌てて囁くクラウディオに、俺は何度も首を横に振った。
ちがう、ちがうんだ。
これは、幸せの涙だ。
おまえの言葉が、想いが、嬉しくて―――。
もともと俺は、香藤の前では泣いてばかりだが―――ここまで脆く泣き崩れたのは、いつ以来だろう。
「キョウスケ・・・」
困惑しきった声を出す彼を、俺は見上げた。
「クラウディオ」
俺はしゃくりあげながら、恋人の名前を呼んだ。
クラウディオの腕の中で、クラウディオに守られて。
「俺で、いいのか・・・?」
みっともなく震える声に焦れながら、繰り返した。
「本当に、俺で?」
それだけ言葉を押し出すと、また涙でじわりと視界がぼやけた。
「・・・俺は男だぞ・・・?」
クラウディオが破顔して、俺の肩をぎゅっと抱きしめた。
重たいエメラルドの嵌った俺の左手を持ち上げ、うやうやしく指先にキスを落とす。
「俺を試すなと、言っただろう」
からかうような声の響き。
唇がそのまま俺の腕を這いのぼり、肩口に強く吸いついた。
「ん・・・っ」
真っ赤に咲いた、キスの痕。
クラウディオはそれを、満足げに見つめた。
それから鎖骨の下に、首筋に。
「おい・・・」
真新しい所有の刻印が、俺の身体を覆っていく。
その度に肌がざわついて、俺は思わず身体をよじった。
「・・・俺は、おまえがいいと言ったはずだ。男に二言はない」
「クラウディオ・・・」
「まさか男に求婚する日が来るとは、思わなかったが―――」
言葉を切って、クラウディオは笑った。
「惚れてしまったものは、しかたない」
憎らしいほど自信に満ちた、晴れやかな笑顔に幻惑されて。
俺はもう言葉もなく、クラウディオに見惚れた。
「それとも」
俺の頬に唇を寄せながら、クラウディオは囁いた。
いつだって俺の理性を失わせる、とびっきり低いセクシーな声で。
「・・・海賊の女房では、不満か?」
「ばっ・・・!」
俺は思わず、目の前の気障な男を睨みつけた。
「何を、バカな・・・」
頬に一気に血が上るのが、わかった。
臆面もなくこんなことを言ってのける男を、俺はひとりしか知らない。
―――ああやはり、これは香藤だ。
香藤が、俺の胸に戻ってきた。
俺はのろのろと両腕を上げて、クラウディオの首に巻きつけた。
「後悔するなよ・・・!」
あの嵐の夜、クラウディオが言った言葉。
俺はその台詞をそのまま返して、彼にくちづけた。
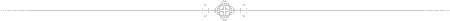
13 May 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月10日、サイト引越により再掲載。当時の原稿を若干加筆・修正しています。