第四章 (5)
☆ ☆ ☆
クラウディオのいない、ひとり寝の夜。
大きすぎる寝台に胡坐をかいて、俺は大きな高窓越しに月を見上げた。
青白い月光が冴え冴えと、だだっ広い城主の寝室を照らす。
部屋の片隅には、主のいないシェーズ・ロング。
・・・まあ、最近はあまり使われていないが。
「明るいな・・・」
俺は、そう声に出して呟いた。
クラウディオはいつも、何の前触れもなく姿を消した。
何処に行くのか、俺に言い置いて去ったことは一度もない。
最初からそうだったので、俺も何も言わなかった。
朝、寝台にひとり残されていたり、夕食の時になって不在を知らされたり。
告げられる状況はいつも違ったが、唐突に放り出される心もとない感覚は同じだ。
―――いつ、帰ってくるのか。
そう、聞けばいいのかもしれないが。
彼の出発を告げるルジェーロが、いつもほんの少しだけ、憐憫を滲ませて俺を見るので。
「そうか」
俺は結局なにも言えずに、あいまいに頷くしかなかった。
―――行ってくる、のひと言くらいあってもいいんじゃないか。
せめて、言えない理由を本人の口から聞ければ。
―――そうしたら俺は、簡単に丸め込まれてやれるのに。
そうは、思うが。
愚痴をこぼすのは、どうにも女々しいような気がした。
「・・・帰ってこないわけじゃ、ないしな」
自分に言い聞かせるように。
俺は無意識に、左手の中指の大粒のエメラルドに触れた。
ケレスの泪。
誓いなのだと、クラウディオは言った。
その言葉を疑うつもりは、ない。
「クラウディオ・・・」
―――何故なのか、自分でもわからないのだが。
香藤の不在は暖かいが、クラウディオの不在は寒い。
共に生き、重ねた年月の差なのだろうか?
香藤と暮らして、寂寥感など、感じたことがあったろうか。
「たいがい馬鹿だな、俺も・・・」
どこか心にぽっかり、穴が空いている感じだった。
こういう静かな夜は、広尾の家のことを思い出した。
いや、リビングから見える庭の情景か。
「・・・懐かしいな」
白い花水木はもう、とうに散り去っただろう。
剪定の加減が難しくてなかなか花をつけない藤は、今年は咲いただろうか。
この季節なら、去年の今ごろ香藤と一緒に買ったクレマティスが、ちょうど見ごろかもしれない。
「香藤・・・」
俺はそっと、その名前を呼んだ。
最近あまり呼ばなくなった、愛しい名前。
今だけは、誰に気兼ねすることなく口にできるから。
「・・・帰って来いよ・・・」
俺は、誰に言っているのだろう?
自嘲気味に、俺は笑った。
・・・不思議なことに。
香藤とふたりで建てた家を思い出し、痛みを伴った甘い感傷を味わっても。
そこに香藤をひとりで残してきたとは、思わなかった。
あの家には今、誰もいないはずだ。
―――香藤は、ここにいる。
数日したら、俺の腕の中に戻ってくるはずだ。
それだけは、揺らぎない確信だった。
クラウディオは、香藤ではないけれど。
それでも間違いなく、俺の香藤の心を持っているから。
香藤のいるところが、俺のいる場所だから―――。
「・・・思い出せよ」
俺を放って黙って出て行った男に、俺は語りかけた。
風ひとつない、しんと静まり返った夜。
そうっと指輪を、右手でなぞる。
「俺だけに記憶があるなんて、不公平だろ?」
俺にとってはこれは、香藤と歩く二度目の人生だ。
これはこれで悪くないが、できることなら、最初の人生を先に全うしたい。
―――最期まで、一緒に。
俺はまだ、その約束を果たしてはいないから。
「・・・なあ、香藤。早く、帰ろう・・・」
俺は窓越しの月を見上げて、ため息をついた。
☆ ☆ ☆
俺は、香藤に恋をする。
いつ、どこで、どんなかたちで巡り逢っても。
俺が何者であっても。
たとえ香藤が、別の名前で呼ばれていても。
―――そう、そして。
たとえ香藤が、俺を見ることを拒んでも。
それでも。
まるで遺伝子がそれを記憶しているかのように、どうしようもなく、香藤という男に引き寄せられる。
何度でも、繰り返し、香藤と恋に堕ちる。
香藤を愛し、香藤に愛されて、俺は俺になる。
それはもう、理屈ではなくて―――。
俺は、香藤に愛を捧げるために存在するのだと。
生涯を賭けて香藤を愛し、狂おしいほど求め、心の底から慈しみ、ありったけの情熱を注ぐために、生まれて来たのだと。
何の気負いもてらいもなく、素直にそう思った。
・・・そうとしか、思えなかった。
運命の絆とか、輪廻転生とか。
そんなものを信じているわけではなかったが。
俺は、香藤に恋をする。
何度も、何度も、恋をする。
それはもう、動かしがたい事実だった。
水が高いところから低いところに流れるように―――。
それが当然の理なのだと、思った。
☆ ☆ ☆
「船!?」
戻ってくるなりクラウディオが宣言したことに、俺は目を丸くした。
柔らかな夕陽の差す書斎の片隅。
俺は、窓際にずらりと並べられた深紅のソファの上にいた。
・・・そこで俺を発見したクラウディオに、のしかかられたままの体勢で。
彼の匂いが、俺を包み込む。
潮騒の匂い、饐えた汗の匂い。
そして、セックスに飢えた野獣の匂い。
―――いつの間にか、俺の脳裏に刻み込まれた匂いだった。
俺は、若い恋人の端正な風貌をじっと見つめた。
クラウディオが頭に巻いた天鵞絨(びろうど)の翡翠色が、残照に光る。
黒真珠と金の耳飾りが、俺の頬のすぐ傍でしゃらりと音を立てた。
いつものことながら、奇抜なファッションなのだが―――。
この男は、本当に何でも着こなしてしまうから不思議だ。
「本気で言ってるのか?」
温かい腕の中で、俺は呆れながら聞いた。
「あたりまえだ。どうして今まで思いつかなかったのか、不思議なくらいだ」
クラウディオが、甘い声で囁く。
ついばむようなキスの嵐が、頭上から降ってきた。
眩(まばゆ)いばかりの笑顔。
こんなに嬉しそうな顔をされると、見当違いの罪悪感が芽生えるが―――。
「・・・俺は航海のことなんて、何も知らないぞ。足手まといになるだけだ。だいいち、おまえの部下がそんなことを許さないだろう?」
「誰にも何も、言わせない」
クラウディオは、あっさり首を振った。
「おまえにもう、寂しい思いはさせたくないんだ」
その言葉に、俺ははっと顔を上げた。
・・・知っているのか。
彼の留守中、俺が独り寝を持て余していることを。
―――誰のご注進なのか、察しはついたが。
「嫌なのか?」
俺はそっと、嘆息した。
「・・・クラウディオ」
「ん?」
クラウディオが項から鎖骨へ、ゆっくりと指を這わせる。
馴染んだ肌を確かめるように。
「おまえのしていることに、口は出さないが・・・」
久々に味わう緩やかな愛撫に、俺は息が上がり始めていた。
肌が火照り、後ろが疼く。
しなやかな指がするりと、襟元の細い紐をほどいた。
「・・・ここで?」
俺は当惑して、小声でたしなめた。
・・・書斎は、剣の間の次に大きな、城の中核を占める広間だ。
かつては正餐の前の貴賓客のもてなしに使われただろう、きらびやかな空間。
たしかに片側の壁には、埋め込みの書架に、所狭しと古書が並んでいるが。
図書館というよりむしろ、応接間と呼んだほうがしっくり来るだろう。
視界を遮るものもない、奥行きのある場所。
もちろん、扉に鍵がかかるわけもなく―――。
「口は、出さないが?」
俺の抗議を微笑ひとつで却下して、クラウディオは先を促した。
彼の指が、露になった俺の乳首をそっと弾く。
「んん・・・っ」
―――今更なのは、わかっているが。
そこが愛撫を待ちわびて固くしこっているのが、どうにも羞恥心を煽った。
俺の身体が、クラウディオに否応なく反応するのが。
「・・・いやだ・・・」
ひょいと片眉を上げて、クラウディオが俯いた俺を覗き込んだ。
「何が、嫌なんだ? 今すぐここで俺と愛し合うことか? それとも、俺と一緒に船に乗ることか?」
したたる毒のような甘い声に、俺は首をすくめた。
俺は深く息を吸って、恋人の瞳を見つめた。
「・・・おまえが何者であろうと、俺はついていく。それはもう、決めたことだ。だけど―――だけど、略奪や殺人の片棒を担ぐのは、俺には・・・できない」
書斎を照らす残照は、まだ暖かかったけれど。
言った途端に肌が震えて、俺は思わず目を閉じた。
いつか言わなくてはいけないと、思っていた言葉。
初めて会ったときからずっと、心の奥底にわだかまりがあったから。
とうとう、言ってしまった。
―――『海賊の女房』失格かも、しれないが。
恋人の生き方を、俺はどうしても肯定できない。
クラウディオを失うかもしれない言葉―――ではないと、信じてはいるが。
「キョウスケ」
彼の人差し指が、俺の顎をついと押し上げた。
俺は吐息をついてから、そろりとクラウディオの顔を見た。
「そんな、悩ましい顔をするな」
俺の表情に何を見て取ったのか、クラウディオはふっと笑った。
彼の手が、怯えた子供をあやすように俺の髪を撫でた。
「・・・そうだろうな。おまえには、無理だろう」
優しい声だった。
「何もしないでいい。何も見なくていい。・・・キョウスケ」
セクシーに掠れた低い声が、俺の官能をかき立てる。
「おまえはただ、俺に抱かれて、愛に溺れていればいいんだ」
さらりと当たり前のことのように、クラウディオはそう言った。
そのまま、キス。
俺はソファの背に押しつけられたまま、クラウディオの貪るようなキスを受け止めた。
「・・・んふっ・・・」
骨も軋むほどのきつい抱擁に、陶然となりながら。
俺はのろのろと腕を上げて、クラウディオの背に回した。
―――そうだな。
何も考えないという手も、ありかもしれない。
おまえしか見えない馬鹿になるのも、悪くないな。
☆ ☆ ☆
「あふ・・・んっ・・・ぐっ・・・ふぁあっ」
「んん・・・キョウスケ・・・」
深紅のソファに浅く腰かけたクラウディオの太腿を、肩で押し拡げる要領で。
俺は書斎の床に跪(ひざまず)いて、彼の怒張を頬ばっていた。
熱いペニスが快感に震え、俺の口腔の粘膜を突き上げる。
溢れ出す先走りが、そのまま喉に落ちて行く酩酊感。
「んっ・・・」
この匂いも味も、どうしようもなく俺を興奮させた。
「・・・はっあぁっ」
俺はふっと口をはずし、快感に歪むクラウディオの顔を見上げた。
汗ばむ額、眉間に寄ったしわ。
乾いた唇をゆっくりと舐める、エロティックな舌の動き。
―――俺の愛撫に反応して、余裕を失いつつあるクラウディオ。
それが堪らなくて、俺は先端部分にねっとりと舌を這わせた。
ズキズキするほどの脈動。
根元に手を添えて、いちばん敏感な部分を、抉るようにこね回す。
射精を促し、何度も、何度も。
「・・・ふっ・・・」
緊張する引き締まった下腹部。
俺の後頭部に添えられたクラウディオの大きな手に、ぎゅっと力が入った。
・・・クラウディオ・・・!
俺にすべてを委ねる恋人への愛しさで、おかしくなりそうだった。
「んふっ・・・キョウ・・・くっ」
クラウディオが突如、腰を引いた。
張りつめた勃起が、勢いよく俺の口から引き抜かれた。
「ばっ・・・」
透明な液が、つうっと長い糸をひいて俺の唇を伝う。
それを手の甲で拭って、俺は目の前の濡れそぼったペニスを掴み直した。
「何を、して・・・」
吐息が乱れた。
―――全身が、クラウディオに貫かれたくて疼いていた。
上目遣いに、クラウディオを睨みつける。
「そんな顔を、するな」
肩で息をしながら、クラウディオが苦笑した。
セックスの快楽を堪えて、わずかに眉を寄せる。
「おまえが、巧すぎるんだ・・・もう、もたない」
長い指が、くすぐるように俺の前髪を撫でた。
「・・・だから」
いやいやをするように、首を横に振って。
俺はもう一度、ゆっくりと舌をペニスに這わせた。
「達っていいから」
とめどなく先走りを零して震えるそれに、キス。
ずっしりした重量感に、目眩がしそうだった。
「キョウスケ・・・」
「・・・いいから、飲ませろ」
言い捨てて、俺はクラウディオの灼熱を再び呑み込んだ。
「あ・・・っ」
食らい尽くすほどの、貪欲さで。
俺は目を閉じて、口内で暴れ回るペニスを堪能した。
舌と、唇と、歯を使って、いつも俺を翻弄する巨(おお)きなものを愛してやる。
―――それは俺には、香藤そのものだったから。
ぶるり、とクラウディオが胴震いした。
「ぅくっ・・・!」
筋張った腿を、ひときわ緊張させて。
クラウディオが腰を揺らめかせて、俺の喉の奥に熱を放った。
「・・・んんっ・・・っ!」
咽せかえるほどの迸りを受け止めて、俺はクラウディオの両膝にしがみついた。
全身が、燃えるように熱い。
クラウディオの大きな手が、ねぎらうように俺の背に回った。
「クラウディオ・・・」
陶然と、俺は恋人を見上げた。
「キョウスケ―――」
扇情的にかすれた、低い声。
濡れた視線が、挑戦的に俺をねめつけていた。
悠然と、ソファに座り直しながら。
「服を脱いで、ここに座れ」
クラウディオは人差し指で、トントンと自分の膝を叩いた。
軽い目眩に、襲われながら―――。
俺はうっそりと、立ち上がった。
書斎にはそろそろ、夕闇が落ちようとしていた。
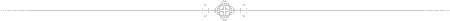
4 July 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月13日、サイト引越により再掲載。当時の原稿を若干加筆・修正しています。