第五章 (1)
海を見たのは、何ヶ月ぶりだろう。
俺は目を眇めて、はるかな水平線を見つめた。
アドリア海は凪いでいた。
―――いや、アドリア海だと、俺が勝手に見当をつけているだけだが。
見渡す限りの大海原。
うねる波がターコイズから群青に色を変え、穏やかにたゆたっていた。
舳先に打ちつける白波が弾け、陽光にきらめいて虹が生まれる。
ゆらり、と時おり船が大きく横にゆれた。
まるで悲鳴のように、船体がきしむ音がする。
そのたびに、甲板のどこかで大きな声が上がった。
陶然と、青い青い海の向こうを眺めながら。
「綺麗なものだな・・・」
ため息のように、俺は呟いていた。
照りつける厳しい日差し。
光と影の、鮮やかなコントラスト。
風向きが変わり、真正面から潮風が強く吹きつける。
―――クラウディオの匂い、だった。
いつの間にか、俺の身体に馴染んだ匂い。
ふと俺は天を仰ぎ、美しい帆船の高いマストに目をやった。
突き抜けるような晴天に、風をはらんだ帆がはためく。
強風に煽られながら、俺はじっとそれを見つめた。
「キョウスケ―――」
気配にまったく、気づかなかったので。
ぐい、と腰を引き寄せられて、俺は驚いて振り返った。
「クラウディオ!」
目を瞠った俺の鼻を、からかうようにつついて。
クラウディオが・・・いや、海賊『ソレントの堕天使』が、笑っていた。
目も覚めるような真紅のアラブ風の衣装に、同じ色のターバン。
オニキスと水晶をあしらった耳飾りが、風にゆれていた。
「いつまでここにいる気だ?」
「・・・派手な装束だな」
同時に話し始めたことに、気づいて。
俺は苦笑しながら、彼の太い腕に手をかけた。
「ここは風が、冷たい・・・」
「ほら、この手を離せ。部下が見てるだろう」
かみ合わない会話に、クラウディオが小さく笑った。
目じりに寄るわずかな皺が、何とも言えない色気をかもし出す。
―――俺は密かに、その精悍な美貌に見惚れた。
「そういう目で見るな―――」
甘えるように額を擦りつけながら、クラウディオが低い声でささやいた。
俺を抱く腕を緩めるどころか、いっそ正面から包み込んで見据える。
力強い抱擁。
「どんな目だと・・・」
その瞬間。
ゆらり、と船が大きく横揺れした。
「うわ・・・っ」
わずかにバランスを崩した俺を、難なく支えて。
クラウディオは、したたるような笑顔を見せた。
「よく似合うな」
若い恋人の指先が、俺の襟元のレースを確かめるようにつまんだ。
「・・・冗談だろう」
俺は大げさに眉をしかめて、自分の姿を見下ろした。
ピジョン・ブラッド色に鈍く光る、タフタのドレス。
ところどころに繊細な黒レースがほどこされた、素人目にもわかる凝ったデザイン。
―――たしかに、美しい衣装かもしれないが。
好きで着ているわけではない。
無理やりクラウディオに押しつけられて、やむを得ず身にまとっているだけだ。
「・・・今さら女の格好をしたところで、何の意味がある?」
俺は呆れ半分に、つぶやいた。
彼の部下たちはとうに、俺の正体など知っているだろうに。
「それもこんな、高価そうな・・・」
「それはもう、聞き飽きた」
「だいたい、女は船に乗せないって―――」
「おまえは男だろう?」
「・・・なら、どうしてこんな」
俺は憮然と、聞き返した。
「珍しく、文句が多いな」
からりと笑って、クラウディオは俺の瞳を覗き込んだ。
「もう何も言うな。そのドレスは既婚者の証だ。今のおまえに、相応しいだろう?」
そう言いながら俺の左手を取り、『ケレスの泪』を撫でる。
「クラウディオ・・・」
彼の指を、ひどく由緒ありげな血珊瑚の指輪が飾っていた。
『イアシオンの誓約』という、大層な名前がついているらしい。
普段、城内ではあまり身につけていないのだが。
それは、『ケレスの泪』と対の指輪なのだと聞かされていた。
俺は苦笑して、彼を見返した。
「キョウスケ・・・いや」
さも可笑しそうに、クラウディオがくしゃりと顔をゆがめた。
子供を宥めすかすように、俺の髪を撫でる。
「今はエレナ姫と呼ぶべきだろうな」
「・・・冗談じゃない」
俺はもう一度苦笑して、くるりと踵を返した。
「部屋に戻ろう。・・・風が冷たい」
☆ ☆ ☆
クラウディオに導かれて、俺は彼の船室に戻った。
海賊の首領の部屋、といっても。
驚くほど質素な作りで、むしろ殺風景なほどだった。
俺はさっさと忌まわしいドレスを脱ぎ捨て、普段着でほっと息をついた。
硬い木の椅子に腰かけ、ぼんやりと窓の外を眺める。
クラウディオは黙って、寝台の上に海図を広げていた。
奇妙に穏やかな時間。
状況を考えれば、不思議な気分だった。
アドリアーナがいない。
今朝それに気づいたときの恐慌が、嘘のようだった―――。
俺を断固として「エレナ姫」と呼び続けた、アドリアーナ。
どこまでもフェラーラの王女に忠実な侍女長。
いつも必ず、側にいた。
身を挺して、俺を守ろうとしたこともある。
たとえそれが、彼女の大事な「エレナ姫」のためだとしても。
俺にとって、この異世界で唯一、ほんとうに味方だと思える人間だった。
・・・クラウディオは、別格として。
そのアドリアーナが一言もなく城を抜け出したことに、俺は衝撃を受けた。
いや、戦慄した。
彼女は確かに、俺に忠実ではあったが。
香藤―――いや、クラウディオを頑として、受け入れようとはしなかったから。
俺の心が何処にあるか、知っていたから。
俺が『ケレスの泪』を受け取り、クラウディオの居室で暮らすようになっても。
アドリアーナは絶対に、彼の存在を認めなかった。
『お姫さまには、シチリアに婚約者殿がおいでなのですよ』
嘆息しながら、そう言われるたびに。
俺は、不可解な罪悪感に囚われたものだ・・・。
『おまえのせいじゃない』
アドリアーナ出奔の報を受けたクラウディオは、冷静だった。
出航の日取りを予定より早めると、淡々と部下に旅支度を命じた。
まるで、いつかこんな日が来ることを予期していたかのように。
『おそらくフェラーラに向かったんだろう。おまえの救出を画策するために』
『クラウディオ・・・』
『心配するな。フェラーラ軍が攻め込んで来る頃には、この城はもぬけの殻だ』
黙って首を振る俺を、クラウディオは抱き寄せた。
『どうした?』
『―――道中、何かあったら・・・』
女ひとりで、あの暗い森に入ったのか。
ここからフェラーラ公国への道のりも、知らないだろうに。
『危険な長旅になるが・・・腕の立つ女なのだろう?』
『それは・・・』
俺は頷いた。
『厩舎から馬が一頭消えている。おそらく丸腰でもないだろう。たちの悪い夜盗にさえ出くわさなければ、何とか生き延びられる。後はせいぜい、強運を祈っておくんだな』
突き放したような言い方だが。
実際ほかにできることなど、あるはずがなかった。
俺は黙って、泰然としたクラウディオを見上げた。
人質が脱走したことで、城内は騒然としていた。
ひょっとしたら、俺が手引きして逃がしたと思われているかもしれない。
その考えに今さらながら思い至って、俺は眉をしかめた。
クラウディオが、俺を妻だと宣言した後も。
部下の中には、もともと囚われの身の俺を認めない古参もいると、ルジェーロから聞かされている。
安易に城内のものを信用するなと、さりげなく忠告されたときのことだ。
アドリアーナ出奔で、クラウディオの立場が悪くならなければいいが―――。
『・・・そうだな』
俺は悄然と頷いた。
何もできない自分が、もどかしい。
『気に病むな』
俺の表情を覗き込んだクラウディオが、ふと笑顔を見せた。
『―――それとも、別の心配をしているのか?』
『え・・・?』
笑顔のまま、彼は俺の髪を撫でた。
『おまえは俺のものだ。誰が何と言おうと、手放す気はない』
わかっているだろう、と念を押されて。
俺は言葉もなく、クラウディオの胸に顔を埋めた。
☆ ☆ ☆
翌日は、大時化(しけ)だった。
季節はずれの嵐に、どす黒い海がうねり、弾け、襲いかかる。
帆船は朝から、押し寄せる荒波に翻弄された。
―――いっそ、船が砕け散るのではないかと思うほど。
激しい雨で、天はうっそうと暗いままだった。
音が―――とどろく波の打ちつける音が、耳をつんざく。
船体が軋み、ぐらりと揺れた。
クラウディオは夜明け前に部屋を飛び出したきり、戻らない。
おそらく、必死の舵取りの指揮をしているのだろう。
甲板からは、大勢の男たちの怒号がかすかに聞こえた。
出航してから数日間、穏やかな海上の生活が続いていたので。
俺はそれが当然なのだと思っていた。
甘い認識だったと、今になって思い知った―――。
「ぐ・・・っ」
胃液が逆流するような、激しい嘔吐感。
ひどく胸がむかつき、えづきが治まらない。
「・・・ううっ・・・」
主のいない部屋で、俺は喉を掻きむしった。
脂汗が流れ、目眩がした。
揺れがひどくて、立っていることも座っていることもできない。
・・・船酔いなど、とにかく初めての体験で。
黙って耐える以外、どうしたらいいのかわからなかった。
寝台の脇にうずくまって、吐き気に上半身を捩りながら。
俺は目を閉じて、ひたすら浅い呼吸を繰り返した。
どれだけの時間が、経ったのだろう。
「あ・・・っ」
ガクリ、と船が大きく揺れた。
床が軋み、右舷に傾く。
朦朧としていた俺は、ふと顔を上げた。
背中をさする、大きな手の感触。
「キョウスケ」
いつの間にか俺のすぐ隣りに、クラウディオが跪いていた。
心配げな薄茶色の瞳が、至近距離でゆらめく。
その顔には、隠しようのない疲労の色が浮かんでいた。
「クラウディオ・・・」
安堵で声が掠れた。
全身からすうっと、力の抜けていく感覚。
弛緩した俺の身体を抱きとめて、彼はゆっくりと俺を起こした。
「キョウスケ」
「・・・クラ・・・」
俺はいいから、部下たちのところに戻れ。
そう言ってやりたかったが、情けないことに言葉にならなかった。
「何も言うな」
低くそう言って、クラウディオは俺を寝台に座らせた。
俺の手を握り、しっかりと指を絡める。
やさしい仕草だった。
「海に慣れていてもこの時化は辛い。おまえがこうなるのは、あたりまえだ」
労わる言葉に、頷きかけた途端。
「うぐっ・・・」
再び襲った嘔吐感に、俺は身体を折った。
「・・・いいからっ」
船酔いでふらふらしながら吐くさまなど、見せたくはない。
俺は無意識のうちに、支えるクラウディオの腕をはね退けていた。
―――えづいたところで、もう何も出ないのだが。
生理的な涙を零しながら、俺は俯いた。
「キョウスケ」
顔を逸らせて荒い息をつく俺の身体を、クラウディオがきつく抱き寄せた。
「・・・ぃやだっ・・・」
身体を強張らせる俺に、驚いたのか。
クラウディオは力任せに俺を寝台に押さえつけ、汗に濡れた髪をすいた。
ジャラリ、と彼の耳飾りが音を立てる。
「どうした。何が嫌なんだ」
優しく問いかけながら、彼がそっと顔を近づける。
くちづけの予感に、俺は必死で顔を振った。
「やめろ、クラウディオ・・・ッ」
身体に力が入らないが、それでも夢中でもがいた。
「キョウスケ?」
「やめてくれ・・・!」
「落ち着け、キョウスケ。何が、気に入らないんだ?」
「こんな・・・っ」
情けなさに、やりきれない思いだったが。
「・・・汚・・・いっ・・・」
苦しい息の下で、俺はそれだけ告げるのが精一杯だった。
「・・・おまえは、馬鹿か」
動きを止めて、クラウディオは俺をまじまじと見下ろした。
太い腕が俺を捉え、絡め取る。
―――そのまま、ごく自然に。
クラウディオは、俺にねっとりとくちづけた。
「・・・んふっ・・・」
俺の抵抗をいとも簡単にねじ伏せて、彼の舌が俺の唇をこじ開けた。
悠々と、いたずらな舌が口腔に侵入してくる。
いつもと変わらない、深い長いキス。
熱く咥内をまさぐられて、俺はあきらめて目を閉じた。
「んん・・・っ」
ひとしきり、俺の口を蹂躙してから。
満足したように、クラウディオは唇を離して俺を覗き込んだ。
ニヤリ、と微笑する。
「やめろと、言ったのに―――」
いたたまれなくて、俺は小さな声で抗議した。
身震いするほどの羞恥。
「・・・何を気にしているのか、知らないが」
ため息をついて、クラウディオは肩をすくめた。
「おまえのもので汚いなんて感じるものは、何もないぞ?」
さらりとそう言って、微笑する。
俺は驚愕して、年若い恋人を見上げた。
―――その台詞は、いつか俺が・・・。
遠い記憶が幻のように甦った。
今の俺と同じ状態の香藤に、かつて俺が言った台詞。
「あたりまえだろう。おまえのすべて、俺のものなんだから」
「クラウディオ・・・」
覚えず、俺は唇を震わせた。
「違うか?」
余裕の笑みを浮かべて、クラウディオが問いかける。
―――香藤の記憶を、持たない男。
それでもクラウディオはこうして、俺たちの関係を、本来あるべき姿に近づけてくれるのか。
・・・目頭が熱くなった。
「おい、キョウスケ?」
首をかしげるクラウディオの顔が、涙で滲んだ。
ぐい、と手の甲で顔を拭うと、俺はそのまま彼に抱きついた。
愛おしさに、気が狂いそうだった。
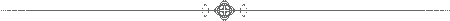
23 September 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月19日、サイト引越により新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。