第五章 (3)
「んあ・・・っ」
ゴポリと、どうしようもなく卑猥な音を立てて。
クラウディオが、二度目の精を吐き出したペニスをゆっくりと引き抜いた。
体内にぽっかりと、空洞が生まれた感覚。
濡れた肛門に、冷たい夜風があたる。
じんじんと疼いたままの柔襞が、驚いたようにきゅうっと収縮するのがわかった。
「キョウスケ・・・」
ぐったりと倒れ込んだ俺を、クラウディオが背後から支えた。
身体を裏返されてようやく、恋人の顔が目に入った。
額にうっすらと汗の浮かぶ、愛しい男の笑顔。
俺はそれを、美しいと思った。
―――キスが欲しい。
俺は緩慢に、腕を伸ばした。
ねだるような顔をしていた、かもしれない。
「可愛いな、おまえは」
何とも嬉しそうに笑って、クラウディオは俺にくちづけた。
深い、だけど穏やかなキス。
「んん・・・」
執拗に絡まる舌が、気持ちいい。
クラウディオの大きな手が、やさしく俺の全身をなぞる。
労わるように、名残を惜しむように―――。
うっとりとキスに酔いながら、俺は彼の腕の中で身体を弛緩させた。
「後始末も、できないな・・・」
ねっとり俺の尻をまさぐっていたクラウディオが、大真面目に眉をしかめた。
「・・・当然だろう。こんなところで―――」
恥ずかしさに真っ赤になりながら、俺は小声で応じた。
久しぶりのセックスに夢中になったのは、彼だけではない。
―――できることなら、もっともっと愛し合いたい。
クラウディオを渇望する自分に、俺は苦笑した。
「バカ・・・」
「うん?」
クラウディオが、目を細める。
おまえのことじゃない、という言葉を俺は呑み込んだ。
―――素直じゃないな。
呆れ半分で、俺はそっと天を見上げた。
相変わらずの、凛とした月夜。
蒼い月光が、冴え冴えと甲板を照らしていた。
「え・・・」
見るともなく、漫然と辺りを見渡して。
俺はそこで、思わず硬直した。
「え・・・?」
船内から甲板に上ってくる、狭い階段の陰に。
舵の向こうの、太い縄が山積みされているあたりに。
―――何人もの人影があった。
クラウディオの部下たちが遠巻きに、食い入るようにこちらを見ていた。
「・・・!!」
月の光がスポットライトのように当たり、彼らの表情までも鮮明に判別できる。
頬が一気に、火照るのがわかった。
「・・・クラウディオッ」
押し殺した声でクラウディオを呼び、俺は彼の手を握りしめた。
「どうした?」
身体を強張らせた俺の視線を辿って、クラウディオが顔を向ける。
その途端、男たちはそわそわと身じろぎした。
ギクリと顔を逸らす者、そそくさと姿勢を変える者。
うごめく人影を、俺は凝視した。
―――いったい何人、いるのだろう。
いつからそこに、いたのだろう・・・!?
覚えず、身体が震えた。
考えるだけで、羞恥で目が眩みそうだった。
「・・・覗きとは、いい趣味だ」
悠然と、クラウディオが笑った。
「おまえの声は、どうにも色っぽいからな―――」
俺の肩を抱き寄せて、ため息のように囁く。
「女を陸(おか)に置いてきた連中には、堪らないだろう」
むしろ誇らしげな口調。
「せいぜい指を銜えて、見ていればいい」
まったく動じる気配のない恋人を、俺は呆然と見返した。
「あのなあ―――」
そういう問題じゃ、ないだろう。
たしなめようとして、俺はふいに脱力した。
「わかるわけ、ないか・・・」
―――今さらこの男に、何を言っても無駄だ。
この状況を恥ずかしいと感じない人間に、俺のいたたまれなさは理解できないだろう。
俺は嘆息して、クラウディオを見上げた。
「なんだ?」
愛情にあふれた、優しい瞳が俺を見返す。
「・・・部屋に戻ろう」
俺はそれだけ言うと、目を閉じて身体を恋人にゆだねた。
実際のところ、疲労困憊して、とてもまともに歩けそうにない。
返事の、代わりに。
俺を抱く逞しい腕に、力がこもった。
☆ ☆ ☆
闇に融けるブルー・シフォンが、しゃらりと音を立てる。
柔らかい布地が、俺の全身を覆い隠していた。
―――ドレスを着せられていることをありがたいと思ったのは、初めての経験だった。
居並ぶクラウディオの部下たちの、興味深げな視線。
いや、好奇心むき出しの視線、というべきか。
生々しい欲望を滲ませた、せわしない呼吸音。
居心地の悪い、べとついた無言。
その中を、恋人の腕に抱きかかえ上げられたまま、進んでいく。
どうしようもない羞恥心で、頬が火照った。
クラウディオは、涼しい顔だ。
衆人環視の甲板から、船内に戻る階段を降りる。
周囲のあからさまな戸惑いを、見事なまでに無視して。
腕の中の俺をものともせず、悠々と自室に向かった。
ずっと瞳を閉じたままでいれば、よかったのだが。
ざわめく肌の焦燥に負けて、俺はうっすらと目を開けた。
その瞬間。
「あ・・・」
俺たちを食い入るように見つめるニコと、眼が合った。
「・・・っ・・・」
ぎらついた、思いつめたまなざし。
―――これは、どこかで・・・?
背筋を、ゾクリと寒気が伝った。
それは、天からこぼれ落ちて来たような既視感だった。
「どうした?」
身体を強張らせた俺に気づいて、クラウディオが低く尋ねた。
「なんでもない・・・」
忌まわしい連想を忘れたくて、俺は小さく首を振った。
☆ ☆ ☆
それから数日は、穏やかな日々が続いた。
海に慣れる―――とまでは、いかないかもしれないが。
なんとか波と折り合いをつけて暮らす方法を、身体が覚えた感じだった。
クラウディオや他の男たちと違って、俺にはこれと言った仕事がない。
居心地の悪い客分のようなものだ。
うろついていても邪魔になるので、特に呼び出されない限り、クラウディオの居室にいることが多かった。
ひとりで過ごす時間には、慣れていた。
クラウディオは日中たいてい、甲板に出ている。
たまに俺をからかいに戻って来るが、長居はしない。
―――ペットの様子を見る、ようなものか。
俺は何冊か置いてある本を読み、海図を紐解いて眺めた。
小さな窓の外から、果てしない大海原を眺めたりもした。
単調な生活。
だが、考えてみれば、クラウディオの城にいたときと同じことだ。
不満はなかったが、ひとりでいると碌なことは考えない。
海が荒れればクラウディオの身を案じ、そうでないときは、香藤のことに思いを馳せた。
―――会いたい。
ときおり、痛切にそう思った。
ここにはクラウディオがちゃんといるのに、と頭では思うのだが。
そう思うたびに、心が悲鳴を上げた。
香藤の笑顔、その笑い声。
甘える仕草と、拗ねたときの表情。
恋しくて、恋しくて堪らなかった。
―――違う、違う、違う。
クラウディオを、愛している。
彼も全身全霊をかけて、俺を愛してくれている。
それなのに、クラウディオは、俺の香藤にはなり得ない。
香藤なのに、香藤ではないのだ。
「いつまで、続くんだろう・・・?」
クラウディオが、今の俺の幸せだ。
離れたくはない。
心から、そう思っているのに。
「いつまで俺は、香藤なしで生きていけるんだろう―――」
これは矛盾だ。
俺の手の届くところにいるのに、誰よりも遠い恋人。
相反する感情が、せめぎあう。
・・・最高に甘美な悪夢を見ている、そんな気分だった。
☆ ☆ ☆
「エレナ姫」
食事を運んできたアンジェロが、ふと口を開いた。
「うん?」
俺は首を傾げて、先を促した。
「あの―――」
ニコとアンジェロ。
どちらもクラウディオの側近だった。
城で俺の面倒を見てくれたルジェーロは、船に乗らない。
留守居役ということだろう。
航海に出てからは、主にニコとアンジェロが、俺の世話役を任されていた。
・・・世話、と言っても。
船の中では、陸のような贅沢ができるわけじゃない。
食事の準備と、衣服の支度。
そのくらいだが、余計な手間には違いないだろう。
首領の女の世話をさせられている事実を、どう思っているのか。
俺には知る由もなかったし、彼らはめったに口を利かなかった。
―――まあ、好かれてはいないだろうな。
俺は、その程度の認識でいた。
改めて話しかけられるのは、初めてだったかもしれない。
「ニコのこと、ですけど」
感情を読ませないクールな表情で、アンジェロが言った。
その突き放した口調は、本当に小野塚くんそのものだ。
「なに?」
俺は苦笑を堪えながら、彼を見返した。
「・・・あいつは、もの凄く馬鹿だから。あまり刺激しないでやってください」
にべもなくそう言うと、アンジェロはさっさと立ち上がった。
「え・・・?」
「じゃ、失礼します」
くるりと踵を返した彼に、俺は呼びかけた。
「アンジェロ、それは・・・」
ちろり、と振り返った彼が小さく笑った。
「意味は自分で、考えてください」
ゲームを面白がっているような、そんな口ぶり。
俺は面食らって、黙って彼の背中を見送った。
☆ ☆ ☆
朝から雨が降っていた。
海が黒く濁り、波が不機嫌にうねっていた。
「・・・ぁぐっ・・・うう・・・っ」
帆船の揺れには、大分慣れてきたつもりだったが。
俺はその日、気分がすぐれずに寝台にいた。
前回の船酔いほど、症状は酷くなかったが。
それでも胃のむかつきが治まらず、毛布の下で丸くなっているしかなかった。
「ん・・・っ」
クラウディオは、いない。
悪天候で、舵取りに苦労する手下たちを気遣って、甲板へ出て行ったきりだ。
甘えてはいけないのは、わかる。
船の上では、誰もが一蓮托生だ。
・・・そこに彼のぬくもりがないのが、寂しくはあったが。
我が儘を言ってる場合ではない。
でも―――。
戻らない恋人の帰りを待ちながら、俺は疲弊して目を閉じた。
「・・・姫、エレナ姫」
躊躇いがちの小さな呼びかけに、俺は目を醒ました。
鼻先を、美味そうな食べものの匂いがくすぐった。
「・・・ニコ?」
俺はのそりと起き上がって、寝台の脇に膝をついた青年を見下ろした。
心配げに、俺を見るまなざし。
「スープをお持ちしました」
「ああ・・・」
途端に、俺は空腹を意識した。
具合が悪かったせいで、朝から何も口にしていない。
「何か食べたほうがいいと、首領が―――」
重い頭を振って、俺は頷いた。
「そうだな。ありがとう」
それ以上、言葉は続かなかった。
窓の外には、黒い深い闇。
雨がまだ降っているのかどうか、わからなかった。
差し出された熱いスープのボウルを、俺は緩慢に受け取った。
黙って、匙ですくって食べ始める。
ニコも何も言わず、じっと俺の口元を見ていた。
普段は穏やかな、礼儀正しい青年なのだが。
瞳の奥にひそむ熱が、俺を不安にさせる。
―――思い出したくもない事件。
ぎこちない空気に、俺は嘆息した。
「・・・ニコ」
「はい?」
後はひとりで大丈夫だから、退出していいよ。
そう言うつもりで、俺は顔を上げた。
と、そのとき。
ドシン、という鈍い音が外から聞こえ、帆船がぐらりと傾いた。
「うわ・・・っ!」
大波が砕ける轟音。
「エレナ姫!」
俺の手から滑り落ちたボウルが跳ねて、シーツの上に転がった。
慌てて身体をずらしたが、遅すぎた。
「ひ・・・っ」
はずみで熱いスープが、俺の胸から腹に飛び散る。
「あつ・・・っ」
「姫!?」
仰天したニコが、シーツを掴んで俺の身体を拭こうとした。
彼の指が、俺のシャツに触れる。
その瞬間。
「やめろ・・・っ」
俺は咄嗟にその腕を跳ね除(の)けて、叫んでいた。
どうしようもない嫌悪感に、鳥肌がたった。
「なに・・・!?」
ニコが驚愕して、俺を見つめた。
あの羽田のホテルでの一件。
忘れようはずがない、忌まわしい記憶。
・・・ニコは、宮坂くんじゃない。
そう思う理性は、何の役にも立たなかった。
あの視線、あの息遣い、あの声。
思い出すだけで、全身がおぞましさに震えた。
「なんで、そこまで・・・」
ニコの声が、ふと低くなった。
ぎらつく目つきが、彼を傷を負った獣のように見せていた。
寝台に上半身を乗り上げた姿勢のまま。
「―――嫌われるようなことは、何もしてないだろう?」
がらりと変わったその口調には、怒りが満ちていた。
俺の過剰な拒絶に、衝撃を受けたのか。
それとも、俺のひそかな怯えに気づいたのか。
睨みつける視線を、逸らさずに。
ニコはゆっくりと、俺の―――俺とクラウディオの寝台に膝をついた。
大きな男の指が、俺の顎を捉える。
「・・・やめろっ・・・」
激しい嫌悪感に身震いして、俺は後ずさった。
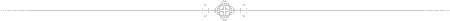
26 November 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月22日、サイト引越により新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。