第五章 (5)
紅い月が出ていた。
波を受けて、ぎしり、みしり、と帆船が揺れる。
不安定な船底にいるような、心もとない感覚。
「・・・ん・・・」
俺はクラウディオの腕の中で、ようよう目を醒ました。
温かい抱擁、確かな鼓動。
恋人は規則的な寝息を立てて、よく眠っていた。
俺は嘆息し、そっと身体を捩った。
クラウディオの甘やかな吐息、しんなりと額を覆う薄茶色の髪。
健やかな若い男の寝顔を、俺は瞬きもせずに見つめた。
「香藤・・・」
声に出せない名前を、唇の先に乗せる。
先刻の刃傷沙汰を、俺は心の痛みとともに反芻した。
血飛沫(しぶき)と、低い唸り声。
鬼神のような形相のクラウディオ。
―――あれは、不可避だ。
繰り返し、俺は自分に言い聞かせた。
クラウディオの立場と生きている時代を考えれば、きっと当然のことなのだろう。
衝撃的だったが、それは俺にも理解できた。
ニコが指を切り落とされただけで済んだのは、稀有の僥倖なのだと。
首領の処置は、むしろ甘いくらいなのだと。
船上の誰もがそう囁き交わしていると、夕刻、アンジェロがそっと教えてくれた。
おそらくそれは気休めではなく、本当にその通りなのだろう。
アンジェロが、謝意を滲ませてそう報告したとき、俺は何も言わなかったが。
いや、何も言いようがなかったが。
・・・俺には痛いほど、わかっていた。
クラウディオを止めたのは、俺じゃない。
―――思いがけない胸の痛み。
あれほど激怒していても、彼は冷静な判断力を失ってはいなかった。
彼自身の自制心が、あそこで剣を降ろさせたのだ。
わずかな自嘲とともに、俺はそれを確信していた。
無力感は、拭いようがなかったけれど。
「・・・そうか・・・」
否応なく、俺はあのときの香藤の反応を思い起こしていた。
宮坂くんのことを香藤に打ち明けた、あの北海道の夜。
『殺す!』
血相を変えてそう唸った香藤は、凄まじい怒りに震えていた。
筋肉が鋼のように強張り、俺を弾き飛ばしそうな勢いで。
全身が痙攣するほどの激情。
あれが本物の殺意だったことを、俺は知っている。
―――いつだって穏やかで、懐の大きい香藤。
何があっても現実から目を逸らさない、そんなしたたかさを持った男。
ああいうふうに度を失うところなど、今まで見たことがなかった。
「もしかしたら・・・」
俺はずっと、あの激昂した香藤を、すんでのところで押しとどめたと思っていた。
東京に帰ってからも怒りの鎮まらない恋人を、必死で宥め、制止したつもりでいた。
が―――。
「・・・ちがう、のか?」
俺はそれに思い至って、慄然とした。
クラウディオを止めたのが、最終的には、彼自身の冷静さであったように。
香藤もまた、あの激しい殺意をねじり伏せたのは、俺の言葉のせいではないのかもしれない。
香藤自身が、超えてはならない境界線を見失わなかった。
そういうことなのかもしれない。
逆巻く憎悪に、目が眩んでいるのだとあのときは思っていたが。
それでも香藤は、後戻りできなくなるギリギリのところで踏みとどまった。
―――俺の力じゃない。
思い上がったつもりはないが、今なら、それがわかる。
あれは香藤の、香藤自身の、強靭な精神力のなせる業だ。
・・・そして、それは―――。
「ああ・・・」
究極には、俺のため、なのだろう。
身を切られるほどの切ない想いに、胸が痛かった。
香藤も、そしてクラウディオも。
愛に突き動かされ、愛に赦しを余儀なくされる。
まっすぐに俺を見つめて、正々堂々と俺を愛おしみ、誠意の限りを尽くしてくれる。
俺のために怒り、俺のために堪える。
・・・大きい、と思った。
どちらも、俺には不相応なほどの果てしない愛情を、惜しむことなく与えてくれる。
「どうしたら―――」
香藤と、それからクラウディオ。
香藤であり、クラウディオでもある恋人。
どうすれば俺は、与えられるありったけの想いのほんの一部でも、彼に返すことができるのだろう。
どうしたら、それだけの愛情に応えられるのだろう・・・。
愛されるほどに、もどかしい。
クラウディオの胸に抱かれて、俺はぎゅっと目を閉じた。
☆ ☆ ☆
「ん・・・」
肌をまさぐる熱い手のひらの感触で、俺は目覚めた。
「・・・クラウディオ?」
ぐいっと、腰に回った腕に力が入る。
至近距離で、はらはらと薄茶色の髪が降りかかった。
さらさらと、絹糸が零れるような。
それを緩慢にかきあげて、俺は恋人の瞳を探した。
「・・・もう朝か?」
「ああ」
窓の外を見ようと、身体を少し捻ろうとした途端。
顎を掴まれて、俺は目を瞠った。
「・・・んっ」
突然の熱いくちづけに、息を奪われる。
俺はゆっくり目を閉じて、クラウディオの太い首に両腕を絡ませた。
起きぬけには辛いほどの、長いキス。
俺は胸を喘がせて、終わらないキスに応えた。
「・・・ふぁっ・・・」
ぎゅっと、抱擁がいっそうきつくなる。
クラウディオが、滾る下半身を俺の股間に擦りつけてくる。
あからさまな求愛の仕草。
それなのに、いつもと何かが違った。
・・・違う気がした。
求められているのは、セックスではなくて―――。
「・・・どっ・・・した?」
息を継ぐ間をぬって、俺は小さく聞いた。
見上げると、クラウディオの瞳が揺れている。
「キョウスケ・・・」
不安ではなく、恐れでもなく、ただ―――。
漠然とした居心地の悪さ、だろうか。
俺の態度が気になる・・・?
―――昨夜の一件のせいで、ということだろうか・・・?
いつも傲慢なほど、自信に満ちあふれたクラウディオ。
その彼が見せた思いがけないゆらめきに、俺は目で微笑した。
「キョウスケ・・・」
もう一度、確かめるように名前を呼ばれて、俺は頷いた。
愛している、と告げる代わりに。
俺は黙って両手を伸ばし、クラウディオの下半身を探った。
力強い腰骨を摩り、筋肉の弾力のある腹を辿り、茂みをそっと愛撫する。
薄い下着の下で、熱を持ち始めているペニス。
「・・・ん・・・」
愛しくて仕方のないそれに、指を絡めた。
「キョ・・・」
瞳を閉じて、クラウディオが俺の肩に顔を埋める。
熱い舌が俺の首筋をねっとりと舐め、柔らかい肌にキスを落とす。
もう一方の腕が、俺の身体をしっかりと抱き寄せる。
「んあ・・・っ」
項に噛みつかれる感触に、俺は全身を震わせた。
俺の手の中で、ペニスがどくん、と脈動する。
濡れた先端が力を得て、更なる刺激を欲しがる。
―――そのすべてが、愛おしかった。
生々しい男の欲望に、肌が火照る。
「クラウディオ・・・」
俺はうっとりと、恋人の名前を呼んだ。
キスが欲しくて。
何も考えられないほど、めちゃくちゃに愛されたくて。
応えるように、クラウディオの唇が頬に触れる。
「・・・んんっ・・・」
俺は顔をずらして、その唇を塞いだ。
明け方の光が、弱々しく寝台に差していた。
海は穏やかで、船はほとんど揺れていない。
俺たちはほとんど言葉を交わさず、ただ怠惰な朝のセックスに溺れた。
「泣くな、キョウスケ・・・」
何度か、そう囁かれたのは記憶にある。
なぜ泣いたのか、俺には思い出せなかった。
とにかく考えることを、放棄したかっただけかもしれない。
執拗に愛されて、何もわからなくなって。
暖かい腕の中で、意識を飛ばしてしまいたかった。
言葉にならない想い。
拭いきれない寂寥感。
それを正視するのは、辛かったから。
身体で誤魔化していいときも、あるはずだ―――。
そう、自分に言い聞かせて。
快楽だけを求めて、俺たちは何度も抱き合った。
☆ ☆ ☆
「視界が悪いな」
その日は朝から、霧雨が降りしきっていた。
甲板から戻ったクラウディオが、眉をしかめてそう言った。
疲れたような顔色。
小さな木机に腰かけていた俺は、上半身を捩るように彼を見上げた。
「少し、眠ったほうが―――」
ここ数日、帆船が安定しないらしくクラウディオたちは操舵に四苦八苦していた。
船体に破損があるのか、何か物資が不足しているのか。
どの程度、危険な状態なのか。
俺は何も、知らされていなかった。
昼夜を問わず、クラウディオは部下に呼び出されることが多くなった。
もう何日も、まともに寝てはいないだろう。
「・・・休まないとよくない、クラウディオ」
「ああ」
俺の顔色を読んで、クラウディオが微笑した。
「心配するな」
そう言って、座ったままの俺を後ろから抱き寄せる。
「でも・・・」
クラウディオの指が、俺の着ている灰褐色のドレスのレースをなぞった。
つう、と首筋を軽く愛撫する。
「こら」
俺は苦笑して、その悪戯な指先を掴んだ。
大きな手のひらには、無数の傷があった。
赤く乾燥したひび割れと、ひどい擦過傷。
爪の先にも、どす黒い油のようなものがこびりついている。
甲板で作業している間に、ついたものだろう。
「キョウスケ」
眉をひそめて男の手を見つめる俺に気づいて、クラウディオが苦笑した。
「すまないな」
「・・・バカ」
手を引こうとしたクラウディオを制して、俺はその傷だらけの手にくちづけた。
「キョウスケ・・・」
痛々しく肌の剥けた指の一本一本に、丁寧にキスをする。
これで傷が癒えるものならば―――。
それから、鈍く光る血珊瑚の『イアシオンの誓約』にも。
「おまえは、本当に・・・」
クラウディオの声が甘く掠れた。
どこかで、爆発音がしたような気がした。
ドォン、と鈍い轟音―――大砲のような・・・?
次の瞬間、帆船はいきなり激しく横揺れした。
「・・・!?」
その衝撃に、俺は木机から吹っ飛ばされそうになる。
「うわ・・・っ」
咄嗟に、クラウディオが俺を横抱きにしてよろめいた。
すぐ後ろの寝台に、二人して背中から倒れ込む。
「な・・・んだ!?」
俺がクラウディオを覗き込んだ途端、再び轟音がした。
今度は、先ほどよりも近く。
クラウディオが、渾身の力で俺を抱きしめた。
「・・・くそっ・・・!」
それから、俺を突き放すようにひとりで立ち上がる。
「クラウディオ?」
ギシリ、と船が軋んだ。
『しゅ、首領・・・っ!!』
部屋の外から、彼の部下の悲鳴が聞こえた。
明らかに色を失った叫び声。
今度は立て続けに、爆発音が聞こえてきた。
大砲―――だとしか、思えない。
・・・敵に襲われている・・・?
「ここから出るな、キョウスケ」
屈み込んで、額にキス。
「まさか・・・!?」
そのまま部屋を出て行こうとするクラウディオの背中に、俺は問いかけた。
扉に手をかけて、一旦は躊躇してから。
クラウディオは振り向いて、うっそりと微笑した。
「・・・ガレー船だろう」
「・・・!!」
俺は言葉もなく、恋人を見つめた。
「おそらくは、フェラーラ軍が―――」
言葉を切って、クラウディオはやるせない表情で俺を見つめた。
その暗い瞳が、ひどく疲れて見えた。
☆ ☆ ☆
じきに、砲撃戦が始まった。
帆船は、荒波にもみくちゃにされているように感じた。
耳をつんざく爆発音。
バリバリと、まるで落雷のような響き。
鈍い音を立てて、木が軋む。
遠くで、雄叫びが何度も聞こえては、爆音にかき消された。
窓の外には、不気味なほどに静かな海。
そこには、何も見えなかった。
この船を襲う軍団がいるのは、間違いないのに。
「クラウディオ・・・」
他に何もしようがなくて、俺は彼の居室でただ待った。
船が、悲鳴をあげて左右に揺れる。
ドォン、と近くで大砲が打ち込まれる。
爆音と衝撃。
海戦の真っ只中で、激しい砲撃に晒されているのだけれど。
―――不思議と、恐怖心はなかった。
その代わり、疑問が次々に湧いた。
・・・フェラーラ軍、なのか?
俺・・・いや、エレナ姫を奪い返すために?
だとしたら、アドリアーナの手引きということか?
彼女は、無事にフェラーラ公国に到着したのか。
この帆船の航路を、知っていたのか・・・?
・・・どうやって?
答えの出ない疑問の羅列に、俺は苦笑した。
―――こんなふうに。
何ヶ月か以前も、襲撃された船の中に閉じ込められていた。
あのときは、俺の側にはアドリアーナがいた。
「不思議だな」
今俺の側には、あのとき俺を攫ったクラウディオがいる。
そしてフェラーラ公国の船は、俺たち『ソレントの堕天使』一味にとって「敵」というわけだ―――。
俺は拳を、ぎゅっと握りしめた。
祈る以外、俺には何もできないが。
―――神を信じているわけですら、ないが。
それでも俺は、クラウディオの無事を祈った。
彼と引き離されたくない。
それしか、考えられなかった―――。
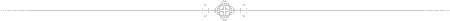
18 December 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月26日、サイト引越により新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。