第五章 (6)
「エレナ姫!!」
ノックの音ももどかしく、アンジェロが部屋に転がり込んで来た。
「どうした?」
振り返った俺は、よろめいて膝をついた彼の姿に息を呑んだ。
額から血を流した、蒼白の顔。
そこに、いつもの小生意気な表情は陰も形もなかった。
「アンジェロ・・・!」
思わず手を貸そうと腰を折った俺の顔を、彼は食い入るように見つめた。
「首領が・・・っ」
絞り出すようなアンジェロの声に、俺は全身が震えるのを感じた。
嫌な予感に、背筋を寒いものが伝う。
「・・・クラウディオは、どこにいる」
つとめて冷静に、そう聞いた―――つもりだった。
アンジェロは小さく頷いた。
「甲板にっ・・・お、お怪我を・・・でも・・・っ」
その続きを、聞く必要はなかった。
「あっ・・・エレナ姫!?」
制止しようと腕を伸ばすアンジェロの手を払い、俺は駆け出していた。
「・・・待ってくださいっ・・・」
長い灰褐色のドレスの裾が、脚に纏わりつく。
それが鬱陶しくて、俺は裾を片腕にからげて走った。
狭い船内は、もうもうと粉塵が舞っていた。
うねるような波に足元を掬われるように、帆船が左右に揺れる。
ドォンとまた、腹に響く轟音がした。
「うわ・・・ええっ!?」
俺とすれ違ったクラウディオの部下が、素っ頓狂な声を上げる。
ぐらり、と船が傾ぐ。
「エレナ姫、そちらは・・・っ!」
「放せ・・・っ」
近づいてきた男の手を、俺は跳ね飛ばした。
細い階段の手すりに捕まって、一気に甲板への階段を駆け上った。
甲板に出れば、見渡す限りの空と大洋・・・の、はずだったが。
そこに足を踏み出した俺は、目の前の光景に絶句した。
どす黒い噴煙の巻き上がる船上。
「ぐああ・・・っ」
あちこちで上がる悲鳴。
剣の凌ぎあう金属質の音。
だらりと横たわったまま、動かない男たち。
饐えた―――生肉の焼け焦げるような、不快な臭い。
船がめちゃくちゃに、横揺れする。
ところどころ破けた帆を張ったマストが、不気味に軋んだ。
風が、生暖かい。
「・・・クラウディオ!!」
五里霧中で、俺は恋人の名前を呼んだ。
「どこだ、クラウディオ!」
ギシリ、と船体が揺れる。
しゅるる・・・と、何かが飛んでくる音がした。
「・・・っ!!」
俺の右手のほうで、何かが弾ける音がした。
炸裂する衝撃に、俺は反射的に耳を覆ってしゃがみ込んだ。
目の前に、ひどく濃い靄のようなものが立ち込める。
それを払おうと、無意識に腕を振り回した。
「な・・・っ!?」
その腕を力任せに引っ張られ、俺は驚愕した。
バランスを崩して、ぐらりと横倒れする。
「馬鹿な・・・っ」
舌打ちをする低い声に、俺は慌てて顔を上げた。
「クラウディオ!!」
・・・俺は、恋人の腕の中にいた。
がっしりと抱き寄せられ、俺は抱擁のきつさにもがいた。
「・・・なぜここにいる、キョウスケッ」
歯ぎしりしそうな憤怒の表情で、クラウディオは俺を睨みつけた。
「死にたいのか、この馬鹿・・・っ」
そう罵倒しかけて、それから思い直したように、彼は口を噤んだ。
熱いまなざしと、ほんのわずか震える唇。
「・・・クラウディオ・・・」
俺はそろりと手を伸ばして、恋人のこめかみに触れた。
汗でべったりと額に貼りついた薄茶色の髪。
いつもはふわりと風に流れるはずの髪が、血糊で固まっている。
今朝は真っ白だったシャツは、今はすっかり煤けていた。
ところどころ無残に破れ、汗ばんだ肌にこびりついている。
ざっくりと斬られたような痕が、左肩に見えた。
生傷は幸いにも浅手らしく、血はすでに止まっていたが―――。
「こんな・・・っ」
俺は言葉に詰まって、クラウディオの疲弊した顔を見返した。
嫌な轟音がもう一度、今度は少し遠くでこだました。
諦めたように、クラウディオが苦笑した。
「本当に、馬鹿なやつだ」
指先で、そっと俺の唇をなぞる。
それからゆっくりと立ち上がり、ドレスの裾を捲り上げたままの俺に気づいて、今度は声を立てて笑った。
「とんでもないじゃじゃ馬に見えるぞ」
「首領・・・っ!」
マストの向こうで、誰かの声がする。
「今行く!」
俺から視線を逸らさずにそう怒鳴り返し、クラウディオは深い息を吐いた。
「・・・キョウスケ」
ゆらり、と船が揺れる。
「襲撃をかけているのは、フェラーラ公国の正規軍だ」
クラウディオは静かにそう言って、海の向こうを指差した。
霧と粉塵でぼんやりとした視界の果てに、幻のような影が見え隠れする。
「おまえを取り戻すのが目的だからだろう。この船を沈めようとは、思っていないようだが―――」
俺は黙って、その低い声に耳を傾けた。
「悪天候続きの上に、船は不具合を抱えてる。向こうに沈めるつもりがなくても、おそらく、もう・・・」
その先の言葉を飲み込んで、クラウディオは首を振った。
苦笑するその目尻には、隠せないほどの疲労が滲み出ていた。
・・・諦念、なのか・・・?
何も言うべき言葉がなくて、俺はクラウディオの左手を取った。
「ん・・・?」
彼の指を飾る『イアシオンの誓約』に、俺の『ケレスの泪』を擦り合わせる。
ぬくもりを伝えたくて、指を絡める。
ざらりと荒れたクラウディオの手が、俺の手を力いっぱい握りしめた。
「わかっている」
緩慢に、彼は頷いた。
「・・・俺だっておまえを、手放したくはない」
恋人の腕が再び、俺の腰を抱き寄せた。
汗の匂い、血の臭い。
硝煙のつんとする異臭―――。
「だがそれ以上に、おまえを死なせたくはないんだ・・・」
掠れた声で囁いて、クラウディオは俺の額にくちづけた。
☆ ☆ ☆
「クラウディオ・・・」
―――冗談じゃない。
死ぬことも、別れることもあり得ない。
俺にとっては―――俺たちにとっては、生きることと側にいることは、同義語のはずだ。
何があっても、香藤と二人で生きていくのだと。
ともに生を選ばなければ、意味がないのだと。
そう誓ったのだから―――。
「し、首領・・・!!」
悲鳴のようなそれが、合図だった。
「どうした―――」
ずしん、ともの凄い衝撃。
今までとは比較にならないほどの、鼓膜を破るような轟音。
その衝撃に、帆船全体が軋んだ。
俺たちは縺れ合って、甲板に転がった。
「な・・・っ」
目の前の光景が信じられず、俺は手の甲で目を擦った。
「あれは・・・!!」
あるはずのないところに、船の舳先。
帆船の胴体を真っ二つに割るような格好で、ガレー船が突っ込んで来ていた。
「・・・フェラーラ軍だ!」
「左舷から、乗り込んで来るぞーっ」
「応戦しろ!!」
あちこちで、唸るような雄叫びが上がった。
その数はわずかで、多勢に無勢なのは明らかだったが。
それでもバラバラと、クラウディオの部下が剣をかざして躍り出る。
―――白兵戦、というのか。
生々しい海戦の展開に、俺はぐっと拳を握った。
「うわあーっ!!」
「行け!」
地響きのような叫び声を上げて、ガレー船の兵士たちが乗船してきた。
「エレナ姫!!」
先頭を行く兵士が、俺の姿を見とめて安堵の声を上げた。
「よくぞ、ご無事で・・・!」
「キョウスケ、こっちへ!」
ぐい、とクラウディオが俺の手を引いた。
「クラウディオ!」
短く頷き、俺は船内に通じる階段の近くに身体を屈めた。
クラウディオが俺のすぐ脇に膝をついて、剣を抜いた。
「寄るな!」
フェラーラ軍の兵士を見据えて、クラウディオが低く吐き捨てた。
一歩、威嚇するように前に出る。
紅蓮の炎を背負ったクラウディオの形相に、男たちが思わず足を止めた。
「・・・近づくな」
しんと、水を打ったような緊迫感。
周囲を睥睨したまま、クラウディオはゆっくりと髪をかきあげた。
斬り込むタイミングを計っているような仕草。
身動きできずに、兵士たちの表情が歪んだ。
「・・・ぐっ・・・」
恐怖からだろうか、誰かが喉を鳴らした。
俺は息をすることすら忘れて、クラウディオの背中を見守った。
「くそっ」
焦れた兵士がひとり、躍り出てきらめく剣をかざした。
クラウディオが、すうっと目を眇める。
ひらりと躱(かわ)しながら、彼の剣がひとたび振り下ろされた。
「・・・ぐぅっ・・・」
一瞬のインパクト。
ほとんど音もなく、兵士がその場に突っ伏した。
クラウディオは、倒れた男に一瞥もくれない。
ただ、俺の姿を確認するようにちらりと視線を巡らしただけ。
・・・ごくり、と。
兵士たちが固唾を呑んだ。
と、そのとき。
「首領―――・・・っ!!」
けたたましいほどの悲鳴がした。
誰もが一斉に、声のする方向を注視した。
「・・・うわっ・・・」
俺は驚愕して、思わず声を出していた。
―――こんなことが、あり得るのか。
マストが―――帆船のマストの最上部がへし折れ、崩れ落ちていた。
ゆらり、ばさり、と破れた帆がたなびく。
まるで無造作に叩き伐られたように、縄で組んだ枠組みが、落下を始めていた。
スローモーションのような悪夢。
「危ない・・・っ!!」
「逃げろっ」
フェラーラの兵士たちが、慌ててガレー船のほうに走り出した。
―――轟々と、不気味な音を立てて。
堅牢なはずの丸太が崩落し、ぐさりと甲板に突き刺さった。
☆ ☆ ☆
めりめりと音を立てて、マストの残骸が甲板を割っていた。
ぎしり、ゆらり、と船が揺れる。
波の音が―――ずいぶん遠くで聞こえる気がした。
このままでは、帆船が沈む。
悲惨なありさまを茫然と眺めながら、俺はようやくそれを悟った。
これ以上この船が損壊すれば、フェラーラの兵士たちも俺たちも、文字通り海の藻屑となって消えてしまうだろう。
それこそ跡形もなく、ただ水泡に帰すことになる。
ここにいる人間すべて、まさに一蓮托生なのだ。
―――それは、だめだ。
命が惜しいとは言わない。
ただ、クラウディオやその仲間を死なせたくはなかった。
すでに多くの犠牲者が出ているのは間違いない。
これ以上、誰も命を落として欲しくはなかった。
まして俺はまだ、香藤を取り戻してはいない。
―――死ぬわけには、いかない。
それだけは、あってはならない。
俺はゆっくりと立ち上がり、クラウディオに近寄った。
「キョウスケ・・・」
間近でじっと、愛しい男の瞳を見つめた。
クラウディオは―――俺の恋人は、途方に暮れた目をしていた。
迷いではなく、弱さでもなく。
八方塞りの現実に直面して、愛情と責任感の狭間で苦悩していた。
―――それは、彼が俺に始めて見せる表情だった。
・・・ああ、これだ。
そのとき俺は、唐突に理解した。
今までずっと、クラウディオが香藤ではないと感じ続けてきた理由。
俺と過ごした年月の記憶が、ないからではない。
そんなものはなくても、彼は香藤なのだと、心が、身体が、どうしようもなく認めているから。
それでも一抹の違和感が、どうしても拭えなかった理由。
―――これだったのだ。
クラウディオはこれまで、ただの一度も、俺に弱みを見せたことがなかった。
不甲斐ない俺を支え、辛抱強く導き、ありったけの愛情を注いでくれるが。
今もこうして命をかけて、俺を守ってくれるけれど。
俺たちの立場は決して、対等ではなかった。
彼の世界に迷い込んだ異邦人の俺は、確かに、何もできない。
だが、それだけが理由ではないだろう。
・・・クラウディオは、俺に甘えることはあっても、俺に頼ることはなかった。
ただの一度も。
迷いや葛藤を、俺に曝け出すことをしなかった。
時代が違う、価値観が違う。
そんなことでは、説明がつかないほどに―――。
目の前のクラウディオは、憔悴していた。
自分の力ではどうしようもない事態に、もう虚勢を張ることもできずに、俺をただ見つめる若い男。
敗北感と、屈辱と。
―――そして、俺に縋って救われたいという、心の奥底のひそかな願望。
そんなせめぎあう感情に、翻弄されていた。
俺は遠い昔の、若き日の香藤を思い出していた。
・・・俺の愛が見えないと、震える声で告げた年下の恋人。
いつも自信に満ち溢れ、年齢以上に大人びていた香藤が見せた、意外な脆さ。
不安と焦燥を素直にぶつけてくる香藤が愛しくて、愛しくて堪らなかった。
あのとき俺は、本当の意味で、香藤を愛することを知ったのだ―――。
・・・香藤。
心からの思慕と憧憬を込めて、俺は心の中の伴侶に呼びかけた。
やっと、俺のところに還ってきたな―――。
「クラウディオ・・・」
堪らなく、狂おしいほどに愛おしくて。
俺は目の前の男を抱き寄せ、思いの丈を込めて唇を重ねた。
周囲の兵士たちがざわめき、息を呑む。
構わず、俺はクラウディオの頭を抱いて、小さなキスを繰り返した。
「・・・キョウッ・・・」
俺の決心を、悟ったのだろう。
咄嗟にキスから逃れて何か言おうとした恋人に、俺は首を振った。
クラウディオの瞳を、まっすぐに見つめたまま。
―――何も言わなくていい。
俺はここにいるから。
今だけでも、俺の腕の中で安心していいから―――。
俺の決意を促すように、船が大きく横揺れした。
「・・・隊長どの」
ひとつ深呼吸して、俺はフェラーラの兵士を振り返った。
「攻撃を直ちに中止してください。俺は、貴殿と一緒にフェラーラに行きますから」
「キョウスケ!!」
ぐいっと、容赦ない力でクラウディオが俺の肩を抱いた。
「何を言って・・・っ!」
掠れた声が、耳に痛い。
怒りと驚きで、薄茶色の瞳が燃えていた。
俺は目を逸らさず、じっとクラウディオを見つめた。
「・・・船が沈んだら、何かも終わりだろう」
「・・・っ」
「俺もおまえも、おまえの部下も、死んでしまうぞ」
「それは・・・っ」
俺はわずかに、口元を綻ばせた。
「忘れたのか。俺は、海賊の女房なんだろう」
「キョウスケ・・・」
「だったら、おまえとこの船のために俺ができる唯一のことを、して当然だろう?」
「ば・・・っ」
唇を噛んで、クラウディオは俺を睨みつけた。
「クラウディオ」
俺はそっと恋人の名前を呼んで、彼の左手を握りしめた。
誰が認めようと、認めまいと。
そこには、俺たちを繋ぐ指輪がある。
「おまえを守ってやりたいんだ」
瞳を閉じて、俺は淡々と言葉を続けた。
結婚式の誓いの言葉のように。
「・・・生きていれば」
指から伝わるぬくもりを感じながら、俺は静かに言った。
「生きてさえいれば、いつかまた、きっと会えるから」
―――どこかで聞いた台詞だ、と思った。
「嫌だ!!」
子供のように首を振って、クラウディオが俺を抱き寄せた。
「行くな。行くな、キョウスケ・・・っ」
顔を俺の肩に擦りつけて、恋人が唸る。
クラウディオの心が、泣いていた。
彼にも無論、わかるのだろう。
今の状況では、他に選択肢などないことが。
「・・・ばか」
胸が張り裂けるほど、愛おしい。
この男を、俺の命と引き換えにしても守りたかった。
やるせなくて、どうにかなりそうだ―――。
「キョウスケ・・・」
「クラウディオ」
俺は小さく笑って、クラウディオの髪を撫でた。
今は艶を失って煤けた、薄茶色の髪。
俺が何よりも、誰よりも愛する男の―――。
「待っているから」
クラウディオの身体をゆっくり俺から引き離しながら、囁いた。
のそりと、彼が顔を上げる。
「キョウスケ・・・」
揺れる瞳が、行くな、と言っていた。
苦笑しながら、俺はゆっくりと首を振った。
―――そっと、絡めた指を解く。
愛している。
愛している。
愛している。
いつまでも、待っているから。
心の裡でそう呟いて、俺はクラウディオに背を向けた。
・・・痛いほどの視線を、背筋に感じながら。
俺は緩慢に、フェラーラの兵士たちのいる方向へ歩き出した。
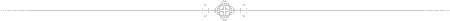
23 December 2006
藤乃めい(ましゅまろんどん)
2013年1月27日、岩城さんの43回目の誕生日。サイト引越により新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。