さしも知らじな 第五章 その1
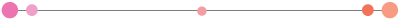
「じゃ、リカちゃん、こっち振り返って?」
「はーい」
抜けるように肌の白いモデルが、無邪気に振り返った。
がらんとした、無機質なスタジオ。
窓のない空間で、俺は無性に喉が渇いてた。
「こんな感じ?」
華奢な腰と、日本人離れした長い脚。
長いアンバーの髪の毛が、傘のようにぱあっと広がった。
真っ直ぐな視線が、ファインダー越しに俺を見つめる。
うん、すごく可愛い。
―――だけど。
「・・・もうちょっとゆっくり、しなを作る感じでやってみてくれるかな」
「しなってなあに?」
あどけない質問に、俺は脱力した。
「あん香藤クン、どうしたのー」
「何でもないよ」
俺はない知恵を振り絞った。
「・・・うーんともったいつけて、スローモーションで行こう?」
「はーい」
久しぶりの、ファッション雑誌の撮影。
巻頭じゃないけど、フルカラーで8ページのグラビアだ。
俺にとってはでかい仕事だった。
ギャラは値切られたけど、自由にやらせてもらえるのはありがたい。
こんな上等の依頼、めったに来るもんじゃないから。
「そうそう、少し睫毛を伏せて、可哀相な感じでねー」
たとえモデルが、素人に毛の生えた新人でも。
可愛いのに色気ゼロでも。
その、俺の半分くらいの歳のコドモに、『香藤クン』呼ばわりされても。
―――間違っても、腹を立てちゃいけない。
「いいよ、リカちゃん!」
にっこり笑って、俺は頷いた。
脳みそ少なめの美少女を、うまく乗せて。
貸スタジオの制限時間内に。
スポンサーのイメージ通りの写真を撮るのが、真のプロってもんだ。
「ごめん、ライトさ、もうちょっと近くしてくれる?」
スタジオが手配してくれたアルバイト学生に、俺は声をかけた。
「こうっすか?」
めんどくさそうに、彼が答える。
「もうあと一歩、前に来て。それからレフ板だけど―――」
俺は、スタジオの壁に立て掛けてある角板を指差した。
「銀じゃなくて、白いほうにして」
「はあ」
・・・周りが素人ばっかりでも、文句を言っちゃいけない。
キレたら負けだ。
こんなときこそ、すべては俺の腕次第なんだから。
「はい、じゃあ、次のポーズね!」
俺は額の汗を拭って、カメラを構えなおした。
「お疲れさま、香藤クン」
俺がカメラ数台を片づけ終わるのを待って、モデルが声をかけてきた。
「よかったよ、リカちゃん」
営業スマイルを返すと、彼女はぽーっと頬を染めた。
―――16歳、だっけ。
こういう仕草は、年相応でかわいいな。
「・・・このあと、まだお仕事あるの?」
ためらいがちの上目遣いに、俺は内心、どきりとした。
西洋人形みたいな、睫毛バサバサの瞳。
「リカ、今日はフリーなんだよ」
・・・こんな可愛い子に、思わせぶりに誘われて。
昔の俺だったら、一も二もなくOKしてただろう。
据え膳のレベルの高さは、この業界のいちばんの役得だしね。
だけど、今は―――。
「ごめん」
俺は本気のため息をついて、謝った。
「俺このあと、どうしても抜け出せない用があるんだ」
見え透いた嘘。
思わぬ拒絶に、彼女が顔を強張らせた。
・・・ああ、そうだろうな。
露骨なお断りだってのは、彼女にもわかるんだろう。
男なら、せめてメルアドを聞くとか。
もうちょっと嬉しそうな、そして残念そうなふりを、してやればいいんだろうけど。
「ごめんね、ホント」
「・・・うん」
ふわふわの金髪が、左右に揺れる。
もったいないと全く思わないって言ったら、ウソになる。
でも、受け入れる気分にはなれない。
俺は嘆息して、カメラバッグを肩にかけた。
カメラ二台にレンズ五本で、多分10キロはある。
「お疲れさま、じゃあね」
女の子を傷つけるなんて、サイテー野郎だ。
・・・でも、どうしょうもないじゃないか。
リカちゃん、ごめん。
君を可愛いと思うのは本当だよ。
俺なんかより、ずっと君に相応しい相手が他にいるはずだ。
―――心で詫びながら、俺はスタジオを後にした。
☆ ☆ ☆
地下鉄に乗り込んで、俺はどさりと腰を下ろした。
ちらりと、時計を見る。
そろそろ、帰りのラッシュアワーが始まる時間だろう。
・・・この路線の先には、大手町がある。
あの人は今、あのビルにいるんだろうか。
まだあと何時間も、仕事に没頭するんだろうか。
それともどこかに、出張に行ってるのかな。
「岩城さん・・・」
瞳を閉じて、俺はため息をついた。
岩城さんに会いたい。
もう一度、岩城さんを抱きたい。
今の俺は、それしか考えられなかった。
―――あの、悩ましい姿態。
それが瞼に浮かび上がって、俺を翻弄する。
バカみたいだ、と唇を噛んだ。
冷たい、人を寄せつけない孤高の瞳。
それを裏切る、熟れた身体。
あの日以来、俺の脳裏から離れない。
あの人のことを考えるだけで、下半身が疼く。
欲しくて、欲しくてたまらない。
こんなに誰かに飢えたのは、初めての体験だと思う。
セックスに逆上せるような年齢じゃないのに。
なのに気がつくと、あの夜のことを考えてる。
あの夜の彼を、何度も何度も、夢で犯してる・・・。
―――岩城さん。
とんだ早とちりだったのは、わかっている。
俺に強請られてると勝手に勘違いして、確かめもせずにホテルに誘ったのは彼のほうだ。
じゃなきゃ、あの晩の出来事はあり得なかった。
ゆきずりの情事。
二度とは訪れないはずの邂逅。
・・・でも。
どんな理由であれ、身体を重ねたのは事実だ。
たとえ、錯誤からであっても。
あの人とのセックスに夢中になったのは、間違いない。
―――会いたい。
これが恋愛の始まりなのか、ただの欲望なのか。
もう俺にも、わからなくなっていた。
なんていうのか、どっちでもいい気分だった。
「岩城さん・・・」
どっちにしても、忘れられない。
寝ても醒めても、あの人の幻影が俺を襲う。
絞り出すような悲鳴も、甘い体臭も。
みっしりと硬い、あの下肢の感触も。
会いたくて、やりたくて、我慢できない。
「やばいよな、ほんと」
俺はもう一度ため息をついて、携帯電話を取り出した。
☆ ☆ ☆
絶対に、確実に、嫌がられる。
嫌われるだけじゃ、済まないかもしれない。
そんなことはわかっていたけど。
他に方法が、思いつかなかった。
彼のオフィスに行っても、たぶん埒があかないだろう。
あの人はもうきっと、二度と俺を振り返らないだろうから。
―――ねえ、岩城さん。
「もう俺、限界なんだ・・・」
そんな言い訳をして、俺はそのマンションを見上げた。
あの晩、ホテルの一室。
岩城さんがシャワーを使ってる間に、俺は彼のスーツを探った。
そんなことしちゃいけないって、頭ではわかってたけど。
でもどうしても、何かのよすがが欲しかった。
なんでもいいから、「次」への手がかりが欲しくて。
黒革の札入れの中の運転免許証。
それを見つけ出した俺は、こっそりその写真を撮った。
―――ホントにやばいよな、俺。
自嘲しながらも、衝動は止められなかった。
あれからひと月。
ろくに知らない男に誘われて、うっかり色香に迷って寝たことなんて、本来なら忘れたほうがいいに決まってる。
あの人を追いかけても、何が得られるわけじゃない。
今ならまだ、気の迷いで済むかもしれない。
・・・でも、駄目だった。
忌まわしいどころか、あの晩の記憶はあまりにも鮮烈だった。
ありえないほどの昂ぶり。
思い出すだけで、喉が渇く。
あんなセックスがあるなんて、俺は知らなかった。
―――昼となく、夜となく。
禁断の記憶は、俺の心をじわじわと侵蝕した。
苦しげにひそめられた柳眉。
喘ぎをかみ殺そうと、必死で身を捩る仕草。
何とも艶(なまめ)かしい、彼の四肢のしなやかさ。
そしてあの秘処の、とろけるような熱さ。
―――あの人は、麻薬だ。
俺の理性を根こそぎ奪って、夜の都会に消えた。
「責任、取ってくれよ―――」
諦め半分で、俺はそう呟くしかなかった。
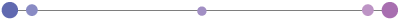
藤乃めい
2 March 2007
2013年3月19日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。