さしも知らじな 第六章 その1
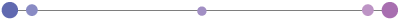
☆ ☆ ☆
岩城さんの靴音が聞こえた。
いつの間にか俺の耳に馴染んだ、規則正しい歩み。
廊下の照明が、人影に遮られてふと、暗くなる。
俺はゆっくりと、顔を上げた。
「おまえ・・・」
ドアの前に蹲ってる俺を見て、岩城さんがため息をついた。
「おかえり」
にっこり笑った俺を、ちらりと目の端で見て。
彼は首を振って、腕の時計に視線を走らせた。
「こういうのはやめろと、何度言ったらわかる」
呆れたようなバリトン。
「もう終電、終わってるぞ」
「どうしても岩城さんに、会いたかったんだ」
俺はのっそりと立ち上がって、尻の埃を払った。
寒さで全身が、すっかり凍えてた。
「いたた・・・」
筋肉が凝り固まっている。
俺はのんびり伸びをして、岩城さんに向き直った。
「なんかずいぶん、久しぶりって気がする」
俺の笑顔を無視して、岩城さんは憮然と訊ねた。
「・・・何時間、ここにいたんだ」
「さあ」
「さあって・・・」
「そんなの、どうでもいいもん」
俺の間抜けな答えに、岩城さんは訝しげに眉をひそめた。
「岩城さんが帰って来るのを待つのは、楽しいから」
「・・・」
「あと1時間、いや2時間したら会えるって。そろそろ、オフィスを出たかもしれない。今頃、地下鉄に乗ってるかもしれない。もうすぐあの廊下を歩いて、俺に向かって真っ直ぐ歩いてくる・・・ってね」
俺はぺろり、と舌を出した。
「頭ん中、好きな人のことでいっぱいにして待ってるんだもん。楽しいに決まってるでしょ」
「・・・言ってろ」
心底、呆れた様子で。
岩城さんはくるりを俺に背を向けて、ドアの鍵を開けた。
・・・くしゃん!
途端に、なぜか寒気がして。
俺は盛大にくしゃみをした。
思いがけず大きな音が、マンションの廊下にこだまする。
「うわ、ごめ・・・っ」
俺はぶるりと震えて、鼻をすすった。
―――さすがに、寒いや・・・!
「バカが・・・」
俺に背中を向けたまま。
低く呻くように、岩城さんが悪態をついた。
「は・・・っくしょ・・・っ!」
まさかの二連発。
健康には自信があるけど、さすがに身体が冷え切っていたんだろう。
「ごめん!」
抑えようがなくて、俺は慌てて岩城さんから顔をそむけた。
静かにドアを開けて、灯りをつけて。
それからゆっくりと、岩城さんは俺を振り返った。
困ったような顔。
いや、逡巡してる顔・・・かな。
眉を寄せて、すっきりした唇を引き結んで。
―――ああ、やっぱり綺麗だ。
連日の残業で、ちょっと疲れてる感じなんだけど。
それがまた、あやうげな色気をかもし出してた。
「・・・ったく」
うっとり見つめる俺に、岩城さんはもう一度ため息をついてみせた。
ずいぶん、間を置いてから。
「入れ」
さも不本意そうな低い声で、岩城さんが言った。
「・・・え!?」
俺はきょとんと、彼の不機嫌な顔を見つめた。
聞き間違い、じゃないよな?
「冷えてるんだろう」
仕方ない、と言わんばかりの口調。
それでも俺は、狂喜して飛び上がった。
「うん!!」
一歩、そそくさと踏み出した俺を、岩城さんは睨みつけた。
「・・・言っておくが」
「へ?」
「変な誤解はするな」
「変なって・・・」
「触れようとしたら、即刻たたき出す」
そっけなく、そう警告して。
岩城さんはさっさと、ドアの向こうに姿を消した。
「ふは・・・っ」
風呂あがり、腰にタオルを巻いて、俺はやっとひと息ついた。
きょろきょろと、辺りを見回す。
洗面台に並ぶ、ローションやアフターシェイヴ。
ブランド品じゃないのが、彼らしいかな。
香水のボトルは、ひとつもない。
岩城さん、香水、使ってると思うんだけど。
・・・歯ブラシが二本あるのには、気がつかないふり。
俺は肩にかけたタオルで、髪の毛を拭き始めた。
―――岩城さんの部屋。
もちろん、上がらせてもらうのは初めてだ。
小ぎれいだけど殺風景な2DK。
いかにも彼らしく、几帳面に片づいてるけど。
「信じらんない・・・」
俺はぶんぶんと、頭を振った。
俺が勝手に、ストーカーみたいに彼を追っかけ回してるだけだった。
だから俺が風邪を引こうが、車に轢かれようが。
岩城さんは、放っておいていいはずなのに。
―――でも、そうしなかった。
寒さで震える俺に、手を差し出してくれた。
もう電車がないから、やむを得ずって感じで。
「やさしいね、岩城さん」
その名前を、舌先でそっと転がしてみる。
岩城さん。
きれいで冷たい岩城さん。
「でも・・・」
思ったより、面倒見がいいね。
俺を風呂場に押しやって、てきぱきと着替えを出してくれた。
憮然とした表情は、そのままだったけど。
少しだけ、自惚れちゃうよ。
「好きだよ、岩城さん・・・」
俺は、そっと声に出してみた。
ああ、いいな。
本当に俺、あんたに惚れてるみたいだよ―――。
岩城さんの姿を探して、俺はリビングに入った。
黒とベージュばかりの、地味な色合いだけど。
落ち着いた、趣味のいい部屋だった。
「岩城さん・・・?」
音量を絞ったテレビから、24時間放送のニュースが流れてた。
それを見るともなく、見ながら。
岩城さんはソファに深く沈みこんで、缶ビールをあおってた。
帰宅したときの姿のままで。
・・・いや。
ネクタイをはずして、シャツの襟を大きく広げた、しどけない格好で。
そこに突っ立ってる俺を、緩慢に見上げる。
「どうした」
岩城さんは静かに聞いた。
声のトーンが、さっきよりずっと頼りない。
岩城さんがものすごく疲れてることに、俺はようやく気づいた。
ぐったり、というか。
さっき俺を牽制した迫力は、もう感じられない。
憔悴してる、そんな感じ。
「大丈夫?」
「・・・ん?」
「疲れてるみたいだね」
そっと言うと、岩城さんが喉で笑った。
「仕事だ。仕方ないさ」
「うん。それは、わかるけど・・・」
不思議に、穏やかな会話。
眉を寄せた俺を、岩城さんは面白そうに見上げた。
「・・・きつそうだな」
俺が着てる、岩城さんのトレーナーとジャージ。
「そうかな」
サイズは合うはずなんだけど、身体の厚みが違う感じかな・・・?
俺はちょっと照れて、微笑した。
「貸してくれて、ありがとう」
「ただの古着だ」
疲れたように呟いて、岩城さんはそっと目を閉じた。
なんだかもう、そこで寝入ってしまいそう。
「あの・・・」
「ビールなら、冷蔵庫にある」
声はもう、眠たげに掠れていた。
「岩城さん?」
無防備な岩城さんが、目の前にいた。
襟元から覗く、鎖骨のライン。
はっとするほど白い、なまめかしい肌。
―――俺は思わず、ごくりと喉を鳴らした。
ある意味、信頼されてるってことだろうけど。
これって、けっこう苦しい。
いや、試されてるのか・・・?
「・・・なんだ?」
目を閉じたまま、うっそりと岩城さんが訊ねた。
俺の葛藤を、まるで察知したみたいに。
―――いや、実際、まる分かりなんだろう。
それからゆっくりと、彼は眠たげな瞳を開けた。
濡れたような漆黒のまなざしが、ゆらりと揺れる。
俺をうつろに眺める。
視線が、上下に彷徨う。
「・・・っ」
その拍子に、下半身に力が漲るのを感じて、俺は慌てて俯いた。
―――ちょっと待て!
男の身体って浅ましい。
俺のバカ息子は、節操なく元気になっていた。
岩城さんに反応して、勝手に頭を擡げ始めている。
「ごめ・・・っ」
身体が硬直して、もうその場から動けない。
俺の変化に、気づいたのだろう。
「・・・本当に、男で勃つんだな」
岩城さんは、呆れたように肩をすくめた。
「・・・やっ、そうじゃなくて・・・っ」
これは、岩城さん限定の反応なんだけど・・・!
「俺は、あっちで寝るから―――」
顎で、寝室らしい隣室を示して、のそりと立ち上がる。
「おまえはここで、好きにしてろ」
低くそう言って、俺の脇を通り過ぎた。
ふわり、と。
すれ違った瞬間、官能的な香りがした。
あの夜の俺を惑わせた、岩城さんの体臭。
俺はぎゅっと、拳を握った。
「・・・ありがとう、岩城さん」
ありったけの理性を総動員して、彼の背中にそっと言った。
ドアノブに手をかけて、岩城さんがゆっくりと振り向く。
ほの白い頬に、あまり血の気はなかった。
「おやすみなさい、岩城さん」
「・・・ああ」
囁くようにそう返して、岩城さんは扉を閉めた。
☆ ☆ ☆
―――眠れるわけがない。
初めて足を踏み入れた、岩城さんのテリトリー。
俺の存在を、受け入れてくれた。
すぐ隣りの部屋に、彼がいる。
一度は肌を合わせた片恋の相手が、そこに寝ている。
いっそ、襲ってしまえばいいのか。
今のあの、無防備な状態の彼を。
・・・きっと岩城さんは、抵抗しない。
なぜか、絶対の確信があった。
口では何と言おうと、最後は身を任せてくれるだろう。
いや、抵抗しても、今なら力でねじ伏せられる。
―――俺を自宅に招き入れた時点で、そうなるかもしれないと予期したはずだ。
それは、恐ろしく甘美な誘惑だった。
ひどく甘く、破滅的な妄想。
抱いてしまえば、あの熟れた身体は喜悦に震える。
二度目のセックスに、理由なんかいらない。
溺れてしまえば、あとはなし崩し。
・・・そう、たぶん。
「ダメだよ、それじゃ・・・!」
俺はほうっと、深呼吸した。
深夜のリビングルーム。
岩城さんを抱きたいのは、本当に本当だけど。
でもそれ以上に、欲しいものがあるんだから。
俺は首を振って、危険な妄想を振り払った。
素直に、お許しの出た缶ビールを飲んで。
俺は本棚に並んでいるものを、あれこれ眺めた。
岩城さんの読んだ本。
岩城さんの聴く音楽。
それからソファに、ごろんと横になった。
ほのかに岩城さんの匂いのする場所。
―――なんだか、夢みたいだ。
俺は、彼を無理やり襲いたいんじゃない。
部屋はほかほかと、心地よくて。
ここにいられる幸運を、感謝しなくちゃいけない。
「おやすみ、岩城さん―――」
片思いの少女みたいに、そっと呟いて。
俺はうっとりと、睡魔に身を任せた。
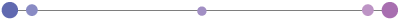
藤乃めい
8 March 2007
2013年3月24日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。