さしも知らじな 第六章 その3
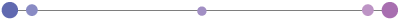
☆ ☆ ☆
「おはよう、岩城さん!」
次の週末。
俺は朝いちばんで、岩城さんの部屋のベルを鳴らした。
浅い春の、気持ちのいい朝。
―――ちょっとした、運だめしのつもりもあった。
岩城さんが日曜の朝、ひとりでいる保証はない。
あの男が―――誰かが、泊まっているかもしれない。
でも、そういう相手と過ごしてる確率のほうが、低いはずだと思ったから。
「・・・また、おまえか」
地を這うような不機嫌な呻り声が、ドアの向こうから聞こえた。
ほんの少しだけ、扉が開く。
「何時だと思ってるんだ」
寝起きの掠れた声。
チェーンをかけたまま、岩城さんが俺を睨みつけた。
黒―――いや、紺色のパジャマ姿。
「もう、八時は過ぎてるよ」
にっこり笑いかけた俺に、岩城さんはため息をついた。
「帰れ。おまえに用はない」
「ダメだよ、岩城さん。俺が、用があるんだから」
俺はチェーンを指先で弾いた。
「今日、すっごくいい天気なんだよ。ドライブしよう?」
「・・・はあ?」
ぽかんと口をあけて、岩城さんは俺をまじまじと見つめた。
「気は確かか? なんで俺が、おまえとドライブしなくちゃいけないんだ」
「俺がしたいから」
俺は微笑して、目の前に車のキーをぶら下げた。
「ふざけるな」
「ふざけてなんかいないよ」
「・・・馬鹿も休み休み・・・」
「デートしようよ、岩城さん」
「・・・」
岩城さんは黙って、ドアを閉めようとした。
「おっと!」
俺は慌てて、靴の先をドアの隙間に捻じ込んだ。
表情を変えずに、岩城さんが俺を押し出そうとする。
「いたた・・・」
「・・・足をどけろ」
「やだ」
「やだって」
心底呆れた、と言わんばかりに。
岩城さんは肩をすくめて、嘆息した。
「からかうのも、大概に・・・」
「俺は、からかってなんかいないよ?」
暝い瞳が、ちらりと揺れた。
きついまなざしが、月影に隠れるみたいにけぶる。
なんだろう、この感じは・・・?
「ねえ、岩城さん。俺は本気だよ?」
「・・・何のことだ」
「好きだって言ったのは、マジだから」
ドアの隙間は、ほんの10センチ。
その向こうに立ち尽くす男を、俺はじっと見つめた。
こんなに必死で誰かを口説いたことなんて、人生で今までないかもしれない。
「ねえ、岩城さん」
「・・・なんだ」
「俺のこと、嫌い?」
「・・・っ」
よほど意外な質問だったのか。
何か言いかけて、岩城さんは結局、口を噤んだ。
「・・・嫌いじゃないなら!」
憤然とした表情で黙り込んだ岩城さん。
にっこり笑って、俺はそっと言葉を続けた。
「今日だけでいいよ。お願いだから、俺につきあって。何もしないから、岩城さんの時間を少し、俺にください」
俺はぺこりと、頭を下げた。
―――そのまま、長い沈黙。
それから、カチャリ、と小さな金属音。
恐る恐る顔を上げると、岩城さんが腕を組んで俺を睨んでた。
「まったく、おまえは・・・」
チェーンが外されていた。
開いたドアから、部屋の中が見渡せる。
「こういうゲリラ戦法は、迷惑だ。二度とするな」
大きくため息をついて、彼は顎をしゃくった。
「・・・俺はシャワーもこれからだ。支度するから、中で待ってろ」
☆ ☆ ☆
「・・・ずいぶんいい車に乗ってるんだな」
岩城さんが、目を瞠った。
朝陽を受けてぴかぴか光る、艶やかな赤のBMW。
「俺のじゃないよ、残念だけど」
俺はウィンクして、助手席のドアを開けた。
「外資系の投資銀行に勤めてる先輩から、借りたんだ」
早起きして、せっせと洗車とワックスがけをしたのは俺だけどね。
「すっごい高給取りなんだけどさ。忙しすぎて、せっかく買った車に乗る暇がないんだって。もったいないよね」
くすりと笑って、岩城さんは俺を見返した。
「なるほどな」
「ま、先輩にしてみれば、大事なペットの散歩を頼んだ気分じゃない?」
にんまりと笑って見せると、岩城さんは可笑しそうに俯いた。
「そうか」
そのまま大人しく、俺の開けたドアにもぐりこむ。
さらさらの髪。
ほのかなシャンプーの香り。
とげとげしさが消えて、なんだか急に素直になったみたい。
―――さっきまで、あんなに嫌そうだったのに。
嬉しくて、俺は思わず頬を緩めた。
なんだかさっきから、デレデレしっぱなしかもしれない。
岩城さんが可愛い。
可愛すぎて、クラクラする。
俺はすでに最高潮に盛り上がっていた。
「はい、これ!」
後部シートに腕を伸ばして、俺はコンビニの袋を取り出した。
「なんだ?」
岩城さんが、小さく首を傾げる。
・・・意外に幼いっていうか。
こういう仕草も、めちゃくちゃに可愛い。
「朝飯。食べてないでしょ?」
俺は上機嫌で、エンジンをかけた。
「また一緒に朝飯を食おうって、先週約束したじゃない」
「・・・何を言ってるんだ」
呆れたように、岩城さんが苦笑した。
なんだか、ちょっとリラックスした感じで。
ああ、すごく嬉しいな。
本当の本当に、デートするみたいだ。
岩城さんは早速、ビニール袋の中身を物色し始めた。
「・・・変な取り合わせだな」
ぽつりと、ひと言。
―――確かに。
近くのコンビニで、おむすびや菓子パンを、適当に見繕った。
ドリンクも、緑茶からコーヒーまで何本か。
「だって岩城さんの好きなもの、俺は何にも知らないから」
そう言うと、岩城さんが心持ち俯いた。
ありがとう、って小さく呟く。
戸惑いを隠せないような、照れくさい感じの。
「・・・じゃ、行こうか」
岩城さんがシートベルトを締めるのを横目で確かめて、俺は車を出した。
ホントは、素直に礼を言う岩城さんが、可愛くて可愛くて。
今すぐここで、抱きしめたいくらいだった。
「海・・・?」
順調に湾岸線に入った俺を、岩城さんが見つめた。
「どこに行くんだ?」
無邪気な質問に、俺は微笑した。
こないだまで、あんなにガードの固かった人が。
徹底的に、俺を拒絶してたはずの岩城さんが。
何も聞かずにここまで、俺の車に乗ってたってほうが信じられない。
―――もしかして俺、信頼されてるのか。
それとも岩城さんがそれだけ、すれてないってことかな。
「ディズニーランド!」
短くそう言うと、反応を見たくてちらり、と横を見た。
「・・・え?」
きょとんと、岩城さんが俺を振り返る。
「今は、東京ディズニーリゾート、って言うんだっけ」
「・・・!」
度肝を抜かれたみたいに、岩城さんは息を呑んだ。
「ほら、これ」
俺は胸のポケットを探って、二枚のパスポート券を取り出した。
「偶然なんだけど、先週タダ券をもらったんだ。仕事の役得ってやつ?」
「・・・」
「一日でどれだけ回れるのか疑問だけど・・・って、あれ?」
彼があんまり、びっくりした表情で俺を見るので。
「聞いてる、岩城さん・・・?」
俺はちょっと不安になって、恐る恐るお伺いをたてた。
「もしかして、テーマパークとかって嫌い?」
―――そりゃ、まあ。
大の男ふたりで行く場所なのかって聞かれると、ちょっと答えに窮するけど。
「・・・あ、いや・・・」
「岩城さん?」
「・・・そういう問題じゃ、なくて」
車窓に顔を逸らせて、岩城さんは小さく笑った。
―――自嘲っぽい、哀しい笑い。
どうしちゃったんだろう。
さっきまでの明るさが、唐突に消えたような気がする。
「・・・おまえは本当に、健康なんだな」
「へ?」
「・・・俺は・・・俺たちみたいな、人種は」
言葉を選ぶみたいにちょっと考えてから、彼は続けた。
「そういう健全な場所って、あんまり行かないから」
健全・・・健康。
俺たちみたい・・・って。
―――そうか。
コンプレックス。
男同士だってのを、気にしてるんだ。
自分が生まれつきそういう性癖の人間だって、彼はわかってるみたいだから。
隠すべきもの、忌むべきもの・・・?
マイノリティという負い目。
引け目を感じて、日陰者みたいに生きて来たのか。
つきあった相手も、似たような考え方をする奴が多かったのかもしれない。
ひたすら隠し、誤魔化してきた性癖。
それがばれて、世間の冷たい目に晒されることに怯えて―――?
息を潜めて、周囲を欺いて―――?
俺は思わず、大きなため息を漏らした。
・・・せつなくて、胸が痛い。
「ねえ、岩城さん」
前方を見たまま、俺はゆっくりと岩城さんに語りかけた。
「そういう言い方、やめよう? 悲しいよ」
「―――」
「・・・たしかに俺はさ、男とつきあったことなんてないし、自分がゲイだと思ったこともない」
「・・・」
「この歳まで女としか恋愛したことないから、だからわかってないかもしれない。こんなこと初めてで、正直ちょっと、戸惑ったよ」
すうっと、彼が息をひそめるのがわかった。
俺の言葉の辿り着く先を、窺ってる感じ。
「でも、岩城さんが好きだって気持ちを、恥じたことはない」
「・・・」
道が混んできて、俺は慎重にブレーキを踏んだ。
渋滞は嫌いだけど、こういうときには助かる。
俺は真面目に岩城さんを見つめた。
「だって、恋愛ってホント、理屈じゃないもん。惚れちゃったら、どうしようもない」
「それは・・・」
「男だろうと女だろうと、好きな相手なら、俺は大事にしたいし―――」
「香藤・・・」
戸惑うような低い声。
俺の言葉を遮ろうとしてるのか、先を促してるのか、わからないけど。
「岩城さんに、俺の恋人になってほしいよ?」
舞浜を目前にして、車の流れはすっかり停まっていた。
―――タイミングがいいって言うか、悪いって言うか。
「でさ、岩城さんが恋人だったら」
岩城さんに向き直って、俺はにっこり笑った。
「きっと俺、嬉しくて舞い上がってさ。家族にでもダチにでも、大いばりで見せびらかすと思うよ?」
「・・・!」
そう、誰にも何も言わせない。
俺が本気で惚れた相手を、恥じるわけがない。
恋をするのに、後ろめたいことなんてないはずだから。
そのまま、心なしか甘い沈黙が落ちた。
「―――バカ」
しばらくして、岩城さんが小声で言った。
「世間知らずだな」
「かもね」
俺は岩城さんを見据えて、にんまり笑った。
呆れたような顔で、岩城さんがしかめ面を作る。
口先だけなら何とでも言えるって、言いたそうな顔で。
「おまえは神経、太すぎだ」
「あ、それ、よく言われるね!」
今度の彼の苦笑は、吹っ切れたような清々しさ。
俺は内心ほっと、胸を撫で下ろした。
☆ ☆ ☆
雑踏を掻き分けて、俺たちはのんびり歩いた。
カラフルで陰のないファンタジーの世界。
俺たちよりでかい着ぐるみのキャラクターたち。
どこに行っても、明るいメロディーがエンドレスに流れてて。
いつもどこからか、甘いお菓子の匂いがした。
あくまで健全な、張りぼてのファミリー・エンターテイメント。
「・・・異世界だな」
呆れたように、岩城さんが呟いた。
ぽかぽかと暖かい春先の休日。
歓声を上げて走り回る子供たちを、左右に避(よ)けながら。
「そうだねー」
俺は岩城さんの、いかにも居心地の悪そうな困惑顔がおかしくて。
頬が緩んでどうしようもなかった。
だって、可愛いんだ。
こんなに可愛い人だなんて、知らなかった。
信じられないけど、テーマパークは生まれて初めてらしくて。
眉をしかめて、しょうがないって仕草をする。
―――お日様の下で、堂々とデートしよう!
そう宣言して駐車場に降り立った俺を、呆れたような顔つきで見返して。
「調子に乗るな」
そっけない言葉を、俺に返した岩城さん。
そのくせ怒るわけでもなく、大人しく俺についてくる。
文句も言わずに、アトラクションの長い行列につきあってくれる。
物珍しそうに、綿菓子みたいなパステルカラーの世界を眇めて見てる。
ずっと、俺のそばにいてくれる。
「帰る足がないから」
なんて、憎まれ口を利きながら。
・・・もう、たまんないよ。
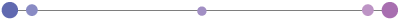
藤乃めい
16 March 2007
2013年3月28日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。