さしも知らじな 第六章 その6
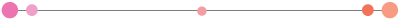
「おまえに慣れるのが怖いな」
岩城さんはときどき、そう言って低く笑う。
あんまり楽しそうじゃない、寂しい微笑なんだ。
―――どういう意味だろう。
慣れるって何に?
俺が懲りずに、能天気に通い続けることだろうか。
それとも俺がいつまで、岩城さんに執着してるかってこと・・・?
俺の存在に。
俺のこの気持ちがいつかは冷めるって、そう思ってるってことかな。
・・・俺がいつか、傍にいなくなるとか?
それは嫌だって、考えてくれてるんだろうか。
そういうときの岩城さんは、儚げでとても綺麗だ。
でも、ふっといなくなってしまいそうで、俺は不安になる。
俺を捨てて、仕事もマンションも捨てて。
何の前触れもなく、姿を消しそうな危うさがある。
なんだかすべて、厭になったと言わんばかりに。
どうしてそう思うのか、俺にもわからない。
―――ねえ、岩城さん。
俺はほんとに、あなたが好きだよ。
あなたを大事にしたいと、本気で思ってるよ。
ずっと傍にいたい、抱きしめていたい。
そろそろ信じてくれても、いいと思うけど―――。
☆ ☆ ☆
花冷えの日曜日。
朝からしとしとと、冷たい雨が降っていた。
俺は鼻をすすりながら、岩城さんのマンションに向かった。
「やっぱ風邪かなあ・・・」
傘の柄をぎゅっと握って、俺はため息をついた。
前日の仕事が、とんでもない暴風雨の真っ只中で。
『こういうのもドラマチックでいいじゃない!?』
なんてほざくディレクターのせいで、どしゃ降りの雨の中で撮影を決行した。
―――たしかに絵的には、よかったけどさ。
ずぶ濡れになってカメラを構えてた俺には、さんざんだった。
レンズの防滴性能ギリギリの悪天候。
体力に自信のある俺だけど、あれは酷かった。
そのせいか、ずっと熱っぽい。
岩城さんには、もう三週間以上会ってない。
俺がもう飽きたと、思われていたら・・・?
そう考えると、矢も楯もたまらなかった。
どうしても、どうしても顔が見たかった。
ノックの音で、岩城さんはすぐにドアを開けてくれた。
「おまえ、大丈夫か」
俺の顔色を見て、眉をひそめる。
普段着の紺色のセーターに、いつものツーポイントの眼鏡。
久しぶりのすっきりした美貌に、俺はうっとり見惚れた。
「会いたかったよ、岩城さん」
微笑した俺を、あっさりとかわして。
「熱でもあるんじゃないか」
相変わらずのそっけない口調で、岩城さんが聞いた。
「うん、そうかも。・・・ねえ、岩城さん」
「なんだ?」
「久しぶりに、デートしよう」
玄関に立ったまま、岩城さんは俺をまじまじと見つめた。
「・・・病人が、何を言ってる」
呆れたまなざしに、俺は少し慌てた。
断られたら、ここにいる理由がなくなる。
すごすごと自宅に帰されたら、俺、岩城さん不足で変になるよ。
「このくらい平気だよ」
肩をすくめて、俺は外を見やった。
「あいにくの雨だけど。風邪っぽいっていうか、調子いまいちだけど。でも俺、銀座にいい店を見つけたから―――」
だから、俺と一緒にいて。
岩城さんは腕を組んで、首を横に振った。
「冗談じゃない」
ばっさり斬り捨てるみたいなひと言。
にべもない拒絶。
「気が乗らないなら、えっと・・・」
俺は必死で、別のアイディアを探した。
・・・ああ、頭がよく働かない。
岩城さんは眇めた目で、俺を探るようにじっと見つめる。
「岩城さん・・・」
「駄目だ」
小さなため息。
帰ってくれ、ってことだろうか。
―――こうやって、やっと、やっと会えたのに。
やっと会う時間を作ってきたのに。
そりゃまあ、俺が一方的に追いかけてるのかもしれないけど。
なんだか、目の前が暗くなる気がした。
「馬鹿」
俺の表情を読んで、岩城さんが小さく言った。
「こんな天気の日にわざわざ、出かけなくてもいいだろう?」
「え・・・」
俺は呆然と、岩城さんを見つめた。
少し照れたみたいに、岩城さんが微笑する。
「岩城さん、それって・・・?」
上擦った俺の声に、苦笑しながら。
「いいから、入れ」
岩城さんは顎をしゃくって、俺を部屋の中に促した。
☆ ☆ ☆
夢じゃないよね・・・?
ソファに座った俺に、岩城さんはコーヒーを出してくれた。
「すみません」
俺はどきどきしながら、マグカップを受け取って頭を下げた。
「何を、緊張してるんだ」
岩城さんが低く笑う。
以前とは違う待遇のよさが、なんだか気恥ずかしい。
―――岩城さんの部屋は、ずいぶん久しぶりだ。
っていうか、こういうふうに、普通に招き入れてくれたのは初めて。
柄にもなく、俺は感動してた。
デートはたしかに、何度もした。
半ば強引に岩城さんを連れ回し、キスも何度か。
甘い抱擁が、独りよがりばかりじゃないのも知ってる。
彼なりに俺を受け入れ、甘やかしてくれているとも思う。
でも、俺たちはそれでも、恋人同士じゃなかった。
次に会う約束はしない。
相手の予定も聞かない。
それ以前に、俺は岩城さんの携帯電話の番号も知らない。
―――見えないラインが、そこにあった。
なんでか、聞いちゃいけない気がしてるんだ。
俺たちは、つきあってるわけじゃない。
だからいつも、俺が一方的に岩城さんの部屋に通って、一方的にデートに誘う。
それに頷くかどうかは、岩城さんの自由。
それだけの関係だった。
―――いや、それでも充分に、俺には甘い関係だけど。
岩城さんにそれ以上を要求しちゃいけないって。
俺に、彼を拘束する権利はないって。
・・・そう、思っていた。
勝手に気持ちを押しつけてる自覚はあったから、余計にずっとそう思ってた。
―――いつか、認めてもらえることを夢見て。
こうやって、部屋に上げてくれて。
普通の恋人みたいに―――いや、友達みたいに扱ってくれるなんて。
なんだか幸せすぎて、怖いぐらいだ。
☆ ☆ ☆
「・・・どうした?」
静かなインストゥルメンタルの音楽。
壁際の本棚にあるコンポをいじってた岩城さんが、ふと振り返った。
「なんでもないよ」
なんとなく恥ずかしくて、俺は言葉を詰まらせた。
「変なやつだな」
小さく笑って、岩城さんは俺の向かいの椅子に腰を下ろした。
自宅なんだから、当然かもしれないけど。
俺の前でこんなにリラックスしてる岩城さんを見るのは、初めてだった。
「いつもの元気がないな。やっぱり―――」
具合が悪そうだから帰れ、って言われたくなくて。
俺はむきになって、首を振った。
「ううん、大丈夫!」
「・・・風邪薬、出してやろうか」
「ううん、平気だよ。・・・ありがと」
「そうか」
それきり、沈黙が落ちた。
黙って俺たちは、コーヒーをすすった。
―――俺たちいつも、何をしゃべってたっけ。
居心地が悪いわけじゃないんだけど、すらすらと言葉が出てこない。
頭がなんか、ぼうっとする。
熱のせいと・・・寝不足もあるのか。
俺はそっと目を閉じて、音楽に耳を傾けた。
独特のリズムが心地よい、ジャズっぽい音。
そうか、岩城さんはこういう音が好きなのか―――。
暖かい部屋。
窓の外には、雨の音。
すぐ目の前に岩城さん。
なんだか全部、ふわふわと気持ちがいい。
「・・・眠いなら、寝てていいぞ」
うつらうつらした俺に、岩城さんの声が聞こえてきた。
ふと見ると、文庫本を片手に俺を見つめてる。
見たこともないような、優しい笑顔。
「うん・・・」
ああ、こんなに幸せなのに、もったいないな。
そう思いながら、俺はいつの間にか意識を失っていた。
どのくらい、寝たんだろう。
目が覚めたとき、岩城さんは目の前にいなかった。
「あれ・・・」
ソファから起き上がると、キッチンでカタコト音がしてた。
「岩城さん?」
「ああ、起きたのか」
ひょいと顔を覗かせて、岩城さんが俺を見下ろした。
「昼飯、食うか?」
「ええ!?」
その言葉に、俺は飛び上がった。
「なに、大きな声を出してるんだ」
岩城さんが眉をしかめる。
「岩城さんが、作ってくれるの?」
そういえば、なんだか香ばしいいい匂いがしてる。
「・・・作るってほどのものじゃないが」
ちょっと苦笑して、岩城さんは俺をテーブルに促した。
「うわ・・・」
「豆腐しかなかったから・・・」
ご飯と味噌汁と、マーボ豆腐。
それからスポーツ飲料が、ペットボトルごと出てた。
「すごいね」
俺は目を細めて、感嘆した。
「・・・ただのレトルトだぞ」
「充分おいしそうだよ」
なんだか楽しくなって、俺は笑って席についた。
「あれ・・・岩城さん、これ」
「なんだ?」
大皿に盛られた、ほかほかのマーボ豆腐。
確かにおいしそうだけど、よく見ると、ひき肉もネギも入ってなかった。
出来合いのソースにホント、豆腐を入れて炒めただけ。
―――岩城さんっていつも、こんなふうなんだろうか。
「・・・どうした?」
「なんでもないよ」
可笑しくて、俺は忍び笑いを漏らした。
「岩城さんらしい・・・のかな」
どこか調理の仕方がおかしい、って気づいたらしい。
岩城さんは、むっとして俺を睨んだ。
「・・・たかが、レトルトだろ」
「味噌汁も?」
「嫌なら食うな」
岩城さんは、しかめ面をして見せる。
でもそこには、以前みたいな棘がなくて。
―――なんか俺、こんなに幸せでいいんだろうか。
「ううん、いただきます。ありがとう、岩城さん」
真っ直ぐに礼を言うと、岩城さんは照れたみたいに顔を背けた。
☆ ☆ ☆
食後、俺たちはソファに並んで映画を見た。
と言っても、日曜日の午後にテレビでやってる映画なんて、たかが知れてる。
古ぼけたハリウッドのアクション映画。
はっきり言って、退屈なんだけどね。
―――別に、映画なんか本当はどうでもいいんだ。
岩城さんと一緒にいられるなら、何でも。
気だるい春の午後。
規則的な雨だれの音が、まだ聞こえていた。
とろんと眠たい気がするのは、岩城さんにもらった風邪薬を飲んだからか。
「岩城さん・・・」
「うん?」
緩慢に振り返った彼の肩を、俺はゆっくりと抱き寄せた。
怯えさせないように、ごくさりげなく。
くすり、と岩城さんの忍び笑いが聞こえたような気がした。
しなやかな身体が、静かに俺にもたれかかる。
黒いつややかな髪が、俺の右肩で揺れていた。
「ん・・・」
俺はその頭のてっぺんに、そっとキスを落とした。
岩城さんは、逃げない。
伸びやかな身体も、緊張した感じはない。
―――いい、ってことだよね。
俺はそのままゆっくりと、右手で岩城さんの腰を抱き寄せた。
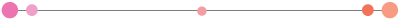
藤乃めい
9 April 2007
2013年4月6日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。