さしも知らじな 第七章 その1
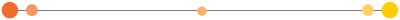
暗転。
そして、振り出しに戻る―――。
「ふう・・・っ」
俺は深く深く嘆息して、空になったビール缶を握り潰した。
―――午前二時。
アナログ壁時計の秒針が、耳障りな音を刻む。
「ったく、ざけんなよ・・・!」
悪態をついて、俺は仰向けにベッドに転がった。
振動で、傍らの小さなテーブルが揺れる。
ビール缶が幾つも、不機嫌そうにカタコト踊った。
「・・・冗談じゃねえ」
苛立ちに、心が蝕まれていく。
やり場のない荒々しい感情が、俺を支配する。
怒りと痛み。
脇腹を抉られるような不快感で吐きそうだ。
岩城さんの拒絶。
絶たれてしまった淡い期待。
「ちくしょう・・・っ!」
どうしようもなくて、俺は髪をかきむしった。
・・・わかってる。
最初からわかってたはずだ。
俺はほろ苦い心持ちで、自分に言い聞かせようとした。
―――岩城さんには、恋人がいる。
自宅の鍵を渡すほどの、深いつきあいをしている相手。
それは知っていた。
知っていた、はずだった。
見たところ、あの男は同じ職場の上司で、それも不倫で。
愛人関係、ってことなのかもしれない。
考えたくないけど、認めたくはないけど。
それって岩城さんのほうが、愛人ってことだよな。
男同士で、一方は既婚者。
・・・禁忌、だ。
絶対に陽の目を見ることのない関係。
彼らがサラリーマンである以上、何重にも足枷のある繋がりだろう。
もし関係がばれたら、たぶんビジネスの世界ではお終いだ。
破滅、といってもいいかもしれない。
それだけのリスクを冒しながら、なお離れられない相手なのか。
それだけの結びつきがあるってことなのか。
それだけ、好きなのか・・・?
「―――克哉、って呼んでたな・・・」
確かにいい男だったけど、でも。
険のある、冷たい雰囲気をまとっていた。
どこか屈折してるし、岩城さんを上から見下ろしてる感じだった。
相思相愛には見えなかった。
俺がそう思いたいだけ、かもしれないけど。
「・・・あんまり幸せそうな関係じゃないよ」
―――それでも、俺はお呼びじゃないのか・・・?
惚れているのか、あの男に。
離れられないと思っているのだろうか。
「岩城さん・・・」
俺は、何度目かのため息をついた。
嫉妬してない、わけがない。
あんなふうに簡単に追い払われて、すげえ悔しかった。
認めたくはないけど、嫉妬で気が狂いそうだ。
―――でも、ここ数ヶ月。
俺に少しずつ、心を開いてくれていた。
岩城さんは、揺れていたはずだ。
戸惑いながらも微笑を俺に向けてくれるようになった、あれは演技ではないはずだ。
「身体だって・・・」
許してくれていた、じゃないか。
あれだけ俺に、さんざんつけこむ隙を与えるくらいだから。
岩城さんとあの男の間はたぶん、上手くいってないんだろう。
―――俺には、わかる。
あれは、ゆっくりと破綻へと向かってる関係だ。
俺にわかるんだから、岩城さんにだって、本当はわかってるはずだ。
あの男と一緒にいても、絶対に幸せにはなれないって。
あの男は、岩城さんを幸せにしたいって考えるようなタイプじゃない。
「・・・だけど」
―――もともと岩城さんは、幸せを求めていない。
そこが問題だった。
自分が幸せになれるはずがないと、彼は端(はな)から決めてかかってる。
・・・期待しなければ、失望もしないで済むから?
いや、それ以前に。
幸せを望むという発想すら、ないのかもしれない。
「わかってるくせに・・・」
最初から、ひどく冷めた目をしていた岩城さん。
自暴自棄みたいに、あの夜、俺に身を任せた。
何も望まないから、刹那的で、自虐的なんだろう。
自分を大事にしない、というより。
自分自身が好きではないのかもしれない、と今は思う。
寂しくて、寂しくてたまらないくせに。
「馬鹿だよ・・・」
あの人は、心に積もった哀しみを持て余している。
ときどき、縋るような瞳で俺を見つめる。
俺を信じたくて、でも信じられなくて。
助けを求めたくて、でもどうすればいいのかわからなくて。
俺に捨てられるのを待ってるような、恐れているような、そんな顔で。
「悲しすぎるよ、岩城さん―――」
俺はもう、岩城さんしか見えてないのに。
どうしたらいい?
どうしたら、信じてもらえるだろう。
彼にも幸せになる権利があるってことを。
先の見えないあの男との関係に、甘んじなくていいってことを。
俺の本気を。
俺が彼を、幸せにしたいって本気で思ってることを。
俺は何も持ってないけど、でも、俺のすべてを岩城さんにあげたい。
あの人の傷を癒して、冷えた身体をあっためてあげたい。
あの人を守り、愛して、誰よりも大事にしてあげたい。
俺の腕の中で、安心して笑っていてほしい。
「・・・岩城さん」
やるせなくて、俺はもう一度嘆息した。
☆ ☆ ☆
次の週末、俺は再び岩城さんのマンションに向かった。
だけどドアは固く閉ざされたまま、人の気配すらなかった。
もちろん、留守はこれが始めてじゃない。
俺は部屋の前に座り込んで、岩城さんの帰宅を待った。
―――あれで終わりなんて、絶対に言わせない。
そう心に誓って、何時間でも待つ気で。
でも彼は結局、夜まで戻らなかった。
そんなことが、二度続いた。
三週目は、俺が撮影でグアムに飛んでた。
常夏の海を眺めながら、俺は岩城さんの夢を見てた―――。
その次の週末はもう、蒸し暑い六月だった。
俺は、32歳になった。
梅雨が近いことを感じさせる、湿った重い空気。
肌にじっとりと纏わりついて、息苦しくなるような。
・・・岩城さんに、晩秋の野宮神社で出会ってから半年。
彼と知り合って、俺の人生は激変した。
とても近しいところで繋がっているようで、まだまだ彼は遠い。
触れることも、キスすることもできるのに。
それでも岩城さんは、俺のものじゃなかった。
―――今は、まだ。
さらにその次の週末、彼のマンションが留守だったとき。
俺はさすがに、ため息とともに自覚した。
このままじゃダメだ。
危機感がやっと芽生えた、というべきか。
―――避けられてるとは、実は思ってない。
認めたくないけど、あえて避けられるほどの精神的な繋がりは、俺たちにはないから。
俺がそばにいるのが嫌なら、岩城さんはひと言、そう告げるだけでよかったから。
本気で拒絶されたら、俺はそれを甘受するしかないから。
「岩城さん・・・」
あれからひと月、ふた月。
もうずいぶん、岩城さんの顔を見てない気がする。
「・・・声が、聴きたいよ」
俺はそろそろ、臨界点に達していた。
☆ ☆ ☆
夜のベッド。
変わり映えのしない日常。
仕事は順調だけど、可もなく不可もない生活。
―――カメラを持つときのわくわく高揚した気分を、俺は忘れかけてた。
岩城さん以外の被写体に、興味が持てないから。
岩城さんの幻影ばっかり、追いかけてるから。
プロとして、それじゃまずいだろうって思うけど。
携帯電話が鳴って、俺は飛び起きた。
「あれ、俺、いつの間に寝てたんだろ」
慌てて、枕元に置いたはずの小さな機械を探す。
「はいはい・・・!」
『なんや、寝起きの声やな。寝るには早い時間やろ』
くすくす笑う穏やかな声に、俺は目を見開いた。
「吉澄さん!」
『久しぶりやな』
半年ぶりに聴く先輩の柔らかい大阪弁に、俺は顔を綻ばせた。
「ご無沙汰してます。今、どこですか!?」
『仕事で、昨夜から東京に来てんねん』
「仕事って・・・?」
先輩は、ご両親の経営する喫茶店のマスターだ。
出張があるような職業には、思えないんだけど。
『食器の買いつけ、言うんが表向きの理由やけど』
俺の疑問を察したのか、吉澄さんは小さく笑った。
『ま、半分はお遊びやな。せっかくやから、週末までおるつもりなんや』
のんびりしたその口調に、俺は笑った。
「そうですか。ならぜひ時間、作ってください。去年のお礼をしたいんで、奢りますから」
『・・・ああ、去年なあ』
「その節は、お世話になりました」
『それはええけど。あのときの娘(こ)とは、どうなったん?』
からかうような口調。
・・・ああ、そっか。
吉澄さんは、俺がひと目惚れの美人を追っかけて、ふらふらと新幹線までついて行ったと思ってるんだっけ。
―――まあ確かに、俺は岩城さんの美貌にひと目惚れしたんだけど。
「・・・ええ、まあ」
『声、かけたんやろ?』
曖昧に言葉を濁した俺に、吉澄さんは苦笑した。
『君みたいなええ男に口説かれて、なびかん女いてるんか』
「あはは、そんなこと」
『ま、ええわ。その辺は、会(お)うたときに聞かせてもらお』
「そうですね。いつがいいかな」
俺はそう言いながら、キャビネット上のカレンダーに目をやった。
『場所やけど、行きたいとこがあんねん。ちょい待ってや』
受話器の向こうで、ガサガサと紙をめくる音がした。
『ここやここや。えっとな、東京ミッドタウンの、○○ホール・・・』
「何か、やってるんですか」
意外なリクエストに、俺は目を丸くした。
『・・・なに、ボケたこと言うてんねん』
吉澄さんは、心底呆れたような声を出した。
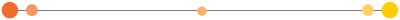
藤乃めい
24 June 2007
2013年4月20日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。