さしも知らじな 第七章 その2
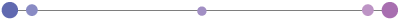
☆ ☆ ☆
ピカピカの新しい高層ビル群と、豊かな緑の森。
六本木ワンマイルに登場した、新しい複合施設。
総ガラス張りのオフィス階があって、ショップやレストランがあって、美術館があって。
平日なのになんだかすごく人が多い、華やかな都心の新シンボル。
―――東京ミッドタウン、って名前のセンスはともかく。
「いや、すっごいとこやねー」
梅雨晴れ間のきつい日差しに、細い目をいっそう眇めながら。
吉澄さんは、のんびりと辺りを見回してため息をついた。
雑踏を避けて、わずかによろめく。
「東京は何年か来ないと、ほんま、まるでわからんようになるなあ」
素直な感想がいかにも彼らしい。
「住んでたって、そう思いますよ」
一緒に青白い高層ビルを見上げながら、俺は笑った。
グラビア撮影に使ったりするから、話題のスポットには案外と縁があるけど。
「で、○○ホールってどこなん?」
インフォメーション・デスクでもらった施設案内のパンフレットを手に、吉澄さんは額の汗を拭った。
―――もう夕方近いのに、ヤバいくらい暑い日差し。
「あっちじゃないかな・・・?」
洒落た案内の標識を頼りに、俺は指差した。
「ほな、行こか」
助かったって表情で笑って、吉澄さんは歩き出した。
☆ ☆ ☆
ひんやりとした、打ちっぱなしコンクリート。
複雑に入り乱れたスポットライトの照明。
ふんわりとほの暗い空間に、冷たい空気が流れていた。
ひそやかなざわめきと、カツカツ響く靴の音。
「えらい立派やなあ」
「・・・そうですね」
真新しい○○ホールは、別世界だった。
外の世界から完璧に遮断された、人工的な静謐。
自然と、俺たちの会話もひそひそ声になる。
「こっちやな」
効きすぎる空調に、肩をすくめながら。
吉澄さんはそろそろと滑るように歩き出した。
「××賞受賞作品展示会」
そっけないほどの小さなプレート。
俺はその前で、いったん足を止めて深呼吸した。
―――岩城さん。
この半年、本物の岩城さんに夢中で、すっかり忘れてた。
あの、奇跡の写真。
暮れなずむ野宮神社と、闇に融けていきそうな岩城さんの横顔。
この世のものとは思われない、儚げな麗人。
俺の心を一瞬で捉えた人。
あの写真を、俺は××賞に出品したんだった。
岩城さんと初めて口をきいた、直後のことだ。
もちろん、被写体の許可は得てない。
快諾してくれるとは、とても思えなかったから。
『好きにしろ』
―――あのときの言葉を、拡大解釈しただけ。
判別できるほどには、顔が見えないってのもあるし。
どうせ受賞するわけないから、というのも理由だった。
―――言い訳かな。
何しろ、天下の××賞だ。
芸術写真のコンクールとしては、たぶん日本で最高ランクの賞だろう。
俺みたいな売れないファッション・カメラマンにとっては、身のほど知らずの挑戦。
・・・っていうより。
記念受験、って感覚に近いかもしれない。
―――岩城さん。
あのときの俺の高揚と、降臨した稀有のビジョン。
俺なりに精一杯、カメラに収めたつもりだった。
俺の最高の、一期一会。
生涯の記念になるはずの一枚だったから。
会場は意外にも、大勢の客でごった返していた。
静かな群集を掻き分けるように、俺たちは展示された作品をひとつひとつ眺めた。
今どきの写真はスケールが小さいとか、誰かの猿真似だとか。
そういう批判も、よく耳にするけど。
そこに並ぶ作品は、どれも真摯な力作に見えた。
本気でアートとしてのフォトグラフィを目指す人間の、気概や気負いが透けて見えてくるような―――。
見ているだけで、興奮で肌がざわざわした。
「君の写真は、どこやろな」
独り言のように、吉澄さんが呟く。
「ここにはないんちゃうか」
「みたいですね」
「ほしたら、あっちの―――」
受賞作品は、いちばん奥まった特設エリアにある。
吉澄さんはちらりと、そっちに視線を走らせた。
「受賞してるわけないですってば」
俺は苦笑した。
そう、俺はここでは門外漢だ。
適当に・・・とは言いたくないけど、なんとかカメラで食ってる程度の人間に、こんな名誉は似合わない。
―――卑下するわけじゃない。
だけど、場違い感は否定できなかった。
展示作品が放つ、独特の緊迫感。
高評価を渇望する、チリチリした自意識。
俺には、そこまで剥き出しの欲望はない。
―――名誉がほしくて応募したわけじゃない。
それが果たして良いことなのかどうか、わからなくなる。
「・・・あれは?」
吉澄さんが、白い壁のいちばん奥に視線をやった。
特設エリアのすぐ入口。
そこだけ妙に、人だかりが出来ている一角。
壁の隅に、巨大な生け花が鎮座してた。
「今年の大賞のコーナーじゃないですか」
首をそちらに向けて、俺は答えた。
「見てみよか」
忍び足って感じの歩き方で、吉澄さんが歩き出す。
俺は頷いて、その後に従った。
「うわー・・・」
そう唸ったきり、吉澄さんが口を噤んだ。
吸い寄せられるように、パネルに見入ってる。
「吉澄さん?」
その肩越しに、俺はひょいっと白い壁を覗いた。
押し殺された、幾つもの吐息。
周囲の人間の衣擦れの音すら聞こえてくる静けさ。
熱気をはらんだ空間に、一筋のスポットライト。
「え―――」
俺は思わず、低い声を漏らした。
―――息が、止まるかと思った。
何十と言う視線が交錯し、集中するその焦点に、彼がいた。
闇に佇む、輪郭線もぼやけた岩城さん。
色を落としたわけでもないのに、墨染めみたいなスティル。
俺の、最高の一期一会。
「うっそ・・・っ!!」
うっかり喉から、素っ頓狂な声が出た。
隣りに立ってるおばさんが、眉をしかめて俺を睨みつける。
「・・・!」
ゴホン、とご丁寧に咳払いまでして。
周囲がざわめく。
「香藤くん?」
その場で立ちすくんだ俺を、吉澄さんが振り返った。
「どないした・・・」
言いかけて、ふと。
やっと思いついたように、パネル下のプレートに目をやった。
小さな金色のリボンが添えられた札には、「香藤洋二」の印字。
「香藤くん、これ、君の・・・!?」
ふだん飄々としてて、めったに大騒ぎしない吉澄さんが、あんぐりと口を開けた。
「は、はい・・・」
俺もただ呆然と、子供みたいに頷いた。
他に言葉が出てこない。
俺の写真。
たしかに、俺の写真だ。
―――信じられない・・・!
「え、えらいこっちゃ・・・!!」
俺の両腕をむんずと掴んで、吉澄さんは叫んだ。
珍しく興奮してるのか、声がでかい。
「大賞やんか、君の写真!!」
「吉澄さん、そんな大きな声で・・・」
俺たちの会話を漏れ聞いて、一気に周囲が色めいた。
ざわめきが広がり、波紋のように広がる。
視線が俺たちに―――俺に突き刺さった。
「あ・・・あなたが撮ったの?」
隣りのおばさんが、俺を見上げて訝しげに問いかける。
「そうです」
「まあ・・・!」
「・・・去年の秋、京都で偶然・・・」
茫然と、呟く。
俺は再び、全紙サイズのパネルの中の岩城さんを見つめた。
―――俺の、岩城さん。
ほの暗い神社の鳥居で、無防備に晒された憂い顔。
人待ちのやるせなさを滲ませた、淋しい淋しい美人。
「岩城さん・・・!」
今の俺は、岩城さんのいろんな表情を知ってるけど。
この横顔が、俺の原点だ。
この人に魅せられて、どうしようもなく恋に落ちて半年。
俺の人生は変わってしまった。
―――岩城さんが好きだ。
今の俺は、彼の肌の熱さも、吐息の甘さも知ってるけど。
それでもまだ、彼は俺にとって憧れの人だった。
忘れ得ぬ麗人。
―――もうずいぶん、会ってない。
ふと、俺はとてつもない渇きを感じた。
岩城さんへの、凶暴な飢え。
それは本当に思いがけないほどの、唐突な衝動だった。
欲しい。
会いたい。
がっしり抱きしめて、めちゃくちゃに愛し合いたい。
本物の、本当の恋人同士として・・・!!
「吉澄さん!」
「うん?」
俺は振り返って、頭を下げた。
「すみません、俺、急用を思い出しました」
「はあ!?」
吉澄さんが、首を傾げた。
「今、どうしても、会わなくちゃならない人がいるんです」
パネルの中の岩城さんに視線をめぐらせて、俺は大真面目に続けた。
「俺はあの人を、失いたくない」
「はいー?」
「だから・・・ごめんなさい!」
「ごめんて、君・・・」
吉澄さんが、目を白黒させる。
「また、連絡しますんで・・・!!」
捨て台詞のようにそう言って、俺は駆け出した。
会場を抜け出して、ぎらぎら夕陽の照りつける街に飛び出す。
目眩がするほどの蒸し暑さ。
すぐに汗が吹き出して、首の後ろを伝った。
―――会いに行こう。
今、すぐに会いたい。
あの声が聴きたい。
・・・何を畏れていたんだろう。
ぐるぐる考えてても、岩城さんは俺のものになってはくれない。
「岩城さん―――」
迷うことなんて、何もない。
ただ真っ直ぐ、ぶつかっていくしかない。
ようやく吹っ切れた気分で、俺は地下鉄の駅への階段を駆け下りた。
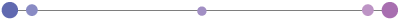
藤乃めい
24 June 2007
2013年4月24日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。
それにしてもホント、返す返すも、振り回される吉澄さんがお気の毒です(自分で書いておいて無責任だけど)。こんな寛大な先輩、いないよね・・・。