さしも知らじな 第十章 その1
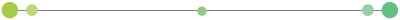
翌朝。
なぜだか俺は、ずいぶん早く目が覚めた。
岩城さんの部屋で迎える朝。
もちろん、これも初体験だ。
カーテンの隙間からは、強い夏の日差し。
裸のままそろそろとキッチンから戻って、俺は寝室の中ほどで足を止めた。
「あは、かわいい―――」
岩城さんは、すーすーとまだよく寝ていた。
初めて見る寝顔だった。
目じりにはうっすらと涙の痕。
くちゃくちゃの黒髪が、彼を幼く見せていた。
嵐の後みたいに乱れたシーツが、しんなり身体を覆ってる。
そのきめ細かい白い肌に、俺はこっそり感嘆した。
明るいところで見て、こんなにきれいって凄い。
改めて、無心に寝ている恋人が奇跡に思えた。
愛おしい。
愛おしくて、たまらない。
―――いつもこんなふうに、安らかな顔でいてくれるのなら。
俺はマジで、なんでもできると思った。
彼を守りたい。
なんだか胸がいっぱいになる。
「・・・ありがと、岩城さん」
そうっと布団にもぐって、俺はなめらかな肩を引き寄せた。
暖かい身体が、しなやかに波を打つ。
ゆるりと、俺の胸元に抱き込んで。
「好きだよ―――」
口にするたびに、愛しさがつのった。
左肩に感じる彼の重みが、心地いい。
彼の鼓動が聞こえる。
静かな寝息が聞こえる。
岩城さんの存在が、俺を幸せにしてくれる―――。
「・・・あは」
ふと、間近で見ると。
鎖骨にもうなじにも、薄紅色のキスマーク。
さくらの花びらみたいに散って、彼の白い肌を飾っていた。
―――女の子相手でも、俺。
「こんなにつけたこと、ないけどな・・・」
自分がどれだけ貪欲に、岩城さんを欲しがったかが分かる。
気恥ずかしい、でも悪くない気分。
『痕はつけるな』
最初のセックスのときの、彼の台詞を思い出す。
昨夜はもちろん、そんな制止はなくて。
やたら所有の証を刻みつけたがる俺を、岩城さんは許してくれた。
―――男のエゴ、丸出しだよな。
テンション上がりっぱなしで、まったく余裕のなかった俺。
笑ったり怒ったり、みっともなかっただろうと思う。
憤慨のあまり、彼を怖がらせてしまった場面もあった。
でも岩城さんは黙って、やさしく包み込んでくれた。
―――こんな俺でいいの?
俺の心の奥底にあった、ほんのかすかな迷い。
それに気づかないふりをしてくれた。
「ありがとね、岩城さん」
あたたかな胸で、俺の激情を受け止めてくれた。
慈しむように、全身で。
正直、岩城さんも、昨夜はそれどころじゃなかったのかもしれないけど。
「ふふ・・・」
この上なく満ち足りた気分で、俺は岩城さんの肌をなぞった。
―――ほら、ここにも。
狂おしい一夜の記憶を辿る。
ゆっくり指先で、乳首の噛み痕をくすぐって―――。
「・・・こら・・・」
ほとんどため息のような、甘い響きだった。
うっそりと目覚めた岩城さんが、ぼんやり俺を見上げた。
「なに、して・・・」
「おはよう、岩城さん」
俺はにっこり笑って、彼の頬に手を添えた。
「・・・んん・・・」
そのまま、甘ったるい朝のキス。
舌で岩城さんの唇をこじ開けて、深くくちづけた。
ほの白い肌がざわめいて、俺の腕の中でそそけ立つ。
「・・・はっ・・・」
思いがけない濃いキスを交わした。
ねっとりと唾液を絡めとってから、俺はそっと顔を離した。
「おまえっ・・・何を・・・」
岩城さんが、むせ込んで胸を喘がせる。
「おはようのキス。お約束でしょ?」
「・・・馬鹿。朝から、こんな―――」
すっかり頬を上気させて、岩城さんが呟いた。
「いいじゃん。それより、ね?」
「なんだ?」
俺はがっしりと、岩城さんを抱き寄せた。
「好きだよ、岩城さん。ゆうべは最高だった」
俺としては、極上のキメ声で言ったつもりだったんだけど。
「・・・!」
ぽかんと口をあけて、岩城さんは俺をまじまじと見返した。
まさに、鳩が豆鉄砲を食らったような顔。
それから頬が、見る見るうちに真っ赤に染まった。
「バカ・・・ッ」
隠れるように、俺の胸に顔を埋める。
―――俺、そんなに意外なこと言った?
そう、聞こうと思ったとき。
何かを思い出したように、岩城さんが急に顔を曇らせた。
「あっ・・・」
「どしたの?」
俺の抱擁から逃げ出そうと、もがいて身体を起こす。
「へ?」
シーツに片手をついて、上半身を起こそうとして。
「ぐっ・・・」
まるで力尽きたみたいに、岩城さんはベッドにへたり込んだ。
「岩城さん!?」
「つう・・・っ」
驚愕の顔つきで、岩城さんが俺を見つめる。
茫然、って感じで。
「あれ・・・?」
眉間にしわを寄せながら、岩城さんの手が伸びた。
そろそろとシーツの下へ。
裸のままの自らの下半身を、恐るおそる下りてゆく指先。
ぎこちない、確かめる仕草。
彼の背中を抱き支えながら、俺は首を傾げた。
「どうしたの?」
「あ―――っ」
腰の下まで手を這わせて、はたと。
岩城さんは、困ったように俺を見た。
「香藤」
「うん?」
きれいなきれいな暝い瞳が、不安に揺らめいた。
いや、逡巡かな。
「おまえ、もしかして・・・そのっ・・・」
彼らしくないしどろもどろの口調。
ゆらぐ視線に、俺はやっと気づく。
「あ、もしかして、後ろ・・・?」
仰天して、岩城さんが息を呑んだ。
「・・・なっ・・・!!」
上気した顔から、さあっと血が引くのがわかる。
「一応、後始末したつもりだけど、俺」
ぱくぱくと、紅い唇が動いた。
俺の言葉が、心底、信じられないというように。
岩城さんは俺の腕の中で、ただ呆然としていた。
「岩城さん、意識を失っちゃったから―――」
「・・・!!」
ぺろりと舌を出して、俺は苦笑した。
「あんなに中で出しちゃった俺が悪いんだし、ね」
「・・・!」
「でも、ちゃんとできてるかは―――」
「ば、馬鹿ッ」
耳まで真っ赤に染めて、ふいに岩城さんが俯いた。
「そんなの、おまえがすることじゃ・・・っ!」
「ごめん。ダメだった?」
俺は困って、彼をそうっと抱き寄せた。
あたたかな身体が、それとわかるくらい震えていたから。
「大事なことだって思ったから、俺・・・」
俺は宥めるように、肩口に柔らかいキスを落とした。
「ごめんなさい。嫌なら、もう勝手にしない」
それから額と、髪の毛に。
「あのまま寝ちゃったらまずいだろうって・・・俺、先走っちゃったね」
「ちがっ・・・そうじゃ、なくて!」
わななく唇を噛んで、岩城さんが首を横に振った。
「うん?」
何か言いあぐねて、絶句してる。
よく見ると、岩城さんは怒ってるわけじゃなくて。
むしろ恥ずかしいとか、いたたまれないって感じの―――。
「・・・香藤・・・っ」
ふいに岩城さんは、俺の胸に縋りついた。
しなやかな腕が、俺の背中に廻される。
「い・・・わきさん!?」
じわりと、俺の胸に熱いものが伝った。
―――涙・・・!?
岩城さんは泣いていた。
震える肌が、俺の身体に擦りつけられる。
「・・・くっ・・・」
動転しながら、俺は岩城さんを背中からすっぽり抱きかかえた。
「ど、どうしたの!?」
「・・・ぉっ・・・」
俺の名前を呼ぼうとして、失敗して。
―――唇を震わせて、岩城さんは涙を零した。
俺の腕の中で、子供みたいに泣きじゃくっていた。
「岩城さん・・・!!」
俺が、泣かせた?
―――なんで、なんで、なんで・・・!?
戸惑いながら、俺は必死で恋人の背中をさすった。
ほかにどうしたらいいのか、皆目わからなかったから。
ただ、ぬくもりをあげたくて。
「ねえ、泣かないでよ」
ふるふると揺れる黒髪に、俺はキスを落とした。
ねえ、好きだよ。
心から愛してるよ。
お願いだから、泣かないで。
あなたに泣かれると、俺、辛くて・・・!
「ごめん、岩城さん。本当にごめん」
裸の肩をゆっくりと摩りながら、俺は繰り返した。
ほかに、何を言えばいいのかわからない。
「俺が悪かったなら謝るから、もう、泣かないで・・・」
憤然と、岩城さんは首を横に振った。
違うのだと。
伝えたいことは他にあるのだと、言いたげに。
「岩城さん・・・?」
「・・・かとっ・・・」
嗚咽をこらえて、俺を呼ぶ恋人。
そう、恋人なんだ。
俺はその顎を捉えて、顔を上げさせた。
涙に濡れた顔が、ゆっくり現れる。
―――ああ、なんて綺麗なんだろう。
ふるえる睫毛。
その奥で、澄んだ瞳がまたたいた。
俺を見る目が、なぜか痛々しい・・・いや、眩しそうで。
―――嫌われたわけじゃないよね?
すがるような視線。
甘い吐息。
彼は、俺を嫌がってるわけじゃない。
それがなんとなく分かって、俺はこっそり胸を撫で下ろした。
「香藤・・・」
わななく唇が、好きだ、と言った気がした。
せつない吐息交じりで、うまく声にはならなかったけど。
「・・・え?」
涙でぐちゃぐちゃに濡れた白皙。
それでも岩城さんは、顔を逸らしはしなかった。
何より雄弁な、燃えるような瞳。
もう迷わないと、そう言いたげな眼差しだった。
「・・・香藤」
魔法の呪文みたいに、何度も俺の名前を呼ぶ。
あたたかい肌が、俺の胸に押しつけられる。
「うん?」
じっと俺の目を見据えて、岩城さんが口を開いた。
ありがとう、と。
小さな小さなささやき。
それから、力強い両腕が、ぎゅっと俺を抱き返してくれた。
「岩城さん・・・っ!」
俺は夢中で、彼を抱きしめた。
岩城さんの抱擁。
腕の中の恋人が愛しくて、おかしくなりそうだった。
―――愛されているのかもしれない。
本気でそう思ったのは、その瞬間が初めてだった。
ただ許されるだけ、与えられるだけではなく。
俺の存在を、岩城さんはみとめてくれた。
心を預けてくれたのだと、そのとき俺は確信した。
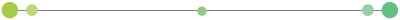
藤乃めい
11 September 2007
2013年6月11日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。