さしも知らじな 第十章 その2
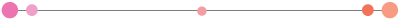
☆ ☆ ☆
「―――落ち着いた?」
シャワーを浴びて戻ってきた岩城さんに、俺は微笑した。
きっちり着込んだ、爽やかなシャツとジーンズ。
ちょっと上気した頬。
「ああ」
照れくさそうに、岩城さんが頷いた。
そんな仕草ひとつに、胸が躍った。
「お腹、すいたでしょ」
朝日の降り注ぐキッチン。
コーヒーのいい香りが、部屋いっぱいに充満していた。
俺はにっこり笑顔で、テーブルを回って岩城さんに近づいた。
「そのまま座って?」
椅子についた彼の手から、バスタオルを取り上げる。
「おい・・・?」
ためらいの抗議は、このさい無視。
俺は濡れ髪をさっさと拭き始めた。
「ホント、きれいな髪だよね」
感心しながら、俺は岩城さんのつややかな髪を撫でた。
ついでにちょこんと、つむじにキス。
「何をしてる」
戸惑うような、小さな声。
でも身じろぎひとつしないで、俺に好きにさせてくれる。
―――慣れてないんだよね。
今さらだけど、俺は改めてそう思った。
甘えること。
甘やかしてもらうこと。
バカみたいな睦言を言ったり、言われたりすること。
―――そういう恋人同士のささやかなスキンシップを、岩城さんは知らない。
それがわかりすぎて、哀しいくらい。
「ねえ、岩城さん」
「なんだ?」
岩城さんが、視線をまっすぐに上げて俺を見つめる。
「好きだよ」
俺は細い頤(おとがい)を捉えて、キスを落とした。
岩城さんは苦笑して、目を閉じてそれに応えてくれる。
「大好き・・・」
「・・・ん・・・」
そっと舌を絡めて、唾液を交わしあう。
深いけど、やさしいくちづけ。
しばらく柔らかい咥内の感触を、存分に味わってから。
ちゅ、と音を立てて、俺はゆっくり唇を離した。
視線が絡み合う。
俺はそっと指先で、岩城さんの首筋を撫でた。
白い、きれいな項。
風呂あがりの肌の淡い香り。
「・・・ん・・・」
シャツの襟をぐっとくつろげて、俺はそこにもキスをした。
見えないところに、紅い刻印。
舌先でゆっくりと、キスマークをなぞる。
「香藤・・・」
ため息のように俺を呼ぶ声。
岩城さんの手が後ろにまわり、俺の頭を捉える。
引き寄せたいのか、押しとどめたいのか。
―――自分でも、どっちなのかわからないのかもしれない。
「おい・・・」
「うん」
俺は身体を起こして、にっこり笑った。
「朝ごはん、できてるよ」
もう一度、岩城さんの髪を撫でる。
くすぐったそうに肩をすくめて、彼は頷いた。
―――そう。
岩城さんが甘やかされる悦びを知らないのなら、俺が教えればいい。
恋人といちゃいちゃする楽しさを、少しずつ覚えていけばいい。
そうやって絆は、深まるものだと思うから。
岩城さんらしいって、言えなくもないけど。
正直、冷蔵庫に大したものはなかった。
だからずいぶん、ありあわせの食卓だったけど。
「おまえは、器用だな」
岩城さんはにこにこしながら、ご飯をおかわりしてくれた。
炊き立てご飯とハムエッグ。
それにツナとトマトのサラダ。
―――実際、めちゃくちゃな取り合わせなんだけどね。
「美味しい?」
「ああ」
「俺、今度はもっとがんばるよ」
嬉しそうに笑ってくれる岩城さんが、本当に嬉しくて。
俺は惚けたように、岩城さんの笑顔を見つめた。
「・・・食べにくいだろう」
繋いだままの片手に視線をやって、岩城さんが苦笑した。
「イヤ?」
「そういう意味じゃ・・・」
「じゃあ、このままでいいじゃん」
いつでも岩城さんに触れていたいんだよ。
そう囁いたら、彼は真っ赤な顔をして俯いた。
―――マジ、かわいすぎ・・・!
心臓がバクバクして、股間が不埒にざわめく予感。
昨夜あれだけ愛し合ったのに、また彼を押し倒してしまいそうで。
俺は必死で、暴走しそうな欲望にブレーキをかけた。
☆ ☆ ☆
「おい、香藤・・・」
マンションの外に出たところで、岩城さんがふと足を止めた。
「なに?」
「なに、じゃなくて―――」
困り果てたような表情で、岩城さんは俺を見つめた。
「あ、ごめん」
繋いだままの手と手。
それに気づいて、俺は苦笑した。
エレベーターの中からずっと、指を絡めたままだったから。
ほとんど人通りのない、日曜日の朝だけど。
「行こっか!」
俺はにっこりして、名残り惜しげに腕を放した。
暦の上では秋。
と言っても、まだまだ残暑の厳しい季節。
まぶしい強い日差しが、容赦なく降り注いでいた。
おとなしくついてくる岩城さんと一緒に、俺は地下鉄に乗り込んだ。
「どこに行くんだ?」
乗客もまばらな先頭車両に腰かけて、岩城さんが聞いた。
「秘密だよ」
―――本当は、昨日から決めてたことだけどね。
俺は何も言わずに、さりげなく岩城さんに寄り添って座った。
「こら、香藤」
ぴったり身体をくっつけた俺を、たしなめるような口調。
全身をわずかに強張らせて、周囲を気にしてるのがわかる。
「こうしてれば、わからないでしょ」
悪戯っぽく笑って、俺はことん、と彼の肩に頭を乗せた。
「・・・!」
「お・や・す・み」
さっさと目を閉じて、俺は速攻で眠ったふり。
「・・・まったく」
諦めたような、嘆息交じりの言葉。
その吐息が、俺の耳をくすぐって髪を揺らした。
「ふふ」
俺はこっそり笑って、体重の半分を岩城さんに預けた。
☆ ☆ ☆
昨日は、駆け足で後にした東京ミッドタウン。
なんだか今日は、まるで違う場所に見える。
「こっちだよ」
○○ホールを目指していた俺は、ゆっくりと岩城さんを振り返った。
すっと腕を伸ばして、彼の表情を窺う。
「手、繋ごうか?」
「は?」
「迷子になるといけないし」
「・・・バカ」
さっきよりは、余裕があるのかもしれない。
小さく笑ってから、岩城さんは小さく悪態をついた。
「さっきから、調子に乗りすぎだ」
俺が差し出した手を、じっと眺めて。
それからパシリ、と手のひらを軽く叩いた。
ほんの一瞬の触れ合い。
それでも、岩城さんのほうから俺に触ってくれるのが嬉しい。
「痛いよー」
「ウソつけ」
「・・・久しぶりのデートなのに」
「何を言ってる」
相変わらず、言葉はそっけないけどね。
「つれないなあ」
でも清々しいほどの、邪気のない笑顔を見せてくれた。
この人って、こんな屈託のない顔で笑えるんだって思った。
恋人だけに見せる表情、だよね・・・?
「岩城さん・・・!」
俺を受け入れた岩城さんは、まぶしいくらい美しい。
彼のまとってる雰囲気の柔らかさに、俺はなんだか泣きたくなった。
こんな幸せでいいんだろうか。
こんなに幸せそうな岩城さんを見られるなんて。
「どうした?」
「なんでもないよ」
岩城さんは、俺のものだ。
俺だけの恋人だ。
岩城さんが、この世に存在する奇跡。
―――俺のそばにいてくれる、二重の奇跡。
俺は改めて、彼との出会いに感謝した。
昨日の今日だから、勝手はわかってる。
・・・つもりだったけど、展示の最終日のせいか、ホールは思った以上に混んでいた。
―――日曜日の朝なら、すいてると思ったんだけどな。
俺は内心、ため息をついた。
計画を変更するつもりはないけど、これはちょっと予定外。
「香藤、ここ・・・?」
打ちっぱなしコンクリートのエントランスの、小さなプレート。
『××賞受賞作品展示会』
それを見て、岩城さんが首を傾げた。
「うん?」
「おまえ、出してるのか?」
目を瞠って、小声で聞いてくる。
「知ってる、この賞?」
「聞いたことくらいはある」
憮然とした岩城さんの返事に、俺は苦笑した。
―――そりゃあ、そうか。
芸術写真のコンクールとしては、日本で一番有名だし。
最近じゃ、国際的にも注目されてるらしいしね。
岩城さんがどこかで耳にしていても、不思議はない。
そう考えると、余計に胸が躍った。
「見せたいものがあるんだよ」
俺はにっこり笑って、岩城さんを奥のスペースに誘(いざな)った。
「けっこう人がいるもんだな」
「そうだね」
会場はかなり混雑していた。
昨日よりも飾られた花が増えてるように見えるのは、俺の気のせいだろうか。
白い壁のコーナーには、ずいぶん大勢の人が群がっている。
―――正直、ありがた迷惑なんだけどなあ。
「あそこだよ、岩城さん」
それでも俺は、岩城さんの腰を後ろからそっと押し出した。
「え?」
俺の表情に、何かを感じ取ったのかもしれない。
「あそこって・・・?」
半信半疑の視線が、流れるみたいにゆれた。
「うん」
吸い寄せられるように、岩城さんは足を踏み出した。
ひそやかな雑踏。
ため息のようなざわめき。
壁の向こうの大賞受賞作品を眺める、たくさんの眼差し。
それをかいくぐるように、岩城さんが真っ直ぐに向かっていく。
ある種の予感と慄(おのの)きを持って。
俺は黙って、彼の背筋の伸びた後ろ姿を追って歩いた。
「・・・!!」
視界が開けて、パネルが姿を現した瞬間。
岩城さんは唐突に足を止めて、息を呑んだ。
「香藤・・・っ?」
かすれた声が、俺の耳に甘くせつなく響いた。
周囲の視線もざわめきも、一気に遠くなった。
「・・・うん」
俺は静かに頷いて、岩城さんの隣りに立った。
全紙サイズのパネルの中に、ひっそりと佇む岩城さん。
憂いを含んだ淋しい横顔。
晩秋の闇に融けていくような、淡い麗人のポートレイト。
俺の渾身の一期一会。
作品のタイトルは、「さしも知らじな」。
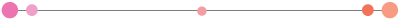
藤乃めい
17 September 2007
2013年6月14日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。
なお、かなり蛇足だとは思いますが>>
『かくとだにえやはいぶきのさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを』
(藤原実方朝臣、後拾遺集)
私流に訳せば、「私がどれほど恋い慕っているか、この燃え上がる思いを、あなたはご存じないでしょう」・・・という感じでしょうか。