さしも知らじな 第十章 その3
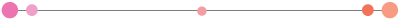
とても長い時間だったような気がする。
いや、あるいは、ほんの一瞬だったのか。
ただ、呆然と。
息をするのも忘れて、岩城さんは俺の写真に見入っていた。
いや、写真の中の自分自身に。
―――去年の秋の、やるせない孤独。
そのときの記憶の痛みを、思い出しているのかもしれない。
「おまえの写真・・・?」
「うん」
「大賞、なのか」
「そうだよ」
ため息みたいに息を吐いて、俺はひっそりと口を開いた。
「覚えてる、岩城さん? この写真、前に見せたの」
「・・・ああ」
嘆息のようなか細い答え。
岩城さんは、パネルに釘づけだった。
「これね、俺が、岩城さんに恋をした瞬間だよ」
―――そのときは、気づいてなかったけど。
「ひと目惚れ、だったんだ」
「・・・ばっ・・・」
慌てたように、岩城さんが周囲に視線を巡らせた。
俺は岩城さんの背中を宥めるように撫でて、きっぱりと首を振った。
「いいから、聞いて」
「・・・でも、香藤!」
困惑しきった彼の呼びかけ。
それでも俺は、やんわりと遮った。
「××賞に出品しようって決めたとき、タイトルにすごく悩んでね・・・」
俺はちらりと、パネルの下のプレートに目をやった。
―――岩城さんにも、見えているはずだ。
「結局、百人一首でこれを見つけたんだ。かくとだに、ってやつ」
「ああ・・・」
かすれた相づちが、呆然と返ってきた。
「さしも知らじな、か―――」
きれいな音を舌の上で転がすように、岩城さんが言った。
「うん。燃ゆる思いをってのが、ちょうどそのときの、俺の気持ちにぴったりだったから」
岩城さんの端正な美貌を、俺はじっと見つめた。
彼は全身を緊張させて、俺の言葉を聞いていた。
「っていうかね。この写真を見て、自分の気持ちに気づかされたんだ」
「香藤・・・」
「俺は岩城さんが好きなんだ、って」
「・・・っ」
息を呑んだ岩城さんの、切れ長の瞳が揺れた。
彼の頬が、わずかに紅潮する。
―――周囲の人間が、さざ波みたいに囁きあうのがわかったけど。
俺にはもう、何も気にならなかった。
岩城さんしか、俺には見えなかった。
本当に大事なものは、他に何もなかったから。
「・・・こんな、ところで・・・」
岩城さんが、くちびるを震わせた。
ぎゅっと握りしめられた拳。
逃げ出したくて、いたたまれなくて。
それでもどうにか、踏みとどまっているんだろう。
「好きだよ、岩城さん」
俺は彼の手を引き寄せて、手のひらを重ねた。
指をからめて、しっかりと手を繋ぐ。
周囲から、小さなどよめきが起きた。
「・・・!」
「俺なら、岩城さんにあんな顔はさせない」
きっぱりとそう言って、俺はパネルの中の彼を見つめた。
それは、今までの彼。
この世のものとは思えないほど、儚げな立ち姿の美人。
魂を奪われるほど、ものすごく綺麗だけど。
でも、哀しいくらい孤独だった。
胸を締めつけられるほどせつない―――。
「ずっと傍にいる」
「・・・」
「一生ずっと、こうやって岩城さんと手を繋いで歩きたい」
「・・・香藤・・・」
「何があっても、離れない」
不安にわななく紅い唇が、俺の名前を呼んだ。
「一生、幸せにする。・・・約束するよ、岩城さん」
俺はにっこり頷いて、繋いだ手を力強く握りしめた。
「これが俺の、本気だよ」
―――だから、岩城さんも覚悟を決めて。
心の裡でそう続けて、俺は岩城さんを見つめた。
どのくらい時間が経ったんだろう。
実際には、ほんの数秒だったかもしれない。
それでも俺には、永遠に近いほど長かった。
「・・・香藤」
ふと、掠れるような声。
「うん?」
岩城さんの視線はまだ、白い壁に飾られた俺の『さしも知らじな』を見据えてた。
「手を・・・」
その声はなんだか、震える吐息みたいに聞こえた。
「うん」
そっと頷いて、俺はゆっくり手を放した。
彼はすうっとひとつ、深呼吸をして。
それから静かに、俺の顔を見ないままで言葉を紡いだ。
「おまえの携帯の番号を・・・」
「え?」
「教えてくれないか」
「あ・・・うん」
思いがけない台詞だった。
俺は頷いて、ジーンズのポケットから携帯電話を引っ張り出した。
それにちらりと一瞥をくれてから、彼は11桁の数字を口にした。
岩城さんの携帯電話の番号。
この一年間ずっと、欲しくてしょうがなかった。
慌てて俺は、その番号をプッシュした。
「あの、岩城さん・・・?」
彼の腰のあたりで、軽快な着信音が鳴る。
周囲の人間が眉をしかめた瞬間、俺はさっさと電話を切った。
岩城さんは、しばらく俺の写真のパネルを見つめたまま。
「えっと・・・」
つくねんと俺は、そんな彼の様子を窺っていた。
まるでそこだけ、時間が止まったような―――。
「あのう、もしかして・・・」
近くにいた女性がひとり、恐る恐るといった感じで声をかけてきた。
「この写真をお撮りになった、香藤洋二さんですか」
弾かれたように、俺は振り返った。
「え・・・っ」
ホールのざわめきが、急に俺の耳に飛び込んできた。
途端に、現実が押し寄せる。
岩城さんと俺だけの世界が、結界が、音を立てて砕け散った。
「そ、そうです」
取り繕ったような笑顔で、俺は頷いた。
「大賞、おめでとうございます!」
「あ・・・ありがとうございます」
「すっごく綺麗ですね、これ。幻想的で、なんだか・・・!」
興奮気味の賞賛に、俺は照れ笑いを返した。
「まさか、ご本人にお会いできるなんて」
「はあ・・・」
「―――帰る」
ひそりと、穏やかな低い声がした。
踵を返す岩城さん。
「岩城さんっ?」
俺は驚いて、立ち去ろうとする彼の背中を見つめた。
「ちょっと、待って・・・!」
話しかけてくれた女性に会釈して、俺は岩城さんの後を追った。
逃げ出すってわけじゃ、ないんだろう。
岩城さんはゆっくりと、○○ホールの外に出ようとしていた。
窓の外には、強烈な日差し。
はめ込みの窓からきらきらと差し込む。
それが、彼の優雅なシルエットを浮かび上がらせていた。
「岩城さん!」
エントランスのあたりで、俺は彼の肩に手をかけた。
びくりと揺れて、細い身体が硬直した。
「香藤・・・」
ほろりと零れたその声は、戸惑いに満ちていた。
やさしい響きでは、あったけれど。
「あの、岩城さん」
「―――少し時間を、くれないか」
ぽつりと、小さな声。
躊躇いがちに振り返って、岩城さんは俺を見つめた。
漆黒の瞳がまたたく。
―――何が、不安なんだろう・・・?
俺を映してゆらゆらと、深い湖みたいに揺れていた。
「どうしたの、岩城さん」
言い募ろうとした俺を遮って、彼は首を振った。
「しばらく、ひとりにしてほしい」
短くそう言って、岩城さんは唇を噛んだ。
何だか辛そうな―――いや、身の置き所のない感じ、だろうか。
迷いというか憂いというか、そういう感じ。
・・・拒絶、じゃないよね・・・?
「え・・・」
「考えたいことがあるんだ」
「うん?」
「・・・気持ちの整理がついたら、きっと連絡するから」
俯いて、岩城さんはジーンズのポケットを指でなぞった。
そこに携帯電話があるってことかな。
無意識の仕草だろうけど、その色っぽさに俺は苦笑した。
「・・・わかった」
ひとり、考え込んでしまった彼。
俺はしいて、明るい笑顔を返した。
言いたいことは、正直、いっぱいあったけど。
この場はこれ以上、踏み込んじゃいけないと思った。
「すまない」
「・・・ううん」
俺たちは今、やっと始まったばかりだ。
まだまだお互い知らないことだらけで、あたりまえなんだから。
「じゃあ、待ってるから」
天井を向いて、一度深く呼吸をしてから。
俺はにっこりと岩城さんに笑いかけた。
「送って行きたいけど、我慢するね」
俺の軽口に、岩城さんはほのかに口元を綻ばせた。
―――そうやって笑ってくれるなら。
充分だって思うことにしよう。
今までは俺が、俺だけがずっと、岩城さんを追い続けてきた。
一方的な恋が、やっと実ったところなんだから。
岩城さんからの連絡を待つのも、悪くないと思った。
「じゃあね、岩城さん」
一度だけ少し、後ろを振り返ってから。
岩城さんはひとりで、東京ミッドタウンを後にした。
☆ ☆ ☆
俺のありったけのプロポーズ。
思いの丈を、全部さらけ出したつもりだった。
ただ単に、好きだって繰り返すだけじゃなくて。
一生ものの覚悟であることを。
何があっても彼を守るって、そう誓ったつもりだった。
「―――の、はずなんだけど・・・」
岩城さんは終始、無言だった。
身体を強張らせて、ずうっとそこに立ち尽くしたまま。
周囲のざわめきなんて、まったく聞こえないようだった。
その表情からは、どう考えてるかが読み取れなくて。
「連絡くれるって、言ってくれたんだから・・・!」
信じなくちゃいけない。
信じない理由はないはずだ。
岩城さんは俺を、受け入れてくれたんだから。
だからこそ、いろいろ考えたいことがあるんだろうから。
拒否されたわけじゃないんだから。
「でも、キッツイなあ―――」
岩城さんに会いたい。
今すぐ、会いたい。
あの柔らかな熱い身体を、この腕に抱きしめたい。
とびっきりの甘い声でもう一度、俺の名前を呼んでほしい。
俺を欲しがってむせび泣く、あの声が聞きたい。
せっかく思いが通じたのに、もどかしすぎる。
じりじりと待ってることしかできないなんて。
「岩城さんは、俺に会いたくならないの・・・?」
今この瞬間、どこにいるんだろう。
たまには俺のことを、思い出したりするんだろうか。
寂しいと思うことも、あるんだろうか。
会いたい。
会いたい。
会いたい。
俺はなんだか、おかしくなりそうだった。
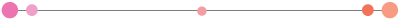
藤乃めい
17 September 2007
2013年6月18日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。