さしも知らじな 第十二章 その1
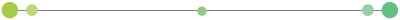
その電話が来たとき、俺は仕事の真っ最中だった。
金曜日の午後、まだ早い時間。
都内の貸スタジオで、女性ファッション雑誌の巻頭グラビアを撮ってた。
『―――香藤?』
「・・・おわあっ!」
ずっとずっと待っていた、恋人の声。
びっくりして、俺は携帯電話を取り落としそうになった。
「おっとと・・・っ!」
ワタワタしながら、小さな端末を必死で握りしめる。
「い、岩城さんっ!?」
声はみっともなく裏返ってた。
ああ、もう、俺って格好悪すぎだろ・・・!
「えっと、ちょっ・・・ちょっと待ってて!!」
片腕をぶんぶん振り回して、俺はディレクターに休憩のサインを送った。
「すみません!」
びっくり顔のスタッフが、モデルと一緒に振り返る。
「10分だけ、ブレイクいいですか・・・!」
―――緊急事態だって、思ってくれるといいけど。
下手くそなパントマイムよろしく、俺は拝むしぐさをした。
俺の勢いに呑まれたのか、皆が頷く。
愛用の一眼レフを床に置いて、俺は周囲にペコリと会釈した。
あとは猛ダッシュで、扉を開けて飛び出した。
「岩城さん、まだいる!?」
『・・・あ、ああ』
古ぼけた雑居ビルの外まで、俺は階段を一気に駆け下りた。
幸い周囲には、誰もいない。
「ごっ・・・ごめんね、待たせちゃって」
駐車場に向かって歩きながら、携帯電話をそっと撫でた。
ホントなら、熱烈なキスを送りたいくらいだ。
『今、都合が悪いなら・・・』
息を切らせてる俺を気遣って、岩城さんが言った。
穏やかなバリトン。
―――ああ、ホントに岩城さんだ・・・!
じわりと、嬉しさがこみ上げてきた。
「ううん、大丈夫だよ」
『仕事中に、すまなかったな』
「いやホント、気にしないで!」
『何時ならいいか、わからなくて・・・』
懐かしい岩城さんの声、息づかい。
俺の名前を呼ぶ、やさしい響き。
初めて聞く電話越しの声に、俺は柄にもなくどぎまぎした。
「ありがとね、岩城さん」
『え?』
「電話、嬉しいよ」
『・・・ああ』
「元気だった、岩城さん?」
『ああ』
やさしい低音が、耳にさらりと心地いい。
―――めちゃくちゃ会いたかったよ。
言いかけて、俺はその言葉を呑み込んだ。
なんだか、恨み言みたいに聞こえてしまいそうだったから。
「あの」
小さな沈黙が、俺を不安にさせる。
「岩城さん・・・?」
『ああ、うん』
また沈黙が落ちる。
滑稽なくらい緊張して、俺は上手くしゃべれなかった。
まるでガキの頃の恋愛みたいな、ぎこちない会話。
「えーっと・・・」
『あのな、香藤。この週末、時間は空いてるか』
岩城さんがさりげなくそう言った。
「へっ!?」
『いや・・・その、先約があるなら、来週でもいいんだが・・・』
「う・・・ううんっ!!」
頓狂な声が頭のてっぺんから出た。
我ながら呆れるくらい、上擦った声。
だって、岩城さんからのお誘いは、全然さりげなくなかった。
「この週末って・・・今週末ってこと!? 今日は金曜日だから、今日からだよね!?」
―――先約なんて、あるわけない。
「ないない、予定なんか何にもないよ!」
いや、たとえあっても、岩城さんより大事な用なんてあり得ないけど・・・!
「・・・たしか、日曜日の夜から仕事が入ってるけど。それまでは、大丈夫のはずだよ」
俺は急いで、脳内でスケジュールをチェックした。
『そうか』
ほっとしたような響き。
「今日、会えるの?」
『・・・おまえさえよければ』
それを聞いて、俺のほうが安堵のあまり脱力しそうだった。
「ほえー・・・」
膝に力が入らない。
俺はぐったりと、自分の車にもたれかかった。
『どうした、香藤?』
「ううん、なんでもないよ。ゴメン、ちょっと気が抜けちゃって・・・」
『は?』
不思議そうな岩城さんの声。
俺は急に、ここ何週間かの葛藤が恥ずかしくなった。
岩城さんを信じてるって、呪文みたいに繰り返してたくせに。
そのわりには、恋に悩む乙女よろしく、ぐるぐるエンドレスに悩んでいた。
まるで全然、彼を信じてないみたいに。
「―――今、しみじみと実感してるよ」
『何をだ?』
ポケットからキーをやっと取り出して、俺は車にすべり込んだ。
運転席にどさりと腰を下ろして、ひと息つく。
それからやっと、携帯にキス。
―――わかってくれたかな?
受話器の向こうで忍び笑いが聞こえた、ような気がした。
「俺って本当に、岩城さんにゾッコンなんだなあ、ってね」
笑ってつぶやくと、小さく息を吸い込む音がした。
「電話ひとつで、心底、舞い上がってるもん」
『香藤・・・』
「嬉しいよ、岩城さん。声が聞けて、本当に嬉しい」
『・・・馬鹿』
そう返す岩城さんの声は、甘くかすれていた。
『・・・仕事は、まだ時間がかかりそうなのか』
「ううん。もうすぐ終わると思うよ」
『上手く行ってるみたいだな』
「ああ、うん。まあね」
『―――新聞で見た。おまえの記事』
ぽつりと、岩城さんがそう言った。
『ずいぶん高く評価されてるんだな。凄いと思った』
「ありがとう。いっとき話題になったけど、今はもう普通に仕事してるよ」
岩城さんが俺のことを気にかけてくれたのかと思うと、なんだかこそばゆい。
俺は、ちらりと腕時計を見た。
「今日は、あと一時間もすれば上がると思う。岩城さんは?」
―――なんて言うの?
まるで普通の恋人同士みたいに、予定を確認してる俺たち。
それだけでなんだか、ものすごく幸せだった。
大げさだけど、ここまで来た、って実感が押し寄せてくる。
『まだ職場だ。俺も、早く上がるようにするから』
「えへへ・・・俺に会いたいと思ってくれてる?」
少しだけ冗談交じりに、俺は笑ってみせた。
『・・・バカ』
今度の「ばか」は、さっきよりも更に甘く聞こえた。
『そうだな、じゃあ8時頃に―――』
初めてのデートの約束。
「うん?」
告げられた待ち合わせの駅名に、俺はちょっと首を傾げた。
「うん、わかった」
岩城さんの自宅でも、勤務先の最寄り駅でもない場所。
どこか、レストランを予約してるとか・・・?
―――なんだか本格的なデートみたいだね。
「うん、絶対行くよ!」
俺は浮き立つ気分で、素直に頷いた。
『じゃあ、後で』
「ちょ、ちょっと待って!」
あっさりと電話を切ろうとした岩城さんを、俺は慌てて引きとめた。
『どうした?』
―――久しぶりなんだから、もう少しだけ。
その声を聴いていたい。
香藤って、もう一度呼んでほしい。
我がままを言いそうになって、俺は思いとどまった。
「ううん、なんでもない」
いけない、いけない。
岩城さんはたぶん、仕事の合い間に電話をしてくれてるんだろう。
約束どおり、連絡をくれた。
あと何時間かで会える。
それ以上を望んだら、バチが当たるってもんだ。
『香藤?』
岩城さんがそっと口にする、俺の名前。
それだけで俺は、幸せな気分になる。
「なんでもない。じゃあ、後でね!」
携帯電話の向こうの恋人に、俺はにっこり笑いかけた。
☆ ☆ ☆
「岩城さん、ここ・・・っ」
俺はあんぐりと口を開けたまま、そう呟いた。
とにかく意外すぎて、他に言葉が出てこない。
「これって、いったい・・・!?」
「珍しいね、彼女からの電話だった?」
スタッフにさんざんからかわれながら、俺はなんとか無事にグラビアの撮影を終えた。
「じゃ、お疲れ!」
一目散にスタジオを飛び出して、地下鉄に乗る。
岩城さんに会える、それだけで嬉しくて。
ラッシュアワーの混雑も、重い機材バッグも何のその。
全速力でスキップしそうな勢いで、待ち合わせの場所に向かった。
約束の時間よりずいぶん早く、着いたつもりだったけど。
「―――岩城さん!」
そこには、ちょっと照れた表情の岩城さんが待っていた。
俺の姿をみとめて、ぎこちない笑顔を見せる。
「香藤」
かすれた吐息みたいに俺の名前を呼ぶ。
俺はもうそれだけで、天にも昇る気分だった。
―――俺の恋人。
雑踏の中でも際立つ美貌。
ああ本当に、どうして男同士って、世間では「イケナイ事」なんだろう?
そうじゃなかったら、その場で彼を抱きしめられるのに。
他人の目ってのがなかったら、熱烈な再会のキスができたのに・・・!
岩城さんが俺を連れて向かったのは、駅からほど近い住宅街だった。
「いいから、来てくれ」
その言葉に、俺はもちろん喜んで頷いたけど。
こんな展開は正直、まったく予想外だった―――。
新築マンションのひと部屋。
壁も天井も真っ白な、とてもシンプルな部屋。
窓にはカーテンもない。
殺風景な―――いや。
殺風景なわけじゃないと、俺はすぐに気づいた。
広いリビングの片隅に積み上げられた段ボール箱。
窓枠にかかったハンガーに吊るされたスーツ。
オープンプランのキッチンにも、使われた形跡はない。
どう見ても、引っ越してきたばっかり―――。
「岩城さん、これ・・・!?」
振り返ると、彼は照れくさそうに小さく笑った。
「ああ、引っ越したんだ」
「引っ越したって・・・!!」
びっくりしてオウム返しに聞いた俺に、岩城さんは一歩近づいた。
「先週末、入居したんだ。まだ何も片づいていないが」
「どうして、いきなり・・・?」
俺の驚愕に、ようやく気づいたみたいに。
岩城さんが苦笑して、俺の腕にそっと触れた。
「驚かせて悪かったな」
「ううん。それは、いいんだけど・・・」
でも、どうして。
視線が絡まり、岩城さんの瞳の奥がゆれた。
俺はゆっくりと腕を伸ばして、岩城さんを抱き寄せた。
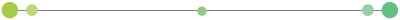
藤乃めい
22 October 2007
2013年6月25日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。