さしも知らじな 第十三章 その2
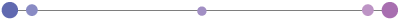
☆ ☆ ☆
「ここ・・・!?」
都心の老舗デパート。
一階のジュエリー売場は、ゴージャスな異空間だった。
高い天井に、きらめく照明。
どこからともなく漂う甘い香水の匂い。
凝ったディスプレイを競い合うカウンターがひしめく。
その一角にはずらりと、海外ブランドの専門店。
綺麗な女性たちのさんざめく、華やかな雑踏がそこにあった。
―――不景気とか言うけど、嘘だよなあ。
土曜日の午後ってこともあって、もの凄い混雑だった。
もちろん女性同士か、こじゃれたカップルが大半だ。
「おい・・・」
「こっちだと思うけど」
パーティみたいな雰囲気に圧倒されたんだろう、岩城さんが立ち竦む。
「香藤、これは・・・」
戸惑っているのが、ありありとわかる声だった。
「気にしない!」
微笑して、俺は彼の手を引いた。
ちょっと強引だったせいか、岩城さんが半分前のめりにつんのめる。
「・・・っ」
「ごめん、大丈夫?」
咄嗟に俺の胸に手をついて、それから慌てて身体を離して。
俺の手を振りほどいて、岩城さんは肩で息を吐いた。
「香藤・・・」
―――ああ、困った顔もかわいい。
朱色に染まったきれいな頬。
途方に暮れたような、彷徨う眼差し。
居心地が悪そうに、恐る恐る周囲を見渡す。
さっきから注目の的だから、まあ、無理はないけど。
「こんなところ、おまえ・・・っ」
「気にしないの」
俺は繰り返した。
―――大丈夫だから。
俺はさらりと、岩城さんの火照った頬に指をすべらせた。
なめらかな肌が、ピクリと震えた。
「よせ・・・」
近くにいた女の子たちが、どよりとざわめく。
気づかないふりで、俺は岩城さんの顔を覗き込んだ。
「ねえ、どれがいい?」
「・・・!!」
結婚指輪のコーナー。
ショーケースの中には、きらきら光る指輪がいっぱいだった。
ゴールド、プラチナ、ダイアモンド。
ルビーやエメラルドのついてるリングもある。
―――昔そういえば、一度だけ。
女の子を連れて、こういう店に来たことがある。
分不相応の高級店。
目いっぱい格好つけて、男のプライドのために、俺はねだられるままにバカ高いファッションリングを買った。
金のかかる恋人の我が儘に振り回された―――と、当時の俺は思っていたけど。
今ならわかる。
そういう彼女を選んだのも、彼女を喜ばせたくて見栄を張ったのも、俺自身だ。
要するに、背伸びしてただけ。
―――なにも分かってなかったよなあ。
俺は今まで、知らなかったのかもしれない。
好きな人にプレゼントするってことが、こんなにわくわく幸せなことだなんて。
「ね、どれにしようか?」
俺は大まじめだった。
岩城さんは嘆息して、まじまじと俺を見返した。
「あのなあ」
「やっぱり、プラチナがいいかなー」
「おい、香藤」
「なあに、岩城さん」
俺はよっぽど、間の抜けたニヤケ面をしてたんだろう。
岩城さんは観念したみたいに首をすくめた。
「正気か、おまえ」
「そうだよ?」
「結婚指輪・・・を買うのか?」
「もちろん!」
さっきまで、考えてもみなかったけど。
―――岩城さんに、マリッジリング。
最高のひらめきだとしか、思えなかった。
「俺、賞金の使い道、ずっと考えてたんだ」
「・・・」
「これ以上の記念ってないと思わない?」
岩城さんと出会った、運命のあの日。
その衝撃を永遠に閉じ込めた、俺の一期一会。
俺たちが今こうして一緒にいるのは、あの奇跡のショットのお陰なんだから。
「まったく、おまえは―――」
俺の考えていることがわかったんだろう。
くすぐったそうに、岩城さんは微苦笑を見せた。
「本当に馬鹿だな」
「えー、なんで」
「せっかくの賞金、もっと大事なことに遣うべきだろう?」
「俺にとっては、岩城さんより大事なものなんかないよ?」
「!」
「いいじゃない、ね?」
「・・・俺なんかにそんな、思いつきで散財しなくても・・・」
「我ながら、最高のアイディアだと思ってるけど?」
「・・・俺は男だぞ?」
「知ってるよ」
「もったいないだろう」
「そういうのはダメ」
「駄目って・・・」
当惑して、岩城さんが少し俯く。
「・・・俺は、指輪なんか・・・」
「普段はしないかもしれないけど、でもさ」
俺はそこで言葉を切った。
そろそろと岩城さんが顔を上げる。
「これは特別だよ。俺のけじめだから」
「けじめ・・・?」
俺は笑顔で頷いた。
「プロポーズだもん。指輪、いるでしょ?」
「・・・!」
ぱあっと、岩城さんの頬が朱に染まった。
小さく、ほんのわずかに、唇が震える。
「・・・女相手ならそうかもしれないが―――」
「俺があげたいの。ね、いいでしょ?」
「あのなあ・・・」
「もらってくれる、岩城さん」
「香藤・・・」
「いらないってのは、ナシだよ」
とっておきのウィンク。
言葉を失って、岩城さんはため息をついた。
決まりだね、と頷いて。
俺は岩城さんを促して、ふたたび結婚指輪のカウンターに近づいた。
「岩城さん、指輪のサイズは?」
「そんなの・・・」
知らない、と岩城さんが首を振った。
「そっか」
俺は頷いて、ディスプレイケースの向こうの女性店員に声をかけた。
「あの、サイズがわからないんですけど」
寸分の隙もない完璧メイクの彼女は、それまで俺たちを呆然と見てたけど。
「あ、はい!」
弾かれたように動き出して、俺にリングゲージを差し出した。
「岩城さん、手を出して」
当惑して、岩城さんが俺を見つめる。
「ちょっ・・・」
「左手、出してくれる?」
リングゲージを持った俺の手を、押しとどめて。
岩城さんは真っ赤な顔のまま、ふと視線を逸らした。
「こんなところで、あまり―――」
「岩城さん・・・」
岩城さんを困らせたいわけじゃない。
恥ずかしがってる・・・いや、いたたまれない思いをしてる。
それは手に取るようにわかる。
―――強引な男でごめん。
そう思ったけど、俺は引き下がらなかった。
仮に男同士じゃなかったとしても、岩城さんはこういう状況は苦手だろうな、とは思う。
―――長いこと日陰の道を歩いてきた人だから、余計に。
そういうものだと、岩城さんは信じていた。
その意識を、俺は変えたい。
変わってほしいと思う。
少々、強引なやり方ではあるけど。
にっこり笑って、俺はそっと聞いた。
「じゃあ、自分でやる?」
「かと・・・」
だって、俺たちが愛し合っていること。
お互いをパートナーに選んだこと。
それを俺は、誇りに思っていたいから。
俺たちには何も疚しいことはないって、信じてるから。
「すみません、見せてもらってもいいですか?」
岩城さんを半ば抱きこむように、ガラスケースを覗き込んで。
俺はいくつか、シンプルなペアリングを指差した。
「これと、そっちと、それから、その奥のを」
「畏まりました」
深紅の布敷きのトレイに、指輪がいくつも乗せられた。
俺はそのひとつを、指先で摘まんだ。
「綺麗だな、これ。どう、岩城さん?」
「どうって・・・」
本当に戸惑った顔つきで、岩城さんがその指輪を眺めた。
「それともこっちのほうが、すっきりしてていいかな」
「香藤・・・」
「うん?」
「本当に本気なのか」
「そうだよ」
俺は笑って、細いプラチナの指輪を選んだ。
斜めに一本ラインの刻まれた、ごくシンプルなデザイン。
「ねえ、つけてみて?」
「・・・っ」
岩城さんは視線を泳がせて、周りの様子を窺った。
目の前の女性店員も、ぽかんと口を開けて俺たちを見ていた。
「ほら、手を出して」
周囲のざわめきは、気合で黙殺。
俺はうやうやしく岩城さんの左手を取った。
白い、綺麗な手なんだよね。
筋張った固い見た目は、たしかに男性の手なんだけど。
「香藤・・・」
ためらいを含んだ甘い声で、そっと俺を呼ぶ。
「いいから、ね」
まるで結婚式の指輪の交換みたいに。
俺は微笑しながら、ゆっくりと岩城さんに指輪をはめた。
もちろん、左手の薬指に。
関節でちょっと引っかかったけど、あとは楽だった。
―――岩城さんに指輪を贈った人間は、今まで一人もいないはずだ。
正真正銘、俺が初めて。
じんわりと何かがこみ上げて来た。
「サイズ、丁度いいみたいだね」
返答のしようがなくって、岩城さんは苦笑した。
邪気のない顔が、困ったみたいに傾げられる。
抱きしめたい、そんな衝動に駆られながら。
「よく、似合うよ」
彼の手の甲を掲げて、俺はかすめるようなキスを落とした。
「・・・!」
一瞬、唇が触れただけなんだけど。
岩城さんの手が、ほんの少し震えた。
周囲がひときわざわついた、そのとき。
「・・・京介?」
背後から声がかかり、途端に岩城さんが全身を強張らせた。
「え―――」
「・・・っ!!」
岩城さんと俺は、ほとんど同時に振り返った。
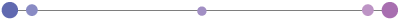
藤乃めい
10 November 2007
2013年7月20日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。