さしも知らじな 第十三章 その3
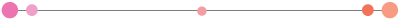
そこに立っていたのは、見覚えのある長身の男だった。
オッサン・・・と呼んでおかしくない年代ではあるけど、すらりとした美丈夫。
ほどよく履きこなれたジーンズ姿が、嫌味なくらい決まってる。
「あっ・・・!」
そう、忘れられるわけがない。
岩城さんが『克哉』と、名前で呼んでいた男。
俺の恋人が、長年つきあっていたらしい不倫の相手―――。
「部長・・・」
心底、想定外だったんだろう。
目を見開いて、岩城さんが呆然と呟いた。
「―――おかしなところで、会うものだな」
ゆったりした口調だった。
偉そうで、いかにも親しげな眼差し。
ここで会ったのは偶然なのだと強調するように、男は手にした紙袋を掲げてみせた。
肩をすくめる仕草がいかにも気障で、きまってる。
それがまた、俺の神経を逆なでした。
―――振られたくせに、何かっこつけてるんだよ。
俺は内心、悪態をついた。
「ここで何を・・・」
微笑しかけた男の表情が、ふ、と固まった。
俺に気づき、それから。
冷ややかな視線が、さりげなく岩城さんの手元に注がれる。
「・・・おまえこそ」
男が顔色を変えたのを見て、俺はほくそ笑んだ。
岩城さんの薬指にはもちろん、はめられたままの指輪。
―――俺の贈るマリッジリング。
「岩城さん」
割って入ろうとした俺を、岩城さんは静かな眼差しで制した。
「でも・・・」
「いいから」
「・・・なるほど、な」
一歩近づいて、男はじろじろと俺を見つめた。
明らかに俺を値踏みする、わざとらしい視線。
俺のこと、覚えてないのか?
「そういうことか」
からかい混じりの微笑。
その鼻っ柱を折ってやりたかったが、俺はぐっとこらえた。
―――これは、岩城さんのテリトリーだ。
「奇遇ですね、こんなところで」
男の皮肉に気づかないふりで、岩城さんが淡々と言った。
それから、息づまるような沈黙。
眉をひそめた男の表情は、穏やかさを装っている感じかな。
気のないそぶりをしてるけど、本心では興味津々ってところだろう。
「ね、岩城さん?」
対する岩城さんは、落ち着いていた。
ゆるやかに会釈して、俺の腕をそっと叩く。
「いいから、香藤」
「うん・・・」
「俺は大丈夫だから」
そう言われたら、俺は頷くしかない。
渋々、岩城さんの腰に添えていた手を離した。
本音を言えば、彼の腕を取ってこの場から立ち去りたい。
逃げたいわけじゃない。
だけど、この二人を会わせておきたくない。
―――でも、守りたいってのは、男のエゴだ。
頼まれてもいないのに、俺の出る幕じゃない。
・・・わかってるさ。
俺は堪えて、ひそかにため息をついた。
「あの、お客さま・・・?」
そのとき、店員が後ろからおそるおそる声をかけてきた。
俺は周囲のざわめきに、ふと我に返った。
「ああ!」
岩城さんが値札つきの指輪をしたままだから、気にしたのか。
「すみません。俺、あれ買うから」
「いえ、ですが・・・」
「大丈夫ですから」
俺は宥めるように微笑して、財布からクレジットカードを引っ張りだした。
「すぐですから、ね」
それだけ言うと、視線を岩城さんに戻した。
「部長・・・」
「まったく」
男は、何とも言えない笑みを片頬に浮かべていた。
「白昼堂々、男連れで買い物か。大胆なものだ」
「・・・ええ、まあ」
「おまえらしくないな、京介。それとも、そう思うのは俺の買いかぶりか」
「そうかもしれませんね」
あっさりと相槌を打って、岩城さんはちょっと微笑した。
ひそかに俺は、舌を巻いた。
―――なんだか、余裕を感じるんだけど。
今までの岩城さんなら、こういう態度はあり得ないだろう。
そう思ったのは、俺だけじゃないらしい。
「驚いたな。どうした心境の変化だ?」
まるで岩城さんを、初めて見るかのように。
真意を確かめるみたいに、男が一歩、俺たちに近づいた。
「さあ」
岩城さんは小さく笑う。
それから指先でそっと、プラチナのリングをなぞった。
満ち足りた甘やかな顔つき。
ほとんど無意識みたいに、ちらりと俺に流し目をくれて。
それからまっすぐに、男を見据えた。
「バカが移った・・・のかな」
さらりとひと言。
悪戯そうな笑みが、思いがけずこぼれた。
「・・・!」
男も俺も、絶句した。
「ちょっと、岩城さーん!」
俺は、大げさに顔をしかめてみせた。
「それってあんまりなんじゃない?」
わざと子供みたいに口を尖らせて、俺は抗議した。
抗議するふりをした、というべきか。
内心、その場で岩城さんをぎゅっと抱きしめたいくらい、嬉しかったけど・・・!!
「ひどいよー、それ」
「・・・おまえのことだとは、ひと言も言ってないぞ」
ふふ、と彼が小さく微笑する。
なんだか、小悪魔的な余裕すら感じさせて。
「もう、岩城さん・・・!」
―――妖艶すぎて、目眩がしそうだ。
俺は天井のシャンデリアを仰いで、派手に嘆息した。
いつの間に化けたんだろう、ホントに!
岩城さんが変わっていく。
俺の目の前で、どんどん進化していく。
「―――呆れたな」
ふと気づくと男が、隠しようのない微苦笑を浮かべていた。
なぜかその口元に、年齢を感じる。
「俺はおまえの、何を知っていたんだろうな・・・」
疲れたような表情で。
思いがけない弱気の台詞・・・だよね。
岩城さんが、それを聞いて瞠目したから。
それは男が、岩城さんを永遠に失ったことを理解した瞬間。
俺はもちろん、聞こえないふりをした。
「あなた、ここにいらしたのね」
鈴を振るような声がして、俺たち三人はいっせいに振り向いた。
「どこに行ったのかって、ずいぶん探して―――」
幼い少年の手を引いた、ほっそりした美人がそこに立っていた。
「夏実」
男が小さく名前を呼ぶ。
「あら・・・ごめんなさい、お知り合いの方?」
慌てたように髪に手をやって。
その女性は岩城さんと俺にそっと会釈した。
「まあ・・・!」
黙礼する岩城さんに、驚いたような声を出す。
「えっと・・・岩城さん、でしたわよね。まあ、ご無沙汰しております」
「パパ!」
息子が父親の手を掴むのを横目で確認して、彼女は深々とお辞儀をした。
「いつも主人がお世話になっております」
「いえ、こちらこそ・・・」
言葉少なめに、岩城さんも丁寧に挨拶を返した。
―――なるほど。
お互い、顔見知りなのか。
同じ職場の上司と部下なんだから、もの凄く不思議ってほどじゃないけど。
俺は複雑な気持ちで、三人の様子を眺めた。
岩城さんの心中は計り知れない。
この奥さんには、想像もつかないんだろうな。
目の前にいる旦那の部下が、まさか長年の不倫相手だったなんて。
―――どういう神経なんだよ。
妻を不倫相手に引き合わせてた男の心境なんて、わかりたくもないけど。
「・・・あら!?」
再び顔を上げた彼女が、俺をまじまじと見つめた。
「あなた、もしかして」
「な、なんでしょう?」
俺はどぎまぎしながら、次の言葉を待った。
「テレビに出ていらっしゃいませんでした?」
「・・・え?」
「いつだったか・・・先月くらいに」
「はあ」
「そう、大きな写真展で賞をお取りになって、インタビューを受けてらした・・・?」
「ああ・・・!」
俺だけじゃなくて、男も岩城さんも、同時に息を呑んだ。
「写真展だって・・・?」
男が反芻するようにつぶやいて、妻の顔を見下ろした。
「本当か」
「ええ。こんなお若い方が受賞なさったって、ずいぶん話題になったのよ。女性雑誌にも載って・・・」
心持ち自信なさそうに、彼女は俺に視線を走らせた。
「・・・ですよね?」
「はい。えーっと、俺・・・」
「その通りです」
どう説明しようか考える間もなく、岩城さんがにこやかに答えた。
「こいつは××賞を受賞した、写真家の香藤洋二です」
彼の視線は、まっすぐに男に向けられていた。
微笑を浮かべて、堂々と顔を上げて。
「まあ、やっぱり!」
「あ、ど、どうも・・・!」
紹介されるままに、俺はぺこりと頭を下げた。
―――なんだか俺、岩城さんに翻弄されてない?
途惑いというより、どこか妙にくすぐったい感じだった。
俺の目の前で、恋人がどんどん変化していく。
嬉しい、そしてどきどきする。
それはもう―――さなぎが孵化して、美しい翅(はね)を広げるようで。
「やっぱり、そうでしょう!」
夏実と呼ばれた女性は、嬉しそうに頷いた。
「おめでとうございます。ねえあなた、凄い方とお知り合いなのね」
「・・・ああ」
男が言葉に詰まって、曖昧に返事をする。
それが妙に可笑しくて、俺はくすくすと笑い出した。
「香藤?」
岩城さんが、不思議そうに俺を覗き込む。
俺はにっこり笑って頷いた。
「それじゃあ、まだ買い物があるので、俺たちはここで―――」
俺は会話を打ち切って、岩城さんに向かいなおった。
「行こ、岩城さん」
左手にはまったままの指輪に、ちらりと視線を落とした。
「それにしようか」
「・・・ああ、そうだな」
蕩けるような甘い笑みを見せて、岩城さんが頷く。
―――迷いのない、強い眼差し。
「失礼します」
凛とした声でそう告げて、岩城さんは頭を下げた。
―――吹っ切れたって言うのかな。
決別、という言葉がふたたび脳裏をよぎった。
「どうも」
俺も並んで挨拶した。
岩城さんの気持ちは、今は俺にある。
揺るがない想いを、寄せてくれている。
―――なんの気負いもなく、そう信じられた。
あの男とのことは、本当にもう終わったこと。
俺が気にすることなんて、何ひとつない・・・!
「行こう、香藤」
「うん!」
俺は清々しい気分で、踵を返した。
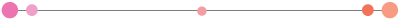
藤乃めい
18 November 2007
2013年7月26日、サイト引越に伴い新サイト(新URL)に再掲載。初掲載時の原稿を若干加筆・修正しています。